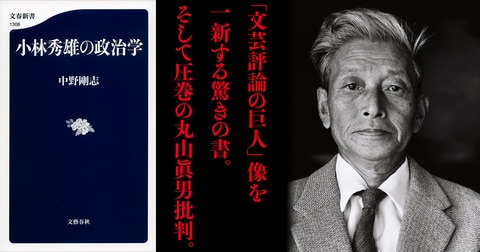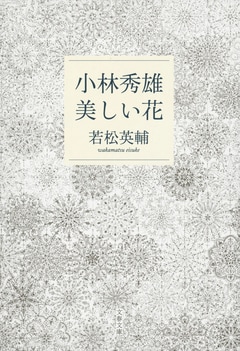III
だが、本書の語り口は、その第三部、特に「恆存の晩年」に入ってから転調していく。脳梗塞の後遺症もあって、恆存は、その「仮面」を操る巧みさを失ってしまうのである。
逸氏自身、その「あとがき」で「恆存の晩年」を書くことは「私には気が重かつた」と述べているが、しかし、だからこそ注目すべきなのは、それを書くまでの氏の心の動きである。
「最後に書くつもりの「恆存の晩年」を書くべきか──果たして本当に書けるのか、心のうちでは煩悶してゐた。が、第二部すべてを書き終へ、平成二十八年の暮れに第三部の「近代日本をいとほしむ」に取り掛かる頃には、腹を括つて「晩年」を書くことを自らに課す、といふ気分にはなつてゐた。」 (本書「あとがき」)
この言葉が、私にとって印象的なのは、第三部の「近代日本をいとほしむ」で論じられていた主題こそ、まさに他者との「距離感」であり、また、その「距離」を「いとほしむ」ことだったからである。つまり、逸氏は、恆存の言葉によって「距離」を論じて後に、実際にその教えを、父・福田恆存に向けて実践することを決心しているのだ。
むろん、「距離感」というのは、冷たさとは違う。冷たさとは、そもそも関係すること=距離をとること自体の否定であり、本書で言及される遠藤浩一の言葉を借りれば、それは、「他者(西洋)との交流を排して自己(日本)に内向すること」に近い。つまり、「孤独」というよりは、「孤立」を内に宿した態度だということである。
が、「距離感」というのは、一度はそれに近づき、同一化までしようとした人間が、しかし、それとは同一化し切れぬギリギリの場所(ずれ)に見出した一つの自己認識、つまり、「孤独」の自覚として浮かび上がってくるものだろう。だから、それは常に、相手に対する「いとほしさに近い感情」を伴うことになるのだ。
たとえば、「骨身に応へる話―吉田健一(二)」のなかで逸氏は、恆存の吉田健一宛の手紙にあった言葉──「真似が不可能といふことの方が骨身に応へます」を引きながら、そこに「完璧を求めることの不可能と無意味が滲み出てゐる気がしてならない」と書いているが、「恆存の晩年」に感じられるのも、その「完璧を求めることの不可能と無意味」の感覚ではなかろうか。
父のことを「一番解つてゐるのは自分だといふ自負」と、その裏返しとしての、「完璧」ではなくなりつつある父への苛立ち。そして、その苛立ちの背後から次第に立ち昇ってくる「父殺し」と「王位簒奪」の無意識の衝動。第三部を読み進めるにつれて、それら一連の葛藤自体が、父・福田恆存に真似ぶこと(学ぶこと)を運命づけられた人間の悲劇のように見えてくる。が、しかし、そのなかから次第に生まれてくるものが、「私の人生は父の存在と影響なしでは成り立ち得なかつた」という逸氏自身の、諦めとは全く違う、静かな自己認識だったのだとしたらどうだろう。それこそは、半世紀近くを福田恆存と一つ屋根の下で過ごしてきた息子の「距離感」、そのなかで引き受けるべくして引き受けられた、親子の「宿命」の形だったのではないか。
しかし、それなら、ここにある親子の交わりこそ、あのマルセルの語った「相互主体性」の生きた姿だったのかもしれない。恆存が、わざわざ夕刊を切り抜いてまで息子に送ってよこしたという、マルセルの講演を紹介したエッセイには、「自分が自分でありながら他でもあり、他が他でありながら自分でもある」(西谷啓治)という言葉があったというが、恆存と逸氏もまた、そんな「相互主体性」を生きていたのではなかったか。いや、だからこそ、その「主体性」は、自他の融解ではなく葛藤を、馴れ合いではなく緊張を二人に強いたのであり、また、その葛藤と緊張を通じてこそ逸氏は、ようやく、父・福田恆存を「いとほしむ」ための「距離」を手にしたのではなかったか。
果たして、マルセルの言うように、その「相互主体性」のなかから生い立ってくるものが「文化」なのだとすれば、本書が描いているものこそ、その「文化」の具体的様相にほかなるまい。他者との信頼と葛藤、喜びと悲しみ、愛と憎しみ、そして、それにまつわる悲劇の全てをその身に引き受けながら、なお、その宿命を「いとほしむ」こと。「福田恆存」を「文化」として生きるということは、おそらく、そのようなことを言うのだろう。