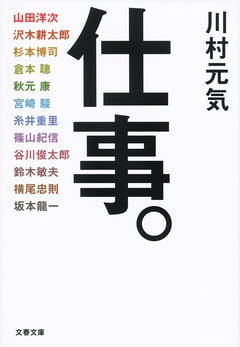人間は体じゃなくて記憶でできているということ?
小説の中で、メインではない登場人物の一人が人工知能研究者との対話でそう尋ねる。そうです、と人工知能研究者は答える。
人工知能を扱った小説はだいたい、多少なりともこの主題に触れないわけにはいかない。カズオ・イシグロの『クララとお日さま』もそうだったし、フランスのベテラン作家マルク・デュガンの意欲作『透明性』もそうだった。その人をその人たらしめているのが記憶なのだとしたら、それを滅びない体に移植すれば……。
でも、いったいどの時点での記憶を移植すれば、「その人」ということになるんだろう。記憶は日々変化する。まずだいいちに、失われていってしまうし、新たなものが付け加えられるし、夢や物語や他人の記憶と混じってしまう。
幸いなことに(!)『百花』の主題は人工知能ではない。
記憶を失くしていく老いた母親と、息子の物語だ。
小説はSF的なところなどぜんぜんなくて、回想やアルツハイマーの母親の混乱した脳裏に浮かぶ断片的な思念が混じるものの、リアリズムの視点で語られる。
でも、読んでいるうちに、ふと思うのだ。
認知症とはなんと、人間らしい病気であることかと。
AIがいつか、記憶の失い方をも模倣する日が来るだろうか。そんな機能は必要ないものとして、ビルトインされないのではないだろうか。効率よく記憶を整理する機能が装備されたとしても。
主人公の葛西泉はレコード会社で働く三十七歳の男性で、アルツハイマー型認知症を患った母、百合子は、シングルマザーとして彼を育てた。泉は香織と社内結婚し、もうすぐ第一子が生まれてくる。ストーリーは淡々と紡がれるから、記憶を失くしていく母の様子と、もうすぐ親になる泉と香織のとまどい、会社でもそれなりの地位にいる中堅社員である泉の、かなりストレスフルな仕事の描写などが、泉が思い出す幼いころの光景とともにつづられていく。三十七歳の生身の男性の抱える、静かな筆運びによる日常の描写が、この小説のリアリティを支えている。
たいていの人にとって、介護の現実はこんなふうに存在するのではないだろうか。
老親に直面するとき、自分は壮年で、仕事もしなければならないし、子育てにも追われている。もちろん人によって、人生のステージの時期がずれるけれども、介護のほかにやらなければならないことを持っていない、という人はあまりいない。だからこそ、たいていの人は、親に十分なことをできなかったのではないかという、慢性的なうしろめたさを抱えつつ、その事態に直面することになる。
だから、泉が仕事に追われて実家に行けず、ヘルパーさんに介護を任せきりにしていて、その間に母の病状が進行していく前半は、身につまされる思いで読み進む。「一気に進んだかと思えば、突然穏やかになったりもする」と医師が説明する病気の進行はまさにその通りで、家族はどうしても振り回される。それでも、母の病状が進めば決心して、仕事帰りに実家に行き、泊まり込み、記憶を失っていく母の行動にときにいら立ちながらも、せいいっぱい世話をする泉の姿にも、多くの読者が自分を重ねるだろう。失禁する母にシャワーを使わせ、徘徊したと聞いては駆けつけ、介護の現実はそう、ほんとうにたいへんだ。
泉は、母親思いの、そうした、ふつうの男性に見える。じっさい、そうだ。人に「ふつう」という決まりきった型があるわけではなく、人にはそれぞれ個性がある。親子のつきあい方も、十人十色だ。でも、時々、けっこう濃い母子関係なんだなあと思わされることがある。まず、冒頭、母と息子は二人だけで新年を迎えている。大みそかの夜に、泉は母が一人暮らす実家に戻り、紅白を観ながら年越しをする。元日が母の誕生日だからというのもあって、二人の恒例行事であるらしい。認知症を患うよりずっと以前から続く慣習なのだ。妊娠した妻を一人にしても、母と二人での正月を選ぶのだから、濃い関係といってもいいのではないだろうか。