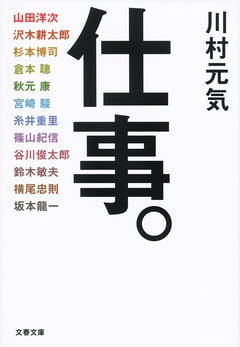それに泉の回想の中で、婚約を告げられた母親が泣きだすシーンがある。「ふたりで生きていくのに精一杯だった」「これからやっと、親子らしいことができると思っていたのに」と。息子が結婚するとなれば、心中おだやかでない母親はじっさい少なくないだろうけれど、しっかり者の母親らしく描かれるピアノ教師のシングルマザーは、のちのアルツハイマー患者の混乱ぶりとは別のところで、どこかちょっと奇妙さを漂わせている。
徘徊は認知症の中核症状ではなく、周辺症状だそうだ。認知症になれば直接的に徘徊が始まるのではなくて、認知症で認知機能に障害が起こったときに、なにかに触発されて、徘徊行動が起こる。だから、徘徊する人もいればしない人もいるのだけれど、一般には徘徊が認知症のシンボルみたいに思われていたりする。しかし、読み解くべきはなにに触発された行動なのか、なのだ。
百合子もやはり何度か徘徊をする。そしてそれは、彼女のとても深いところに結びついた行動らしいことが、小説を読み進むとわかってくる。百合子はいちばんはじめから、迷子になった息子を探しているのだ。小さい時の泉は、すぐに迷子になった。だからしょっちゅう百合子は、探さなくてはならなかったのだ。そもそもなぜ泉は、そんなに迷子になったのか。徘徊する母を探しながら、泉は幼い自分の記憶を引っ張り出す。あの頃、なぜ自分は迷子になったのだったか。だとすれば、年老いた母の行動は、なにゆえなのか。
小説の核心は、母と息子がつとめてなかったことにしている、ある、決定的な一年間の記憶にある。母がその記憶をも手放し、あるいはほかの記憶と混濁させていく中で、息子は封印していたものを見せつけられることになる。それも、施設に入った母のために家を整理していて見つけた、当時の母の生々しい手記、日記として。
この一年があるために、百合子と泉の関係は、とても独特のものなのだと読者は知らされる。奇妙な濃さと、どこかためらいがちな距離との、この母子のスペシャルな色が、くっきりと浮かび上がってくる。
小説の魅力は、母が記憶を失っていくと、息子に記憶が戻ってくる、その不思議なバランスが描かれているところだ。忙しく生きている壮年の人物にとって、幼い時の記憶なんて、そうそうよみがえってこない。けれどたしかに、親を失うと思うとき、いつか記憶の引き出しの奥のほうにしまい込んでいた何かが、澎湃(ほうはい)と思い出されてくることがある。あなたはきっと忘れるわ。そう、母が言ったことを、泉は思い出す。忘れたことを思い出す。母が忘れた、そのときになって。
認知症という病気はしばしば、ある人から唐突に人間性を消し去る残酷な病気のように描かれることがある。自分を忘れてしまい、親しい人のこともすっかり忘れ、人格が破壊され、人ではないものになってしまうかのように。でも、おそらくそうではないのだ。この小説には、それが、とてもよく描かれていると思う。人は、記憶を失っていく。でも、そのプロセスの中で、その個人は、痛いほど、悲しいほど、愛おしいくらいに、その人であり続ける。泉の母は、百合子は、無防備なむき出しの百合子になる。幼い百合子になり、若い母の百合子になり、自分のためだけに生きることを夢想したときの百合子になり、息子と二人で生きていくことを決断した百合子になった。百合子にあらわれた症状は、たしかに個人が記憶を手放していく過程なのだけれど、線香花火のようにぱちぱちと、いろんな顔を見せる百合子の晩年の姿から、泉はたくさんの記憶を受け取っていく。そうした意味で、老いた認知症患者はけっして、介護する側にとってむなしい空っぽの存在ではない。
いつか、泉も忘れてしまうだろう。思い出し、受け取ったはずのものすら、いつか消え失せてしまうだろう。それじたいは、誰にも引き継がれないものかもしれない。
でも、きっと泉は生まれてきた息子に、なにかを話すだろう。直接、母の話をしなかったとしても、泉と息子の間には、また新しいなにかが生まれ、語られ、それを泉は自分の記憶を手放すのと引きかえに、息子に思い出させるのかもしれない。
人間は記憶でできているのだという。
読み終わって、静かな温かいものが残った。