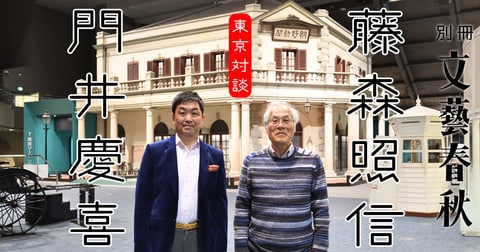なぜ東京を「とうきょう」と読んではいけないのか――直木賞作家、門井慶喜が「東京の謎」を解き明かす!

東京を「とうきょう」と読むのは間違いである、という話から始めたい。
男女という熟語がある。「ダンジョ」と読むが「なんにょ」も正しい。男女七歳にして席を同じゅうせずのときは前者だし、老若男女のときは後者である(カタカナとひらがなの書きわけの法則はあとで述べる)。ところが両方をごっちゃにして、
ダンにょ
なんジョ
と読んだらペケ。混ぜるな危険。テストの点数がもらえないという以前に、むずがゆいというか、誰しも生理的な違和感があるのではないか。
そもそも漢字には、音読みと訓読みがある。そのうち音読みというのは中国語の発音をそのまま(に近いかたちで)日本語へ取り入れたものであるが、これはさらに二種類にわかれる。呉音と漢音である。
大ざっぱに言うと呉音というのは中国南方の方言が起源であるもの、漢音というのはもう少し北の長安(現・西安)のことばが起源であるもの。前者が先に、後者があとで日本に来た。
純粋に日本語の発音として見た場合には呉音のほうが柔らかく、拗音促音が多い傾向があるのに対し、漢音のほうが音(おん)がきつく、濁点が多い。「なんにょ」と「ダンジョ」の差はまさしくこれである。ここでは呉音をひらがなで、漢音をカタカナで書いたわけだ。私たちは明確には意識していないけれど、こういう二字熟語を読む場合は、呉音なら呉音で、漢音なら漢音でそろえるというのが原則なのだ。その原則が外れたとき、私たちの心の耳は、かすかな不協和音を聞くのである。
(ほんとうを言うと漢字の音読みには他にも上古音、宋音があるのだが、これらは数が少ない上、いまの私たちの生活にはさほどの影響をあたえていないので省くことにする。)
と、ここまで言えばもうおわかりだろう。あの混ぜるな危険、生理的な違和感をもよおさせる「ダンにょ」とおなじ読みかたで、私たちは「東京」を読んでいる。藤堂明保編『学研漢和大字典』をひらいてみれば、
東……呉音「つう」、漢音「トウ」
京……呉音「きょう」、漢音「ケイ」
とある。少し大きい漢和辞典ならみなおなじ記述のはずだ。東京はつまり「トウきょう」なのだった。
そもそも東京という地名は、人工的に案出されたものだった。ガマの群生地だから蒲田だとか、天然の良港があるから津(三重県)だとかいうのとは異なり、維新のどさくさで、田舎から来た志士あがりの元勲たちが「東の首都」くらいの意味で命名したのである。
しかしいくら田舎の志士あがりでも、漢籍の教養はこんにちの私たちより数等も上だった。彼らはこの東京という新地名をまちがいなく「トウケイ」と読んだだろう、そう人々に読まれることを想定しただろう。漢音は漢音でそろえるべし(東の呉音「つう」は当時から一般的ではなかったので「つうきょう」は候補外)。ところがその一般法則は、民衆の、特に江戸の民衆の感覚にはなじまなかった。
あるいはそんな一般法則などあっさり押しつぶしてしまうくらい、それくらい彼らにとって「きょう」の読みは重かった。京ことば。京おんな。京の着だおれ。京白粉(おしろい)。京縞(じま)。京小袖。京極……みんなみんな「きょう」じゃないか。
いろは歌のおしまいも京。日本橋から西へと向かう第一の橋の名前も京橋(名前の由来は諸説あり)。もちろん京洛(ケイラク)、京師(ケイシ)などという漢音系の語もあったけれど、これらは知識人のもので、日常語ではなかった。たぶん江戸の民衆には、いや、ほかの地方の人々にも、漢音「ケイ」は少しきつすぎたのである。
呉音「きょう」のやわらかい響きのほうが、街のイメージと調和した。こんにち京都と呼ばれるあの街のおっとりとした、繊細な、気品ある印象。その余波として「トウきょう」という木に竹を接ついだような読みはあるのだった。
その「木に竹」にも、いまや私たちはすっかり慣れてしまった。「トウきょう」が当たり前。それが自然なのであり、「トウケイ」はやっぱり不自然で……と言いたいところだが、じつはこんにち、私たちは、或る特定の分野においては東京の京を「ケイ」と呼んでいる。
ありふれた日常のことばとしている。歴史の矛盾? 日本語の矛盾? その分野とは、そう、鉄道の分野にほかならないのだ。
京王線、京成線、京浜急行線、京葉線……いずれも明確に「東京」の意を示していながら、とつぜん読みが変わってしまう。
呉音が漢音になってしまう。これは一体なぜなのか。おそらく京のみやこは女性のイメージで、近代の鉄道は男性のイメージで、それぞれ語られることが多かった事実と関係があるのだろうが、ともあれ本書はこんなふうに、これから東京という街をいろいろ考えようと思う。
読者もいっしょに考えてもらえたら幸いである。なおその方法としては、従来あまり人が目をつけなかったところに目をつけることは当然として、その上で、なるべく視点は自由でありたい。
空間的には東西南北へ、ときに東京の外へと飛翔しつつ、時間的には歴史をしばしば昇降する。いわば視点の三次元運動。それはひょっとしたら司馬遼太郎が名著『この国のかたち』や『街道をゆく』で日本および日本人について考えたときの態度に近いかもしれず、その意味では、本書のもうひとつのタイトルは「この東京(まち)のかたち」であると言ったらおこがましいだろうか。
(「はじめに なぜ東京を「とうきょう」と読んではいけないのか」より)
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。