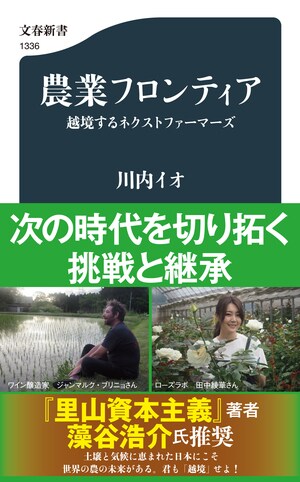
日本の食卓を支える高齢者
なんとなくイメージは伝わっただろうか? 産業規模が8.9兆円に達する農業という広大なフィールドは課題が山積みで、日々深刻化している。そのなかで彼ら、彼女らは機転を利かせ、それまで誰もやってこなかったことにチャンスを見出し、すべてを懸けた。その姿はまるで、荒野に挑む開拓者のようだ。
そう、日本の農業は今、新たな開拓時代に突入していると言ってもいいだろう。戦後、農業界を効率よく動かすために作られた従来のシステムや慣習は経年劣化して、維持するのが難しくなってきている。その現実は、数字に表れている。
例えば、自営業で農業に従事している人の数は、2015年の175万7000人から2020年には39万4000人減少し、136万3000人になった。神奈川の横須賀市や大阪の豊中市の人口に匹敵する数の人たちが、この5年で農業から離れたことになる。とんでもない数だ。
その主な要因とされているのが、高齢化。一般企業では2025年4月より定年が65歳に引き上げられるが、農業界の平均年齢は67.8歳で、65歳以上の割合が69.6%を占める。全国のおじいちゃん、おばあちゃんが豪雨でも、酷暑でも、寒波が来ても農作業を続けることで、日本の食卓を支えているのだ。
高齢者におんぶにだっこの危機的状況から脱するため、農林水産省は「2023年までに40代以下の農業従事者を40万人に拡大」する目標を掲げ、新規就農時の資金面のサポートなどを行ってきた。しかし、毎年だいたい6万人弱いる新規就農者のなかで、49歳以下の世代は直近6年をみると2015年の2万3000人をピークに減り続け、2020年は1万8400人にとどまっている。率直に言って、国を挙げたラブコールは40代以下の世代に届いていない。
新規就農者の75.5%が「食っていけない」
それではなぜ、若い世代が増えないのか。いくつかの要因が考えられるが、大きな理由として「稼げない」という現実がある。日本では2020年の時点で農業経営体が107万6000あり、そのうち家族経営(個人経営体)が103万7000。ということは、96%が家族経営にあたる。そして、家族経営の農家における1時間あたりの所得、簡単にいうと1時間でどれだけ稼げるかという金額は、平均722円(2015年のデータ)。ちなみに、2020年の最低賃金は最も金額が低い県でも792円……現実は厳しい。
2017年に発表された調査では、就農10年以内の新規参入者2265人に就農後の農業所得を聞いたところ、「生計が成り立っていない」と答えた人が75.5%にのぼった(一般社団法人全国農業会議所 全国新規就農相談センター「新規就農者の就農実態に関する調査結果─平成28年度─」)。100人いたら75人が「食えない!」と訴えているのである。
後を継ぐ者がいないから、耕作放棄地も増え続ける。1995年に24.4万ヘクタールだった耕作放棄地は、2015年に42.3万ヘクタールとほぼ倍増した。これは富山県とほぼ同じ広さにあたる。さらに、耕作放棄地とは別に、作物の栽培が実質的に不可能とみなされた「荒廃農地」もあり、こちらは28.4万ヘクタール(2019年)で神奈川県よりも広い。富山県と神奈川県が草ぼうぼうの無人の空き地で、それが年々広がっていると想像してみてほしい。

















