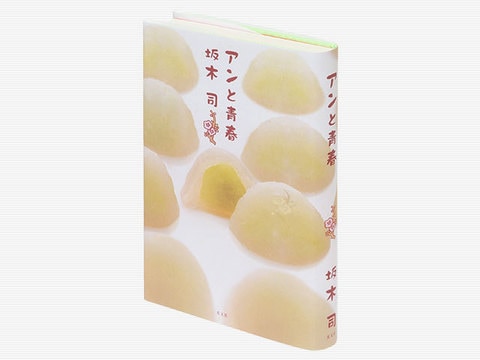ショートケーキが大好き。
生クリームのコクに、甘酸っぱいイチゴ。ふわふわのスポンジは口の中でしゅわっと消えるのが最高だけど、シロップがじゅわじゅわに染みたのも、手作りっぽいどっしりしたものも好き。でも何よりときめくのは、上に載った一粒のイチゴ。白い大地にぽつんと灯された希望のような赤。特別で、大切で、唯一無二のものって感じがして本当に好き。
なのに。
そんなショートケーキが食べられなくなる日が来るなんて、思ってもみなかった。
フォークを持つ手が止まる。
目の前にあるのは、無残に崩れたケーキ。ぼろぼろのスポンジと、流れ落ちたクリーム。味は変わらないとわかっていても、食欲が湧かない。
いや、味は違うんだった。このケーキには、イチゴが存在しない。
「ねえママー、もうない?」
テーブルの横で私を見上げる、三歳の娘。奈々。
「うん。ないねえ。ほら」
私の皿を見せると、見える距離にもかかわらずぐいぐい体を押しつけてのぞき込んでくる。
「ホントだあ」
言いながらも、フォークを伸ばして崩れたケーキをさらに崩す。
「なかにものこってないねえ」
そうだね、と答えるとしゅんとうつむく。
「イチゴは、どうして食べるとなくなっちゃうのかなあ」
ふくらんだほっぺた。長い睫毛。幼児独特の横顔のフォルムが可愛らしい。言っていることも、かわいい。かわいい。かわいいの塊だ。
ふと、私の方を見上げる。
「ねえママ、なーちゃんはイチゴがせかいでいちばんおいしいとおもうよ」
ほら、かわいい。
「うん。ママもそう思うよ」
にっこりと微笑んで娘のほっぺたをつつく。
可愛いと思う気持ちは本当だ。でも、それと同じくらい違う感情が渦巻く。
――ままならない。
*
私は特にグルメだとか食いしん坊なわけじゃない。食べる量もほどほどだし、甘いものに関しても強い執着はない。好きなものも嫌いなものもこれといって激しいものはないし、食に関して何か言うことがあるなら「ケーキセットと共に過ごすお茶の時間が好き」、くらいだろうか。つまり私は、自分の人生における「食」の割合は高くない方だと思っていた。
でも、子供が生まれてからそれが変わった。
要するに、ままならないのだ。
最初にそれがわかったのは、好物のショートケーキを前にしてフォークが止まったとき。
「――胸焼けかな?」
昨日食べ過ぎてもいないし、おかしいな。なんかイチゴの酸っぱさも妙に気持ち悪いし、もしかして食あたり? そんなことを考えていたら、妊娠がわかった。
すごく嬉しかったし夫と手を取り合って喜んだけれど、つわりが始まったとたん、好きなものどころかほとんどすべてのものが食べられなくなった。最初はつらくても「こんなものなのかな」と思っていたけど、食べ物だけではなく日常的なすべての匂いが鼻につきはじめたときには怖くなった。息を吸うだけで気持ちが悪くなり、それを支えてくれるために近寄ってくれる夫の匂いにすら吐き気を覚えたのだ。
「こういうのは、個人差があるからねえ」
何も食べられず衰弱してしまった私に、担当の産科医は困ったような笑顔を浮かべながら点滴の針を刺した。
そのころ食べられたものは、冷たい絹ごし豆腐をスプーン一杯、冷ました鶏のササミの塩焼きをひとかけら、冷ましたご飯に塩をかけたものを少し、水。それだけだった。白っぽくて、お供え物みたいな食卓。夫の食事を作るのも目の前で食べられるのも無理だったので、その時期は自炊してもらって完全に食事を分けていた。
(なんでこんなことに)
通常、つわりはある程度の時期におさまる。でも私は出産までおさまらなかった。
(妊娠後期って――もっとこう、楽しい時間なんじゃないの!?)
夫と二人きりの最後の時間だから、日帰り旅行に行ったりデートしたり。
「産まれちゃったら忙しくなるから、フルコースをゆっくり食べておこうね」
なんて甘い夢を語っていたのに。
現実は、白いお供え物。しかも食事は別々。相手の匂いすら嗅ぎたくない。これじゃ愛が深まるどころか、離婚直前の夫婦だ。
唯一の救いは、夫が「無理なものは無理だよね」と割り切れる性格の人だったこと。そして自炊や家事がそれなりにできていたこと。
「気持ち悪がってごめんね」
ホルモンバランスが崩れ、マタニティブルーになった私が泣き出すと、夫は私に向かってまずこう言った。
「手を伸ばしてもいい?」
私がうなずくと、夫は空気中に匂いが広がらないようにそろりと手を伸ばす。そして、私の頭をそっと撫でた。
「色々頑張ってくれて、ありがとう」
まるで美女と野獣のようなやりとりに、私はようやく微笑むことができた。
それが、最後のロマンチックだった。かも。
産後、ようやくつわりがおさまった。食欲が戻ったときに私が求めたのは、色味があってバランスの良い食事。
目の前に並んだほかほかのご飯とお味噌汁。肉じゃがとか唐揚げとかの茶色い系おかずに、しゃきっとした緑のほうれん草のごま和え。そういうものに、ものすごく飢えていた。
なので実家の母が来てくれた一週間は天国だった。食欲が戻った私はあれが食べたいこれが食べたいとわがままを言って、母と夫に甘え倒した。「お祝い」という言葉にかこつけて、何度もショートケーキを食べた。妊娠中はあれほど気持ち悪く感じた生クリームが、天上の美味のように感じた。けれど母が帰ってしまうと、食生活は再び残念なものになった。今度は純粋に、手が足りなかったのだ。
夫は育休を申請してくれたのだけど、一週間しか取れなかった。だから母と合わせて都合二週間、私は休むことができた。でもその先は、いわゆるワンオペ育児。生まれたての小さな生き物を育てるほぼすべての責任が、私の肩にのしかかった。
新生児は、二時間から三時間おきにミルクを欲しがって泣く。それが夜中の二時だろうと、明け方の四時だろうとおかまいなし。それに合わせているうちに睡眠時間は削られ、しだいに朦朧としてくる。それでもつわりのときとは違って、お腹が減る。何か食べたいと思うけど、少しでも音を立てるとせっかく寝た赤ちゃんが起きてしまう。そこで私は忍者のようにそっと移動し、夫に買っておいてもらったサンドイッチを口に押し込む。
(なんでこんなことに)
真冬なのに、温かい紅茶すら飲めない。狭いマンション住まいのせいか、ポットからお湯を出す音にも赤ちゃんは反応してしまうのだ。お米が食べたかったけど、コンビニのおにぎりのパッケージを開けるカサカサとした音にも反応する。あと、おにぎりだと栄養が偏って母乳に影響が出るかもと心配した。
夫が出かける前に皿に出して、音が出ないようにゆるくラップをかけておいてくれたサンドイッチ。それを無言で素早く食べる。食事じゃなくて、ただの補給行為。
ハムとレタスとパン。あの時の私はそればかり食べていた。
*
怒濤の三ヶ月が過ぎると、少しだけ気持ちに余裕が出てきた。もしかしたら少し、産後うつのような状態だったのかもしれないと思えたのはこの頃だ。
だってよく考えてみたら、食事がサンドイッチである必然性はない。パッケージを開けてもらったおにぎりと卵焼きとかでもなんとかなったはずだ。野菜だってレタス一枚より、デリで買ったおひたしやひじきサラダの方が栄養があっただろうに。
「とにかく死なせないのに精一杯で、視野が狭まりまくってたんだよねえ」
初めてできたママ友の「さとこちゃん」は、しみじみとそう言っていた。
「わかる。なんかもう、世界と違うところに隔離されたみたいな気がしてたよ」
この続きは、「別冊文藝春秋」11月号に掲載されています。