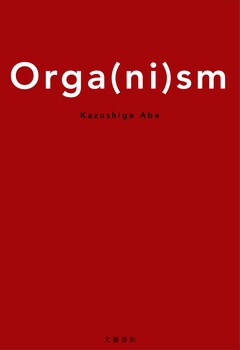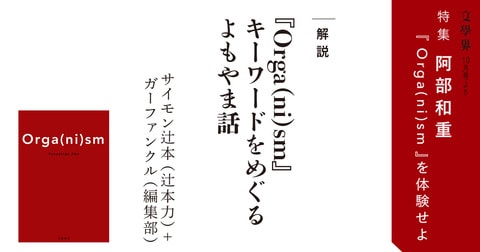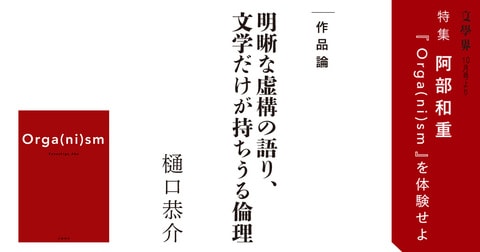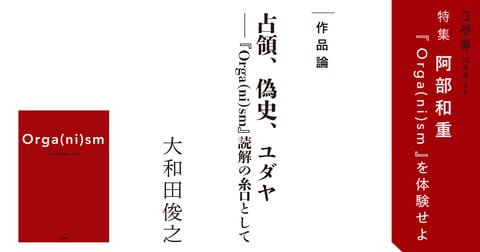住人がいっこうに出てこない。このまま待ったほうがいいのか判断に迷う。かなりの高齢者らしいから、単に反応が遅れているのかもしれない。
皇児は心をととのえ、コンクリートの門袖に設置されたインターホンのボタンをもういっぺん肘で押してみる。それでもやはり応答がない。居ねむりでもしているのか、あるいは老人ぽっくりいってしまったか。
風雨にさらされ水垢まみれになっているそのインターホンにはカメラ機能はない。骨董品みたいな旧型だからきっと録音もできない通話専用機なのだろう。ざっと門まわりを見まわしても防犯カメラなどは見あたらないから、ここにただつっ立っているだけなら姿や声が記録されることはまずなさそうだ。つまり呼びだしボタンに指紋を付着させさえしなければなんの痕跡も残さず立ちされるのだが、この異様な待ち時間がどうしようもなく不安をあおる。まさか警官到着までの時間かせぎか。
じつはだまされているのはこちら側で、すでに通報されてひそかに顔写真を撮られている可能性もあるのかと思いあたり、皇児はぞっとする。しょせんは年よりとなめてかかるや、逆に罠を仕かけてくるあくどいジジイやババアもいるというから要注意だ。現行犯なら痕跡があろうがなかろうが即逮捕連行にちがいない。だったらただちにここを離れたほうがよさそうだが、しかしそれはそれで面倒くさい問題にぶちあたる。受け子が手ぶらでもどるなど先輩らは絶対に許しちゃくれない。
警官と先輩、どちらにつめられるのがましかといえば前者だと皇児は確信している。こっぴどく追いこんでくるのは一緒だとしても、腐っても法の番人ではあるのだから警察の悪事にはどこかで歯どめがかかるはずだ。治安の悪いよその国ならともかく、取調室で未成年者に大金を請求したり半ごろしの目に遭わせたりする不正は日本じゃさすがに考えにくい。が、法の外ならなんだってありうる。とりそこねた額のでかさによっては半ごろし程度の処分じゃ済まないかもしれない。まだ一七になったばかりで海外に行ったこともないのに海底に沈められたくはない。
だからとにかく手ぶらでは帰れない。念のため指示を再確認してみると、表札も住所表示もメモにあるとおりだから訪問先をまちがえたわけではないとわかる。じれた皇児は屋内の状況を調べずにはいられなくなり、敷地内への侵入をはかる。もしもババアがのんきにうたた寝でもしてやがったら蹴飛ばしてたたき起こしてやりたいところだ。
指紋がつかぬよう肘を使ってアルミの門扉をそっと開ける。つづいて山野みたいに草木が生いしげるアプローチを歩いてゆくと玄関ドアが見えてくるが、さらにその奥へ進むと雑草だらけの庭がひろがっている。ひとり暮らしの老人があるとき急におっくうになって手いれをすっかりあきらめてしまったかのように、どこもかしこも自然にまかせているという感じの裏庭だ。
それが住人の趣味なのかどうかはさだかでないが、敷地がこんな荒れ放題で築五〇年はいっちゃってそうな古ぼけた一軒家に数千万円分もの札束が保管されているとはとても思えない。ひょっとして植木屋を呼ぶ金もない家なのではないか。あのボロ家にはタンス預金がたんまり眠っていると知らせたのは、美人局にはまって命ごいしてきた保険屋のおっさんだ――あいつの出まかせにみんなしておどらされてしまっているんじゃないかとにわかに疑わしく感じられてくる。
しかしあいつは単にドスケベなだけのおっさんでしかない。海底旅行どころか生きたまま豚の餌にするぞと先輩らから脅されているというのに、わざわざ自分の首を絞めるような噓をぺらぺらとまくしたてるだろうか――などと思案するうち、家畜が人肉を食らう血みどろの惨劇を想像してしまい、たちまち吐き気をもよおした皇児は必死に口をむすんで未消化物の逆流を気合で封じこめる。