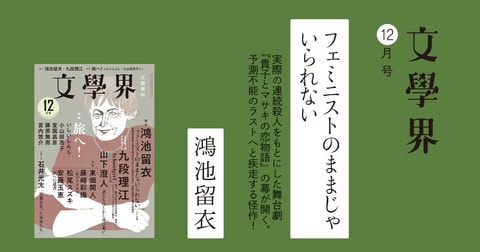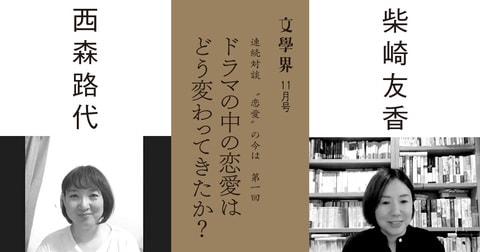夢だ。私は夢を見ている。
私は自宅のキッチンに立っている。調理台にはたくさんの食材が置かれている。普通、家庭では扱わないような巨大な肉の塊。同じ方向に寝かされた、これまた手に余るサイズの魚が数十種類。野菜や果物、缶詰だとか調味料の瓶まで揃っているけれど、どれもこれも実際よりひとまわりずつ大きい。これから何を作ろうか? 豊富な選択肢を前にして戸惑いながらも、どの材料を選び、どこの部分を切り取り、何と何を組み合わせれば娘がもっとも喜ぶかを考えている。そこに娘が帰ってくるのだが、その変わり果てた姿を認めて、私はもう料理どころではなくなってしまう。娘の体は、まるで途中で描くのをやめたデッサンみたいに、あるべきものが少しずつ欠けているのだ。左目のおさまっていた場所が空洞になっていたり、右の耳がなくなったりしている。左腕がなく、腕のバランスを補うようにして右足がない。
娘は半分になっている。ある法則のもとで半分に。夢の中で私は妙に物わかりがよい。頭はこの上なく冴えている。半分の娘の法則。つまり二つ備わっている臓器についてはその片方がもれなく失われているということを、私はすでに知っている。同時にこれは夢で、現実ではないのだともわかっている。それでいてなお夢が終わらない。夢。これは夢。絶対に夢だ。眠っている自分をたたき起こすつもりで、何度も夢を見ていることを知らせようとする。けれど夢のほうではまったく聞く耳をもたず、私に異様な夢を見せ続ける。目が覚めない。
不可解な状況にあって私は不自然なほど冷静に、娘を元に戻すためのスイッチか何かを探す。そこに並べられたありとあらゆる種類の食材をかき分けながら、探しものを求めて目を動かしていると、「中の臓器もそれぞれひとつずつになっています」と頭上から機械による解説の声。「腎臓は半分です。卵巣は半分です。血液は半分です。骨髄液は半分です」娘はアプリで彩度を加工したような青白い顔に、硬い笑顔を口元に浮かべて言う。「ただいまお母さん」
目が覚める。娘がいなくなる。
あさ、眼をさますときの気持は、面白い。
昔々あるところに私はいて、目が覚めるとそんなふうに、朝の気分について話していた。小さいころはなんでも話せる仲の良い女友達がいたから、いつもその子を相手に延々と、心にひっきりなしに浮かんでくる考えを、空っぽになるまで喋り続けたものだ。お父さんがいないことで、すぐに泣きたくなってしまうという話。でも私には大事なお母さんがいて、お母さんにいろいろなことをしてあげたいと思っている話。それから顔の嫌なところ、誰にも知られたくない自分のずるさ、下着の刺繍のことまで、私は彼女に何から何まで教えた。彼女もまた私にそうした。私たちのあいだに秘密はなかった。ちょうど起きたばかりで、体がまだ形をとらずにぬるい毛布と溶けているとき、とくにグロテスクな夢を見た朝などは積極的に、あのころ喋ったとりとめのない話を取り出す。そうして全身をすみずみ遠い記憶に浸して、このまま親しかったあの子を思いながら、もういちど眠りたい。今なら引き返せる。まだ、ドアを開けて光がわずかに入ってきているだけで、外に踏み出していないもの。境界線の上で目隠しをして、爪先で立っているだけだから、ほんのささいな風、蝶の羽ばたきほどの空気のふるえで、軽々こちら側へよろけて、夢の中へ落っこちて、そうすれば今度はきっと、よい夢を見られる気がする。ほかの考えは一切忘れて、朝がおもしろかったころの楽しい気持ちだけ、頭の裏側から引っ張りだす。私はこう言った。朝は灰色で、日の光にあてられるとなんともいえず、照れくさいのだと言った。するとあの子はちゃんと私のことを、まるごとわかってくれたのだった。そう、箱を開けると箱の中に、箱があるんだよね? 箱、箱、また箱。それが何度か続くけれど、最後には何もない、空っぽなの。箱の話をしたのはどっちだろう? 箱の次は虚無の話。虚無。虚無は、彼女のほうから言い出したはず。虚無のあとは眼鏡の話。眼鏡の話は目の話になって、それで、……それで?