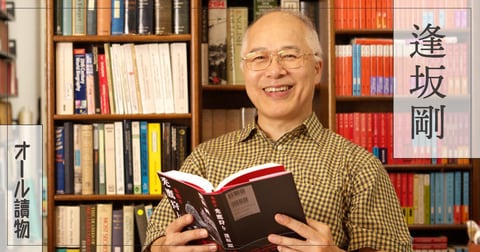事件の「捜査」が主役の警察小説
シリアスな捜査小説で真っ先に上がるのが髙村薫『マークスの山』だろう。
合田雄一郎警部補が所属する警視庁捜査一課七係は、目黒区で起きた殺人事件の捜査にあたることになる。なぜ落魄した元ヤクザが、閑静な高級住宅地で殺されたのか。それから間もなく北区の公務員住宅付近で、住人の法務省高級官僚が殺される。同じ凶器が使われたことが判明し連続殺人の疑いが濃厚になるが、捜査は難航する。
髙村作品の中心キャラクターである合田雄一郎が初登場した作品だ。精神を病んだ殺人者マークスの視点によるパート以外は、ほぼすべて合田視点で、リアルで詳細な捜査の過程が描かれる。「動物園」と喩(たと)えられる七係にふさわしく、喧嘩腰の捜査会議は大荒れになることが多い。それというのも情報の抱え込みや抜け駆けが当たり前だとどの刑事も思っているからだ。七係の同僚に対してもそうなのであるから、他の刑事に対しては言うまでもない。組織捜査でありながら、基本は個人技、一匹狼の世界であり、油断していると寝首を掻かれかねないのだ。横軸の中央に位置しているのはそういうことである。
横山秀夫の『第三の時効』(03年)も捜査小説の極北と呼べる連作短編集だ。緻密な捜査で知られ、決して笑わない「青鬼」朽木の一係。公安出身で上司も部下も眼中になく、単独捜査も厭わない「冷血」楠見の二係。常人にない天性のひらめきで事件の筋を見通す「捜査の天才」村瀬の三係。個性豊かで優秀な三人の係長たちで構成されているのが、F県警捜査第一課なのだ。そして本書は作者が手がけた最初の捜査小説でもある。常勝集団と畏れられる3人の係長は、部下を手足の如く使いながらも、自分以外は決して信用していない。事件で食ってきたのではなく、事件を食って生きてきた3人それぞれの物語は、実に濃密で圧倒される。
そんな捜査会議の場に身を置いたら失神してしまいそうなのが、川崎草志『署長・田中健一の憂鬱』(15年)の主人公だ。四国の小さな町の所轄署に赴任した田中健一は三十代半ば。東大から公務員Ⅰ種試験に合格し、うっかり入庁してしまったキャリア警察官だ。警察官の鋭い視線が怖くてならず、地元の市役所にでも就職すれば良かったと、捜査会議があるたびに後悔に駆られる弱虫キャラなのだ。決裁印を押すのが仕事のお飾り署長と割り切り、趣味のプラモデルのことしか頭にない。ところがうっかり口から漏れてしまったプラモデル作成に関わる悩みを、勝手に部下たちが曲解した結果、それが事件解決の糸口となってしまうのだ。さらに偶然も重なり、署長自ら身体を張る羽目にもなってしまうという、謎解きの妙もある楽しいシチュエーションコメディなのだ。