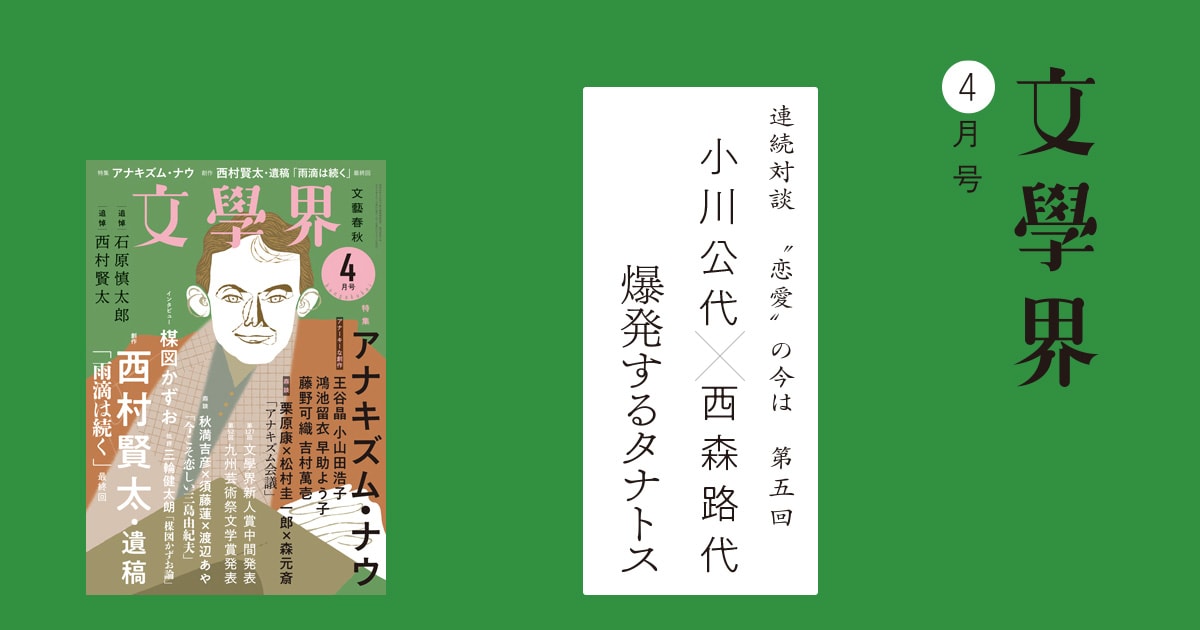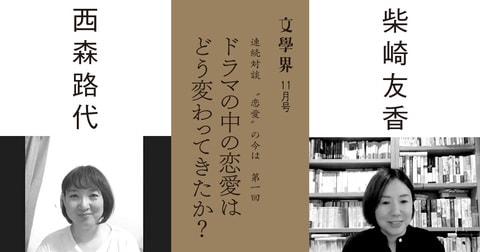恋愛の描き方を主軸にドラマや映画を語りつくすノンストップ対談、後編はキャラクターの暴力性と、時にそれに共鳴するわれわれの心について。
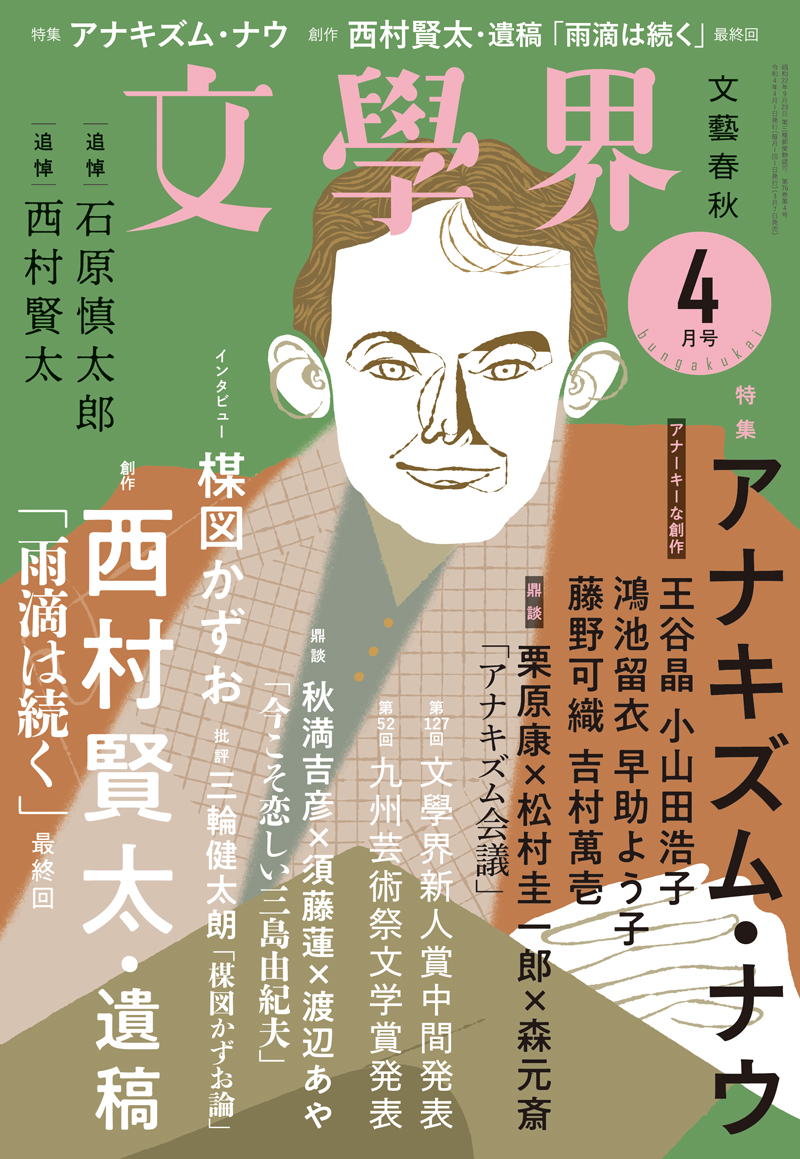
■『イカゲーム』ドクスとは何者か
小川 前回、フィクションとか嘘が現実を作っていくんだという話をしていた中で、平野啓一郎さんの『マチネの終わりに』を思い出したんですよね。蒔野聡史という天才ギタリストと海外で活躍する小峰洋子という知的な記者との恋愛なんて、現実にはほぼないと思うんですけど、『愛の不時着』にしても私はそういうものには憧れの気持ちがあるのかなって。
西森 ないことだからこそ、その世界の話に関心が湧くんですね。人によってどういうお話に惹かれるかっていうのはいろいろ違いがありそうですね。
小川 自分の世界の中ではありえないし、それこそが「おとぎ話」じゃないですか。そういう意味で『マチネ』の中でも、洋子は、戦争の暴力の中心に身を置いて「どうすれば、イラクの現実とヨーロッパの日常を生きる人たちの頭の中とを媒介できるか」というジャーナリストの使命について真剣に考えている。こういう理想像を作るという作業を丁寧にしているんですよね。しかも、蒔野と洋子というふたりの異性愛の話ではあるんですけど、最終的には行き違いがあって結婚しない。洋子は新自由主義的なアメリカ人のリチャードと結婚するんですが、子どもが生まれた後にリチャードという夫が、リーマンショックの一連の大騒ぎを起こしてしまった業界と癒着し、知らないフリをしていたうちの一人だということを知るんです。彼は完全に新自由主義な価値にどっぷり浸かっていたんですね。
西森 自分のやったことを振り返ったりしないんですか。
小川 逆に「洋子、お前は何を言ってるんだ。これは「幸せになるための新しい科学」なんだよ」って言うんですね。心は離れていくけれど、ふたりの間に子供がいて、そこは「おとぎ話」ではなく紛れもない現実なんですね。そこで洋子は「我慢して夫と生きていくしかない」とは思わない。「この人といては駄目だ」と考えるんです。そこにヘレンという女性が現れて、リチャードと不倫をする。でも洋子は「このふたりは恋愛に陶酔する似た者同士で、お似合いだ」と考える。
西森 そういう意味での、お似合いってのは確かにありますね。
小川 C・S・ルイスが『四つの愛』という本を書いていて、友情(Friendship)、聖愛(Charity)、恋愛(Eros)、それからもう一つが母親の愛情(Affection)なんですね。ルイスはその中でエロスが一番厄介で、それはオーウェルの主人公ウィンストン(『一九八四年』)がしてしまうことなんですけど性的欲望と混同してしまう。ルイスは本来の「エロス」は相手を愛することだというんですね。目指すのは、友情だと言ってるんです。欲望からも、義務からも自由なので。もちろんホモソーシャルで排他的になることには慎重になるべきですけど。結局、蒔野と小峰洋子の間に築き上げられていくものは、価値観を共有する同志みたいな関係性だから、結婚というかたちでは成就しないんですよね。そこをすごいきっちり描いていたんです。反対に、ヘレンとリチャードが……。
西森 それはもう勝手にお幸せにどうぞっていう。
小川 本当に。でも、細かく描いてくれているからこそ分かるヘレンの嫌な面なんですよね。彼女は本質主義的で、「男ってみんなこうだよね」と言ってしまったり。洋子はそういうとき、「そんなことないでしょう。男の人だからといって必ずそうじゃないよね」と言うわけです。だから、価値観で結ばれる人というのは、ルイスの『四つの愛』で言うと友情であって、恋愛に落ちる人は、恋愛に陶酔してしまう人。『愛の不時着』で言うとユン・セリの家の長男夫婦なんですよ。長男の妻って元女優で、いつも外見を気にしてバッチリメイクしていて相手の不幸を祈っているという。私、それを見ながら「あっ、『マチネの終わりに』のヘレンだ」と思ったんですよ。平野啓一郎さんは人間の負の側面を描きながらも、やっぱりここに向かいたいという理想をきっちり書きたい人だと思うんですね。野木亜紀子さんも大事にしておられるんじゃないかなって。そういう姿勢を私は尊敬するんですよね。