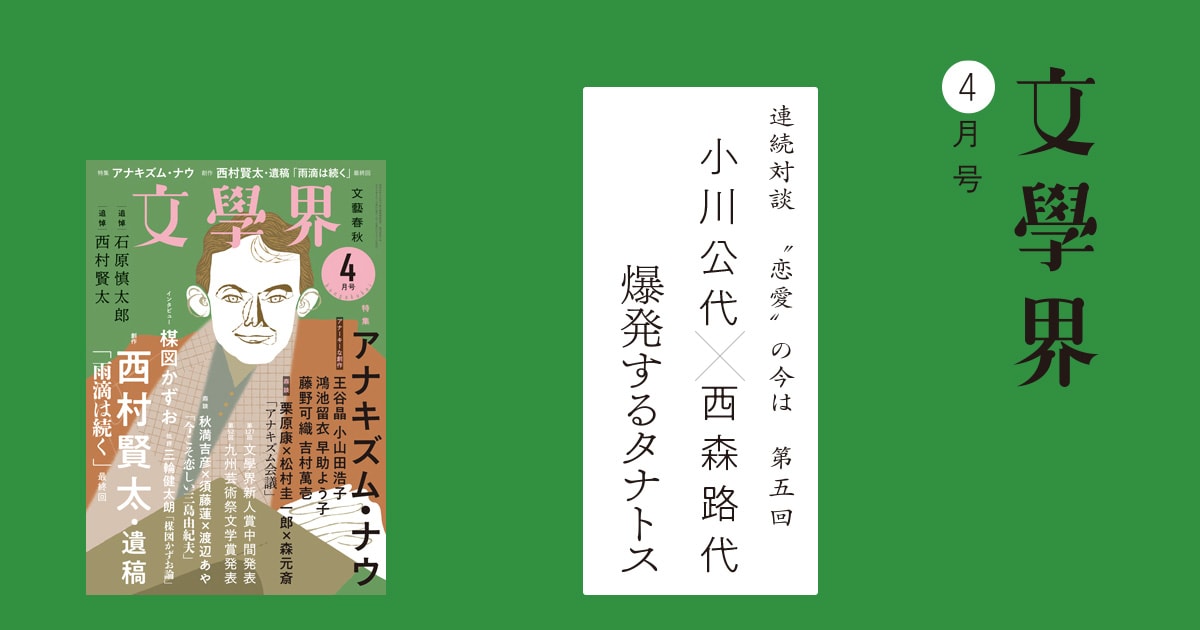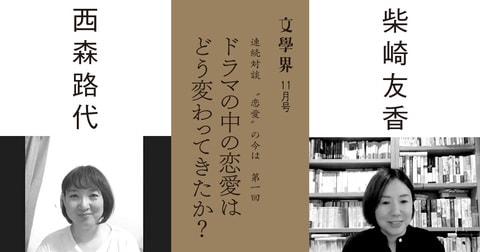西森 確かに、『MIU404』では、ベトナム人留学生のことなんかも現実のままならなさを描きながら、それでも、このままではいけない、それにはどうしたらいいのかということにたどり着いていました。それと、『逃げるは恥だが役に立つ』も『MIU404』も、プロデューサー、脚本家が女性で、『逃げ恥』は原作者も女性、『MIU404』は演出家が女性で、すごく意思疎通をとりながら、納得のいくものを作って、その上で結果を出してきたんですよね。
小川 そういうこともあったんですね。『逃げ恥』と『愛の不時着』にも共通点があるとしたら、ヴィランが効いているなと思いました。『逃げ恥』はそこまで分かりやすい人は出てこないんですけど、『愛の不時着』には曖昧性のないザ・悪漢がいるじゃないですか。例えば、チョルガンっていう、裏では犯罪を重ねながら、主人公たちをいじめ抜く人が。野心のためならどんなこともやってしまうという。ああいうキャラクターが一人いるだけでリアルになりますよね。私はタナトス的なキャラクターと呼んでるんです。『イカゲーム』にも出てきますよね。
西森 ドクスというキャラクターですね。
小川 西森さんがハン・トンヒョンさんとWEZZYでやっていた対談を読んで、ドクスとミニョという女性について話されている部分が面白いなと思ってたんです。
西森 ミニョがデスゲームの中で生き残るためにドクスと関係を持ったり、彼と一緒に身を投げるシーンについて、納得がいかないと話してたところですね。
小川 そういうキャラクターってジェーン・オースティンの作品にも出てくるんです。古典的な配置といいますか。オースティンの作品って、必ずヴィランがいたり、自分のセクシャリティをアピールする女性登場人物も出てくる。『高慢と偏見』にも、ダーシーにぞっこんのキャロライン・ビングリーという女性キャラクターが出てくるんですが、欲しいものを手に入れようとして必死なミニョと一緒なんですよ。古いとはいえ、必要なキャラクターなのかもしれない。
西森 ただ、最近はヴィランにも背景があったりすることが多いし、ミニョみたいな人も、どういう心理の上で行動しているのか、わかるようになってる気はしますね。日本では、あからさまなヴィランは描きにくくなっていて、ヴィランの背景も描くことが多いし、妙にリアルなのになぜそんな行動をしているかわからないヴィランに混乱するかのどっちかが多い気もします。ミニョとかドクスとかチョルガンみたいなはっきりしたキャラクターを見るのは、やっぱり現時点では韓国のものが多いし、それがやっぱり新鮮なのかもしれません。
小川 日本でもうあんまり出てこなくなっちゃいましたね。
西森 そうですよね。わりと誰も悪くない世界になりつつあるので、あからさまに悪い人とかあからさまに男性目線を内面化した女性みたいなものは出てきにくくなってますね。
小川 『愛の不時着』に出てくる婚約者のダンさんは、そんなに悪い人じゃなかったし、ミニョ的でもなかった。
西森 そうですね。そういう変化は韓国にももちろんあると思います。ヒロインに意地悪するだけの、あからさまな恋のライバル、みたいなものは減っているとは思いますね。あと、やっぱり私とハンさんがミニョにモノ申したのは、そういうキャラは昨今少なくなっているし、もう十分そんなことはわかってる、みたいなところもあったのかなと思います。ミニョとドクスが身を投げるシーンはどう見られましたか?
小川 ガラスの上を渡るシーンで落ちていくところですね。ミニョがドクスをガッチリ抱き込んで「離さない」っていう。あそこは、迫真の演技だと思いました。そこまでして……。
西森 負の執着があるというか。
小川 そうなんです。人間の執着が描かれていて。私には説得力がありました。ミニョなりの人生哲学があって、本当に地獄に落ちるという、芥川龍之介の世界じゃないけど、垂直に落ちていく演出に私は「なるほどな」と思ったんです。
西森 単に自分には関係ないとしてドクスだけを突き落とすこともできるけれど、自分も一緒に落ちることに、確かに、より激しい怒りを感じるということはあるかもしれないですね。自分で落とし前をつけるしかない、みたいな。昔から韓国ドラマでは、因果応報のテーマがけっこう多いので、悪いことをしたら、やっぱり報いがあるべきだってことは強いんですよね。
おがわ・きみよ●上智大学外国語学部教授。1972年生まれ。『ケアの倫理とエンパワメント』『文学とアダプテーションII ヨーロッパの古典を読む』(共編)など。
にしもり・みちよ●ライター。1972年生まれ。『韓国映画・ドラマ わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』(ハン・トンヒョンとの共著)など。
構成●西森路代 撮影●深野未季
この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。