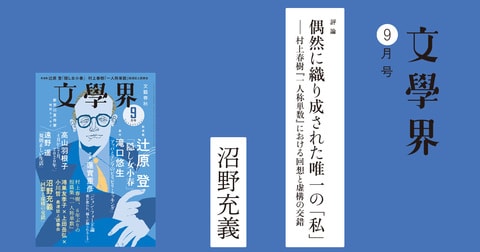■テキストの再発見

野崎 これは主人公の妻・音の「声」がずっと響き続ける映画で、見ている側もその声に呪縛されます。しかもそこにテキストの新発見といいたくなるような体験が加わる。つまり、村上春樹とともに、チェーホフのイメージも映画によって一新させられる。「ワーニャ伯父さん」の台詞がここまで新鮮に響くとは驚きでした。
濱口 「ワーニャ伯父さん」は以前に演劇で観ていたし、戯曲を読んでもいたんですが、主人公・家福が口にする言葉として今回読み直すことで再発見していく機会になりました。通常上演される「ワーニャ伯父さん」では、百年以上前のロシアの風俗がときに障壁になり、「まさに今『お芝居』を見ている」という感覚からなかなか抜け出せなかったりする。ところが戯曲の一部を抜粋したときに、すべての人に当てはまる普遍性が立ち上がる。そういう力強いテキストをチェーホフは書いていたんだと感じました。
野崎 西島さん演じる家福は、妻に吹き込んでもらった「ワーニャ伯父さん」の台詞のカセットテープを車の中で繰り返し聞いて練習しますが、ああいう台詞の覚え方は俳優さんたちにとっては一般的なんですか?
濱口 僕もよくは知らないんですが、タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)でもレオナルド・ディカプリオ演じる主人公がカセットの録音を聴きながら台詞の練習をしていたので、そういうこともあるんだろうなと。
野崎 ただ家福は自分で運転しながらカセットに合わせてしゃべっていて、見ていてけっこう危なっかしい(笑)。そして案の定、事故を起こしもする。彼は一種、「取り憑かれた男」とも言えますね。妻の声に取り憑かれ、同時にそれがチェーホフを生き直すことにもなる。台詞を絶えず流していることで、妻が亡き後もあの車が彼にとって一種の寝室、親密さの空間になる。その親密さを侵す人間が現れたとき、映画は動き出すんですね。
■「キアロスタミができる」
野崎 どこまでが村上さんの小説にある要素でどこからが映画オリジナルなのか区分けが難しいくらい、緊密なアンサンブルの映画になっているという感じがしました。原作にも車の中で家福が台詞の練習をする描写がありましたが、それだけではなくベートーベンの弦楽四重奏を流したり、もう少しノーマルな車内生活を送っている。
濱口 そうですね。実は『ドライブ・マイ・カー』の企画が決まってまず思ったのは、恥ずかしながら、これはアッバス・キアロスタミができるんじゃないか、ということだったんです。
野崎 なるほど、『そして人生はつづく』(92)から最後の『ライク・サムワン・イン・ラブ』(2012)まで、キアロスタミにはいろいろと自動車映画の傑作がありますね。
濱口 はい。自動車の中で人がしゃべり、風景の中を車が移動している際も言葉が響く。その言葉とともに車を追っていくと風景の見え方が変わったりもする。言葉と移動が常に一緒にあるイメージが初めからありました。以前東北で記録映画を作っていたときも、取材時に車で移動しながら、この閉鎖された移動空間だから話せることがあるという感覚を持ったんですね。誰もが同じ方向に向かっていて目線は合っていない。その空間だからこそ紡ぎ出されてくる言葉がある。車を降りて同じ人と一緒に家に帰って話しても、もう全然違う言葉になっている。
野崎 村上さんの小説では家福が乗るのは黄色いコンバーチブルです。これを赤い車に変えたのはなぜなんでしょうか。
濱口 車の中でしゃべる映画になることは明らかだったので、同録の音が使える車というのが大前提で、そうすると原作のようなオープンカーでは無理だと判断しました。またキアロスタミの映画のように引いた視点で車が街中を走っていくのを撮ったときに黄色は意外と風景に埋もれるような気がして。
野崎 サンルーフはどこから来たんですか? これがとても印象的な場面につながっていましたよね。
濱口 お願いしていた劇用車会社の方に色々候補をあげてもらい、まずはサーブを見に行きましょうという話になり行ってみたところ、社長さんが乗ってきたのがこの赤いサーブだったんです。すごく使い込まれ、大事にされている感じで、これはかっこいいぞとすぐに決まりました。その車にサンルーフがついていたんです。
野崎 赤いサンルーフ車が濱口さんの前に忽然として現れたわけなんですね。それを生かそうということで、家福と、三浦透子演じる女性ドライバーみさきとの、あのシーンにつながったわけですね。
濱口 ええ、せっかく開くなら使おうということで。
■長いアバンタイトル
野崎 中盤から後半にかけてこの赤い車の存在感がどんどん増していきますが、その前に場所が変わります。四十分ほど経ったころでしょうか、物語中で二年が経ち、東京から広島へ舞台が移り、そこで初めてタイトルが出る。あれが何とも、かっこいい(笑)。なるほど、ここまでがアバンタイトルだったのかと驚きました。タイトルが出た瞬間の“やられた感”は映画の醍醐味の一つだとさえ思います。タイトルの登場に驚かされた映画として忘れがたい作品に、『アマル・アクバル・アンソニー』(77)という、インドのスター、アミターブ・バッチャン主演の名作がありました。ヒンドゥー教、キリスト教、イスラムの三人の男たちが力を合わせて悪者を倒す壮大な娯楽篇なんですが、一時間たったところで三人がようやく出揃い、タイトルがバーンと出る。あれは興奮しました。ただ、インド映画研究家の松岡環さんに「あのくらいはインド映画では普通です」と言われてしまいましたが(笑)。濱口作品にはそういうケレン味の面白さもあるんです。『ドライブ・マイ・カー』はそこまででも十分濃密なドラマがあったのに、「またここから始まるんだ」と仕切り直す感じで嬉しくなりました。