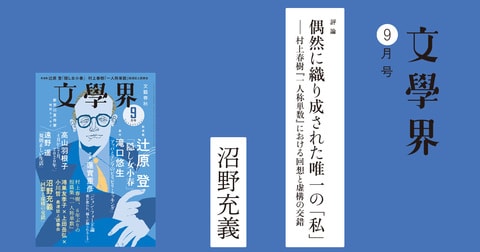■演出とは何か
野崎 演劇ができあがっていくところを映すことが、映画作りの安易なメタファーなどではない、それ自体が濱口さんの映画なんだということがよくわかりました。同時に、このルノワール=濱口メソッドが役者にどんな反応を引き起こすかも興味深く描かれていますね。本読みの最中、台湾から来た俳優ジャニス(ソニア・ユアン)が「私たちはロボットじゃありません」と言う場面があります。その気持ちもよくわかるわけです。見ていると、家福は表情のない発話を全員に対し均等に求めているように見えて、どうも高槻(岡田将生)という俳優への指導がとくに厳しい気がする。そこから家福の心理的葛藤が浮かび上がってくる。
濱口 やはり本読みやリハーサルをしているだけでは観客が楽しめないでしょう。いろんな気持ちが混在しているのが実際の稽古場だとも思います。みなプロフェッショナルに仕事をしている一方で、彼らだって感情を持ってやっている。その感情が抑えきれないようなこともある。そうしたいろんな要素を入れた結果、あの稽古場のシーンが出来上がっていきました。
野崎 ルノワールの「イタリア式本読み」はあくまで準備段階で、そこからどういうふうに役を作っていくかが重要なわけですよね。映画では、ジャニスとユナ(パク・ユリム)の女性二人が公園で演じる非常に美しいシーンがある。「今、何かが起こった」とその場にいるみんなが言いあい、見ているその気持ちをこちらも共有しながら、演出とは一種の神秘だという気持ちになってくる。
濱口 神秘的な演出のマジックにより何かが生まれた、という表現になっていますし、たしかに何かとてもよいものが映ったような気はするんですが、もちろん実際はそう簡単には出来上がりません。何度もリハーサルを重ね、ひたすら準備と仕込みを重ねた結果なんです。
野崎 その準備と仕込みが画面を重層的に支えている。同時に、濱口さんの作品には、映画において演出がどうあるべきかは、なお未知の領域なのであって、それを改めてまっさらな気持ちで開拓していかなければいけないという覚悟が感じられるんです。それが毎回、濱口作品に新たな息吹を与えている。考えてみると、演劇においても、演出家という存在は案外歴史が浅く、リアリズムの登場と並行して生まれた、要するに近代の産物じゃないでしょうか。モリエールやラシーヌの時代には演出家は存在せず、座付き作家が俳優に自分の考えを伝えて演じさせていたわけですから。それだけに、演出家がどういう力をふるうべきなのか、あるいはどういう権利をもっているのか、実は誰もよくわかっていないのかもしれない。その点が今、改めて問われている。『ドライブ・マイ・カー』はそれを根本から考えさせてくれる映画だと思います。
先ほどのジャニスという女性が家福に、「指示してくれればもっと上手に演じられます」と言いますね。俳優は常に演出家の指示を待っていて、指示にあわせてうまくできれば達成感を得られる。ところが家福は「うまくやってもらう必要はない」と言う。本当に重要なポイントはそこにはないのだと。そういうやりとりをとおして、演出や演技指導というものが刻んできた歴史が捉え返されている気がします。
映画の演出をめぐっては、統一した見解というのがあるわけではまったくなく、それどころか正反対の立場がありうるわけですね。ハリウッドで映画監督の地位が確立されたころの名匠を例にとれば、エルンスト・ルビッチは全俳優の役柄を手取り足取り、全て自分で演じてみせて、完璧なディレクションをした。ところが同時代のもう一人の名匠であるフランク・ボーゼージの場合はまったく逆で、カメラの位置を決めたらあとは「アクション」の声と同時に俳優に背中を向けて葉巻をふかしていた。とまあ伝説的に言われています(笑)。でもその結果、ボーゼージは『第七天国』(27)などの名作を撮っている。だから演出というのは何が正解なのか、やっぱりよくわからない。そういうなかで濱口さんは自分のロジックと現場を結び付け、さらにそこで立ち上がってくる演出家と俳優の関係自体から豊かなドラマを引き出している。有名監督にまつわる逸話としてのみ伝えられてきた、演出をめぐる神話の内実を正面から見据えて、そこに映画にとって実に面白いテーマを発見したのだと思います。
■車内での対話シーン
野崎 後半、「ワーニャ伯父さん」の上演が果たして無事行われるのかという危機的状況が立ち上がります。転機になるのが家福と高槻の車内での対話シーンです。そもそも高槻だけですよね、何回も車の窓を叩いて、あの親密な空間を揺るがそうとするのは。彼が長台詞を語るシーンに異様な迫力があります。あのとき、二人の俳優さんは正面を向いていますね。
濱口 はい、カメラをまっすぐ見ている状態です。
野崎 濱口さんの映画は、真正面からのショットがひとつのトレードマークになっていますが、それにしてもあのクロースアップにはやられました。まったく別のコミュニケーションが成り立ってしまったかのような臨場感がある。

濱口 自分で撮っていても驚きました。あの場面はそれこそ異界を感じる瞬間でした。
野崎 正面のショットが持つ、何かを超えていく力が現れたシーンだったと思います。しかも運転席にはみさきがいる。さまざまな三角関係がこの映画を引っ張っていきますが、このシーンでみさきの担う役割が一気に重要になるんですね。各人のあいだに、そして彼らとわれわれ観客のあいだに、ただならぬ出来事が起こっている。しかもそれが滑らかに走る車の中で起きている。ここから、キアロスタミを凌ぐかというゾクゾクする展開になります。
濱口 家福と高槻の対話シーンは、おっしゃったように、みさきが運転席で聞いていることがとても大事でした。原作と違い、家福と高槻は、バーでは決してああいうふうには話さない。彼女が聞いていることが、あの二人にドライブをかけている部分がきっとある。また二人のあの話を聞くことによって、みさきの物語内での地位も特権的なものになってくる。そうすることで、後に行われる家福とみさきのドライブがそれまでとは何か違うものを共有しているように見える。そうなってくれたらよいなと考えていました。
野崎 車内で聴いていたカセットテープもこの場面以降使われなくなり、それまで後部座席に座っていた家福が助手席に並んで座るようになる。そういう変化があの二人の間で起こっていくわけですね。