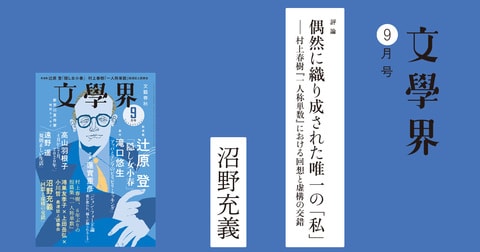濱口 深い考えがあったわけではないんですが、やはりそこまでの部分は、実際タイトルは最後まで出ませんがアバンタイトルだということになるでしょうか。原作に書かれていない部分だし。ちなみに、前半部分がなかったら二時間二十分ぐらいのごく一般的なサイズに収まっていたわけです(笑)。
僕としては冒頭シーンと同様、「ここから全く違う話を始めます」と観客に対し宣言する意味合いがありました。新たにいろんな人物が登場しますし、中盤に来て人間関係を一から拾っていくのは観客としてはなかなか大変でもある。タイトルが出たあと二分間くらい音楽と風景の流れに身を委ねる。この移動の感覚に身を任せつつ、ここから新たに始まる物語を見る態勢を整えていただきたいなと。けっこう観客にとって負荷の高い物語展開をしている自覚はあったので、「ちょっとお休みください」という感じでしょうか。
■俳優を選ぶ
野崎 広島の演劇祭に家福が招待され、かなりの稽古時間をかけてチェーホフの劇を練習していく。ここで重要になるのが、家福が車の運転を禁じられることです。ドライバーのみさきが親密な閉鎖空間に割り込んでくる形になって、家福は露骨に嫌な顔をする。サスペンスが生まれますが、絶妙な運転技術をもつ女性運転手をどう造形するか、アイデアは早くからあったんですか?
濱口 人物造形は姿かたちとアクションから生まれますが、姿かたちはもうキャスティングで決めるしかない。みさき役の三浦透子さんとは『偶然と想像』(2021年12月公開予定)という別の映画のキャスティングの際にお会いしました。『ドライブ・マイ・カー』も同時進行していて、みさきを誰が演じられるだろうかと考えていたところに彼女が現れ、「この人だ」と感じました。実は三浦さんは当時まだ車の免許を取っていなかったので、すぐにオファーして免許を取って特訓をしていただきました。僕は運転ができないので、どのようにうまくなっていったのかちょっと判断がつかないんですが、ひとつ言えるのは、とにかく「彼女は運転が巧そうな顔をしている」ということです(笑)。
野崎 実際は免許すら持っていなかったわけですね(笑)。しかも監督ご自身運転をしない。それにも関わらず名ドライバー役が誕生するんだから映画はすごい。演技指導うんぬんの以前に、俳優を選ぶ段階がすごく重要なんですね。
濱口 本当に七割八割方ここで決まってしまうと思います。
野崎 それを見極めるのは第一印象ですか?
濱口 お話をして「この人だ」と確信していく感じでしょうか。実を言うと、いろんな役者さんと話していて、ちゃんと話せた、という感覚になることがすごく少ないんですよ。逆に、話せたなと思えたらすなわち現場でもコミュニケーションができるということなので、そう思えた人には自然に任せられる。これまでの経験上、話せたな、と感じた方はやはり魅力的なことが多いですね。
野崎 役者の立場からすればなかなか話せないものでしょうね。そもそも監督と役者という人間関係には、非対称性があるわけですから。
濱口 ええ、それははっきりとあります。だからこっちも話してもらうために努力をします。そのとき、自分を曲げてこちらの正解を探ってしまう人がいる。「こういうことを言ってほしいのかしら」「こういうことを望んでいるのかしら」とこちらの意図を探られる感じで会話が進行していくと、お互いむなしい時間になってしまう。ですからまず役者さんに、自分を曲げる習慣がないことが望ましい。一方で我が強すぎるのも現場で困る。この二つの矛盾した側面を持っている人、つまり自分を曲げないけど相手とコミュニケーションが取れる人が魅力的な人だと思う。さらに、あるキャラクターを演じるのに造形的にふさわしいかどうかという要素も加わって、それらを総合して決めていくことになります。
野崎 濱口さんが映画作りの過程においても、また映画のテーマとしても、常に矛盾するものの共存を求めていることがよくわかりますね。その点においてとても頑固というか、妥協がない。この映画ではまさに、俳優と演出家の関係はどうあるべきか、そこで何が起こるのかということに物語がシフトしていく。「ワーニャ伯父さん」という戯曲に登場人物全員が正面から立ち向かっていくのが中盤以降の筋立てになっていきます。稽古風景が大切な要素になっていくのは濱口さんの映画を昔から見ている人間だと「いよいよ来たな」という感じですが、これは常に緊張や矛盾、謎をはらんだ要素でもあります。
演劇はどう作られていくか。それを描く部分に大変な迫力があるのは確かです。そこで何かが起こるんですね。ただそれはあくまでも映画内演劇であり、演劇が作られていく過程であって、映画自体がどう撮られていくかを描くことが、濱口さんにとって直接のテーマではないのだと思います。とすると、濱口さんがご自分の映画の中で演劇ができあがっていくプロセスを描くのは、映画製作のメタファーになっているのか。それとも演じるということ自体のうちに掘り下げるべき主題を見ていらっしゃるのか。
濱口 実際の映画作りの現場で、自分も家福が行っている本読みと近いことをやっているので、ここで描かれる演劇作りの過程と自分の映画作りが似ているのは間違いないです。ただ、演劇を映画作りのメタファーとして考えたことは基本的にありません。演じることを掘り下げたいというより、演技を仕事にしている人だったら僕にも撮れる、ということでしょうか。もちろん演劇の演技と映画の演技は違う。ただ、役者が日々の糧を得るためにやっている「仕事」として演技を撮ることはできる。出演者は全員俳優ですから、普段演じている身体をそのまま映画に持ち込めるわけです。たとえば漁師の役を演じるためには漁師の訓練をしなければいけないけれど、俳優の役であれば、自分の身体のまま仕事ができる。その事実をそのまま撮ることが映画にとっては力になるんじゃないか。