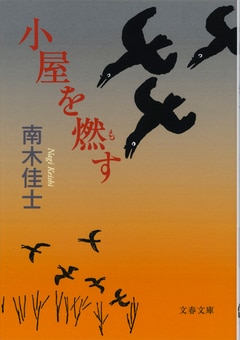氷河時代には厚さ千メートルもの氷で覆われていたという北米大陸北部の森林地帯、「ノースウッズ」。氷河が引いたあとの平らかな土地に、針葉樹林と無数の湖が形成されたこの大自然は、北欧フィンランドの湖水地方にも似て、穏やかで静かな気配に満ちている(本書を読み進めてゆくと、そうとは限らないことがわかってくるのだが)。
カナダとの国境に近いノースウッズの南端に、ムース湖がある。自動車でアクセスできる道路はここで行き止まり。大自然と人里の境界ともいえるこのエリアに、著名な自然写真家、ジム・ブランデンバーグが住んでいる。大学を卒業したばかりの大竹さんは、彼に会って弟子入り志願の気持ちを伝えようと、初めてのアメリカへの旅に出る。
一眼レフのカメラを買ったのはその前年。カメラ撮影の基礎は図書館で借りた本で学んだにすぎない。大胆というか無謀というか、分別のある人間の行動ではないかもしれない。しかし、二十代の前半の若者に分別がないからといって、それがなんだろう。だからこそ、こちらもおもわず膝をのりだすことになる。
覚えておきたいのは、これが一九九九年五月に始まる旅だということだ。私が初めてMacintosh Performa 6310を手に入れたのは一九九六年だった。立花隆の『インターネット探検』も同じ年の刊行。仕事では富士通の親指シフトのワープロを使っていたから、マックはお試し、遊び道具の範疇(はんちゅう)で、Eメールを始めたのは少し経ってからだった。インターネットは着実に広まりはじめていたが、アナログもしぶとく残る過渡期の時代だとおもう。大竹さんの一眼レフも、その場で確認できるデジタルではなく、現像に出さないとなにがどのように写っているかわからないフィルムカメラだった。
旅に出る数ヶ月前、大竹さんはジム・ブランデンバーグへの手紙を「ナショナル ジオグラフィック」気付で投函している。返信は来なかった。しかしそれは幸いなことだった。いまならメールを送って数日もしないうち「あいにく弟子は受け入れておりません」とシンプルなメールが事務所から届いて一巻の終わり、だったかもしれない。
つまり本書『そして、ぼくは旅に出た。はじまりの森 ノースウッズ』は書かれることなく、大竹さんが写真家にならなかった可能性もある──というのは言いすぎだとしても、異なる道をたどって写真家になったとすれば、二十年の歳月をかけた写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』(土門拳賞受賞)とは異なるテーマが選ばれていたかもしれない。この旅に与えられた経験がはかり知れないものであったことが、写真集の冒頭からわかるからだ。
ではこれはアナログの時代がもたらした幸運な旅でしかないのか。それはちがう。大竹さんの思考と行動の中心にあるものは、時代を超えて普遍的な価値をもつ。
それはたとえば、最短、最速を求めないこと。目的は明確でも、手段や方法を単純に効率化しない。ムース湖畔まで車道は通っているのだから、寄り道などせず車で直行し、ジム・ブランデンバーグを訪ねることも可能だった。しかし、そうはしなかった。
「あまりにも事を急ぎすぎている気がしたのです」と大竹さんは書いている。断られるのも怖い。目的地には着きたいけれど、すぐには着きたくない、と。
ことばを変えれば、「このまま会うのでは、なにかが足りない」ということだったかもしれない。経験が足りないのはしかたないとして、ジム・ブランデンバーグの住む「ノースウッズ」の自然を肌身で感じる時間が足りない。そう気づいたとき、この旅のなかで、もうひとつ別の旅がはじまったのだとおもう。
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。