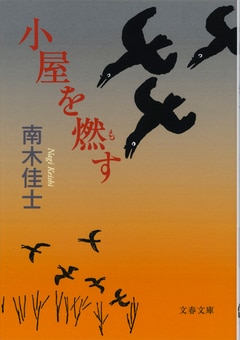ムース湖もふくまれる自然保護区「バウンダリー・ウォーターズ・カヌー・エリア・ウィルダネス」の湖面を移動しながら、遠回りのルートで目的地ムース湖に向かう。しかも、これまで「井の頭公園の貸しボートぐらい」しか漕いだことはないのに、カヌーを漕いでいこうというのだ。読者はここでふたたび、膝をのりだすことになる。
旅の出発点にあるアウトドア専門店で、カナディアン・カヌーとシーカヤックそれぞれの長所短所、湖と湖をつなぐ「連水陸路(ポーテッジ)」の意味と歩き方、宿営地に適した場所、食糧の匂いでクマをおびきよせない方法、さらに中古のカヤックを買っても旅が終われば売却できることなど、すべて実用的な助言を得る。質疑応答の小気味よさ。短時間でカヤックの漕ぎ方のレッスンまで受け、いよいよ湖から湖へと渡る旅がはじまる。
旅の詳細をここで繰り返してもしかたないだろう。カヤック初心者の八日間の旅は、読者がたったいまそれを経験しているような臨場感で進む。五感をすべてひらいた大竹さんの息づかい、鼓動を感じる。本書のなかで引用されるレイチェル・カーソンのことば「『知る』ことは『感じる』ことの半分も重要ではない」(『センス・オブ・ワンダー』)の実践だ。のちに引用されるトーマス・カーライルのことばも、大竹さんの旅の本質につながっている。「人生の悲劇とは、苦しむことではなく、見過ごしてしまうことだ」
初めて遭遇する名前さえ知らない水鳥、ルーン(ハシグロアビ)の、聞いたことのない突飛な鳴き声、予想外の潜水と浮上。耳を澄まし、何も見逃さない姿勢でその経験を伝えてくる。そして、穏やかだった水上の旅は途中で暗転する。おそろしい嵐に見舞われるのだ。天候が回復してしばらくのち、繁る草の陰で抱卵中のルーンに出会ったとき、「きっとぼくが震えながら過ごしたあの嵐の夜も、ここでじっと卵を温めつづけていたにちがいない」と想像する。本書でもっとも好きな場面のひとつだ。
湖に浮かぶ大小の島々には名前がついている。「アメリカ大陸に西洋人がやってくる以前は、どんな名前で呼ばれていたのだろう。いや、そもそも地名なんて必要だったのだろうか?」。あるいはまた、ムース湖に着いてあたりの「人里」を歩きはじめたとき、「私有地」「侵入禁止」の表示がそこここに掲(かか)げられているのを見て気圧(けお)される。ただそこにあるだけの自然「ノースウッズ」の価値は、人間が定めるものを超えて存在することにある。そう気づかせるのも、大竹さんの直感と観察力、ことばの力だ。
面会のかなったジム・ブランデンバーグは、自宅の敷地内にある小屋に大竹さんを滞在させ、写真を撮る者としてもっとも大切なことはなにかを伝え、敷地内で撮影する姿まで見せてくれる。大竹さんが撮った写真についても、予想外の感想を口にする。友人の極地探検家、ウィル・スティーガーにも紹介し、彼の小屋をしばらく借りて過ごせるよう計らい、大工仕事を手伝いながら写真を撮る特別な日々を整えてくれる。ことばのない世界から、ことばでつながる世界へ。さまざまな人間の考えと生き方から受ける刺戟(しげき)は、カヤックの旅に拮抗(きっこう)するなにかを、大竹さんに残したはずだ。
最後に、蛇足かもしれないことを書いておきたい(現在は二〇二二年三月八日)。
二十一世紀に入ってから、「結果を出す」という言い方をしばしば耳にするようになった。最初は誤用のたぐいと聞き流していたが、何度も耳にするうちに、人間だろうが経済だろうが思うように動かすことができる、という驚くべき思い込みが根本にあると感じるようになった。結果は「出る」ものであって、「出す」ものではない。大竹さんの稀有(けう)な旅の記録は、その大切さをあらためて伝えてくる。
新型コロナの感染はまだくすぶり、海外への旅はむずかしい状態がつづいている。止むなく国境を越え、逃れざるをえない戦争もはじまってしまった。かなわない旅とのぞまない旅の時間がふくらむなかで、自然のなかで生きる感覚が更新される旅のすばらしさを、読むことで想像してみよう。本書に描かれる旅の真価を知ることは、誰にとっても、小さくはない希望になるとおもう。