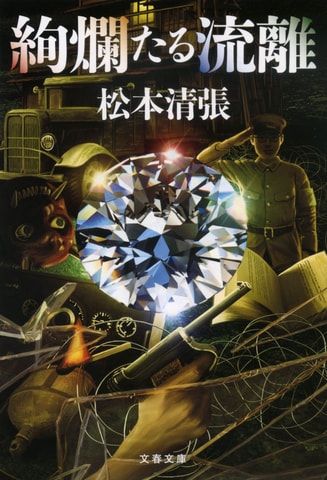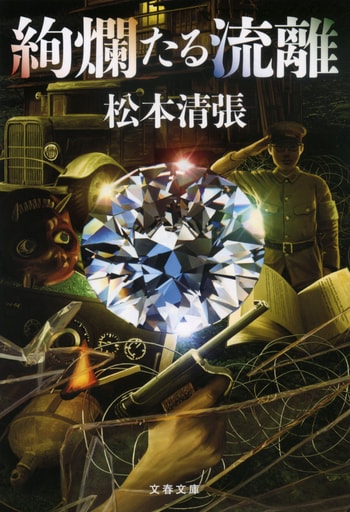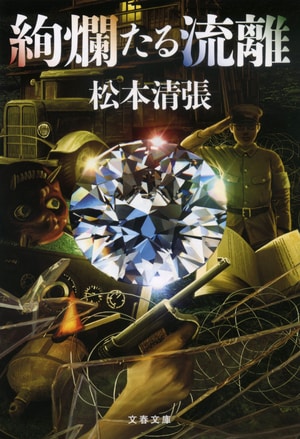
──私は小説ばかりを書いてきたので、随筆はあまりない。(中略)
それでも長い間にはいつか溜ってきて、こんど初めて出版するくらいの量に達した。この中には、随筆とは呼べないようなものもある。(中略)また、発表当時から時間が経っているので、当時の情勢と違う現象も起って、今は多少のズレにもなっているが、わざとそのままにしておいた箇所もある。時間の経過が窺えて、かえって興味があるからだ。──
これは、松本清張さんの第一エッセー集とも呼べる『黒い手帖』(中央公論社、一九六一年九月三十日刊)のあとがきの一部である。目次のタイトルは、「推理小説の魅力」「推理小説の発想」「現代の犯罪」「二つの推理」「推理小説の周辺」となっており、当時の清張さんの推理小説観を窺うための絶好の資料と言っていいだろう。
ことに、「推理小説の魅力」において、清張さんは、刺激的な表現を使って、大胆に自説を展開している。
──(広告会社の調査によると)コメディやメロドラマ、ホーム・ドラマなどよりもスリラー・ドラマのほうが女性にうけているという結果が出たというのである。
以前は、タンテイ小説というと女性読者にはあまり顧みられないものだった。それが近頃なぜ急に読まれだしたのか。
それは近ごろのロマン小説がつまらなくなったからであろう。いつも似たような筋の繰返し、同じような人物のシチュエーション、変りばえのせぬ背景、それらの氾濫にロマン小説の愛好者である女性読者が退屈し、本の途中からあくびをしはじめたからではあるまいか。その間隙を、ともかくもサスペンスがあり、謎があり、人間の知恵の争闘を主題にした推理小説が進出してきたのであろう。普通の小説があまりに一色(ひといろ)になりすぎたため、読者がその平板さに飽き、変った小説を手にとりはじめたという現象と言えないだろうか。──
さらに清張さんは、当時中間小説と呼ばれていたジャンルにも、攻撃の鉾(ほこ)を向ける。
──さて、中間小説という存在がある。それがどうも近頃はさっばり面白くない、というのが一般読者の声である。なぜかというと、中間小説というのは、大体、純文学畑の作家が、みずから調子を落して書く面白さを狙う小説だということになっている。だが、みずからを軽蔑したような、熱意のこもらない小説が面白かろうはずがない。(中略)中間小説が面白くない、という行詰りは、単にマンネリズムだけではなく、それを招いたのは書く者の不熱心と素質にかかっている。(中略)
一体「中間」小説と呼ぶ名前から変テコなものである。純文学と大衆文学の中間ということらしいが、文学にそんな曖昧な存在があるわけはない。(中略)純文学畑の作家が調子をおろして安っぽいものを書いたのが何でも中間小説というのはおかしな話である。──
ここまで読んだ読者は、清張さんが、「これに対して推理小説には、謎があり、トリックもあるから面白い」と続けるものと予想するだろう。ところが、その予想は、外れてしまう。「謎とき」やトリックが推理小説の魅力であることを認めながらも、次のように欠点を指摘する。
──ところが、作者は競争相手の読者を念頭において作品を書くために、いよいよ奇抜なトリックを案出して勝とうとする。そういう作者の脳裡(のうり)にある読者とは、読み巧者の、専門的な、いわゆる「推理小説の鬼」と称する読者たちである。これは数少い選ばれた読者なのであろう。(中略)
このへんから、日本の推理小説は一種の同人雑誌的な狭い小説になってしまったようである。トリックはいよいよ奇想天外となり、手品的となり、現実離れがしてくる。(中略)
推理小説がマニアのみを対象とするかぎり、一般の読者には縁遠い存在となるのは仕方がない。(中略)
文章について言えば、現在の日本ものにはあまりに文句の抑制がなさすぎる。作者が、これでもか、これでもかと、恐怖感や異常感を煽(あお)り上げるのに、ありきたりの陳腐(ちんぷ)な形容詞を大げさに使用する。それで読者を震えさせているつもりであろうが、読者はそんなコケ威しの文句にはあくびをするだけである。──
「推理小説の魅力」の引用が、いささか長くなった感があるが、それには理由がある。私自身が、ある時期、日本の推理小説について、これと同じような思いを持っていたのだ。