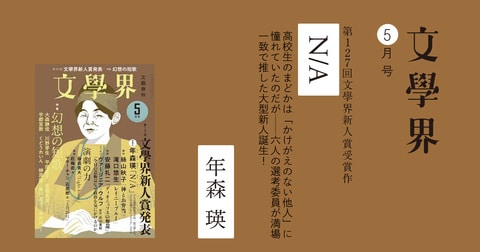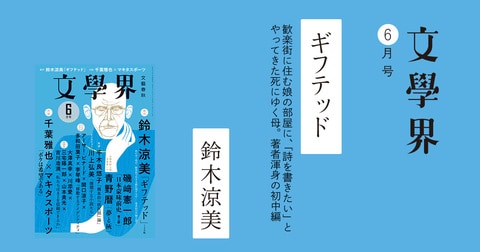西村賢太はなぜ私小説にこだわったのか?
なぜその作品に惹き込まれるのか?
親交のあった作家と文芸評論家が作家の謎、作品の魅力を語り合った。
構成●吉田大助

■世界が変わった
阿部 西村さんが亡くなられたことは、当日(二月五日)の夕方に、スマホのニュースサイトが報じた記事を通して知りました。最初はとにかくびっくりするばかりで、その後も予想以上にショックを受けている自分を発見して驚きました。訃報から一、二週間ぐらい、西村さんのことばかり考える日々が続いたんです。西村さんの作品は昔から一読者として書評などはよく書いていて、イベントでお目にかかってからは、ご著書を毎回送ってくださるようになり、感想をお送りしたりしていたものの、一緒に鶯谷の酒場に行くというような親交があったわけではありませんでした。あくまで作品を読むという立場です。にもかかわらず、なんだかすごく個人的によく知っている人が亡くなったような喪失感がありました。ひとつには、トラブルや健康問題も含めてあれだけいろいろあるのにそれでもしっかり生き、書き続けているというところに圧倒され、それだけに、ちょっと安心していたところもあるかもしれません。簡単には死にそうにない人に死なれちゃったなというか……。小説自体、「この人、死んじゃうな」と思わせるものではなかったことも大きかったのかもしれません。
田中 内容は破滅的と言えば破滅的なんですが、絶望的な感じはしないですよね。
阿部 そうなんです。田中さんは、西村さんと親しくされていましたよね。第一報はどのように受け取ったんですか。
田中 あの日は土曜日でしたが、朝のかなり早い時間に「文學界」の編集長から電話があったんです。このタイミングで来る電話は仕事じゃないな、何かあったんだとは思ったけど、西村さんの名前が出てきて。そこでエーッと叫んだのか、アーッと言ったのか、よく覚えてないですけど、そこから、私にとっての世界の見え方が変わってしまいました。その電話は実は仕事の電話で、追悼文を書けという依頼だったんですが、書きながら「なんで? なんで?」と思い続けていました。西村さんとは十年ぐらいの付き合いで、そんなに頻繁に会うような仲ではなかったのですが、同じ時期に芥川賞の候補になったり、同じ時代にずっと小説を書いてきました。お互いに本を送り合っていたので、西村さんも私の本を読んでくれていたはずなんですね。西村さんの新作が読めなくなったというよりは、「西村さんが自分の小説をもう読んでくれなくなったんだ」という感覚のほうが強かった。まともな生活じゃなかったから、そういうこともあるのかなと自分に言い聞かせてはいるんですけれども、電話を受けた時の「ああ、西村さんはもういないんだ」という感じが消えずにまだ続いています。
阿部 西村さん、田中さんのことはすごく評価していましたよね。どなたかとの対談で、西村さんが「あいつはすごい」という言い方をしていたのを覚えています。
田中 西村さんが私の作品を本当のところどう見ていたかは、わからないですね。ただ、大学に行ってない者同士なわけですよ。私は高卒、あちらは中卒で。私も引きこもりだったりグダグダやっていた時期があるし、西村さんは十代で社会に出ざるを得なくなった。屈折したところがお互いあるし、それを別に隠してもいない、そういう意味でのシンパシーは持っていてくれたんだろうなとは思います。
阿部 お二人の来し方はある種、対照的ですよね。西村さんは家を飛び出して、田中さんは家にこもるという。
田中 そうですね。小説に関しても、王道ではないという部分は一緒ですが、お互いまったく違うものを書いてきた。私は、自分の体験を小説の中に盛り込むとか、自分の心情を登場人物の内側に忍ばせるということはありますけれども、西村さんのようないわゆる私小説は書かないですから。遺作となった『雨滴は続く』(二〇二二年、小社刊)を読んで、西村さんの感覚では、私小説と純文学はちょっと違うんだなということもよくわかりました。西村さんには「俺は私小説書きだ」という意識やプライドがあり、私は純文学を書いている。だから私とは遠すぎず近すぎずで、うまいこと距離が取れていたような気がします。
阿部 西村さんが誰それと酒の席で喧嘩になったという話はちらほら聞きましたが、田中さんとトラブルになるという光景はあまり想像できないですね。
田中 私と一緒の時は、先輩風を吹かせて偉そうにしてましたよ(笑)。酒代は一緒にいる編集者が払うと言っているのに、「いやいや、ここは俺だよ」と言って払うんです。年も五つくらい私が下ですし、西村さんとしてはいい距離感で接することができる後輩だったんじゃないですかね。「もう会いたくない」「顔も見たくない」と思っていた人もいたようですが、私自身は会ってイヤだった思い出はないんです。西村さんと朝まで深酒っていうことはなかったですし、ひょっとしたら西村さんの本当にディープなところは見ていないのかもしれないし、見せないようにしていたんじゃないかなとも思います。仮にシンパシーを抱いてくれていたとしたら、私とどこかでぶつかったら、シンパシーが途切れてしまうわけじゃないですか。
阿部 彼もさすがに四十代、五十代になって学んで、あまり近づきすぎると自分から関係をぶち壊しちゃうんじゃないか、と警戒していたのかもしれませんね。
田中 これは追悼文でも書いたんですが、西村さんとは小説の突っ込んだ話ってあまりしなかったんです。私から「川端はどうですか?」「三島はどうですか?」と吹っ掛けてみるんですけど、「そんなものは」みたいにちょっと嘲ってみせるだけで、意見は言わないんです。
阿部 確かに、文学論は嫌うタイプでしたよね。私がわりとディープに西村さんと小説の話をしたのは、二〇一六年に東大で行った公開インタビューの時でした。その時、西村さんは自分にとっては藤澤淸造よりも田中英光のほうが大事であるということを強調していたんです。読者である我々が知っているのは、藤澤淸造の「歿後弟子」を自称して以降の西村賢太ですが、実はその前に田中英光に入れあげていた。けれど、田中英光の遺族と悶着を起こして、どうにもならなくなってしまった。そこで藤澤淸造にいわば鞍替えをしたというわけです。では、田中英光のどんなところがいいんですかと単刀直入には聞かないまでも、何かコメントをもらおうとしたんですが、「いや、面白いとしか言えないんですよ」というところで議論は止まってしまいました。そこを詳しく語るのは、野暮だと思っていたのかもしれません。
田中 『雨滴は続く』の中でも、藤澤淸造が好きだとは言うんだけれども、必要以上に藤澤淸造の作品について詳しくは書かないし、人に話さないようにしているとありました。「小説ってそんなふうにしゃべるものじゃないよ。一人一人が読んで感じるものでしょう」と思っていたのかもしれません。私自身、そう思っているところはありますし。
阿部 そうなると、今日の対談は非常に難しい(笑)。西村さんの作品そのものも、かなり論じにくいですよね。西村さんという作家の存在を抜きにして作品単体としては語りにくい。
田中 どうしても西村さんと小説の主人公である北町貫多を重ねざるをえないですよね。西村賢太をなるべく頭の中から追い出して、作品それ自体を読むということをやったほうがいいんだけれども、今はまだ無理かなという感じです。
■かつてなく多弁な『雨滴は続く』
阿部 基本的なことから言いますと、『雨滴は続く』は西村さんがデビュー時から書き続けてきた北町貫多シリーズの最新作です。出だしの一行が絶妙で、「このところの北町貫多は、甚だ得意であった」。「このところ」という時間感覚は西村的私小説の接近感を感じさせるものですし、「甚だ得意であった」と言われても、別にこっちは知ったこっちゃないじゃないですか(笑)。それを堂々と一行目に書くという厚かましさ。この時点で完全に、この人の世界に釣り込まれる感じがします。
田中 そうですね(笑)。他の現代作家が書くような小説とは明らかに違う、「これは私小説だよね」と思わせる構築の巧さを感じます。
阿部 三十七歳の貫多は神保町の古書店の手伝いなどをしつつ小説も書いている。「甚だ得意であった」理由は、同人誌に発表した短篇が評価され、「文豪春秋」の文芸誌「文豪界」に転載されたからです。その後、文芸誌からの執筆依頼が来て、定期的に小説が載るようになり、初めての中篇が芥川賞の候補になる。その過程で二人の女性が絡んでくる……というのが話の大枠となります。
これまでの作品との違いで一番わかりやすいのは、長さです。『疒の歌』(二〇一四年)や『蠕動で渉れ、汚泥の川を』(二〇一六年)など、これまでも長い作品はいくつかありましたが、今回は圧倒的に長い。単行本で五百ページ弱、四百字詰め原稿用紙で千枚ほどの大作です。短篇はもちろん、これまでの長篇ともまた違う、長距離用の書き方をしているなと思うところがあって、非常に新鮮でした。
田中 私は、よく貫多の一人語りでこの長さを引っ張れるものだなと思いました。大事件も起こらないし、風景描写がほぼないんですよ。能登の七尾に藤澤淸造の墓参りに行った時、ちょうど雪の時期で、行ってみたら境内が真っ白だったという自然描写はちょっと出てくるんですが、ほかはほぼない。能登だけでなく、神田の古書店街であるとか、風景描写ができそうな場面はいくらでもあるんだけれども、行きつけの古書店の店主と揉めて終わりです。そして、あっちの女性とこっちの女性の間を行ったり来たりする時の心理描写が延々続いていく。私小説は一般的に自分に起きたありのままを書くものだと言われますが、大事件の起きない日常を小説として読ませるのは大変なことですし、なおかつほぼ独白でこの長さを読ませるのは、作家としての技術と相当の才能が必要です。
阿部 わりと最近の『芝公園六角堂跡』(二〇一七年)の表題作などは風景描写が凝っていて、それだけで読ませる腕もあるんですよね。初期の作品は古風なまでに純文学的とも言える文章で、これは昔『瘡瘢旅行』(二〇〇九年)の書評で触れたことなんですが、西村さんの功績の一つは、私小説に「雄弁」と、つい「美文」と呼びたくなるような文章の調子のようなものを作り出したことかなと僕は思っています。おもしろいことに「美文」という用語については御本人に叱られたんですが、まあ、それはおくとして、それが今回は「雄弁」もしくは「多弁」、つまり「おしゃべり芸」のようなもので貫き通している。こんなに多弁な小説、なかなかないですよ。長い小説って、あんまり多弁だと読む側は疲れそうな気がするけれども、『雨滴は続く』は今までの作品よりも勢いがあって読みやすい。読んでいてものすごく心地いいんです。西村さんはいろんな才能がある人だと思うんですが、文章のリズム感の素晴らしさは特筆すべきだと思います。
この続きは、「文學界」7月号に全文掲載されています。