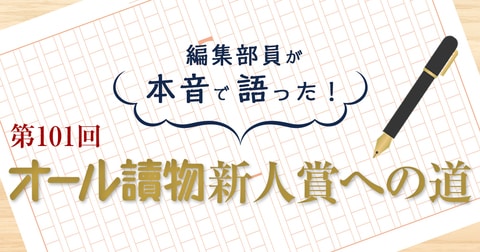横山秀夫、阿部智里、川越宗一ら、幅広いジャンルの人気作家を輩出してきた松本清張賞。今年の受賞作は、架空の国を舞台に、突然ある“異変”に襲われた人々を描くファンタジー小説だ。「多くの読者が、きっと自分の『今』を見いだせる小説だ」(辻村深月氏)、「現実が想像力を凌駕してしまっても、芸術は無力ではないのだと勇気づけられた」(東山彰良氏)と評された受賞作『凍る草原に鐘は鳴る』は、どのように生まれたのか。
社会の変化を書きたかった

本作では、遊牧民アゴールの人々全てが、突然、“動くものが見えなくなる”という異変に襲われます。
「ファンタジー作品には、大勢の身に異変が起こるよりも、一人だけが“特別”として扱われる話が多いです。その人が持っている特殊な力が活用されるか、不幸なものとして扱われるかは様々であれ、物語の中心となる何者かとそれ以外の人々ははっきりと区別されます。
でも“何か不可思議なこと”が多くの人々に同時に起これば、社会の常識や価値観が変わる契機となる筈です。私は、そういう大きな社会の変化を書きたいと思いました。以前、日本ファンタジーノベル大賞の最終選考に残った作品も、二つの国に住む人々から突然“爪が消えてしまう”という物語でした」
そういったファンタジーの設定は、どこから発想されるのでしょうか。
「学者の方が書いた本からひらめくことが多いです。“動くものだけが見えなくなる”というのは、『脳のなかの幽霊』(V・S・ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスリー著)にある、脳の視覚野に損傷を受けた人の症状から着想を得ました。初めは、実際の症例通りの見え方で書かなければならないと思い込んでいたので、調べて症例が少ないことに焦りました。ですが、ある歴史小説家の方が『私は史料がないところから小説の種をもらっている』と仰っていたのに後押しされ、大胆に想像を膨らませることにしました」
アゴールには、草原に額縁を立てその中でお芝居をする「生き絵」という伝統があり、主人公のマーラは、そのための物語を作り、演出を手掛ける「生き絵師」です。
「構想の時に、まっさらな草原に額縁が立って、その中で人々が躍動して物語を繰り広げる――そんな情景が、ぶわっと目の前に広がったんです。
着想はひらめきによるところが大きいですが、振り返ってみると、芸術を取り上げて良かったなと思います。“動くものが見えなくなる”ことで、日常生活は不便になり、今まで出来ていた仕事が出来なくなってしまう人々はたくさんいる筈ですが、人々がただ絶望するだけのお話にはしたくなかったんですよね。たとえ災害や不幸な事故などで今まで通りの生活を送れなくなったとしても、後の人生でその悲劇を呪い、苦しむだけの時間が残る訳ではないからです。
生活の必要性に直結するわけではない、だけど当人たちにとっては、なくてはならないと切実に思えて仕方がないもの、それが芸術だと思いました」
特殊能力や魔法が出てこないファンタジー
遊牧の民アゴールが、新たな生活の仕方を手探りする中で、農耕を生業とし、定住している稲城民(いなきのたみ)も、同じ異変に襲われたことがわかります。
「“動くものが見えなくなる”異変の影響を最も受ける民族として、遊牧民は登場させようと思っていました。また私自身が、学生時代にモンゴルのゲルに1か月間住み込んだことがあるので、生活をリアルに思い描けたからというのもあります。
一方、遊牧とは異なる暮らし方をしている人々も登場させようと考えていました。初めは海の民や狩猟民を出すつもりだったのですが、遊牧民との対比をより描くには、生活であまり動きのあるものを追う必要のない農耕民が良いと思いました。同じ現象でも影響の受け方が全く違う、そんな二つの民族を書きたかったのです」
異変のせいで、アゴールは国外に去るか定住するかを迫られ、マーラは「生き絵」を披露することができなくなります。そんな中、マーラは街を訪れ、奇術師の苟曙(こうしょ)と出会います。
「苟曙は、王のために奇術を披露する選り抜かれた奇術師でしたが、異変後にその立場を追われてしまいます。マーラと苟曙の生活スタイルは違いますが、どちらも異変によって、自分たちが愛していた芸術を人々に楽しんでもらうことができなくなってしまう。
とはいえ、立場は似ていても、二人の芸術に対するスタンスは違います。その違いも感じていただければ幸いです」
大きな異変によって生活や価値観の変化を迫られる――。そんな設定を現在の状況に重ねることもできると思いますが、執筆時に意識はされたのでしょうか。
「意識はしていませんでした。というのも、普通に暮らしていた人たちが突然何かの異変に襲われるという設定は、新人賞への応募を始めた時から書きたいと思っていた題材だったんです。今のコロナ禍は、たまたま現実の方が作品に重なってきたという感覚です。私には、時代性は作者が背負うものではなく、重なる時には自ずと重なるもののように思えます」
1年に1作を目標に応募を続けた
新人賞への応募はどれくらい続けていたのですか。
「大学生の頃から5年間です。1年に1作書くのを目標に投稿を続けていましたが、受賞作は改稿に時間をかけたので、書き上げるまで2年かかりました。初めて投稿したのは現代を舞台にしたローファンタジーでしたが、2回目以降は全てハイファンタジーです。
物語の世界を生き生きとさせたくて、海外ボランティアにも行きました。というのも、上橋菜穂子さんの影響と憧れで、大学では、専攻の漢文学とは別に文化人類学の授業も受けていたんです。実際に授業を受けると、異文化の中で生活をしたくてたまらなくなって、カンボジアやタイに行きました。
ですが現地に行ってみて、異文化を直に知ったらファンタジーが書けるなどという単純なものではないということに気付かされ、今までの自分の“異文化”との向き合い方が恥ずかしくなりました。葛藤しながらも、“異文化”の掴み方に自分なりの答えを得たくて、結局モンゴルに行ってしまうのですが(笑)。
それ以来、作品を書く時には慎重に考えます。作中世界の彼らと私たちとの“違い”とは何なのか。一体どこまで、彼らの日常を、私たちが想像出来る世界に重ねて書いていくのか。彼らにとっての真実を、彼らと同じような深度で納得できるように読ませるにはどうしたら良いのか。これは、作家として一生かけて答えを探していかなければならないことだと思っています」
専攻は漢文学だったとのことですが、中国文学も好きなのですか。
「専攻では、純粋な漢文学だけではなく、和漢比較や日本漢詩なども学んでいました。国文学科に漢文専攻があるという、母校ならではの授業が受けられたと思います。
専攻を決めたきっかけは、正史『三国志』諸葛亮伝の演習を取った時です。せっかくなので三国志の全貌を知りたいと思い、吉川英治さんの『三国志』を手に取ったらハマってしまって(笑)。漢文の響きを取り入れた文章が本当に美しかったんですよね。それから漢文を勉強したい! と切実に思いました」
今後はどのような作品を書いていきたいですか。
「次の作品は、大国に征服された直後で、法体系が錯綜している属州を舞台にしようと考えています。今後も基本的にはファンタジー作品を軸にしていきたいと思っていますが、機会があれば、現代を舞台にしたものやミステリーにも挑戦してみたいです」
【プロフィール】

あまぎ・みこと 1997年東京都生まれ。上智大学文学部卒業。2022年、『凍る草原に鐘は鳴る』(「凍る大地に、絵は溶ける」より改題)で第29回松本清張賞を受賞しデビュー。