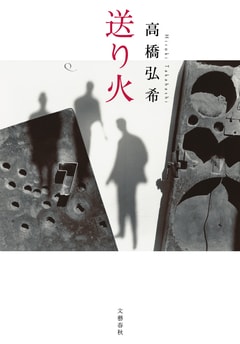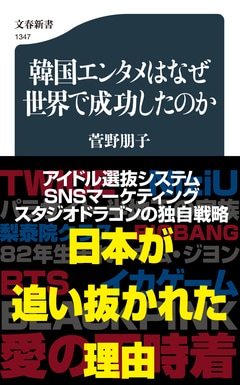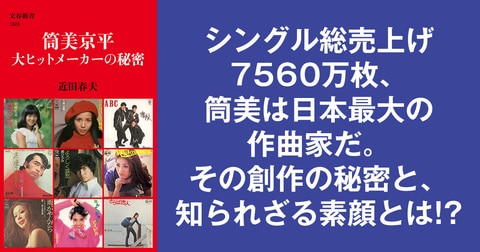東京都港区赤坂に、Eレコーズ本社ビルはあった。受付で自身の名前を告げると、程なくして、チェックのポロシャツ姿の若者がエレベーターから降りてきた。彼の案内で、E社七階の応接室を訪れる。応接室には二人の背広姿の男の姿があった。一人はエルの楽屋で名刺を受け取った中田だ。先日と同じく銀縁眼鏡をかけ、黒の背広を着て臙脂色(えんじいろ)のタイを締めている。もう一人から名刺を貰う。“E株式会社営業部 堺正治” 短髪七三で、ワイシャツの上に桃色のカーディガンを羽織っている。二人とも年齢は三十代半ばほどだろうか。ポロシャツの若者が、人数分のお茶をテーブルへ置き、ソファーの端に座る。書記係でも務めるかのように、モレスキンの手帳を開いてペンを手にする。最初に中田が口を開く。
「先日のライブ後に、何度も音源を聴かせてもらった。君の楽曲には、ときに明るさと感傷が同時に宿る。ときに暴力と繊細さが同時に宿る。つまり矛盾が音楽で調和されている。あまり前例のないロックだ。従来型のロックはもう売れない。それは弊社のセールスにも、如実に表れている。前例がなく、かつ優れた楽曲は、新しい世代の音楽にも成り得る。我々はぜひとも、君のバンドと契約したいと考えている。ただし条件として、大変心苦しいのだが、ベーシストはこちらで用意したい」
「ベーシストを用意する?」
と、今度は堺が、営業マンらしい柔和な笑みを浮かべて、
「福田君の将来の夢はなんですかね?」
「夢?」
「CDを百万枚売りたいとか、どこそこの会場でライブをやりたいとか。ミュージシャンならなにかしら夢があるでしょう?」
「武道館でライブをやることです」
「どうして武道館なんです?」
「ビートルズがライブをしているから」
と、ポロシャツ姿の彼が手帳から顔を上げて、
「六六年のことですね、あれは武道館で初めてロックコンサートが行なわれた日でもありますね」
再び中田が、一人で何度か頷いたのちに述べる。
「バンドを売り出すときには、ある程度の雛形がある。雛形は重要で、整った形にしないといけない。君にも分かると思うが、必ずしも優れた音楽が売れるわけではない。優れた音楽が、大衆に理解されずに埋もれたまま消える。それは我々が、というか私が、最も恐れる事態でもある。我々が準備した雛形に沿って営業を進めれば、近い将来、サーズデイは武道館を埋めることもできるだろう」
「武道館を?」
「ベーシストの件、考えてもらえないかね?」
E社との面談を終え、埼京線に揺られて帰路を辿りつつ、中田の言葉を想起する。武道館でのライブを夢見た理由は、ビートルズではない。小学五年の夏に、父母に連れられ、著名なポップシンガーの武道館ライブを観た。父母も音楽は好きだが、ライブへいくタイプではない。チケットは、新聞社に転職した元同僚から貰ったとかなんとか言っていた。南側の二階席だったゆえ、八角形の会場の全貌を一目にできた。葵は客席を埋める人間の数に圧倒された。全校集会で体育館に集まる生徒は八百人くらいだが、その十倍以上の人間が一堂に会している。生まれて初めて見る光景だった。
会場が暗転され、黄金色の眩い光が差し、主役であり主人公でもある歌い手が、舞台袖から現れる。自分と同じ年ごろの少年だった。彼は黄金色の照明の下で一礼をした後に、青空のポルカを独唱した。後になって知ったが、そのポップシンガーのライブでは定番になっているオープニング・アクトだった。少年のソプラノの旋律を聴くうちに、葵は胸の中で夢の芽がむくむくと生長していくのを感じた。
十歳の少年が夢を抱くのは、ごく自然なことだ。その夢が叶うと本気で信じることも。そして二十歳を過ぎた今、ときに本気で夢を信じられない自分を見つける。十代でデビューして、瞬く間に数万人規模の会場を埋めるミュージシャンは多くいる。一方で自分は、未だ二百五十のキャパも埋められない。ベーシストはこちらで用意したい。E社と契約せずとも、地道にライブ活動を続ければ、エルは埋められるかもしれない。でもあの巨大な八角形の箱を埋める道のりは、余りに遠い。
翌日、リハスタ練習後に、サーズデイの四人はいつも会議に使うファミレスを訪れた。テーブル席の端に、智樹がギターを、啓介がベースを立て掛ける。葵は手ぶらだった。前回のライブで床に叩きつけたギターは、ピックアップが故障したのかハウリング音しか鳴らない。修理するにしても、今月のバイト代が出るまではどうにもできない。四人がテーブル席に座るとき、なぜかいつも配置が決まっている。葵の隣に智樹が座り、向かいに伸也、斜向かいに啓介。
智樹は身長こそ一八〇と高いが、昔から気弱なとこがあり、中学ではちょっとした虐(いじ)めにも遭ったらしい。皆と同じように、高一の春から楽器を始めた。智樹がどの楽器をやりたかったのかは知らないが、空きのあるポジションがギターだった。彼の演奏技術はなんとも無難なものだった。下手ではないが、突出した何かがあるわけではない。結局、智樹はリードとサイドの中間の位置を担い、曲によって葵とその配分を調整している。