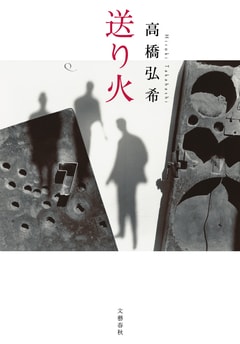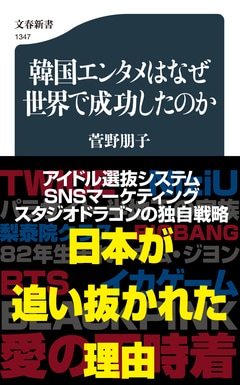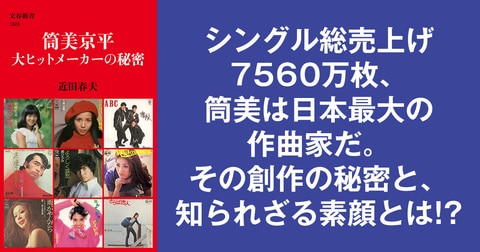作詞・作曲の天賦の才に恵まれた福田葵。彼が幼馴染と結成したバンド「Thursday Night Music Club」がとうとう大手レコード会社の目に留まった。しかしデビューには条件があって……。
高橋弘希さんの長篇小説『音楽が鳴りやんだら』が、いよいよ8月9日(火)に発売となります。
この小説の魅力を一人でも多くの方に味わっていただきたく、第1章を全文無料公開します! 葵たちの運命を大きく動かすこととなる、バンドのデビューをかけたオーディションライブのシーンを、ぜひお楽しみください。

1
ギターケースを背負い、山手線に揺られて新宿駅へ向かっていた。新宿のエルという会場でライブがある。葵のバンドにとって初のワンマンだ。キャパ二百五十に対してチケットの売上は百枚余り、仲間内の客も多いので実質的な売上は八十枚程度かもしれない。百枚の売上は、ライブハウス界隈では成功の部類だ。そして今日のライブはいつもとは違う。レコード会社の社員が視察にくることを、事前に聞かされている。つまりは実質的なオーディションライブだ。審査する人間が良しと見なせば契約になるし、否と見なせばそれまで。審査される音楽なんてクソみたいだ、葵は思いつつも、レーベルとの契約は余りに魅力的だった。その矛盾した感情から逃れるように、イヤフォンを耳にして音楽を再生する。
“Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper”
ヒステリックでチャーミングなシンディの歌声に耳を傾けながら、車窓を流れていく春の街並みを眺める。時おり街の中に桜を見つけ、その桃色の群がりはすぐに後方へと流れていく。ふいに幼稚園児の頃に出場した、市内子供のうたコンテストを想起する。あのコンテストも桜の咲く頃で、そして審査される音楽だった。前日に、祖母がわざわざ宮城の田舎から電車を乗り継いでやってきた。葵は祖母の前で予行練習をした。葵が唄うたどたどしい星の家族を、祖母は目を細め、目尻に皺を寄せて、恵比寿様の顔で聴いていた。歌は人を笑顔にできるのだと思った。その祖母は数か月前に肺炎をこじらせて他界した。祖母をライブに誘ったことはない。自分がやっている音楽は、祖母を笑顔にすることはない。
葵のバンド「Thursday Night Music Club」は、九〇年代にアメリカを中心に流行したオルタナティヴに属する音楽だった。インデペンデントから生まれたこの音楽は、あのシアトルの狂乱的ムーヴメントに後押しされ当時のメジャーシーンを席捲した。マッドハニー、シルヴァーチェアー、スクリーミング・トゥリーズ――、そうしたバンドが再評価され始め、日本のアンダーグラウンドなシーンでちょっとしたブームが起きていた。葵のバンドはこのシーンで約二年の活動を続けていた。二年続けて、百人を集客できるところまできたのだ。
シンディの歌声がフェードアウトを迎える頃、電車は新宿駅へと着いた。イヤフォンを外して駅構内を歩き、東口から野外へ出て歌舞伎町へ入る。派手な色の電飾看板に目が眩(くら)む。葵は埼玉郊外で生まれ育ったゆえに、未だこの街に馴染めずにいる。と、突如、風俗の呼び込みの男に声をかけられ、葵は落ち着きなく視線を動かす。男はそれを見ると、ここぞとばかりに捲(まく)し立てる。
お兄さん、ギターケース背負ってるけど、これからライブでもあるんですか? 音楽もいいけど、風俗もいいですよ、一発抜いてからライブやったらどうですか、集中力が増すかもしれませんよ、今なら待ち時間無しで案内できますよ、ねぇ、お兄さん、音楽より射精のほうが気持ちいいでしょ、若いんだから遊ばないとダメですよ、ねぇ、お兄さん――。街路の右手にエルの看板が見えてきた辺りで、男は舌打ちをして葵から離れていった。
楽屋にはすでにメンバーの姿があった。ギターの智樹、ベースの啓介、ドラムの伸也(のぶや)。皆が二十一歳になる年で、皆が幼馴染だ。葵と智樹は私大の三年、啓介はファミレス勤務のフリーター、伸也は家業の塗装工。今日のライブは絶対に外せねぇよ、煙草を吹かしながら、啓介が言う。何せE社と契約できるかどうかが懸かってるんだ。
ライブハウスの楽屋は、どこも似たようなものだ。八畳ほどのスペースに、使い古されたパイプ椅子やら、穴の開いた革ソファーやら、塗装の剥げた丸テーブルやらが置かれ、アルミの筒型灰皿は吸い殻の山で底の水はヤニで黄色く淀み、小型冷蔵庫にも流し台の戸にもバンドステッカーがべたべたと貼られ、四方の壁面はライブ告知ポスターと油性ペンによる落書きで埋め尽くされている。
そのとても快適とは言えないロックを凝縮したかの小部屋が、葵は嫌いではない。そこに居るだけで、心臓の高鳴りを感じる。自分はミュージシャンなんだと実感できる。でもそれもリハを終えるまでだ。リハ後、開場までバンドは自由時間になる。智樹はルミネへ服を見にいき、啓介はタワレコへ新譜の確認にいき、伸也はパチンコ店へスロットを回しにいった。葵は近場のスタバでイヤフォンを耳にして、再び音楽を聴いて時間を潰す。そして開場の少し前に楽屋へ戻ると、その後は誰とも口を利かずに俯いて延々と煙草を吸う。
アローズでカットソー買っちゃったよ、レッチリの新譜なかなか良かったぜ、あそこのパチ屋ぜんぜん出ねぇのな――、この時間帯、メンバーは誰も葵に声をかけない。ライブに向けて意識を集中させているのだと、彼らは思っている。違う。むしろ意識は散漫になるばかりだ。開場が告げられ、ぽつりぽつりとフロアへ観客が入り始める。興奮や期待の入り混じった話し声が重なり合って耳に届き、葵は訳の分からないものに追い詰められている気分になる。