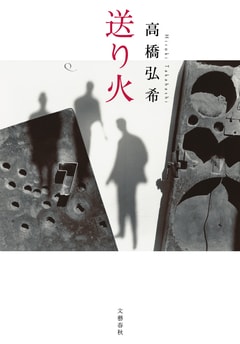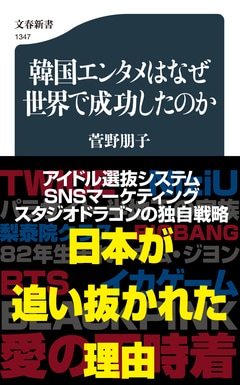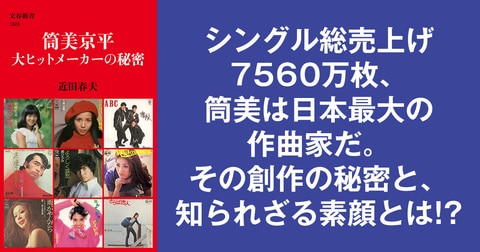葵が思い出すのは、小学校の歌のテストだ。出席番号順に名前を呼ばれて、先生のピアノの前に立って、課題曲を唄う。クラス全員に聴かれる歌声――、上手い奴もいれば下手な奴もいる。テストになると音程を外す奴もいる。喉が締まって上手く発声できない奴もいる。次第に自分の出席番号十九番が近づいてくる。あの感覚だ。ライブDVDで見るロックスターも、この時間帯は出席番号が近づいてくる気分になっていたのだろうか――、ジム・モリソンもジョン・ライドンもイアン・カーティスも、誰とも話さずに俯いてひたすら煙草を吸っていたのだろうか――。
フロアの話し声は、ざわめきに変わっている。掛時計を見上げると、十九時の開演間近だ。スタッフが楽屋に顔を出し、バンドに入りを告げる。伸也、啓介、智樹の順番でステージへと出ていく。聴衆のざわめきに歓声が混じる。葵は最後の一本の煙草に火を点し、一口だけ吸い、それを灰皿に押し付けて潰す。慌てたようにパイプ椅子から立ち上がり、しかしゆっくりとした足取りでステージへ向かう。舞台袖から現れた葵の存在に聴衆が気づくと、どよめきに近い声があがる。葵はその声に気づかない素振りで、あるいは気にしていない素振りで、スタンドからギターを手にする。
もう引き返せないんだ、葵はいつも思う。憂鬱な表情で煙草を吸っていた奴を殺して、風俗の呼び込みを相手に挙動不審になっていた奴を殺して、婆ちゃんが笑顔になるような曲を作りたいなんて考えていた手ぬるくて生ぬるい奴をぶっ殺して、ロックバンドのフロントマンにならなければならない。SEの“サムシング・ガッタ・ギヴ”が消えて会場は暗転し、伸也が四つカウントを取り、バンドの最初の音と共に、眩(まばゆ)い照明が頭上から落ちてくる。もう引き返せないんだ。轟音の中で再び思う。そして十六小節の前奏が終わる頃、葵はロックバンドのフロントマンとしてマイクへ向かう。
ライブハウスは三百人程度の人間を収容する小さな箱だ。客席と舞台があって、演者はそこで自分が作った曲を、つまりは自分の子供のように愛した曲を、聴衆に披露し、ときに拍手喝采を受け、ときに無感動な眼差しを向けられる。聴衆は常に正直だ。差し出された音楽がお気に召さなかった場合、そっと舞台から離れて出口へ向かう。客席後方のあの分厚い防音ドアが開くとき、そこに細長い空間が見える。あの空間を、演者は最も恐れる。舞台上から見る、日常と地続きの空間。不思議とスポットライトより眩くさえ見える、仄白(ほのじろ)い長方形の空間。それでも自分の音楽を信じられるだけの強さが欲しい。葵は舞台上でギターを轟音で鳴らしマイクに向かって叫びながら、幾度もそう願ったことがある。
幸いにも活動初期から、葵の楽曲は多くの人間に愛された。エルの店長は、君の楽曲は古き良き時代のポップスのようだ、と感想を述べた。典型的なオルタナのサウンドなのにメロディはキャッチーで、例えばオジーの“クレージー・トレイン”とか、あるいはザ・スミスの“ディス・チャーミング・マン”みたいな、日陰の中にふいに落ちた日向のような感触があるんだよね。店長の批評は的を射ている、葵は思う。事実、葵は小学生の頃、カルチャー・クラブ、クラウデッド・ハウス、エディ・ブリッケル&ニュー・ボヘミアンズ――、あの底抜けに明るくて哀しくて感傷的な八〇年代ポップスに心酔した時期があった。そのエルの店長の後押しもあって、やや時期尚早とも思える今回のワンマンが実現したのだ。
百人の観客は熱狂した。彼らは自分たちの音楽が好きで、金を払ってまでやってくる熱烈な支持者だ。音程が少し外れても、押弦が一フレットずれても、寛容な心で許してくれる。でも今日は違う。熱烈な支持者ではない、音楽を審査する聴衆が交じっている。眩い舞台とは対照的に、客席は薄闇に沈んでいる。薄闇の中に、聴衆の沢山の仄白い顔が見える。葵はマイクに向かいながらも、ときに聴衆の中にいるはずの部外者の存在を探してしまう。そして自分自身に苛立ちを募らせていく。
オーディションライブなんてのは、本当に音楽の時間の歌のテストみたいだ。採点される歌声なんてあるのか? 採点される音楽なんてあるのか? 俺は消費される音楽を嫌悪してるんじゃないのか? それなのに音楽を商品にする会社に媚売って歌を唄うのか? そしてライブの終盤、葵はストラップを外し、全音符の轟音の中、ギターを床に叩きつけて破壊し、マイクに向かって絶叫に近い声でE社を名指しで批判した。観客は葵の意図を理解していないが、そのロックな振る舞いに客席は大いに沸き興奮の坩堝(るつぼ)になる。一方でメンバーは、薄暗い照明の下でも分かる引き攣(つ)った顔でこちらを見ていた。葵は耳を裂くハウリングが鳴り響く中、足早に楽屋へと引き返した。
タオルで汗を拭い、丸椅子に腰かけて、コークハイを一息に飲み干すと、煙草に火を灯す。これでE社との契約はご破算だが、それでかまわなかった。自分が好きな音楽を、好きなようにやって、一定数のファンがついてくる、それでいい。
二本目の煙草に火を灯した頃、楽屋には場に不釣り合いな、黒い背広姿の男が現れた。葵に名刺を差し出す。“E株式会社制作部 中田聡(さとし)”契約を前提に、一度、葵一人で社に足を運んで欲しいという。