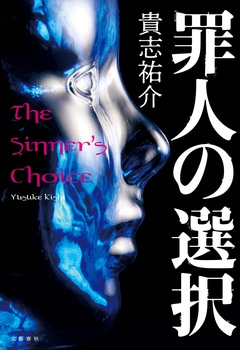思わず初出を確認してしまった。『夜の記憶』が掲載されたS―Fマガジンは一九八七年九月号。一九五九年生まれの作者が二十八歳のとき、つまり『十三番目の人格(ペルソナ)―ISOLA―』で本格的なデビューを果たす九年も前の作品ということだ。マジかよ、である。
〈強い違和感の中で彼は目覚めた。〉
という一文から始まる本作は、読者も違和感にぶつかりながら読み進めることになる。まず数行のうちに、主人公である〈彼〉は知性を持つが、身体は人間のものとは大きく異なり、海洋に適した構造になっていることがわかる。いま〈彼〉はどうやら海中にいるようだが、その海水は〈強酸性〉で、通常の海ではなさそうだ。また〈彼〉が〈鱒〉という名前で呼ぶ魚型生物が登場するが、描写される生態はどう考えても我々の知る〈鱒〉ではない。〈彼〉の用いる語彙は我々と共通しているのに、〈彼〉のいる世界は我々のそれとは似ても似つかない。いったい〈彼〉は何者で、ここはどこなのか。その世界でなにが進行しているのか。具体的な説明のないまま〈彼〉の思考と行動にフォーカスされた描写が続き、読者を違和感の海に引き込んでいく。
並行して語られるもう一つの物語は、我々にも馴染みのある世界が舞台だ。そこには我々の知る海があり、その海で戯れる一組の男女が登場する。二人は恋人同士らしいが、ここでも違和感が、それも不穏な違和感がそこかしこに顔を出す。
一見かけ離れた二つの物語が交互に語られるうちに、両者の違和感が呼応しはじめ、少しずつ解像度を上げていく。読者は世界像を得ようと夢中になるだろう。このあたりの匙加減はすでに手練れの域にあり、本格デビュー前の作家の手によるものとは思えない。二つの流れを使った演出は私もよく用いるが、本作は間違いなく優れた成功例である。二つの世界の繫がりがついに明らかになる瞬間、そこに立ち現れる物語の壮大さは圧巻というしかない。
その『夜の記憶』から二十二年後の二〇〇九年に発表された一編が『呪文』だ。前年に刊行された日本SF大賞受賞の大傑作『新世界より』と同様、本作も作者の充実ぶりが遺憾なく発揮されている。
舞台となるのは、巨大星間企業が銀河を支配する遠い未来、アマテラス第Ⅳ惑星〈まほろば〉だ。主人公である金城と、可憐な声を持ちながらも不気味な顔貌の少女タミのやりとりで幕を開けるこの物語は、彼らの置かれた異様な状況を提示しつつ、宗教、民俗、思想といった要素を色濃くはらんでいく。それだけでも十分に読み応えのあるSF小説たりうるのだが、円熟した作者の視線は、そういったものを突き抜けた先を捉える。
これが架空の世界の物語ではなく、いま正に現代社会で進行しているものの生々しい相似形に思えてならないのは、そのせいだろう。たとえば〈まほろば〉の住人は、顔見知りの者と直に相対するときはきわめて礼儀正しいのに、目に見えない〈マガツ神〉へ怒りを向けるときは憎悪を剝き出しにして半狂乱になる。この様相、面と向かってはなにもいえないのに、ネットの向こうにいる相手に対しては感情の抑えが利かなくなるのに似ていないだろうか。会ったこともない誰か(もしくは特定の集団や国など)を憎むべき悪魔であるかのように見なし、怒りに任せて攻撃するうちに、いつしか自分自身が悪魔的な存在になり果てている。本作の元ネタになりかねないそんな事例すら、SNSを眺めれば容易に見つけられる。
本作が書かれたのは日本版ツイッターがリリースされて間もないころであり、いま(二〇二二年)ほどSNSが一般的ではなかったので、はたして作者がどこまで念頭に置いていたのかはわからない。が、そんなことは問題ではない。意識するしないにかかわらず、人間の普遍的な宿痾とも言うべきものまで描き出してしまう。優れた作家とはそういうものだと思い知らされる作品である。
続く表題作『罪人の選択』は、本書で唯一のミステリだ。ここまでのSF二作品に比べると、かなりエンタメに振っているという印象を受けるかもしれない。
舞台は日本。終戦の翌年、ある防空壕の中に三人の男がいる。そのうちの一人が〈罪人〉として、一升瓶と缶詰を前に、どちらかの中身を口にしろと選択を迫られる。一方に猛毒が入っているのだ。〈罪人〉は生き延びるため、わずかなヒントを元に正解にたどり着こうとする。
並行して語られるもう一つの話は、十八年後の同じ防空壕が舞台だ。ここでも別の〈罪人〉が、一升瓶と缶詰を前に、まったく同じ選択を迫られている。だが彼には、十八年前の〈罪人〉よりも一つだけ有利な点があった。