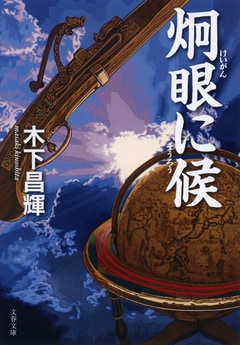上田秀人先生は、ご自分に厳しい方である。
私がなぜ上田先生を「先生」とお呼びするのかは、以前『闕所物奉行 裏帳合(六) 奉行始末』(中央公論新社)の解説でも書いたとおり、小説教室で小説の書き方を教わったからに他ならない。
その教室というのが「山村正夫記念小説講座」、通称「山村教室」で、私にとって上田先生はそこの大先輩にあたる。OB作家という縁で今も年に一度はゲスト講師として教壇に立ち、後進の育成にあたってくださっている。
そんなわけでデビュー前から先生には、ビシバシと鍛えていただいた。私のみならず七尾与史、成田名璃子、千葉ともこ、西尾潤(すべて敬称略)あたりの作家は、上田先生に頭が上がらないはずである。
先生の講評は、とにかく熱い。手を抜いたところは必ず突っ込まれるし、細かな言葉選びも疎かにするなと叱られる。だから怖い。できることなら泣きながらお家に帰りたいくらい怖い。それでも受講生が襟を正して聴いているのは、その厳しい目が常に、ご自身にも向けられていることを知っているからだ。
あれは私が、小説家としてデビューしたてだったころ。二作目の長編の書き方が分からずあれこれと言い訳ばかりしていたら、上田先生は私の目をまっすぐに睨みつけて、こうおっしゃった。
「書け。悩んでる暇があったらとにかく書け。僕はな、今日二十枚書くと決めたら、なにがなんでも書き上げるまで寝ぇへんぞ!」
燃えるような目であった。当時はまだ歯科医と兼業でありながら、数多くのシリーズを手掛けておられた。限りある時間の中で先生は、歯を食いしばって己の作品と向き合っていたのだと思う。惰弱を戒め、作家としてさらなる高みを目指そうとする姿勢は、純粋すぎてつき合いが長くなってきた今でも近寄りがたいものを感じさせる。
さて、前置きが長くなってしまった。本題に移ろう。
『本意に非ず』はまずはじめ、二〇一九年十一月に単行本として上梓された。その際のインタビューで上田先生は、このようにお話しされている。
「僕自身は本意ではなかったり、後悔を残した人生というのは肯定的にとらえています。命の危機にさらされた時でも、まだやり残したことや何か執着があった方がそこは気合が入るでしょう。思いどおりにいかなかった人間の一生の方が、実は意外におもしろいんですよ」
なんだか先生の、意地悪く微笑むお顔が目に浮かぶようだ。
そんな「思いどおりにいかなかった人間」としてピックアップされたのが、各章の登場人物――明智光秀、松永久秀、伊達政宗、長谷川平蔵、勝海舟――である。
歴史にさほど明るくない私でも、「おお!」と手を叩きたくなるほどのオールスターだ。でも松永久秀はけっこう好き勝手して果てた気がするし、長谷川平蔵はどうしたって鬼平のイメージが強い。どこが「本意に非ず」なのかと不思議に思いつつ読み進めると、ふむむむ、なるほど。たしかにそういう心理状態だったのかもしれないと唸らされてしまう。
史実と史実の隙間に存在した「かもしれない」人間の葛藤を、掬い上げるのがうまいのだ、上田秀人という作家は。それは歴史小説のみならず、数々の時代物シリーズにも言えることである。後者のほうが史実の間に差し挟まれるフィクションの分量が多いというだけで、基本的な創作法は同じなのではないかと邪推している。
それにしても上田先生が描いて見せる葛藤の、なんと多彩なこと。たとえば第一章の「逆臣」では、明智光秀の謀反の理由が描かれる。しかし先生はこれ以外にも、本能寺の変を多く手掛けているのだ。
『天主信長〈表〉 我こそ天下なり』『天主信長〈裏〉 天を望むなかれ』(講談社)、『傀儡に非ず』(徳間書店)、『布武の果て』(集英社)などがあり、興味深いことに、光秀の謀反の理由がどれも違う。それなのに一作一作読むたびに、「本能寺の変の真相はこれだったのかもしれない!」と、まんまと思い込まされてしまうのだ。
おそらく史料を丁寧に読み込み、歴史上の人物の人柄や心情を解きほぐしてゆく中で、いくつもの葛藤のパターンが見えてくるのだろう。その手腕が他の章でも、存分に振るわれている。どの登場人物も従来のイメージとは違うのだが、それでもすんなりと受け入れられてしまうのは、史実から窺える彼らの行動と、上田先生が掘り下げた内面に、矛盾が感じられないからである。
ところで本書『本意に非ず』には、対となるべき(と勝手に思っている)著作がある。タイトルもまさに対照的な、上田秀人著『本懐』(光文社)である。
こちらで扱われるテーマは、武士の切腹。六話の短編で成り立っており、登場人物は大石内蔵助良雄、織田信長、狩野融川、堀長門守直虎、西郷隆盛、今川義元となっている。
勘のいい方ならすでに、「あれ、おかしくない?」と、首を傾げていることだろう。
旧主の敵討ちを果たした大石内蔵助はともかく、他の人たちは皆、志半ばか夢破れて死んでない? いったいどこが「本懐」なのよ。
少なくとも、私はそう思った。そして実際に読んでみると、本作の解釈では、大石内蔵助ですら本懐とはほど遠い葛藤を抱えて最期を迎えていたのである。
ああ、なんて逆説的で、皮肉なタイトル――。
「せやから僕は、思いどおりにいかへんかった人間が好きなんやって」と、にこにこしている上田先生の顔が思い浮かぶ。
武士にとっては名誉の死とされる、切腹。しかし当人にとっては、「本意ではなかった」と歯噛みしながら迎える死とどこが違うのか。いいや、腹を切らされるような状況がすでに、本意であるはずがないのだ。
乱世であれ、泰平とされた江戸の世であれ、人権意識が高まりつつある現代であっても、けっきょくのところ人というのは己の抱えるしがらみの数だけ、本意でない選択を迫られる。親子、兄弟姉妹、夫婦や友人関係ですらしがらみの一つなのだから、すべてを断ち切って生きるのは、山奥に隠遁して仙人でも目指さないかぎり無理である。なにも考えずに流されていければ楽なのかもしれないが、理想や志が高ければそれだけ、現実との乖離に苦しむことになってしまう。
本意とは外れてしまった男たちの、生き様と死。それを描き出す上田先生の筆は、簡潔でありながらなぜか温かい。「人とはそういうもんや」という、優しい眼差しすら感じられる。そこにはまさに、「本意ではなかったり、後悔を残した人生」を肯定的にとらえるという姿勢が表れているからなのだろう。
ちなみに『本懐』に於ける織田信長が主役の短編「応報腹」では、本書とはまた別の本能寺の変の解釈が描かれている。未読の方はぜひとも、本書と併せてお楽しみいただければと思う。
さて冒頭でも書いたように、上田先生はご自分に厳しい方だ。
高いところに理想を掲げ、それに向かって妥協することなく、原稿用紙を一文字一文字実直に埋めておられる。きっとこの先どれだけのものを書き上げようとも、「これで充分」と満足なさることなどないのだろう。
「上田秀人先生の著作100冊突破を祝う会」が開かれたのは、たしか二〇一六年の初夏のことだった。さらなる年月を経て、今はいったい何冊になっておられるのか。たとえ著作が二百冊、三百冊を超えようとも、先生の情熱は尽きないはずだ。
だからどうか我々が「不死身なのではないか」と震撼するくらい長生きをして、やり残したことや執着に喘ぐ人間の物語を、鮮やかに描き続けていただきたいものである。
そのためにはどうかどうか、お体を大事になさってくださいませ!
二〇二二年十月某日 不肖の後輩より