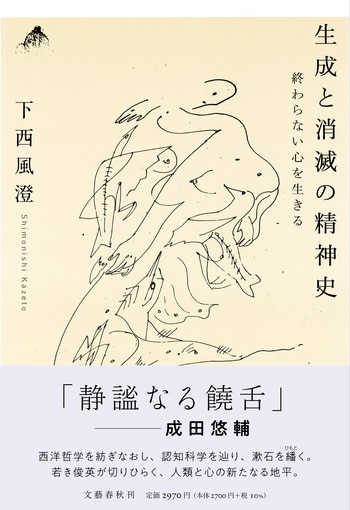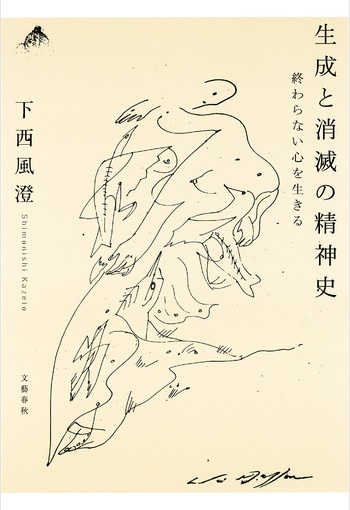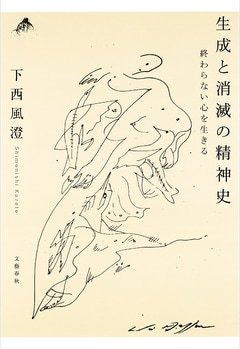■漱石の失敗
吉川 「気」の補助線によって、いろんなことがわかったような気がしました。西洋と東洋というのは自動的に思い浮かぶ二分法ですが、世界を概念的・計算的・離散的に捉える西洋的な考え方と、そうじゃなくてモヤッとしたものとして捉える日本的な考え方、という二分法のほうがむしろ明瞭に見えてくるものがあります。その境界領域に夏目漱石がいるわけですよね。日本的な「気」というフワッとした空気のなかで、西洋近代の薫陶を受けた漱石は頑張っていた。戦っていた。この本のなかでは、漱石は過去の人というよりは、来るべき未来の作家として描き出されています。夏目漱石論の著書がある山本くんとしては、下西さんの漱石論をどんなふうに受け取ったんでしょうか?
山本 あ、私への質問でしたか。
下西 山本さんの『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、本のなかでも引用させていただいています。
山本 さっきの吉川くんの物言いではないけれど、「そうそう!」と我が意を得たりの思いでした(笑)。少し補足で説明すると、夏目漱石は明治政府の命令で「イギリスに留学して、英語を勉強してこい」と言われたのですね。ところが漱石はリテラチャー(文学)の研究に没頭します。今でこそ、この蔦屋書店にも文学コーナーがあったりして、「文学」はお馴染みです。しかし漱石の時代にはそうではなかった。漱石の場合、漢文の文芸であれば親しんでいたけれども、英語で「リテラチャー」というものは何だかわからん。でも知りたい。というので漱石は七転八倒して気が狂わんばかりに研究したわけです。自然科学と対比したり、当時の最新科学である心理学や社会学なども参照しています。そして日本に帰ってきて、東京帝国大学で「文学論」という講義をする。その冒頭で「およそ文学の内容というものは(F+f)という形を取る」という一般化をするんですね。
下西 Fが認識で、fが情緒。あらゆる文学作品はこの二つの要素でできている、と定義した。
山本 ついでながら、拙著『文学問題(F+f)+』の読みどころの一つは巻末付録です。漱石の文学論をその後の百余年にわたって、どんな人がどんなふうに評してきたかという年表を付けています。ご覧いただくとわかりますが、ほとんどの人が貶しています。漱石が苦労して作ったものなんだけれども、当人も「あれは失敗だった」と言っている。それをいいことに「あの本は読まなくていい」と言う人もいたりします。ただ、下西さんがこの本で指摘しているように、『文学論』の見立てが有効か無効かではなく、漱石がこの公式を作るに至った動機は無視すべきでないと思うんです。
下西 山本さんが今おっしゃったように、漱石の文学論はずっと真面目に扱われなかった歴史があり、漱石論を書くときなども(F+f)はまず取り扱わないことになっています。なぜならそれは失敗だから、と。でも、失敗を失敗として受け取ることが大事ではないでしょうか。どうして漱石がこんなことをやらなければならなかったのかということこそ取り組むべき問題であって、自律的で合理的な主体性を伴う心と「気」に混じることができたり神や自然と共にあるような心、その緊張関係の狭間にいた人として漱石を読み直したい、と思ったんです。
吉川 今、すごく重要なことをおっしゃっていただいたと思います。ある水準では、ある試みが、事前の問題設定に対して成功したか失敗したかについて云々することはできるし、我々もしょっちゅうそれをしている。でも、そもそも何でそういう問いを考えることに迫られたのか、という別の水準もあるんですよね。その水準から見たら、あらゆる失敗は我々の考えるリソースになる。さっき時間の流れは複数層ある、と下西さんはおっしゃいましたけど、さまざまな人間の試みに関しても、いくつもの水準の違いがある。そのことに自覚的であることはすごく大事で、この本でもその感覚が活かされていると思いました。
山本 同感です。それに、ある面では失敗したけれど、失敗ゆえにわかることというのもあるんですよね。先人がチャレンジして失敗したことがあるなら、その動機とどこまで到達したかを見届ける。それで足りないところがわかれば、その知見を足がかりにさらに先を目指せばよいわけです。
吉川 「我々の人生、失敗なんかないんだ」「気の持ちようで失敗なんか全部なくなるんだ」とか、そういうことを言っているわけじゃないんですよね(笑)。ある水準においては失敗かもしれない。でも、別の水準ではどうか? その問いかけが下西さんの本では繰り返しなされている。一つの水準に固着しちゃうと、本人が失敗と言っているんだから失敗じゃん、で終わってしまう。
■人間の認識の歴史を辿りたい
下西 お二人にうかがってみたいことがあります。『心脳問題』では議論を進めていくうちに、心や意識の問題を哲学か科学かという形而上学的な問題として扱うと困難に陥る、という結論になっていきますよね。面白かったのは、その議論の後で、「心脳問題は社会へ向かう」と書かれていることです。そこから実際にエンハンスメント(心身への医学的・科学的介入、増強)の問題とか、精神疾患の問題とか、社会的な制度の問題に展開していくじゃないですか。僕の場合、同じような認識から、意識の哲学史みたいな方向に進んでいったんだなと思ったんです。
吉川 なるほど。我々は袋小路の先で社会に、つまり横に向かったわけだけど、下西さんは縦というか、歴史に向かったわけですね。そして、どちらも現在の我々を規定する条件をあらためて考えようとした。
下西 ええ。おうかがいしたかったのは、「社会へ向かう」となったときに、山本さんであれば、西周や漱石の作品そのものを対象にするのではなく、あえて「文学論」を取り扱うなど、人間が意識を表出するときのテクスト的な環境に注目し、あるいはそれを博物学的な視野で捉えて議論を展開されていった。吉川さんであれば、『理不尽な進化』(ちくま文庫)で、進化論そのものではなくて、人間がいかに進化論を受容していったのか、進化論がいかに生命観や人間観を変えたのか、という問いを立てて、考察を展開されている。つまり、お二人とも真正面から問題を扱うのではなく、その問題の語り方そのものを考え直さなければならないのではないか、これまでとは別の語り方を発明しなければならないのだ、という問題意識を持たれて活動されてきたと僕は捉えているのですが、その点をご自身ではどのように考えられているのでしょうか。
吉川 完全におっしゃる通りです(笑)。ときどき想像するわけですよ。私が別の関心、別の能力、別の資質を持っていたら、専門家になって神経科学の研究をしたり、DNAを解析したりしていただろうなと。でも、私はそういうんじゃないんだよなぁというところから、自分なりのやり方で人間の脳や心や意識について語ってみたいと思っているんです。山本くん、どうですか?
山本 下西さんのご指摘のように、吉川くんにしても私にしても、ある問題に関心をもった場合、その語り方や条件に遡って考え直すということをしている気がします。私は「専門は何ですか」と聞かれると、このところは「学術史です」と答えています。言い換えると、分野を問わずさまざまな学術において人があれこれの対象についてどのように認識してきたかについて認識したい。人間が過去に何を認識してきたか、その認識のあり方を辿り直すことに興味があります。なにかそのような視点から見えてくるものがあるんじゃないかと思ってのことでした。
下西 ありがとうございました。
山本 さて、そろそろ時間が尽きますが、最後に好奇心でおうかがいしたいことがありまして……。今回、原稿を書いたにもかかわらず本に組み込まれなかった二つの章ではどんなことをお書きになったのでしょうか。
下西 一つは、この本の出発点になったヴァレラという人についての、取扱説明書みたいなものです。彼は一九四六年に生まれ、二〇〇一年に亡くなったのですが、それはちょうど二〇世紀の後半と重なっています。ヴァレラは二〇世紀後半のアメリカの科学に想像力の核となる思想を提供してきた人物でもあるので、彼がどのような人生を送ったのかを辿ることで、戦後アメリカの自然と技術をめぐる思想を再検討する試みでした。それは、コンピュータの思想だけでなく、ビートニク文学や仏教や瞑想、ヒッピーカルチャーも混じり合った奇妙な文化・思想です。その思想については、第六章の「漱石とサイバネティクス?」という節でも少し書きましたが、ヨーロッパに比べて、急速な近代化を遂げなければならなかったアメリカと日本では、ヨーロッパでは対立項として捉えられている自然と技術がねじれた関係を結ぶ現象が起きました。そのことについて、もっと長く深く書いていた章があったんです。もう一つは第II部の日本編で、『万葉集』と『古今和歌集』を読むことで日本における心の発生と展開を見ていった後、すぐ漱石の話に飛ぶじゃないですか。これ、ちょっとジャンプが大きすぎるんじゃないかと思った人もいるかもしれないんですが、その間を書いていたんです。
山本 おお、なんと。
下西 漱石に至るまでの間に、西行と芭蕉について書いた、「西行と芭蕉」という章がありました。西行は、意識と自然の乖離にものすごく苦しんだ人でした。和歌によってその苦しみを一回引き受けるという作業があり、続く芭蕉は「よく見れば薺花咲く垣根かな」とか「山路来て何やらゆかしすみれ草」といった俳句に象徴されるように、自然と心の再縫合プロジェクトを遂行していった。そこで心と自然は結びついたにもかかわらず、漱石の頃に西洋近代の思想が入ってきて、心と自然は再び分断されていってしまった。西洋のコンテクストと日本のコンテクストから来る、二重の苦しみが漱石のなかにはあった……という構図を作ることで、日本編の見通しがさらによくなるかなと思ったんです。
山本 文藝春秋さん、ぜひこの二章も刊行をお願いします。
吉川 文春新書でもいいです!
下西 いえいえ。この本を書き上げて、今はエネルギーのすべてを失っているので……。
山本 下西さんにやる気を出してもらうためにも、みんなで『生成と消滅の精神史』を買いましょう(笑)。
〔本稿は二〇二三年一月二四日に代官山蔦屋書店にて開催されたトークイベント「心はどこから来て、どこへ行くのか?」を再構成したものです〕
吉川浩満(よしかわ・ひろみつ)●1972年生まれ。文筆家、編集者。慶應義塾大学総合政策学部卒業。著書に『理不尽な進化』『哲学の門前』など。ウェブサイト「哲学の劇場」では山本貴光氏と文系、理系を問わず良書をわかりやすく紹介、批評している。
下西風澄(しもにし・かぜと)●1986年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。現在は哲学に関する講義・執筆活動を行っている。2022年、初の単著となる『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』を上梓した。
山本貴光(やまもと・たかみつ)●1971年生まれ。文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。慶應義塾大学環境情報学部卒業。著書に『マルジナリアでつかまえて2』『記憶のデザイン』など。吉川浩満氏とウェブサイト「哲学の劇場」を主宰。
構成●吉田大助
(「文學界」4月号より)