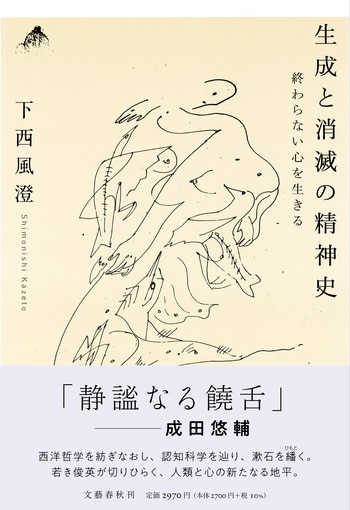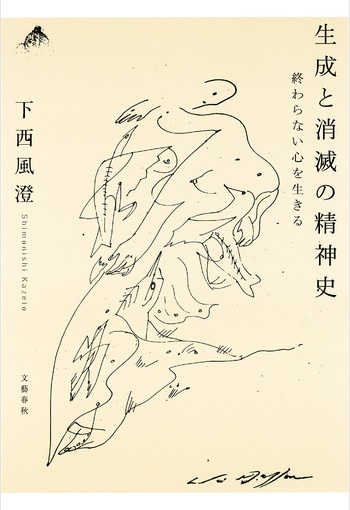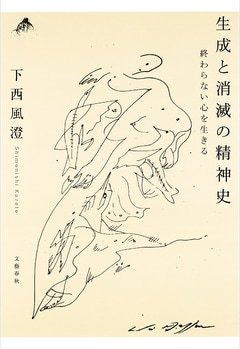■科学と哲学のズレと断絶
山本 別の必然性とはどんなことでしょう。
下西 それは、僕が大学院でフランシスコ・ヴァレラという神経生物学者の仕事を研究していたことに深く関わっています。彼は生物学者でありつつ哲学、現象学にも携わっていた人で、「ニューロ・フェノメノロジー(神経現象学)」という学問を模索していました。科学的に心を見ることと、哲学的に心を見ることの折り合いを付けようとしていたんです。言い換えれば、第三人称的に自然科学が心=脳だと考えて、進めている脳の経験的な研究と、主に哲学が担ってきた第一人称的に心を内側から考察していく超越論的な研究のズレや断絶を解消し、両者の橋渡しをしようとしていたんです。でも、そこには理論的な困難が強く残っている。そこで、僕はそのようなズレや断絶が歴史的に見て、どのように生じてきたのかを辿り直してみようと思ったんです。だからこそこの本は「人間」を経験的かつ超越論的な二重の存在と規定したフーコーから出発し、ソクラテスに意識の最初のメタ化を読んだり、パスカルに意識と宇宙の相互包摂を遡行的に見出したりしました。
山本 お話を聞いて、この本はもちろん頭から読んでもいいけれど、ヴァレラを論じた章をまず読んで、それから冒頭に戻る、という読み方もあると思いました。
下西 そうかもしれません。
山本 これはご本でも詳しく論じられていますが、「私たちが心とか意識と呼んでいる現象をどう説明できますか」という問いに対して、現在、目覚ましい成果を挙げているのは神経科学ですね。脳を構成している神経細胞のネットワークとその働きを研究する手法です。それがわかれば、心や意識といった現象も説明できるのではなかろうか、という作戦です。それでうまく説明できることがある一方で、神経細胞を外から客観的に見ても、この私が感じている意識の質感そのものは扱えないという難問は残ります。第I部で論じられた哲学のアプローチが必要となる場面ですね。心や意識に主観から迫るやり方、客観から迫るやり方の二種類をどう橋渡しできるか、どう重ねられるか。下西さんは、ヴァレラからその問題を引き継いだわけですね。
下西 その問題意識は、山本さんと吉川さんとも共通していると思います。お二人の共著である『心脳問題』(朝日出版社)は、まさに「心と脳の関係は?」という問題について書かれた本ですから。あの本では客観的で科学的な世界像と主観的な世界像の重なり合いや錯誤の問題を中心に論じていますよね。
■心が悲鳴を上げている
山本 そうですね。心について考える場合、先ほど下西さんがおっしゃったように経験的な思考と超越論的な思考の二つのアプローチを取れることから生じる困難があります。下西さんが書いておられるように、「心とは何か」について考えるのもまた心というわけです。「心とは何か」を考えるには、一方では自分の心で何が起きているのかを経験として捉えて考える道がある。これは経験的な思考と言われます。他方では、その経験はどのような条件から生じるか、どのような限界を持っているかを考えるという道もある。これは超越論的な思考と呼ばれます。しかも厄介なことに、この経験的な思考と超越論的な思考は、互いに互いを呑み込んでいるような相互包摂的な関係にある。下西さんは、この困難によって出現した問題にも真摯に向き合い、緻密に解きほぐしていると思いました。
そのようなことを考えたのは、現在進行中の第三次人工知能(AI)ブームからの連想でもあります。第二次AIブームの頃までは、超越論的に心や知能、AIを考える視点が顕著でしたが、このたびのブームではさほど前面に出てきません。
人工知能の父とも言われる数学者のアラン・チューリングは二〇世紀前半、「知能機械」ということを盛んに論じました。そこでチューリングは、「計算機がもし知能と呼べるような働きをするとしたら、それはどういう条件のとき、何ができたときだろうか」ということをいろんな角度から考察しています。チューリングでは、心や知能、AIを超越論的な視点と経験的な視点の双方から見る態度が失われていなかった気がします。現在のAI研究では、超越論的なことは考えなくても、機械翻訳にせよ、画像の自動生成にせよ、会話にせよつくって試してみることもできる。かつてはコンピュータの性能もいまと比べて貧弱でしたから、理屈のほうから考えざるを得なかったという事情もあるのでしょう。
吉川 実装されるAIの機能の向上にばかり注目が集まって、超越論的な視点から考える勢力はすごく小さくなっていきましたよね。どうしてこのような状況になったのかには、いろんな要因があると思うんですけど、下西さんがこの本に書いていた考察を読んだとき、思わず膝を打ちました。いい本を読んだときによくあることなんですけど、「俺もそう思っていた」というやつです(笑)。
山本 えー(笑)。
吉川 現代人はあまりにも過剰な役割を心に持たせてしまっていて、もはや個人では負いきれなくなっている。それゆえその仕事の一部を外部にアウトソースしたいから、AIにどんどん夢を託す状況があるんじゃないか、と下西さんは指摘されている。読むまでそんなふうに言語化できていたわけではなかったんだけど、読んだ瞬間に「俺もそう思っていた」という偽の記憶が立ち上がりました(笑)。
下西 僕たちはもう考える主体でなくともいいのではないか、ということが、AIが出てきたときに最も喚起される僕たちの感覚なんじゃないかと思います。その問題意識と同時に僕が考えたかったのは、AIは突如として登場した技術ではない、ということです。つまり、僕たちの意識には、外界で起きていることを表象して、内面に持ち込み、それらを情報として処理する機能があるんじゃないかと考えたからこそ、じゃあ情報処理するような機械を作れば意識がそこに生まれるんじゃないか、と進んでいった。この順序が重要だと思うんですね。じゃあこの思考を情報処理として捉える発想がどこから出てきたかというと、直接的にはさっき山本さんが言及したアラン・チューリングで、もうちょっと遡ればライプニッツになるわけですが、僕は本に書いたように、その発想をソクラテスのなかに見出しました。ほとんど誰も読まないようなプラトンの『ピレボス』という対話篇のなかで、ソクラテスは「プシュケー(魂)」とは紙のなかに文字を書いたり、イメージを描いたりするようなものなんじゃないかと述べているんです。人間にはある種のメモリーがあって、そこにデータを書き込んでいく、そのデータの書き込み装置こそが「心」と呼ばれるものなのではないかと。ソクラテス以前のホメロスの叙事詩では、「プシュケー」には魂だけでなく、風とか大気の意味もありました。ホメロスの時代では、心はまだ人間の内側に閉じ込められてはいなくて、刻々と変化する環境のなかで、人間と環境の間にその都度、生起し、移ろい消えていくような出来事や現象としてあった。日本的な感じで言えば、それは「鳥と共にある」とか「風と共にある」といったかたちで発生するものだった。でも、ソクラテスは自分のなかに外界の出来事が書き込まれていくデータの情報処理プロセスこそが「心」だと考えた。そこからの必然的な帰結として、身体への侮蔑が始まります。西洋哲学の祖と言われるソクラテス、プラトンの哲学のなかには、人間の身体なんていらないものであって、最も重要なのは、むしろ情報処理機構としての心なんだという発想が埋め込まれているんです。それが連綿と改変を続けて現代まで来た結果として、AIみたいなものが登場する。AIもやはり僕たちの欲望の反映の結果である、と捉えることが重要ではないかと考えています。
■日本の小説は「気」が多い!?
山本 今の古代ギリシャの話に並べてみたいのは、古代中国の例です。私はしばらく前から「群像」で「文学のエコロジー」という連載をしているのですが、このところは「文学においては心をどう記述してきたか」を検討しています。もっとも下西さんのご本とは比較にならないぐらい少ないサンプルです。二〇二三年の二月号では、林芙美子の小説『浮雲』を例に、日本語で心がどう捉えられているかを確認してみました(「『気』は千変万化する」)。これは全体で二十三万字の作品なのですが、およそ八百箇所に「気」の字が出てくる。なかには「電気」や「天気」という「気」もあるので、全部が全部というわけではないものの、「気持ち」「元気」「気が滅入つて」「気紛れ」「悄気てゐる」と、ともかく「気」が満ちているんです。これは一体どういうことだろうと思って他の作家の作品も見てみたら、明治期から現代まで日本語の作品のそこかしこに「気」が現れる。本人たちがどこまで気にしているかわからないけれども、これは面白いことだと思ったのですね。
下西 興味深いです。
山本 こんなとき頼りになるのが『気の思想』(小野沢精一ほか編著、東京大学出版会)です。中国発祥の「気」の思想を時代ごとにまとめた研究書です。同書を見ると、中国の「気」は物質的で、天地開闢以来の宇宙論、世界を構成する万物の根幹をなすものであることがわかります。これはまだきちんと追跡できていないので推測になりますが、日本ではある時期、この中国の「気」の思想を採り入れた。ただし、どうやら物質の側面は薄れていって、心にかんする概念になっていく。
下西 山本さんは中国の「気」について「物質的」というふうに言ったけど、それは「形而上学的」(理念的)でもあるだろうと思います。実際、『易経』における「気」は宇宙の形而上学的な思想に基づいています。これは「気」に限らずなんですが、ある特有の考え方が日本に入ってくると、理念や思想が脱色されたフレーバーだけが残って漂い続ける。僕はこの本で「西洋編」と「日本編」という二本の柱を立てたんですが、普通に考えれば「西洋編」と「東洋編」になると思うんですよね。そこで「日本編」とした理由は、まさに「気」に象徴されるような日本特有の特殊な空気は、日本が輸入した中国の思想や文化からだけでは捉えきれないと思ったからです。「気」の問題は、当然「空気」にも通じていて、ある意味では日本の問題そのものでもあります。