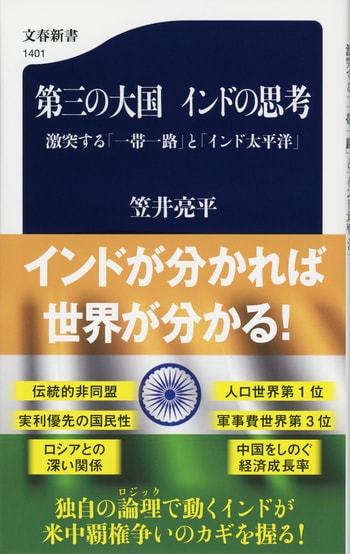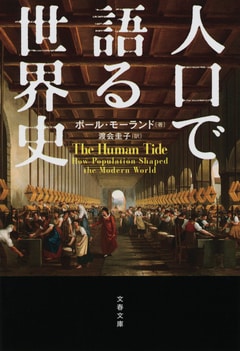文春新書の新刊『第三の大国 インドの思考 激突する「一帯一路」と「インド太平洋」』(税込・1,100円)は、在インド、中国、パキスタンの日本大使館に外務省専門調査員として赴任したアジア情勢研究の第一人者である笠井亮平さんが、現在のインド、さらには中国も徹底的に分析、解説した充実の一冊。世界の政治経済の動向や、今後の日本の進む道を構想し、ビジネスを優位に進めていくにあたっての情報や分析が満載です。
今回は、発売を機に、本書に掲載されたコラム「中華料理を通して見えてくるインド、パキスタン、ネパール」を公開します。
日本ではなかなか食べることが出来ない「インディアン・チャイニーズ」とは? なぜガラパゴス的な発展を遂げたのか?
独自の進化を遂げた、インディアン・チャイニーズ
中華料理ほど、世界各地に広まっている料理はないだろう。アジアはもちろん、アメリカ、ヨーロッパ、果てはアフリカまで、どこに行っても一軒くらいは店が見つかるものだ。
ご多分に漏れず、インドにも中華料理はある。しかし、かなり独自の進化を遂げており、「インディアン・チャイニーズ(インド中華料理)」という新たなジャンルを形成している。筆者は中国の北京にも駐在していたことがあるが、その経験からしても、一見しただけでは中華と思えないような料理も少なくない。
たとえば「レモンチキン」。レモン汁やチリパウダー、ターメリックなどでマリネした鶏肉をみじん切りにした玉ねぎと炒め、醤油やガラムマサラなど複数のスパイスで味を調えて完成という一品だ。また、「ゴビ・マンチュリアン」もインド中華の定番メニューだ。「マンチュリアン」と言っても満洲とは関係がなく、「中国」というほどの意味で、スパイシーで濃い茶色のソースで炒めた料理を指す。ちなみに「ゴビ」は「ゴビ砂漠」─ではなく、ヒンディー語で「カリフラワー」という意味だ。他にも、アメリカ経由で入ってきた「アメリカン・チョプスィ」、南インドの人気メニュー「ドーサ」を唐辛子メインの「シェズワン(四川)・ソース」で仕上げた「シェズワン・ドーサ」をはじめ、フュージョンを重ねた料理がいくつもある。
念のため言うと、こうしたインド中華料理がマズいというわけではない。むしろ、日本人にはインド料理以上に口に合うのではと感じるほどだ。インド人も、都市部ではインド料理ばかり食べているわけではなく、こうしたインド中華も人気だ。東京のインド料理店の中にインド中華を出す店が数軒あるが、日本駐在中のインド人とその家族に支持されている。海外在住の日本人が「町中華」を懐かしむようなものと言えるだろうか。
印中関係の冷え込みが、ガラパゴス的進化を促した
これほどに独特なインドの中華料理は、どうやって形成されたのか。はじめてインドに中国系の移民が来たのは18世紀後半で、カルカッタ(現コルカタ)郊外に定住したと言われている。ここからしだいに中華料理が広まっていったのだが、その過程でインド人の味覚に合わせるべく、現地のスパイスが使われるようになったようだ。ちなみに、コルカタには現在でも小規模ながらインド唯一のチャイナタウンがある。
1962年の国境紛争以降は、印中関係は四半世紀以上にわたり冷却化した状態がつづいた。この間、本場の中華料理が入って来なかったことで、さらに「ガラパゴス化」が進んだ。「マンチュリアン」系の料理ができたのは七五年と言われており、まさに印中が「没交渉」だった時期と重なる。
食材面で言うと、肉の種類が限られるという制約があった。インドでは総人口のうちヒンドゥー教徒が約80%、ムスリムが約14%を占めているのもあり、牛肉と豚肉という、中華料理では定番の食材が使えない。魚も、コルカタやパンジャーブといった一部の地域を除きあまり食べられていない。そうすると肉はどうしても鶏肉がメインになり、そこでバリエーションを増やす方向に進んだのではないかと筆者は見ている。