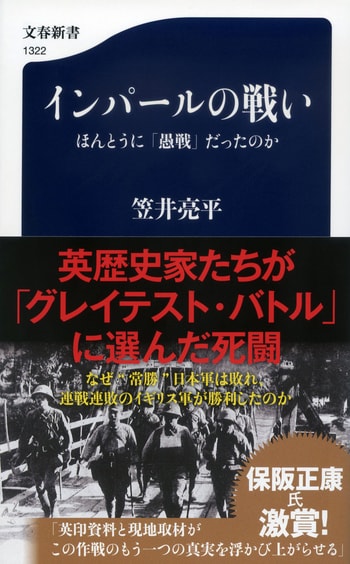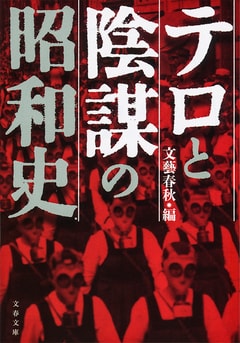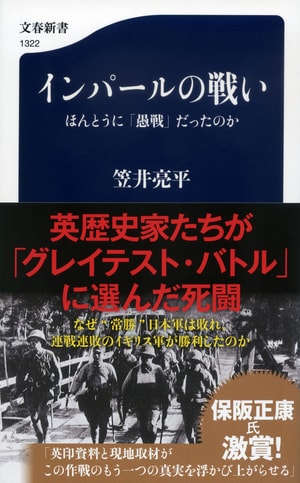
二〇一九年も暮れようとしていた一二月末のある日、わたしはインド北東部マニプル州、インパールの地に降り立った。かつて日本軍が想像を絶する過酷な環境のなかで、甚大な犠牲を払ってでも到達しようとしてついに叶わなかった目的地だ。
しかし、その場所に自分がいることにどうも実感が湧かなかった。それは何と言っても、あまりにあっさりと現地に着いてしまったからだ。前日の午前中にはまだ成田空港にいて、搭乗前には眩しく感じるほど明るい照明のもと、手土産にと日本の菓子を売店で買っていた。成田からデリーへ行き、一泊した後に国内線の直行便に乗ると、昼過ぎにはすでにインパール空港に到着。成田を出てから二七時間しか経っていなかった。
到着翌日から、戦跡めぐりを開始した。最初、ここは一体どこなのだろうという不思議な感覚があった。「インパールの戦い」における主戦場のひとつ、ティディム・ロードからインパール市内に戻る途中、戦跡ガイドのヤイが車を止めさせ、刈り入れが済んだ田んぼのあぜ道に連れていってくれた。西側にそびえる丘陵地帯を指差し、あの稜線を日本軍が行軍していったのだと教えてくれた。ちょうど夕暮れ時で、太陽が山の彼方に沈もうとしているときだった。その風景は、凄惨な戦闘が行われた現場というよりは、日本の農村と言ったほうがしっくりきそうだった。当時も同じような風景を見たであろう日本軍の将兵は何を思っただろうか。故郷の山河や家族の姿を思い浮かべただろうか。それとも、空腹と行軍に次ぐ行軍、それに飛び交う銃弾のなかで、感傷的な思いにひたる余裕はなかっただろうか――そんなことを考えながらわたしは眼前に広がる景色を眺めていた。
マニプル州各地の戦跡をまわるなかで、案内を頼んだ戦跡ガイドのヤイと、インパールの戦いをめぐり多くの話をした。マニプル出身の彼はデリーやコルカタ(旧カルカッタ)で学んだ後、地元の歴史、とくに第二次世界大戦期に現地で何が起きたのかを知りたいと思うようになり、二〇一〇年からは戦跡ガイドの仕事をしている。戦時中に撮影された白黒写真を手にインパールやコヒマ、さらにはミャンマー(旧ビルマ)側の戦跡を丹念にまわって当時と現在の状況を比較したり、膨大な量の英語文献や地元の資料にあたって細部まで検討を加えたり――ヤイからは、ガイドというよりフットワークの軽い、アクティブで情熱的な学者のような印象を受けた。インパールやコヒマの戦いについてマニプルやナガランドの古老たちからの聞き取りも重ね、その成果を一冊の本にまとめて二〇一九年に出版することもしている。
ヤイの客はイギリス人が大半を占めるということだった。英印軍(イギリス植民地下のインド軍。兵士はインド人やグルカ族で、指揮官はイギリス人将校。ただし、インド人将校もいた)の側で戦った将兵にとって、インパールやコヒマは苦難の末に勝利を収めた「栄光の地」なのだろう。それだけに、ヤイはイギリス側の見方に精通していた。
「イギリスの博物館が自国の『最大の戦い』を決める企画を行ったことがあるのですが、そこで選ばれたのが『インパールの戦い』でした」――イギリス側がインパール作戦をどう見ているかに話が及んだとき、ヤイがそう言った。「東のスターリングラード」と呼ばれている、とも。
後日調べてみると、彼の言うとおりだった。二〇一三年四月の国立陸軍博物館による企画で、参加した歴史家たちはインパールとコヒマの戦いを「グレイテスト・バトル」に選んでいたのだ。一九四四年のノルマンディー上陸作戦や一八一五年にナポレオンを破ったワーテルローの戦いを抑えての選出だっただけに、BBCは「サプライズだ」と評している。
「東のスターリングラード」という表現については、すでに一九五五年に出版されたインドの文献で「独ソ戦におけるスターリングラードと同じように、ビルマ戦においてインパールは重要な役割を担った」という言及が見つかった(S. G. Chaphekar, A Brief Study of the Burma Campaign, 1943-45, p.48)。その後、英文の戦史書や記事でインパールやコヒマの(戦いを紹介する際に使われるようになり、最近ではCNNのウェブ記事のタイトルにも登場している(“Revisiting India s forgotten battle of WWII: Kohima-Imphal, the Stalingrad of the East”〈「『東のスターリングラード』ことコヒマ・インパール:インドの忘れられた第二次大戦の戦いを再考する」〉, CNN, October 5, 2020)。
この結果はわたしにとっても意外だった。日本でインパール作戦と言えば、たしかに「激戦」という言葉がついてまわるが、その敗北は英印軍との戦いもさることながら、「自滅」によるものだという印象が強かったからだ。実際、作戦には日本軍の三個師団が参加したが、戦病死や餓死の割合が大きく、戦死者数を上回っていた師団もあったほどだ。手持ちの食糧が底をついても補給などなく、モンスーンがもたらす猛烈な雨のなかでマラリアやアメーバ赤痢といった感染症が蔓延、命尽き果てた将兵の死体は打ち捨てるよりほかなかった――「白骨街道」という言葉とともに、そんなイメージを抱くことが多いのではないだろうか。部下の慎重論を排し、兵站を無視して作戦を強行した第一五軍司令官・牟田口廉也中将の「無謀さ」にも、必ずと言ってよいほど非難の矛先が向けられる。
そんな日本軍が相手だったのだから、英印軍からすれば、「楽勝」とは言わないまでも、終始自分たちのペースで進められる、余裕のある戦いだったはずだ。それがなぜ、「最大の戦い」と位置づけられるのだろうか。スターリングラードに比せられるほどの激戦になったのはなぜか。それほどまでに重視されるインパールの戦いは、英国にとってどのような意味を持っていたのだろうか。
そんな日本軍が相手だったのだから、英印軍からすれば、「楽勝」とは言わないまでも、終始自分たちのペースで進められる、余裕のある戦いだったはずだ。それがなぜ、「最大の戦い」と位置づけられるのだろうか。スターリングラードに比せられるほどの激戦になったのはなぜか。それほどまでに重視されるインパールの戦いは、英国にとってどのような意味を持っていたのだろうか。
わたしはインドをはじめとする南アジアを研究する立場から、インパールの戦いに注目してきた。外務省の仕事でインドやパキスタンの日本大使館に駐在したこともあり、両国の都市部から辺境まで各地を訪ねてまわってきた。二〇一六年には、戦前に日本で生まれ育ち、インド国民軍(INA)の女性部隊に参加したインド人少女の物語を軸に、インド独立運動と日本の関わりをテーマとした本を上梓した。
当時からインパールの戦いを取り上げた膨大な数の文献に接してきたが、そのなかで気になって仕方がないことがいくつかあった。そのひとつは、議論の方向性や記述の内容がひどく内向きなことだった。作戦に参加した将兵自身が記したものであれば、ビルマ・インド国境線にあるアラカン山系を越える行軍や補給の途絶、感染症の蔓延がいかに過酷だったかが縷々としてつづられている。リーダーシップや意思決定の観点から論じたものであれば、牟田口廉也第一五軍司令官の「暴走」とそれを止められずに作戦を容認してしまった河邊正三・ビルマ方面軍司令官や大本営の対応を批判的に取り上げる、といった具合だ。
もちろん、それを否定するつもりは毛頭ない。とくに、将兵の回想録や連隊の文集、記者のルポルタージュを読むときは、筆舌に尽くしがたいほどの戦場の残酷さゆえに、いつも胸が締め付けられるような気持ちになる。生還者の多くが当時の状況を「この世の地獄」と表現しているが、誇張とはとても思えない。司令官を責める議論にも妥当性はあるし、そこから引き出せる教訓はいくつもあるだろう。
ただ、ここで問題にしたいのは、戦いの相手である英印軍の存在が希薄に感じられるという点なのだ。種々の文献で英印軍のことが出てこないわけではない。たとえば、要衝のコヒマを占領した第三一師団の関係者は、敵軍との間に繰り広げられた壮絶な攻防戦の様子を克明に記している。しかし全体としては、英印軍はどこか遠い彼方の存在という印象を受けることが多かった。同じことは、友軍であるはずのINAについても当てはまる。作戦当時、従軍記者として現地で行動をともにした丸山静雄氏の著作など若干の例外を除いて、INAに話が及ぶことはまれで、取り上げられる場合でもごく簡単にしか触れられていないのである。