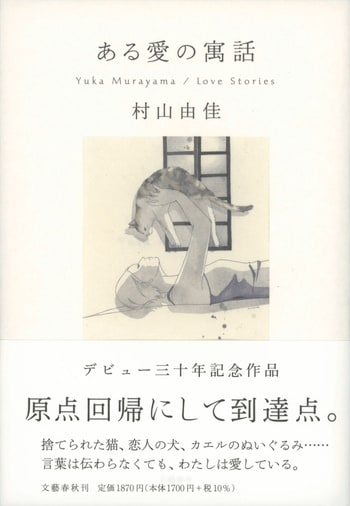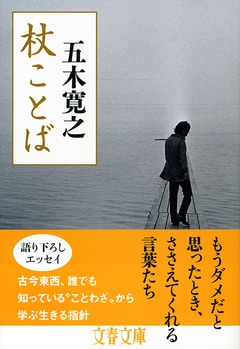うらやましいボケ方
五木 それに関連してあと一つ、村山さんの「訪れ」には、ちょっと変わった奥さんが出てくるじゃないですか。お金の使い方が荒かったり、洗い物が苦手だったり。
村山 シベリア帰りの老人の奥さん。
五木 その奥さんの晩年に、少し認知症が出てくるでしょう。もともと変わっていた奥さんが、さらに違ったような人柄になっていく。いま多くの人が不安を覚えているのはまさにこれで、言い方は乱暴だけれど、ボケた人間とボケてない人間がいかにして共存していくかというのが時代の大問題なんです。「訪れ」にはその断片が描かれていて、お風呂の世話をしていた旦那さんがつい奥さんを叩いて、奥さんが「お父さんごめんなさい」と繰り返すシーンがすごく印象に残っています。あのあたりの描写は、いまの人々が持っている大きな不安に触れている気がして、僕はこれは現在の小説家の大事な仕事だなというふうに思いました。
村山 ありがとうございます。私の母も長いこと認知症だったんです。最終的にはふわふわっとした中で逝ったので、思えば幸せな最期だったのかもしれないんですが、実は祖母と母がまったく同じボケ方をしたんですよね。
五木 へえ、同じボケ方をね。
村山 祖母を看ていた頃、私は高校生だったんですが、後年、母の姿を見て「おばあちゃんと同じだ」という驚きが私自身の恐怖になりました。別の機会に血液検査をして、自分はアルツハイマー遺伝子を持ってないとわかった時はどんなにホッとしたことか。
五木 人間は、体が衰えていくのと同じように年をとると意識も混濁していきます。実に自然な形として混濁していくわけですが、それを遅らせようとか元に戻そうというのではなく、正しく混濁していく、正しくボケていくことが大事なんですね。久しぶりに「文藝春秋」で「うらやましい死に方」という企画をやったんですけれど、その前段階に「うらやましいボケ方」があるんじゃないかと。
村山 なるほど、小説のテーマにもなりそうですね。
五木 先日、新聞の投書欄に、女子中学生の文章が載っていた。彼女のおじいちゃんは謹厳実直な人で、口数が少なく、怖くて、正直言って嫌いだったと。ところが、ボケ始めてからは自分の話を何となく「うんうん」と聞いてくれるようになり、人柄が穏やかになって、人を咎めるような目つきをしなくなった。「わたしはいまのおじいちゃんが好きです」と結ばれていたんですが、そうか、こういうボケ方があるんだなと感動しましたね。
小説に未来はあるか
五木 ところで、ちょっと話が大げさになりますけれども、小説の未来についてはどうお考えですか?
村山 三十年前のことを振り返ると、時代がまだよかったし、環境にも恵まれて、デビュー作からベストセラーという形で送り出してもらえて、幸運だったと思います。その後、いまに至る中で、それこそ初版部数とか、売れ行きとか、重版のかかり具合の面で、ことに小説の場合はどんどん影がさしてきています。それが不安な一方で、本を読まなくなった読まなくなったと言われて久しいけれども、「小説が好き」という読者は確実にいらっしゃるので、なんだかんだ言って先々まで残るのは紙の本なんじゃないかという希望も持っていますが。
五木 映画が発明された時、これで演劇はなくなると言われたんですね。劇場もなくなると。しかし全然なくならないどころか、十九世紀に比べて現在のほうが劇場は多い。テレビが出てきた時にはこれで映画が終わると言われてね。だけど、全然映画は終わっていない。いわゆるSNSが出てきた時、いよいよテレビも終わると言われたけれども終わっていません。つまり、一つのステータスを持った表現領域は、これからも豊かにぜんぶ残っていくと思っているんだけど。
村山 音楽もそうですね。いまアーティストはこぞってレコードを作る。

五木 その時期その時期に応じて新しい表現の形態が出てきて、時々にメジャーな分野は変わっていくけれども、とにかくずっと続いていくと思います。演劇も映画も、詩や歌、それから小説、もちろん紙の本もね。小説家も、いまネットの世界から出てきて、ネットで発表して評価を得ている人も多いでしょう。
村山 小説でなければ、言葉でなければ、手の届かない領域というものが確実にありますから。
五木 じゃあ、最後、新しい書き手に向けて、ベテランとして(笑)、一言アドバイスを。
村山 畏れ多いです(笑)。ずっと、自分はぶきっちょだなと思いながらも、それが自分の持ち味だと考えるようにしてきました。それこそ、最初のデビューの時、『天使の卵』の選評として五木さんが贈って下さった言葉というのが、凡庸さに徹することができるのも才能で、鈍さもまた才能なのだから、それを磨いてシャープにしようなどと間違った考えにとらわれず鈍さをのばしていきなさい、そうすればこの書き手は一家を成すかもしれない、というものでした。
二十九歳だった私は、失礼な言い方になりますけど、正直「どうしてこんな持って回った嫌味を言われなきゃいけないんだ!」と憤ったものです。
五木 選者のひとことは残るよねえ(笑)。
村山 はい(笑)。でも違ってました。最初から五木さんは私の資質をきっちり見抜き、肯定して下さっていた。自分の愚直さをスタートの時点で肯定していただいて、私もそのようにやってきて三十年生き残ってこられたのだから、愚直に、不器用に小説と取り組んだのは正しかったんだ、といまは思えます。
五木 小説を三十年続けるのはすごいことなんですよ。
戦後日本にまだジャズの本格的なプレーヤーが来ることが少なかった時代、ジーン・クルーパというドラマーが来日したんです。その時、日本のあるジャズ青年は、黒人でない自分にブルースがやれるのか、日本人のジャズは所詮イミテーションじゃないかという悩みを抱えていた。彼は楽屋に忍び込んで、ジーン・クルーパに質問したんですね。「一言アドバイスを」と求めたら、本当に一言、「Keep on」と言ったという。聞いた話だけど。
村山 おお! 続けなさいと。
五木 村山さんには、どこかシベリアの女性将校のような逞しさを感じるところがあるんだよね(笑)。
村山 あのバズーカのような?(笑)
五木 いやいや、ルッキズムは駄目です(笑)。とりあえず、今後、危険なこともどんどん追求されていくと面白いと思いますね。
村山 ありがとうございます。私にとっては、いつもいろんな雑誌に五木寛之という「偉大な父」の名前があることが励みで、ずっと第一線で意欲的に書き続けてらっしゃるお姿を見るたび背筋が伸びるんです。
五木 どんな形でも続けて、書き続けていくということが大事だよね。村山さんは「愚直」と言いましたけど、「Keep on」も同じことかもしれない。
村山 キラキラした才能、尖って何かをバンと穿つような才能が自分にないことが、デビュー直後はコンプレックスでした。でも、不器用だからこそ、コツコツ書いて形になった時には、最初からうまくやれた人よりも、少しでも遠くへ行けたみたいなことがあればいいかなと。
五木 三十年で満足しないで、これから先の三十年も「全方位的作家」でね。
村山 はい、胸に刻みます。
◆村山由佳さんのインタビューが「本の話」ポッドキャストでお聴きいただけます。