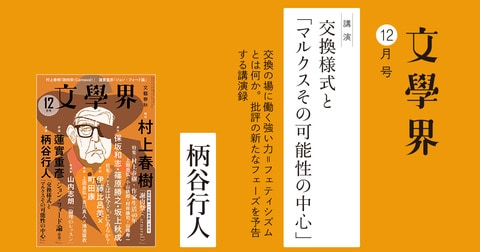二〇二二年十二月、アメリカのシンクタンクが「哲学のノーベル賞」を目指して創設した「バーグルエン哲学・文化賞」を、柄谷氏へ授与すると発表した。
百万ドル(受賞時のレートで約一億四千万円)という賞金も話題になった。
「交換の力」を考え続けたこれまでの歩みを語る。
『力と交換様式』
今回の受賞に際して、皆が真っ先に注目するのは、賞金の額のようです。そして、これだけの賞金をもらうんだから立派な仕事をした人なんだろう、と考える。私自身、やはり賞金に驚きました。この取材がきたのも、その力でしょう(笑)。賞を設立したバーグルエン氏は、この賞に「哲学のノーベル賞」としての権威を与えるには、ノーベル賞と同額の賞金を出さなければだめだ、と思ったのでしょう。しかし、選評からも分かるように、バーグルエン氏は、事業家ではあるけれど、哲学について非常によく分かっている人なのですね。
賞金の使い途をよく尋ねられますが、これほど大きな額のお金の使い方は、考えたことがなかったから、そんなに簡単には決められません。今回の受賞ではじめて、お金をどう使ったらいいのかを考えさせられましたね。
「アソシエーション」と私が呼んでいる、社会運動の組織を援助する資金ができた、とは思っています。アソシエーションには様々な形がありますが、協同組合や労働組合のようなものと考えてもらえれば、分かりやすいかもしれません。すでに二つのごく小さな組織への寄付を決めましたが、残りについては、おいおい考えていくつもりです。受賞が決まってから、為替も大きく動いたので、友人たちには「一番ドル高のときにもらえればよかったのに」と残念がられたりしました。皆、どうしてもお金の話にいってしまう(笑)。
「柄谷行人」ができるまで
柄谷氏は一九四一年、兵庫県尼崎市出身(本名・善男)。一九六九年に文芸批評でデビューして以来、著作を間断なく発表し続けている。善男少年はいかにして「柄谷行人」となったのか。
私は変わった子どもだったと思います。小学校に入学してから二年間、ものを言わなかった。教室でも家でもほとんど話さなかったのです。何かに深刻に悩んでいたわけではありません。対人恐怖症でもなくて、ただ何となく話さなかっただけです。その後、自然に話すようになりましたが、人前に出るのは好きではなかったので、それが文学になじんだことと関係があると思います。
家には読書家だった父の本が沢山あったので、自然と本を読むようになりました。父からは「本を読め」と言われたことは一度もなかったけれど、たぶん、私が本を読んでいたことを喜んでいたと思います。父は本当は学問をやりたかったのではないでしょうか。左翼的な人で、その類いの本がずいぶんありました。
繰り返し読んだのはアレクサンドル・デュマの『モンテ・クリスト伯』や、吉川英治の『三国志』などです。その他に、家にあったので、大人向けの文学全集や哲学書も、小学生のころから、読んでいましたよ。
柄谷氏は西宮市にある中高一貫の名門、甲陽学院に進み、そこから東京大学文科一類に進学する。
小学校は地元の公立でした。自分が勉強できるとはあまり考えたこともなかったけど、高学年のとき、先生から私立校への進学を勧められました。「灘より甲陽のほうがいいよ」と。私はどちらも知らなかった。ちなみに、灘は白鶴、甲陽は白鹿と、どっちも日本酒の酒造が設立した学校なんですが、当時はまだ進学校として知られてはいなかった。私も知らなかった。
その先生は、旧制の甲陽中学で野球をやっていて、その後も少年野球のコーチをしていたのです。甲子園球場の真横にあったこともあって、甲陽中学は戦前から、野球が盛んで、強かった。阪神でプレーして、近鉄や大洋の監督も務めた別当薫も甲陽の出身です。
その結果、その先生の指導のおかげで、同じクラスから、三人も甲陽中学に行くことになったのです。中学以後も野球を続けたのは、一人だけです。北川公一という人で、慶應義塾大学を経て、プロでは近鉄に入団しました。しかし、私ともう一人は違います。その人は、文藝春秋の編集者になった、雨宮秀樹です。娘さんは、アナウンサーの雨宮塔子さんです。
私の場合は、ただ何となく甲陽に入りましたが、野球が自分に向いていると思わなかったから、中学ではやらなかった。かわりに、バスケットボールをやるようになりました。実際、高校のときは、キャプテンでした。
運動にも熱中しましたが、本も熱心に読んでおり、中学生のときにはドストエフスキーの作品をほとんど読みました。すべての書の中で、最初に且かつ最も影響をうけたのはドストエフスキーです。哲学者のデカルトを知ったのも中学生のころ。ソクラテスも好きでしたね。
でも、中高時代に、友人と、本の話や知的な話をしたことがありません。バスケットの友人はたくさんいましたが、彼らとは運動のことしか話さなかった。知的・文学的な友達はいなくて、一人で本を読むだけでした。
球技の他に得意だったのは、数学です。好きというより、たんにできただけですが、全国模試のようなテストで、一位になったこともありました。本番の大学入試でも、数学は最初の三十分で全部解けてしまって、あとは試験時間が終わるのを待っていた、というような生徒でしたね。でも、数学者になれるほどの天才でないことは、自分でも分かっていた。学問として数学をやるなら、そのくらいの年齢で大発見でもしていない限り無理だと思っていましたから。
大学は東大へ行きましたが、それも先生に「なんで東大を受けないんだ」と言われたからです。それで、何となく行くことになった。そもそも大学へ行こうとも考えていませんでした。志望校を書く書類に、自宅から近い神戸大学と書いて提出したことがあります。要するに、大学に関心がなかったのです。
受験では、直前まで理科系を志望していたけど、将来の選択肢が減るから文科系にしました。当時、東大の教養課程は一類(法学・経済学)と二類(文学)の二つで、二類に進むと、やはり選択肢が減りそうだなと思い、文科一類を受けた。その後を考えれば、初めから人文科学を学ぶ文科二類に行っておいた方がよかったのですが。
駒場寮での日々
大学へ進学後、柄谷氏は、まだ学生だった廣松渉(哲学者)、西部邁(経済学者、評論家)、坂野潤治(歴史学者)、加藤尚武(哲学者)らと交流するようになる。
受験のとき、駒場寮を見物しましたが、あまりにも汚くていやだったから、最初は東京郊外の三鷹市にあった東大の学生寮に住むことにしました。入学してしばらく経ってから誘われて駒場寮へ移ったのですが、その部屋が学生運動の中心だったのです。
私よりも上の世代では、駒場寮には学生運動をしていた学生が千人以上もおり、二階すべての部屋がその手の学生たちで埋まっていて、北京通り、モスクワ通りというような呼び名があったそうです。が、一九六一年には、たった二部屋に減っていました。それが社研(社会科学研究会)と歴研(歴史研究会)の拠点で、私はそこに住んでいた。歴研が寝室で、社研が会議室でした。
実は、大学でも短い間バスケットボール部に入っていたのですが、デモで忙しくなり、部活動どころでなくなって、一ヶ月で辞めました。寮にいた頃は、毎日のようにビラを書いていましたよ。でもアジ演説などは苦手で、まったくしたことがありません。
よく私は、ブント(共産主義者同盟)という党派に所属していたと言われますが、当時はもう、正式に加入するような手続きはなくなっていたんです。一九六〇年の安保闘争のデモに行ったために、ブントの人たちと親しくなったけれど、ブントに入る手続きなどはなかった。たまたまそこに住んだ、という感じでした。
ただ、外からは、私が東大駒場を代表するように見えたらしい。駒場があの時代に特異だったのは、他の大学とは違って、学生の大きなデモがあったことです。慶應はデモなんかしないし、早稲田でも少ない。デモが頻繁にあったのは東大だけで、それも本郷校舎ではなく、東大駒場が中心でした。だから本郷や京都からも、よく人が会いにきました。年上の西部邁や加藤尚武、廣松渉なども、寮までよく遊びに来た。
しかし、ふりかえってみると、付き合いがあったのは、皆年上ですね。中学、高校、実は大学でも、私には哲学や文学の話ができる知的・文学的な同級生がいなかった。今から思うと、大学の寮に、よくあんな人たちが集まってきたなと、不思議ですよ。政治運動のためというより、楽しいから、集まっていたのではないでしょうか。彼ら自身も風変わりでしたし、私にとっても、彼らといる空間は、とても居心地がよかった。
結局、私は東大で、本郷にあった学部では、経済学部に進みましたが、大学を卒業する時点で、もう経済学をやる気がなくなっていました。そのころ、私の関心は経済学とか、政治学とか、哲学とかいった既成の学問にはなくて、それらの根底にある何かを考えたい、と思ったのです。文学批評ならそれが実現できると気づき、学部で一年留年をして大学院の英文科へと進んだ。それから本格的に批評を書き始めるようになりました。
私は六九年に群像新人文学賞の「漱石試論」でデビューしましたが、じつはその前にも、東京大学新聞が主催している五月祭賞というのがあって、評論部門で、六六年と六七年の二度佳作に選ばれています(二篇とも『思想はいかに可能か』〔インスクリプト〕に収録)。この五月祭賞は、小説部門で五七年に、大江健三郎が「奇妙な仕事」で受賞して大きな話題になったため、知られるようになったものですが、六七年に終了してしまった。しかし、私のせいではありませんよ(笑)。
その時点からペンネームとして「行人」を使っていました。本名(善男)がいやだったからです。その理由は、いうまでもないでしょう(笑)。
<「柄谷行人」ができるまで──「交換の力」を考え続けた六十年 より>