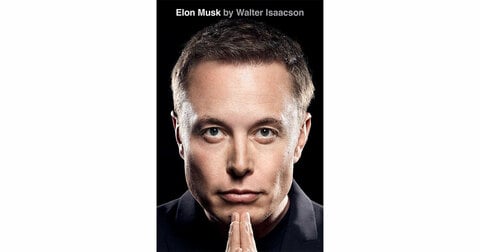『オービタル・クラウド』で日本SF大賞、星雲賞、『ハロー・ワールド』で吉川英治文学新人賞を受賞するなど、SF小説の旗手として注目を集める藤井太洋さんの最新刊がついに刊行になります。
最新作は、VR世界大会を舞台とした青春小説です。
そんな『オーグメンテッド・スカイ』(文藝春秋)より冒頭を紹介します。
どうぞ、お楽しみください!
I 南郷高校蒼空寮
食堂のテーブルに置いたタブレットには、県道から分かれた急坂の桜並木を登る生徒たちが映し出されていた。はらはらと落ちる桜の花びらを額に貼り付けた少年たちは、みな一様に大荷物を抱え、親に連れられて、あるいは親を連れて歩いてくる。
鹿児島県立南郷高等学校の理数科に合格し、親元を離れて蒼空寮で高校生活三年間を送る新入生たちだ。
タブレットの正面に座り、後輩になる少年たちを見守っていた二年生の倉田衛は食堂の時計を見上げた。
「やっと来たね。平川駅の下りは、十二時三十五分だったっけ」
「やっど」と、わざとらしい鹿児島弁で答えたのは、奄美の島言葉を話すはずの結城一郎――ユウキだった。「たった八百メートルに十五分もかかっとらあよ」
マモルとユウキに続いて、タブレットを囲んでいた同学年の寮生たちも口を開く。
「はげぇ、可愛いかねえ!」
「全くだ。俺らもあげん可愛がったっとかい?」
「お前は生意気かったがなあ」
「お前に言わるっとかよ」
「ともかくよ。はげぇ、我きゃぬやっとぅ後輩ぬできゅんちな(うわあ、俺らもようやく後輩持ちかよ)。信じられんがな」
待ち侘びた後輩たちの姿に顔をほころばせる二年生たちは、思い思いのお国言葉で照れ臭さと喜びを分かち合う。坂を登ってくる新入生たちも、きっと同じように色々な鹿児島の言葉を話すだろう。
南郷高校は各学年八クラス、二〇二四年度の生徒数は九百五十四名に達する大型高校だ。一組から六組までの普通科には鹿児島市内に住む生徒たちが通ってくるが、学区制限のない残りふたクラスの理数科には、鹿児島市外と離島から成績優秀な中学生たちが集まってくる。
競争率が三倍に達することもある入試をくぐり抜けてきた地方の秀才たちが暮らすのが、高校の敷地内に建つ男子寮、蒼空寮だ。二棟ある三階建の居室棟に合計三十一の部屋があり、理数科生徒のおよそ三分の一にあたる九十三名の生徒たちが集団生活を送っている。
マモルたちは理科棟の屋上にあるコンピューター制御の天体望遠鏡を通学路に向けて、新生活への期待に頰を上気させた新入生たちの姿を見下ろしていたのだ。
先頭を歩いてきた生徒と、その横でしきりに何かを話しかけている母親が、校門を通り過ぎた。坂を登り始めたばかりの生徒まで数えると、七組はいるだろうか。
ちょうど絵になる頃合いだ。
「望遠鏡、動かしていい?」
マモルは、テーブルの向かい側で大きなノートPCを操作している道直規に声をかけた。
「いま?」
ナオキは、不満そうに頰を膨らませる。
「ちょうどいい感じなんだ。先輩から新入生の写真を撮っとくよう頼まれてるんだ」
ナオキは、食堂の入り口に近いテーブルで、ノートPCを覗き込んだり、VRゴーグルをかけて何やら作業に没入している三年生グループに顎をしゃくった。
「あっちで飛ばしてるドローン借りてきなよ」
「じゃあ、お前が兄貴に頼んでくれる?」
「兄貴いるの――あ、いた」
ナオキが目を丸くする。グループの真ん中でVRゴーグルをかけて両手を忙しなく動かしているのは303号室の道一先輩だった。どうやら、複数のドローンをまとめて操っているらしい。しばらく様子を窺っていたナオキがため息をつく。
「……無理か。VR甲子園の制作、ヤバいぐらい遅れてるもんな」
「だろう? 望遠鏡、借りていい?」
三年生たちは、再来週の土曜に県大会が行われる「VR甲子園」の準備に没頭しているのだった。最大五分間の3Dプレゼンテーションを競い合うVR甲子園で、蒼空寮は全国大会のベスト8入りを果たしたこともある。
今年の三年生たちは、ドローン撮影した映像を使って実写さながらのVR南郷高校を披露する予定だった。全ての教室を歩き回れるオープンワールド型のプレゼンテーションは野心的だが、その準備がかなり遅れている。
「わかった」と、ナオキがノートPCを操った。「望遠鏡のコントロール、タブレットに渡した。どうぞ」
言い終えるのと同時に、タブレットの画面に望遠鏡の操作パネルが現れた。マモルが矢印をとんとんと叩くと、わずかに遅れて理科棟の屋上に設置してある天体望遠鏡が動く。
普段はその目的通り夜空に向けて星を観測している望遠鏡だが、昼間は地上に向けて、映像を録画していることも少なくない。錦江湾の向こうで煙を噴き上げる活火山、桜島は格好の素材だ。
いい映像が撮れた日は、寮の下級生たちがコマごとに映り込む鳥や虫、変な形の雲、チラリと光る船の反射などのゴミを取り除いてから、蒼空寮のアカウントでストックフォトにアップロードする決まりになっている。最新型ではないが、高価な望遠鏡を使わせてもらっている上に、毎日のように撮影しては作業する手間暇をかけているおかげで品質は悪くない。月に二千円分ぐらいは売れていて、寮生活を楽しく、快適にするために使われている。貯めた金は、宅配ピザとおやつ代に消えていく。
マモルが角度を調整していると、学校指定の体育用ジャージに身を包んだ喜入梓が画面を覗き込んできた。
「こんな写真撮って、何に使うの? 寮の広報?」
梓は一学年八十人の理数科に五人しかいない女生徒の一人だ。
誰が伝えたのか知らないが、マモルたちが入寮する一年生たちを望遠鏡で観察していることを知った梓は、女子専用下宿の暁荘から、普段着のままでやってきた。
男子寮の蒼空寮には、食堂まで女子を入れてもいいルールになっている。かつては女子用の部屋もあったので女子トイレもあるし、エアコンも効いていて学校の高速無線LANも使えるので、暁荘に寄宿している理数科の女生徒たちは、自習にやってくることが多いのだ。
もっとも、勉強をするでもなく入り浸っている女子は梓ぐらいしかいないのだが。
「教えてよ。何に使うのよ」
「説教用のネタだよ」
「ネタ……?」
「スマホ見ながら歩くなとか、靴をぞろびって(引きずって)歩くなとか、腕時計は校則違反だ、とか」
「アホらしい」と、梓は盛大なため息をついた。「あんたたち、今年も説教やるの?」
声を上げた梓に、三年生たちが振り返った。
「そうだよ喜入さん」
「伝統だからさ。見守っててよ」
「寮生みんなかっこいいだろう? 説教で鍛えるおかげだよ」
梓は一段トーンを上げた声で「そうなんですねー」と答えると、振り返って鼻の上に皺を寄せた。
「あんたたち。二十一世紀になって何年経つと思ってるわけ?」
「二十四年」
「そんなこと聞いてるんじゃないし、だいたい、数え方間違ってるでしょ。西暦は序数」
「あ、そうか。二十三年だ」
「そうじゃなくて、時代遅れだって言いたいわけ。威張り散らして何の意味があるの、って言ってるの」
マモルは目を逸らした。
坂を登ってくる新入生たちは、今夜、手厳しい通過儀礼を受ける。
三年生の風紀委員たちが、新入生を集会室に集めて正座させ、脅し、先輩・後輩の関係を叩き込むのだ。
蒼空寮の共同生活は同じ学年の生徒が生活を分かち合うルームシェア形式ではない。ルーツが旧制高校のバンカラ寮なのか士官学校なのかは知らないが、三年生と二年生、一年生が同じ部屋に入り、下級生が上級生に従う形式だ。当然のことながら、そこには厳しい上下関係と規律ある生活が求められる。
起床は朝六時。大音量の音楽で叩き起こされた寮生たちは、校庭まで全力疾走して、五十回の腕立て伏せとスクワットで体を温め、掛け声と共に八百メートルの運動場を二周走る。
決して軽くはない運動を終えたら、次は朝食だ。食事の後は二年生が洗濯などのハウスワークを行っている間に、一年生は食器を片付け、寮を清掃してから登校する。ゼロ校時から八校時まで続く理数科のカリキュラムを終えて帰寮するのは十八時。そこから早い夕食をとって風呂を浴びると、二十四時までは私語の禁じられる学習時間だ。
集団生活どころか、自分で配膳をしたことすらない者も多い十五歳の子供たちにとって、寮の生活はあまりにも厳しい。
そんな厳しさに耐えられるような変化を起こすのが、説教なのだ――ということになっている。
自分にも他人にも厳しさを求める風紀委員たちが、集会室に集めた新一年生たちを怒鳴り、竹刀で壁を叩いて、恐怖で、上下関係と、生活の規律を叩き込むのだ。
口の悪い梓が、永遠に続く運動部の合宿を旧軍の士官学校の額縁に入れたような――などと形容する寮の伝統だ。気持ちのいいたとえではないが、中学を卒業したばかりの新入生を散々いびった末に、士官学校で唱和していたという「五省」を絶叫させるのだから反論のしようがない。
マモルは、能天気な顔で坂を登ってくる新入生の写真を撮りながら言った。
「時代遅れなのは認めるけど、でも、手は出してないよ」
「当たり前じゃないの!」と梓。「自衛隊だって殴らないんだから」
梓の両親は、ともに自衛隊員だ。男子よりもミリタリーに通じている部分も多い。
「だから俺たちだって手は出さないんだってば」
マモルは弁解したが、梓は食い下がった。
「まさか今年も、アレ読ませるの? 五省」
「やるよ」
「五省」は帝国海軍の士官学校で使われていた訓示だ。同部屋の風紀委員、塙に命じられたマモルは「至誠に悖る勿かりしか、言行に恥づる勿かりしか、氣力に缺くる勿かりしか――」と墨書された額を集会室に掲げてきたばかりだ。
梓は「馬鹿じゃない?」と笑った。「五省なんてね、旧軍でも十年くらいしか使ってなかった付け焼き刃のスローガンだよ。今年も中国から来る留学生がいるんじゃなかった? 由来とか聞かれて平気なの? 三年生にも中国の人、いるよね」
「呉先輩は、日本人だよ」
「そんなの書類だけの話じゃん。呉さんのご両親は中国生まれだし、志望校だって清華大学でしょ」
「まあ……ね」
マモルは隣部屋の202号室の三年生、呉健民先輩の、何を考えているのかわからない顔を思い出した。一年間、ひとつ屋根の下で同じ釜の飯を食ってきたというのに、話したことは一度もないのだ。
「だいたいさ」と、梓が意地悪な顔で身を乗り出してきた。「今の五省の額、誰に書いてもらったか知ってる?」
「そんなん松田先生に決まってるがな」と、物知り顔で答えたのはユウキだった。「なに流か知らんけど、確か六段とかだろ」
「違いまーす」
梓が顔の横で手を振った。マモルも頷いて正解を伝える。
「猪狩先生だよ」
「まじで?」ユウキは目を丸くする。「なんで脳筋に書かせるわけ? ほんとに?」
「そう。あれを書いたのは体育の猪狩先生。ありがたみがなくなるから、一年には言うなよ、ユウキ」
あだ名で呼ばれたユウキは顔をしかめる。奄美出身者に多い一文字姓の「結」と名前の「城一郎」をつなげて書くと、誰でも「結城、一郎」だと勘違いしてしまう。あだ名を禁じられたマモルたちの世代でも、教師や先輩がそう呼び始めると定着してしまうのだ。
「わかった。でも、マモルも一年の前でユウキはやめてくれんかい」
「わかった。でも、三年は止められないだろ」
ユウキは、音を立てて右の拳を左の掌に打ち付けた。
「やめさせればいいだけじゃがな」
平均身長が百六十五センチに満たない与論島の古里中学校バレーボール部をたった一人の活躍で県大会ベスト8に導いた彼の身長は百九十センチを超える。八十五キロの身体を軽々と動かす発達した筋肉と、柔道でこさえたギョーザ耳は迫力満点だ。去年の三年生たちですら、ユウキに向き合う時は腰が引けていたほどだ。だが、上下関係をぶっ壊すユウキの振る舞いを見逃すわけにはいかない。
マモルはユウキの胸を指差した。
「お前こそ、一年の前で三年を脅すなよ。それこそ示しがつかん」
「わかっとらあよ」と、面白くなさそうに肩を揺すったユウキは、五省の額がかかる集会室の方に顔を向けた。「しかし、あの額が猪狩っちゅうのは、下がるやあ。達筆で読めんち思ってんば、ただ下手くそだったわけな」
PCにかがみ込んでいたナオキがくすくすと笑う。
「コロナの時のドタバタで無くなった五省の額を書き直すとき、教育委員会は松田先生に頼んだってさ。だけど松田先生、組合員だろ。軍国主義の片棒なんか担げるか! って激怒して、頼みにきた委員会を追っ払ったんだって。兄ちゃんが佐々木先生から聞いた話」
「佐々木さんが見てたわけな」
寮監の佐々木隆一の名前にユウキは納得したらしい。
今年三十四歳になる佐々木は、南郷高校の理数科が鹿児島県で一、二位を争う進学校だった頃の卒業生だ。筑波大学に進学した佐々木は東京大学の大学院と理化学研究所を経て、スイスのCERN(欧州原子核研究機構)に赴任して国際チームのサブリーダーを務めていた俊英だ。
しかしコロナ禍のために国から出ていた研究費が止まり、帰国したところで職を失ってしまったのだという。それを拾ってくれたのが、かつての名門にテコ入れをしようとしていた鹿児島県の教育委員会だった。
秀才の誉高い佐々木の薫陶を受ければ、寮生たちも規律を取り戻すだろう――という希望を抱いていたらしい。
しかし佐々木本人は厳しさとは無縁の指導者だった。彼は寮生の学習や規律を自治に任せたのだ。門限破りを注意することはないし、異性・同性交遊の相談にもよく乗るという評判だった。寮監室のテレビチューナーや、フィルターのかかっていない無線LANを寮生に開放し始めたのも佐々木だし、VR甲子園を紹介し、寮生総がかりの3Dプレゼンテーション制作体制を作り上げたのも彼の功績と言えるだろう。
「その話、塙さんからも聞いてるから間違いないよ。風紀委員の打ち合わせで佐々木先生が教えてくれたんだって」
マモルも補足した。マモルがこれから一年間暮らす201号室の三年生、塙典雄は風紀委員長なのだ。
ユウキが大きな拳でテーブルをごつんと叩く。
「お前は、何故さん付けしよっとよ。先輩つけんか」
そのぎこちない鹿児島弁に、マモルと周りの二年生たちが思わず噴き出した。
腹を抱えて笑っていた梓は、ユウキの肩に手をかける。
「お願い、お願いだから、ユウキ、もうやめて。無理に鹿児島弁話すことないじゃない」
「なんば笑よいな。はげえ、梓まで。傷つくばい」ユウキがぶすりと頰を膨らませる。「島言葉で叱るやり方がわからんからよ。ビシッと締めらんばいきゃしゅんが」
「大丈夫だよ。黙って腕組んでるだけで怖いんだから」
「こうな」
ユウキは不機嫌な顔で腕を組む。
「そうそう、それで十分だよ。筋肉すごいな」
「慰めてるわけ?」
笑いながら、マモルは植え込みの向こうをすがめ見て席を立った。
「そろそろ新入生の第一陣が上がってくるぞ。さ、動こうぜ。ナオキも立って。お前玄関の担当だろ」
ナオキはノートPCを畳んで立ち上がる。
「あー、面倒くさいな。掃除かあ」
「疑を言うな(文句を言うな)」
鋭い鹿児島弁でナオキに言ったのは、泊宏一だった。
「俺がどげんトイレ掃除気張ろうが、お前が手ぇ抜かしたら、どげん意味があっとよ。マモル、お前は?」
「俺は食堂」
「そうだった」と宏一。「マモルは怖くねえからな、適材適所やらあ。ユウキは?」
ユウキは背もたれにかけていたタオルで口元を覆った。これから寮生たちは、息子と離れる保護者たちに集団生活で得られる良い面を見せつけるのだ。
自室の片付けすら親に任せていた子供の親は、きびきびと動き回る二年生と、敬語を使う三年生の姿に感銘を受けるだろう。マモルの母もそうだった。昨年の同じ日、説教のあとで「寮をやめたい」と訴えたマモルに対し、母親は「立派な先輩たちじゃないの。もう少し頑張ってみたら?」と諭したのだ。
いそいそと掃除に向かおうとするマモルたちを梓が笑った。
「ほんとわざとらしい。おかあさーん、寮生に騙されてますよー、って教えてあげようか」
「お願い、やめて」
「やらないよ。でも来年はもっとマシな方法考えなよ――わ!」
腰に手を当ててマモルを見下ろしていた梓が、タブレットを凝視していた。
「どうかした?」
「見てみて。この子かっこいい!」
マモルがタブレットを覗き込むと、一人の少年が校門を通り過ぎるところだった。
黒いキャップを被ったその少年は裾を引きずりそうなカーゴパンツを穿いて、くたびれたダッフルバッグを担ぎ、リラックスした歩調で坂を登ってくる。バッグの横にはグラフィティ風の書体で「PUNK」と書かれていた。スケートボードか、壁に落書きをするための缶スプレーが入っているような感じだ。
手脚は長く頭も小さい。まるでモデルのような彼が歩く姿は、他の一年生とはまるで違って見えていた。一瞬、マモルは普通科の生徒が遊びに来たのかと思ってしまった。だが、バッグの大きさを考えると、そうではない気もする。
梓は画面から目を離さずに言った。
「彼も入寮生?」
「……多分」
「誰だろうな」
テーブルを回り込んで画面を確かめたナオキが首を傾げると、ユウキがばちんと指を鳴らす。
「安永じゃがなあ」
「えっ! 孟子くん?」とマモル。
ユウキの言うことが本当なら、この少年はマモルの部屋に入ってくることになる。
画面をじっと見つめたナオキがうなずいた。
「間違いないどぉ。この間、テレビで見たからや」
「ねえ、誰なの?」
焦ったそうに聞く梓に、ユウキがにんまりと笑う。
「唾つけとけよ。あれは去年まで大臣やってた安永公平の息子よ。息子もまた生意気そうじゃがなあ」
周囲の二年生たちも口々に同意した。確かに、安永の顔には、ふてぶてしいと思われても仕方がない落ち着きが感じられた。
他の二年生たちには知らされていないが、安永は小学生でいじめのために不登校になり、シンガポールのイギリス人ばかりが行く寄宿学校の中学を出ている。不登校経験がある代議士の息子で帰国子女、ということになるが、弱々しいお坊ちゃんを想像していたところに現れた安永は映画で見るような「ストリート系の少年」だった。塙も実際に彼を見れば驚くだろう。
「はじめにガツンとやらんばや!」
ユウキが拳を掌に打ち付ける。
「やめてユウキ。俺がちゃんと教育するから、構わないで」
梓が目を輝かせた。
「安永くんって、マモルの部屋に入ってくるの?」
「そうだよ」
「じゃあ合コンしよう。うちの下宿とマモルの部屋で」
マモルは肩をがっくりと落とした。
「無理だよ。一年は、一学期の間は不要な外出禁止なの」
「そういうの流行らないって。あんたたちの伝統って人権侵害することしか考えてないじゃない」
梓が叩いた軽口にマモルはびくりとした。
マモルは寮の伝統のおかげで変わった。もちろんいい方にだ。夏休みに帰省したマモルが家の掃除を勝手に始めたとき、母親は驚いて声をあげたほどだ。敬語も使えるようになったし、料理も不器用ながら自分でやるようになった。だがその「成長」は、上下関係を叩き込まれた一年前の説教で始まったのだ。
三年生たちがあげる怒声を安永はどう受け止めるだろう。
「とにかく彼、紹介してね」
食堂から去っていく梓に手を振りながら、マモルはタブレットに映し出される安永の姿を見て、初めて見た時の違和感の理由に気づいた。
親がきていないのだ。
タブレットを片付けようとすると、宏一がぼそりとつぶやいた。
「梓も固えなあ。人権とかよ。どっちかちゅうと可哀想だろ」
「人権だろ?」
「そんなんじゃ、安永をちゃんとした寮生に教育できねえぞ」
「まあ、なんとかやってみるよ」
マモルの言葉を宏一は鼻で笑った。
「説教の配信も頼んど」
*
学習机に置いたマモルのノートPCを、部屋に集まってきたユウキとナオキ、そして宏一が覗き込んだ。
画面には、二十畳敷の和室が3D映像で映し出されている。食堂や風呂のある本部棟の集会室だ。普段は床の間の壁に据え付けた大型ディスプレイで実家とのビデオ通話を行ったり、押し入れに詰め込んだサーバー群とVRゴーグルを使ってVR甲子園の試聴会を開いたりしているメディアセンターだが、今日だけは様子が違う。
床の間にはディスプレイの代わりに「五省」の額がかかり、PC用品が置いてある棚の前には、無骨なスチールのロッカーがずらりと並んでいた。
マモルは高い位置から全体を見渡せるような位置に仮想カメラを動かした。三十名余りの一年生たちが正座をして顔を伏せ、床の間を背に正座をしている寮長、志布井の話に耳を傾けているところだった。
マモルは一年生たちのジーンズの尻ポケットに、スマートフォンが入ったままなのに気づいた。
「始まったばっかりみたいだね」
そう言うと、ナオキが音量調整をするファンクションキーに手を伸ばした。
「なんだ、ミュートになってるじゃん。マイク置いてあるよ」
「ちょ、待てよ――」
マモルがそう口にした瞬間、スマートフォンのメッセージ着信音とスチールのロッカーを叩く生々しい音が学習室を震わせた。続けて塙の怒声が、まるでこの部屋で怒鳴っているかのように響いた。
「誰よ! スマホ鳴らしとっとは!」
VR甲子園用に調達した3D音場マイクで拾った集会室の音が、部屋に据え付けてあるアクティブスピーカーから、集会室と同じ音量で響いたのだ。どうやら、スマートフォンをマナーモードにしていなかった一年生がいたらしい。
マモルはアプリを消音する方法を探そうとしたが、すぐには思い出せずノートPCのディスプレイを畳んで接続を遮断した。しかし手遅れだった。
廊下から、紙の束が投げつけられる音がして「こら二年! 何しよっとか!」という怒声が響いたのだ。
声の主は二つ向こうの203号室の三年生、鷲尾だ。学習時間に音を出していいのは三年生だけなので「申し訳ありません!」と大声で返すわけにはいかない。マモルが「謝りに行ってくる」とため息をつくとナオキが肩に手を置いた。
「俺が行くよ。鷲尾さん、昨日の試験で失敗して気が立ってんだ」
「いいの?」
「音出したの俺だし。どうせマモルをダシにするから」
「おい、ちょっとひどくないか」
にやりと笑ったナオキはスリッパを脱いで靴下だけになると、僅かな音も立てずに学習室の引き戸を開けて、一年生の時に身につけた抜き足差し足で廊下を走っていった。
「スピーカーぐらい確認しとけよ」と、宏一がため息をつく。
誰だってミスぐらいするよと言い返したいところだが、完璧超人の異名をもつ宏一がスピーカーの音量を確認し忘れるはずもない。マモルはスピーカーの出力つまみを捻ってからノートPCを開き直した。
画面に「再接続中……」という文字が現れると、太い腕を組んだユウキが身を乗り出してきた。
「時間かかるやあ。いいところ見逃すがな」
「もうちょっと待って。一回接続が切れると――」
「わかってるがな」と言いながら、ユウキは部屋を見渡した。「マモルの部屋、歓迎会は盛り上がらんかったわけ?」
「そんなことないよ。なんで?」
「片付いてるからよ」
ユウキの言う通り、四畳半の学習室は新入生の歓迎会をしたのが噓のように片付いていた。
「塙先輩が説教の準備に出てったら、自然と片付ける流れになったんだよ」
宏一がマモルを睨んだ。
「お前は、一年に説教のことバラしたんじゃなかろうな」
「いいや」マモルは首を振った。「俺も塙先輩も、これっぽっちも匂わせないようにしてたよ。だけど、安永は知っててね。イニシエーションはこの後ですかって聞いてきたんだ」
「さすが帰国子女」とユウキ。「マモルはイニシエーションの意味わかった?」
「いや、辞書引いた」
「ばっか。英語IIで習ったばっかりじゃがな。期末にも出たど」
「いいじゃないかよ」
「よくねえよ」と宏一が口を挟む。「イニシエーションなんて普通科だって知ってる単語だろ」
マモルは口を尖らせて画面を睨む。そんなマモルに、慰めるような口調で「暗記すりゃいいんだよ」と厳しいことを言った宏一は、まだ空っぽの安永の学習机に顔を向けた。
「しかし意外だな。坊ちゃんのくせにそういう鼻は利くってわけか」
ユウキがノートPCに映し出された集会室を指差した。
「音、少し出せん? 今、その安永が説教されてるどぉ」
慎重にスピーカーのつまみをひねると、志布井寮長の声がスピーカーから流れ出してきて、マモルの背筋は自然に伸びた。説教や朝礼で散々叱られていたので条件反射のようなものだ。
「――安永くん。私は、寮のやり方が古風なのはわかっている。だが、まだ生計を立ててもいない、十五歳から十八歳の未熟な生徒たちが、道を踏み外さずに集団生活を送るためには、個々人の成長と同時に、規律が必要なんだ。わかるか」
緊張した面持ちの安永が頷くと、平手でロッカーを叩く音が響いた。
「返事は!」
鶏のような声で叱り飛ばしたのは、川内先輩だ。小柄だが、目つきと鹿児島弁の柄の悪さでは誰にも引けを取らない。
「はい――」
「声が小せえ!」
安永が返答し終えるのを待たずに川内が被せる。
「はいっ!」
「返事は良かど、志布井が何言たか分こちょっとかぁ?」
「え? はい――」
「え、じゃねえ!」川内が再びロッカーを叩く。「お前がよぉ、寮長がどんだけ丁寧に話しとっとかわかっとっとか。それを、え? どげんかしとらせんか? 何黙っちょっとよ!」
「きついの来たな。川内監獄だ」
宏一が苦笑いすると、ユウキも肩を揺すって笑った。
「ええと」と口ごもる安永にもう一度怒声が飛んだ。
「志布井が『ええと』とか言うたか? お前は聞いとらんかったとか?」
「ごめんなさい!」
「子供か! 申し訳ありませんでしたやろが! やり直せ!」
「申し訳ありませんでした!」
大声で返答した安永の声に、ユウキが「へえ」と声を漏らした。
「安永、意外と肝が据わってんな。それとも川内先輩が手心しちゅんかい」
「そうでもないよ」とマモルは画面を指差した。「隣の一年――富浦なんか、もう泣きそうにしてるじゃない」
「だからだよ」と宏一。「泣かれると面倒くせえから、太そうな衆をカタに嵌めてんだよ。川内先輩は、ああ見えて相手の反応を結構見てんだ」
見てりゃいいってもんでもないだろう――と言いかけたマモルは、慌てて「そうか」と補い、自分の変化に気づいた。昨年の自分なら、川内がやってみせる「心遣い」に素直に感心していたはずだ。
二年生になり、部屋の後輩ができたせいだろうか。マモルは、大声で――しかし落ち着いた顔で川内に答えている安永を見つめて、自分の変化と関係があるかどうかを確かめようとした。
その時、音もなく戸が開いてナオキが戻ってきた。
「おまたせ。マイクも綺麗に入ってるじゃない。ちょっとごめんね」
ナオキは両手を耳の後ろにかざすと、スピーカーに顔を向けたまま狭い学習室を一周した。
「よしよし、三次元音響に問題なし、と」
「鷲尾さん、怒ってた?」
マモルが聞くと、ニヤリと笑ったナオキは再び引き戸を音もなく開けて、廊下に置いてあったコーラのペットボトルを掲げた。
「これもらったよ。有望な二年は説教のやり方をよく見とけってさ」
「有望って何の話だよ」
ユウキがため息をつく。
「わからんわけ? 次の風紀委員と寮長よ」
「ああ、それか」
ユウキが鼻息を吹くと、宏一はさもありなんと頷いた。確かにこの二人は風紀委員候補の双璧だ。
三年生すら怯ませるユウキがマッチョ枠で塙の跡を継ぐのは確実だ。そして宏一の、自分にも同級生にも厳しく当たる姿勢は、今の寮長の志布井のストイックさに通ずるものがある。
風紀委員といえば、二年生の中で頭抜けたIT技術を持つナオキも候補の一人だ。PCやネット利用と切っても切り離せない寮生活のセキュリティマスターとしても、VR甲子園制作の中心人物としても、ナオキは外せない。
そして三人ともに成績優秀だ。寮の存在意義は、鹿児島の地方出身者に大学進学の道を作ることなのだから、成績優秀でなければ人はついてこない。
「五十九期の委員は、お前らにかかってる感じだな」
ユウキは歓迎会のために用意された紙コップを人数分並べると、ナオキから受け取ったコーラを注いだ。
「マモルもいいとこ行ってんだけどやあ」
「はあ? いや、無理だよ」
「まずは成績あげんばよ」
ユウキはコーラをマモルの前に置いて笑った。
マモルがぶすりと口を尖らせると、コーラを飲みながら宏一が慰めた。
「優しい先輩も必要やっど」
宏一は説教を映し出している画面を指差した。
「今日の説教は安永が標的やらい。応えとらんかんしれんどん、帰ってきたら慰めてやれよ」
*
寮長の志布井が校庭に並んだ寮生の前を駆けていく。
「ランニング始めます! 蒼空うーっ、ファイト!」
「ファイト!」
マモルも、他の寮生たちも続く。
「ファイッ!」
初めて朝のランニングに加わる一年生たちも昨夜の説教が効いたらしく、声を嗄らすようにして張り上げていた。目の前で体を揺らす安永も、他の一年生ほど必死そうではないが、大声で「ファイト」を唱和していた。
桜は散り始めているが、標高百五十メートルの高台にある南郷高校は天気予報よりも一度か二度ほど気温が低い。午前六時、太陽は錦江湾の向こうに横たわる大隅半島に隠されていて、校庭の隅には朝靄も漂っている。湾にどっしりと浮かぶ桜島の、樹木の生えていない剝き出しの裾野は青黒い夜の色に沈んでいた。
朝を感じさせるのは、わずかに輝く山頂と、鈍い光を放つ空だけだ。そんな錦江湾を背にして寮生の前を駆けていく志布井の姿は、シルエットだけが強調されていた。
「校庭二周! ファイッ! 一年から! ファイッ!」
列を越えて駆けていく志布井の背後に一年生がわらわらとついていく。足並みの揃わない一年生に、横を走っていた塙が怒鳴る。
「階ごとに並ばんか! 最前列は新館一階。111号室の丸橋くん!」
「は、はい!」
色白の腕をあげた一年生を塙は指差した。
「今日はお前が新館一階の当番やっど。先頭に行け。次ぃ、新館二階。112号室の富浦くん、居っか?」
「……はい」
すぐ後ろから上がった声にマモルは驚いた。振り返ると、小柄な一年生が目を泳がせている。どうやら別の階の列に紛れ込んでしまったらしい。
「富浦くん、前に出て」とマモルは声を掛けたが、富浦は小刻みに首を振って後退った。説教が効きすぎてしまったらしい。
「富浦くん、どこに居っとよ!」
塙が怒鳴る。マモルは富浦の隣に立って囁いた。
「ここです。行きます、って言って。大きな声で」
頷いた富浦が声をあげようとした瞬間、川内の鋭い声が飛んだ。
「富浦っ! ずんだれとか(だらしないぞ)!」
富浦はすがるような顔でマモルを振り返った。自分の部屋の安永ならしっかりしろと叱りつけるところだが、富浦は風紀委員の川内の部屋の一年生だ。マモルの指導は川内の顔を潰すことになってしまう。
「大きな声で返事して。川内先輩、怒ってないから」
富浦は頷くと「ファイッ!」と大声を出した。
そうじゃない――とマモルは目を覆う。ここです、だ。案の定、川内はピントの外れた返事を叱り飛ばした。
「誰がファイ言えちゅうたよ。早よこっ来!」
「ああっ……」と声を漏らして縮こまった富浦に、マモルは「返事っ」と囁いた。
「はいっ! 行きます」
答えた富浦は、やっとのことで呼ばれた場所へと駆けていく。富浦が新館二階の一年生の先頭に立つと、他の一年生たちは要領が分かったらしい。残りの一年生たちは自発的に列を作って走り始めた。
安永も旧館二階の一年生の先頭に立って走っていた。ハーフカットのパンツからスラリと伸びたふくらはぎには筋肉の陰影がはっきりと刻まれている。昨夜の歓迎会ではスケートボードをやっていたという話だったが、こんな筋肉がつくスポーツなのだろうか。
一際大きな「ファイッ!」の声に振り返ると、ユウキが自分の部屋の一年生の真後ろで大声をあげているところだった。種子島から来た新入生だったはずだ。メガネの下で、大きな目が見開かれているのが見てとれたが、無理もない。ユウキに追い立てられているのだから。
顔を戻そうとした時に、ユウキの体型が気になった。入寮したばかりの頃は、もっと筋肉の形がはっきりしていたというのに、新入生を追い立てている彼の体はふやけて見える。安永のふくらはぎのようなキレは感じられない。どうやらユウキは、一年の寮生活で体が鈍ってしまったらしい。
マモルは逆だ。朝の一・六キロメートルのランニングと腕立て伏せのおかげで、中学時代にはなかった筋肉がうっすらと体を覆うようになった。入寮してからの一年は風邪もひかなかった。
寮生活で体が鈍る者もいれば、健康になる者もいる、ということだ。
違いは体型だけに限らない。集団生活にどう向き合っているのかでも結果は変わってくるはずだ。
そんなことを考えつつ、安永と、他の一年生たちに気を遣いながらランニングと腕立て伏せをこなしていると、いつの間にか朝のトレーニングは終わって朝礼が始まっていた。
まずは部屋ごとの点呼だ。報告は三年生の仕事だが、風紀委員と寮長の部屋だけは二年生が点呼に応えなければならない。
マモルは「201号室、異常なし」と報告する。隣の202号室でも二年生が声を張り上げた。
「202号室、呉先輩が腹痛で朝礼を休んでいます。登校は問題ありません」
はあ、というため息が三年生の間で交わされる。前で腕を組んでいる風紀委員の川内は、苦々しげな表情を隠そうともしなかった。受験が近づくと朝礼を休む三年生は増えるものだが、新学期の初日から休まれると、示しがつかない。幸いなことに、朝礼を休んだ三年生は呉だけだった。
点呼を終えた後、全員の前に立った志布井は、まず三年生に釘を刺した。
「最上級生になった三年生と後輩のできた二年生は、一年生の手本になることを強く自覚してください。登校できるなら、朝礼には出るように。部屋の二年は伝えてください」
言い終えると、志布井はおもむろに頭を下げた。
「それでは、おはようございます」
「おはようございます!」
一年生たちの唱和に朝の空気が震えた。昨日の説教で散々練習させられたおかげだ。
「ようこそ、蒼空寮へ」
まばらに「はい」という声が上がる。
「返事ぃ!」
塙が吠えると、一年生たちは気をつけをして叫んだ。
「はいっ!」
志布井はうなずいて言葉を続けた。
「君たち一年生には、家族や兄弟よりもずっと密接に過ごす仲間ができました。まだ卒業していない私にはわかりませんが、OBの皆さんによれば、寮の三年間で培った交流は一生続くということです」
志布井は列の前を左右に歩き始めた。
「寮は、食事をして、寝て、風呂に入り、勉強をして、自分の時間を過ごすための場所ではありません。人生において、何より重要な大学受験に向き合っている三年生たちと接することで、あなたたち一年生はかけがえのない経験をすることでしょう。まずは寮の生活に慣れ、二年生と三年生がどんな日々を送っているのかをよく観察してください。掃除や洗濯、配膳などは率先して行うように」
マモルは志布井の話に聞き入ってしまった。昨年の二学期から毎朝志布井の話を聞いているのだが、最上級生になったからだろうか、力強く正論を説く姿は去年よりもずっと様になっている。
「そして」志布井は言葉を強めた。「新入生は今日から二週間、私たち三年生の活動に注目してください。私たちはVR甲子園に出場します」
顔を見合わせようとした一年生だが、塙の咳払いで気をつけの姿勢に戻る。
「蒼空寮は、二週間後に行われるVR甲子園の鹿児島県大会で、必ず優勝してみせます。一年生と二年生は、応援と支援をよろしくお願いします」
マモルは反射的に拍手していた。もちろん、他の二年生たちもほぼ同時に。やや遅れて、一年生たちが一際大きな拍手を送る。
桜島の横に昇った朝日が、寮生たちを正面から照らしていた。