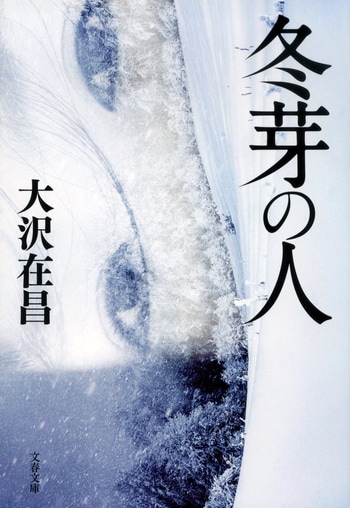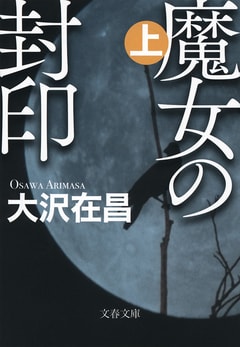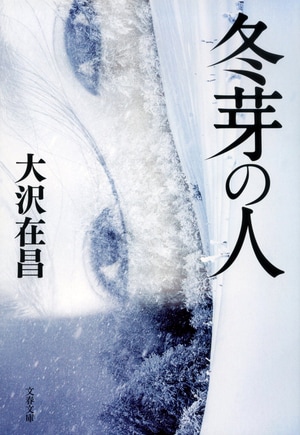
大沢在昌には、女性を主人公とした作品が少なからずある。本書もそのひとつだ。そこでまず女性主人公の長篇作品の流れをたどりながら、本書の特色について述べてみよう。
作者が初めて大きく女性をクローズアップした作品は、一九八五年刊の『夏からの長い旅』だ。
この作品の「あとがき」で作者は、
「女性を描くことに苦手意識があった。
理由ははっきりしている。照れ、である。
三十にもう手が届こうというのに、口にするのではない『言葉』で女性を描くのに、いつも照れがあった」
といっている。ハードボイルド作家として出発したからだろうか。作品世界の中で女性を描くことに“照れ”があったようだ。しかし作者は時間をかけて“照れ”を克服していく。一九八七年には、やはり女性を大きくクローズアップした『シャドウゲーム』を刊行。そして一九九〇年刊の『相続人TOMOKO』で、ふたりの女性を主人公に据えた。国籍を失った氏名不詳のトモコと、コールガールの須藤智子。境遇も立場も違う、ふたりのTOMOKOを共に行動させ、活劇を繰り広げさせたのである。この作品、現在ならば女性たちの連帯を意味する“シスターフッド”の物語といわれるはずだ。
それから数年を経た一九九五年、『天使の牙』が刊行される。脳移植により絶世の美女となった刑事の河野明日香が、新たな肉体に戸惑いながら、相棒兼恋人の刑事「仁王」と共に麻薬組織に立ち向かう、異色の警察小説だ。続篇として、二〇〇三年刊の『天使の爪』がある。
二〇〇六年刊の『魔女の笑窪』から始まった「魔女」シリーズは、地獄島と呼ばれる場所で壮絶な体験をしたことで、男を一目で見抜く能力を得た水原を主人公にして、アンダーワールドが活写されている。「天使」「魔女」シリーズは、特異な設定により女性が主人公であることの意味を際立たせていた。
また、一九九九年刊の『撃つ薔薇 AD2023 涼子』は、近未来の東京を舞台に、麻薬組織に潜入した櫟涼子の活躍を描いている。二〇一九年刊の『帰去来』は、警視庁捜査一課の“お荷物”志麻由子が、捜査中に首を絞められ、気がついたら「光和二十七年のアジア連邦・日本共和国・東京市」のエリート警視・志麻由子になっていたという、パラレルワールド警察小説だ。
さらにいえば、二〇一四年刊の『ライアー』の主人公・神村奈々は、国家に不都合な人物を「処理」する政府の非合法組織の一員、二〇二一年刊の『熱風団地』の主人公コンビの片方のヒナは、元女子プロレスラーであった。このように『天使の牙』以降の女性主人公作品は、設定が特殊であったり、女性を男性と戦えるだけの能力の持ち主にしている。女性を主人公にした物語を真剣に考えた末に、それぞれ創られた世界なのであろう。
このような女性主人公作品の流れを俯瞰すると、本書の立ち位置がちょっとズレた場所にあることが分かる。なぜなら舞台は現代であり、特殊な設定も能力もないからだ。それこそが作品の特色といっていい。
本書『冬芽の人』は、「小説新潮」二〇一〇年三月号から二〇一二年二月号にかけて連載。単行本は、二〇一三年一月に刊行された。なお、二〇一七年にテレビ東京系列でドラマ化されている。主役の牧しずりを、鈴木京香が演じた。
現在、虎ノ門にある小さな商社でOLをしている牧しずりだが、六年前は警視庁捜査一課所属の刑事だった。練馬で起きた殺人事件を、相棒の前田光介と捜査していたしずり。しかし、前田の主導で村内康男のアパートを訪ねたところ、村内が逃亡。前田は重傷を負い、二年間の昏睡状態を経て死亡した。また、逃亡した村内は、追跡したしずりの眼前で、トラックにはねられて死亡する。その後、村内が殺人の犯人と確定した。前田と村内、さらに村内をはねたトラックの運転手の君津と、自分の行動のミスにより三人の人生を損なってしまったと思ったしずりは、警察を退職。商社に転職したのである。だが、過去を忘れることはできず、「わたしは、ただ静かに生きたい、と思ったの。怒りとか悲しみとかとは無縁に、振幅のない、一本の線みたいな暮らしをずっと送ろうと決めた」というように、蹲るような日々を過ごしている。
ところが前田の墓参りで、存在を知らなかった彼の息子・仲本岬人と出会った。しずりの話を聞いた岬人は、自分のバイト先に君津らしき男がいるという。どうやら本当に、トラック運転手だった君津のようだ。諸々のことから、君津が村内を殺す目的ではねた可能性が浮上する。しかし、しずりと岬人が一緒にいるところを目撃した君津が逃亡。埼玉で死体になって発見された。いつの間にか、自分と岬人が危険な状況に陥っていると察知したしずりは、事態を打開するために六年前の事件の真相を追う。
ハードボイルドの主人公は、己のルールを持ち、それを頑なに守る人物が多い。しずりも、そのひとりである。ただし彼女の場合は、己のルールに縛られ、前に進めなくなっている。そんなしずりの人生が、岬人との出会いにより、大きく動き出す。過去の事件の経緯、現在のOL生活、しずりと岬人の関係などを、的確に描くことによって、物語の土台がしっかりと構築されている。いまさらいうまでもないが、この手際がお見事。しずりが君津に疑惑を抱き、そこから六年前の事件のときの前田の行動にも疑いを抱く様子を、読者は無理なく受け入れられるのである。どんな物語でもそうだが、特にミステリーは読者に対する隠し事が多い。だからこそストーリーの組み立てに、細心の注意を払う必要がある。そう、本書のように。
一方で、しずりのキャラクターも見逃せない。女性警察官としてはトップクラスの拳銃射撃術の持ち主で、本人はまだまだだと思っていたが刑事としての能力もある。だが、それを除けば彼女は、割と普通の感覚を持った人なのだ。刑事時代の彼女は、既婚者の前田から迫られていた。男女の関係にはならなかったが、前田の妻から疑われ、憎しみを向けられたことがあり、それを今も引きずっている。十五歳以上も年下の岬人が好きになり、どうすべきか悩む。会社の同僚と飲み屋やカラオケに行き、ささやかな幸せを感じてしまう。よく泣くし、暴力には怯える。事件で新事実が分かれば、保身の意味も込めて、すぐに警察に連絡する。捜査のために遠くに行くときは、有給休暇を取る。その行動や感情は、一般の女性、普通の社会人のものだ。
しかし彼女には、逃げない心がある。戦う勇気がある。しずりの上司である中崎(いいキャラだ)は彼女に、「誰でもなれる可能性をもっている、と俺は思う。別に悪い奴をぶっ倒すばかりがヒーローじゃない。目の前にある戦いから逃げず、そして勝てば、サラリーマンだろうがOLだろうが、ヒーローさ」という。作者はあえてしずりを、普通の感覚を持つ女性とすることで、誰もがヒーローになれる可能性があることを示した。だから本書に、特殊な設定や能力は不要なのである。
これはストーリーにもいえるだろう。しずりの調査方法に、特別な手段も手法もない。事件の関係者を当たり、証言をもとに推理する。雑誌記者を名乗る不審人物が接触してくれば、ひとつでも多くの情報を得ようとする。本書をハードボイルドとして見ると、とてもオーソドックスな構成だということが理解できる。
そして積み重ねてきたエピソードの果てのクライマックスで、比較的静かに進行していた物語が爆発する。一連の事件の真相の奥深さに驚き、主人公のある設定はこの場面のために必要だったのかと感心。さまざまな体験を経て、前に進み始めたしずりの姿に感動。大いに満足して、本を閉じたのである。