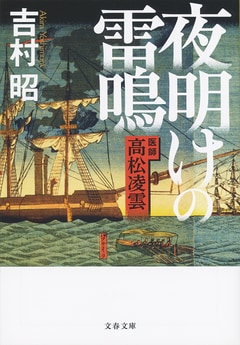吉村昭氏の小説は常に、静かな声で語られる。戦争をテーマとする作品では、ときに無残な死が描かれるが、非日常の異様な状況や心理に迫るときも、決して声高になることはない。
あいまいなこと、大げさなこと、主情的なことを拒む吉村氏の文章の背後には、徹底した取材と調査にもとづく事実の探求がある。
吉村氏の取材の広さと深さ、とりわけ当事者に直接会って話を聞くことを重視する姿勢は、つとに知られるところである。それは、小説にリアリティを持たせるエピソードを拾う、というのとは根本的に違う。
当事者の談話を貴重な歴史の証言として受け止め、しかしすべてを鵜呑みにするのではなく、突き合せ、裏付けを取り、あらゆる角度から検討する。そこから作品を生み出すのが吉村氏のやり方なのである。
吉村氏はこう述べている。
〈記録は、人体にたとえれば骨格に似ている。それに肉をつけ血を通わせるのは、生存者の肉声しかない〉(『万年筆の旅 作家のノートII』所収「眩い空と肉声」より)
私はノンフィクションを仕事にしており、戦争を題材にしたものもいくつか書いている。若い頃から吉村氏の作品を愛読していたが、この職業についたあとで改めて読むと、数行の記述であっても、その背後にどれだけの調査と取材があったかが推測できて、いつも圧倒される思いがする。
では、吉村氏の取材スタイルはどのようなものだったのか。随筆「一人で歩く」(『わたしの普段着』所収)で氏は、他人に調査を依頼することはせず、必ず自分自身で出かけていくと書いている。
吉村氏の担当編集者だったことがある作家の森史朗氏によれば、費用も原則、自弁だったそうだ(吉村昭記念文学館企画展図録『戦後75年 戦史の証言者たち――吉村昭が記録した戦争体験者の声』所収「吉村昭と戦史小説」より)。そして、取材にはいつもテープレコーダーを持参した。吉村氏の子息である吉村司氏はこう書いている。
〈母(筆者註・夫人で作家の津村節子氏)は録音機を基本回さない。自分の作品に有効となる情報はメモをすることで足りる、というのが持論だ。しかし、父の場合、取材帰宅後にテープを再生してみると、証言者達の感情の起伏や、微妙な表現はメモでは書き留めることが出来ないと強く自覚していた〉(同前「父と戦艦武蔵」より)
吉村氏は証言を何より大事にしたが、それは事実を掘り起こすためだけではなく、人間心理の複雑さ、不可思議さを知るためでもあった。そのために細かいニュアンスを逃すまいとしたのである。
実際の吉村氏の取材スタイルを垣間見ることができるのが、本書の表題作「帰艦セズ」である。この作品には、主人公に戦時中の話を聞きに来る小説家が登場するが、この人物のモデルは吉村氏自身である。
「あとがき」にあるように、「帰艦セズ」には先行する作品が存在する。一九七一(昭和四十六)年刊行の長編『逃亡』である。
太平洋戦争末期の一九四四(昭和十九)年、茨城県の霞ヶ浦航空隊の整備兵が、アメリカのスパイだった日本人にそそのかされ、軍用機を炎上させて脱走。国内に潜伏し、終戦まで生き延びる。小説で望月という名を与えられているこの脱走兵は実在する人物で、『逃亡』は吉村氏が彼に直接取材した事実がもとになっている。
『逃亡』の十五年後に書かれたのが「帰艦セズ」で、こちらでは元逃亡兵の男は橋爪という名を与えられている。今風の言い方をすればスピンオフということになるのだろうか、小説家の取材に応えて過去を話したあとで彼が経験したことが描かれている。
「帰艦セズ」で橋爪に取材依頼の電話をかけてきた小説家は、ある人物から彼の過去を聞いたことを話し、「もしもそのことを話してくれる気があるならききたいが、迷惑なら二度と連絡はしない」と言う。逡巡の末に話す決心をした橋爪が家に来てほしいと電話をすると、翌日の夜、雨の中を訪ねてくるのである。
翌日、というところにリアリティがある。橋爪は、軍用機を炎上させて逃亡するという、妻にさえ隠し通してきた過去を話す気になってくれたのだ。その決心が揺るがないうちに、すぐに訪ねるしかない。
橋爪の家にやって来た小説家はアタッシェケースを携えている。新聞記者であれ小説家であれ、インタビューにきた者の鞄がアタッシェケースというのはいささか意外な感じがするが、それがかえって、この人物の持つ小説家らしからぬ雰囲気を読者に印象づける。
だがこれは小説的効果を狙ったわけではない。さきほど紹介した吉村氏の随筆「一人で歩く」には、『戦艦武蔵』の取材で長崎の船具を扱う店の店主を訪れた際、アタッシェケースを手にしていたためにセールスマンに間違えられて「間に合ってるよ」と追い払われた話が出てくる。「帰艦セズ」の小説家は、やはり自分自身の姿なのだ。
橋爪の家に上がった小説家は、突然電話をかけた無礼を詫びると、おもむろにテープレコーダーをテーブルの上に置いてノートをひろげる。子息が書いておられるように、テープレコーダーを回すのも吉村氏自身のスタイルである。
自分自身を登場人物の一人として、主人公である橋爪の視点から描いたこの作品は、吉村氏がどのようにして取材を進めていくかがわかる点でとても興味深い。
作中の小説家は、翌日、再びやってきて話を聞いたあとで、橋爪に向かってこう言う。
「あなたがお話しして下さったことを基礎に、小説を書かせていただくかも知れませんが、よろしいでしょうか。もしも御迷惑でしたら書きません」
この小説家は、最初に電話をかけたときにも、迷惑ならば二度と電話をしないと告げている。おそらくこれは、話を聞かせてもらった相手に、吉村氏が実際に言っていたことだったのだろう。ここからわかるのは、吉村氏が「書く」ということの暴力性を認識していたことである。
隠されていた史実を徹底した調査によって世に出す行為が、意義のあることであるのは言うまでもない。だが、事実というものは、ときに関係する人々の平安を破り、人間関係を損ない、心を傷つける。それでもなお、書くことが許されるのか。吉村氏の中には、絶えずその問いがあった。
元逃亡兵に話を聞きに行った話は、長編『逃亡』の冒頭にも出てくる。こちらは、小説家である「私」、つまり吉村氏側の視点から描かれる。そこで、最初に電話をしたときのことは、次のように書かれている。
私は、かれが受話器を手に立ちつくしている姿を想像した。
御迷惑ならばお話をうかがえなくとも結構です、再び電話はいたしません。でも、もしも話してよいというお気持がおありでしたら、拙宅に電話して下さい――
私には、それだけ言うのがやっとだった。受話器の中で、再び、はい、という声がした。私が、自宅の電話番号をつたえると、静かに受話器をおく音がきこえた。
罪深いことをしてしまった、と私は思った。はい、という言葉のひびきが重苦しく胸にわだかまった。私は、未知の男を闇の奥底から引き出してしまったことを悔いた。
赤の他人の人生に踏み込むことに逡巡するのは人として当然のことだ。それまで誰にも言わずにいたことを語らせること自体が暴力的であるし、さらにそれを文章にして世間に公表すれば、その人の人生を変えてしまうおそれがある。
だが、ものを書く人間の中には、軽々とそれをやってしまう者もいる。自分には、重要な事実を世の中に知らせる大義がある、書く人間にはそれが許されていると思ってしまうのだ。あるいは、普段は人一倍慎重であっても、これぞという事実を摑みかけたとき、それまで自分に課してきたラインを踏み越えてしまうことがある。自分の筆でこのことを書きたいという欲に負けてしまうのだ。ノンフィクションを書いている私には、そのことが身にしみてわかる。
だからこそ、吉村作品の節度と、その奥にある「事実を作品にすること」への畏れの感覚に深い敬意を抱くのだ。
「帰艦セズ」の橋爪は、戦時中に小樽の山中で死んだある機関兵の消息を追いかける。彼は橋爪と同じ逃亡兵だった。官給品である弁当箱を紛失してしまったことから、乗っていた巡洋艦に戻れず山中に隠れ住み、ひとり飢えて死んだのだった。
橋爪は調査のため、男の遺族を探す。資料から六軒に絞り、順に電話をかけていくと、ある家の電話に出た老女が「時夫は私の悴(せがれ)ですが、生きているのですか?」と、叫ぶように言う。遺骨が戻らなかったため、どこかで生きているかもしれないという一縷(いちる)の望みを捨てられずにいたのだ。
機関兵の死の真相は、無残で悲しいものだった。それを突きとめたあと、自分のしたことは果たして正しかったのかと橋爪は自問する。
一人の海軍機関兵の死因を探るため調査をしたが、それは結果的に遺族の悲しみをいやすどころか、新たな苦痛をあたえている。三十数年の歳月をへてようやく得られた一人の水兵の死の安らぎを、かき乱してしまったような罪の意識に似たものを感じていた。
多大な労力をかけて事実を発掘したあとで、眠らせておいたほうがよい事実もあるのではないかという気持ちになったことが、吉村氏にもあったにちがいない。遺族がかかわってくる戦争取材となるとなおさら、知ることが新たな苦しみとなる場合がある。
「あとがき」に「実際に私が経験したことで、いわば私小説の部類に入ると言っていい」とある「飛行機雲」という作品の底にも、事実をあばくことが人を傷つけることがあるという自覚と、書くことへの罪悪感が流れている。
ここにも遺族が登場する。夫の戦死を信じきれないまま戦後の二十六年間を生きてきた妻は、突然の電話に、「君塚は生きていたんですね、どこに生きていたんですか?」と声を上げる。「帰艦セズ」の老母と同じ反応である。吉村氏自身であると思われる小説家は、自分の調査結果が夫人の生きる支えを突きくずしたと思い、「未知の人に一つの大きな罪をおかした」と感じるのだ。
君塚というその軍人の死は、特殊情報班の中国人密偵の報告書によれば、斬首され、水田に遺棄されたというむごいものだった。それを作品の中に書けば、読んだ夫人は衝撃を受けるだろうと思い、小説家は逡巡する。
この作品には、書くべきか否かという迷いが直截に語られている部分がある。
私は、長い間ためらった。書くべきではないという思いと、戦争の実態を記すには勇気を持つべきで、君塚少佐もそれを望んでいるという思いが交叉した。後者の気持が私の背を押し、密偵の報告を書いた。
ここに書かれた交叉する二つの思いも、本当によくわかる。このときの小説家は書くことを選んだが、吉村氏には悩んだ末に書かないと決めた経験もきっとあったに違いない。
密偵の報告書の内容を作品に書いた小説家は、それを読んだ夫人から丁寧な手紙を受け取って安堵する。だがそのすぐあとで、夫人の気持ちをあれこれと推測し、やはり書くべきではなかったのではないかと後悔する。そしてその後も、心の揺れは長く続くのである。
揺れるということは誠実さの証しであり、ここに私が吉村作品を座右に置いて読み返す最大の理由がある。
歴史は人間と離れたところに存在するわけではなく、書く−書かれるという人間同士の関係は、作家にとって逃げてはならないテーマである。吉村氏はみずからの身を削りながら、出会った人たちと誠実に対峙してきたのだと思う。
吉村氏の作品と生き方から私が感じるのは「礼節」ということだ。事実への謙虚さ、人間への敬意、そして「書く」ということへの畏れ――それが、吉村作品が時代をこえて読み継がれている理由だと私は思っている。