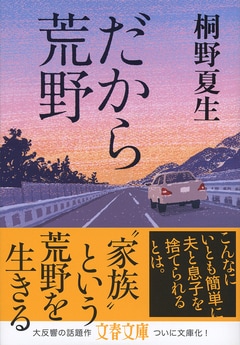桐野夏生の最新作は、『もっと悪い妻』という刺激的なタイトルの短篇集だ。古今東西、世論は、「悪い妻」に対して厳しい視線を注いできた。不倫をした女優に対してのバッシングの嵐は、今も吹き荒れている。
「悪い妻」というテーマを選んだのはなぜだったのか。著者が考える「妻と夫」の関係性について、話を聞いた。
「夫婦の関係性だっていろいろ。型にはまらない家庭のカタチもあるはず」
「2018年に『ロンリネス』(光文社文庫)という小説を書いたときに、章のタイトルとして、『賢妻愚妻』や『賢母愚母』『聖母俗母』というものを付けたことがありました。この頃から逆説的に『悪い妻』というテーマで短篇小説を書いてみたいと考えていました。男性が言う、『悪妻』とはなにか。夫婦の関係性だっていろいろとある。型にはまらない家庭のカタチもあるはずなのに」
第一話〈悪い妻〉には、育児に非協力的だが、多くの女性ファンを持つバンドのヴォーカルの夫が登場する。夫のバンド仲間たちは、ライブハウスで「妻の悪口」をいうことで、ファンの結束を固めていた。妻は、怒りのあまり、子供に厳しく当たることもあり、挙句、ある行動に出てしまう。
「この第一話〈悪い妻〉を書いたときは、作家・開高健の妻で詩人の牧羊子さんや、夏目漱石の妻が、『悪妻』とされていることが気になっていました。牧羊子さんは、開高健より7つ年上で、授かり婚だったからか、『開高健の才能をこの女がつぶしている』と、評論家たちに悪口を言われていた。これは男たちの嫉妬だと思うんです。妻を悪く言うことで、周囲の連帯を強めるのは、卑怯でもあるし、気持ち悪い構造だと思いました」
「男たちを断罪したいわけでもなく、小説で何かを啓発しようとも思っていない」
結婚の時に提示した約束を実現しない夫に愛想をつかし、「こんな男と結婚しなきゃよかった」という後悔を抱える妻を描いた〈残念〉や、妻と離婚した後、「洋服修理店」の若い女性店員のことを、ストーカーまがいに追いかけまわす男の哀歓を伝える〈武蔵野線〉が印象的だ。
いずれの登場人物たちも、「もっといい人生を送れたはずだった」という鬱屈を感じながら生きている。
「不思議に感じることがあるんです。男性は結婚するときに、『幸せにしてあげる』というでしょう。どうやって? なにをもって幸せというのでしょうか? あいまいなところからスタートして、結婚生活の中で齟齬が生じて、お互いに不幸になってしまっている。ただ、そんな男たちを断罪したいわけでもなく、小説で何かを啓発しようとも思っていないんです。
そのうえで、ここ最近の風潮の中で『男性も被害者』といえる一面もある。『つらい』『しんどい』と言えず、『寂しい』と思っていることもあるんでしょう。今作では、男女の意識のずれを書いてみようと思いました」
怒りを抱えた妻たちが描かれる一冊の中で、最終話〈もっと悪い妻〉は、逆説的な一篇だ。
30代後半で子供をもつ妻が、夫公認のもと、別の男性と身体を重ね、公然と不倫を楽しんでいる。この生き方を、「良妻賢母」という言葉で規定し、「悪妻」と断罪する男たちの身勝手な理屈を、切れ味鋭くも、愛情あふれる筆致で描いた今作。
結婚に踏み出そうとするとき、夫婦関係に迷ったとき、ぜひ読んでいただきたい物語だ。