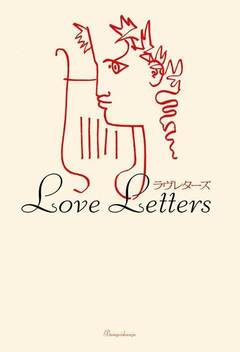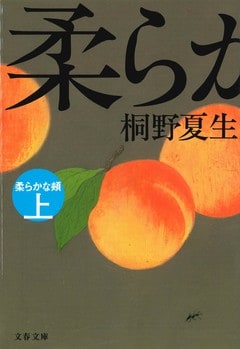誰が言ったか、「涙の強盗」という形容が気に入って、頻繁に使ってしまう。不治の病で誰かが死ぬ、離ればなれになっていた家族が数十年ぶりに再会する、慎ましい生活を送っていた夫婦を襲った悲劇と奇跡……その手のドラマや小説を受け止めて、涙を流す。でもそれは、心底揺さぶられた結果として流れた涙ではなく、こちらの感情とは裏腹に奪われていく涙である。主体的に流しているのではない。そりゃあ、人が白血病で亡くなれば、悲しい。連れ添った妻と会えなくなるとなれば、寂しい。だから、泣く。そういう装置をまったく作為的に適材適所に放り込んでくる作り手は、私たちの涙を見て「思いが伝わった」と感激の涙を流すのかもしれないが、貴方の涙は本物でも、こちらの涙は本物ではないのである。
何丁目の夕日だったか失念してしまったが、あの頃は素晴らしかった、夢があった、希望があった、と万事が前向きだった昭和の時代を見せるのもまた、不治の病と同様に「涙の強盗」の常套手段である。昭和の終盤に生まれた私は、その手の強盗に遭いやすい。古き良き時代のプロジェクトを大仰なBGMで男たちの友情として帰結させる取り組みにも、うっかり多くの涙を奪われてきた。
過ぎてしまった時代の輪郭に、後々から歩み寄っていくことは難儀だ。多くの人物評伝がそうであるように数珠つなぎで人間を辿ることはできても、輪郭をしっかりとつかみとることは難しい。そこでの好都合が、強盗が多発する遠因となる。ドラマチックなストーリーとして昭和が突きつけられる時、史実とともに感情も改ざんされていく。だからこそ私は、感情をいたずらにまぶしてくるそれらよりも、ルポライターやノンフィクション作家が熱を込めた作品から、時代の輪郭を察知しようと試みてきた。ある断片から漂う時代の余熱を感じ、少しでも本人の主観から嗅ぎ取ろうとする。
そういう読み方を続けてきた身からすれば、桐野夏生が紡ぐ物語は、往々にしてルポルタージュである。桐野の作品は時折、「現実を凌駕する」と評される。作品に記した後で同じような事件が現実に起こるから、という指摘もあるようだが、占いの答え合わせをするような分析は浅はかにも思える。時代への嗅覚の積み重ねが現実をまたぐ、ということではないか。桐野は当然、涙を盗まない。読者の感情を盗まない。むしろ、その感情は、貴方の体内にも宿っているものではないですかと、こちらの腹の中をまさぐり、指し示してくる。見透かされた後で小説から立ち上がる情景が、読み手にとっての時代の輪郭となる。読み終えた後で、その明度に畏怖の念を抱く。
本作で描かれる1963年の情景もまた然り。本作は『顔に降りかかる雨』『天使に見捨てられた夜』『ダーク』などに登場する私立探偵・村野ミロの義父・村野善三を描いた作品だ。東京五輪を翌年に控え、街全体が浮つくなか、村野は週刊誌「週刊ダンロン」の“トップ屋”として、街でネタを拾い集めては原稿用紙に向かい続けていた。63年9月、地下鉄銀座線で爆破事件に遭遇、未解決事件として世間を騒がせていた連続爆弾魔・草加次郎を追いながら、自らも女子高生殺人の容疑者として睨まれてしまう。
実際の出版史・ジャーナリズム史に準じた設定が続く。57年、大学を出た村野は、週刊誌づくりの人材を探していた潮流出版の門を叩く。当時は、新聞社系週刊誌が軒並み成功しており、その波に出版社が後追いで乗っかろうとしている時期にあった。情報源やデータベース、遊軍記者を持たなかった出版社に週刊誌作りは難しいと言われていたが、それを覆した存在が“トップ屋”だった。
村野に対して開口一番「俺の作る週刊誌は面白いよ」と吐いたのが遠山良巳。遠山は「新聞社の出す週刊誌なんざ四角四面でつまらない。あいつら週刊誌を新聞のアタマで考えてやがるのさ。その点、読み物作りじゃ出版社に敵わないんだ。見てな、今に抜くからさ」と凄む。遠山の一番弟子となった村野は、「遠山軍団」の両輪となった後藤伸朗と共に、発刊準備から携わった「週刊ダンロン」を動かすと、雑誌は瞬く間に60万部を超え、週刊誌の中で売り上げトップに躍り出る。