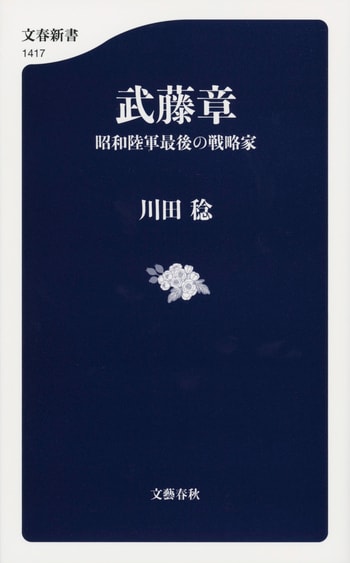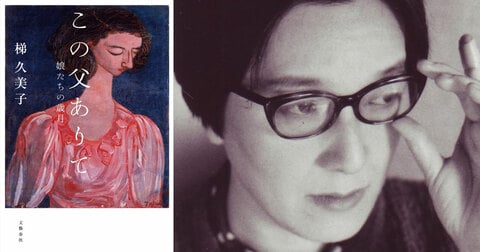武藤章は、東京裁判でA級戦犯として死刑判決をうけた軍人として知られている。
彼は対米開戦時の陸軍省軍務局長で、開戦に至る国策決定において重要な役割を果たした。
満州事変(一九三一年)以降、日本は陸軍がリードするかたちで国策を進めていくようになる。そして、一九三五年(昭和一〇年)頃から、その陸軍で主導権を握ったのが、いわゆる統制派だった。武藤はその統制派における理論的中心人物だった。欧州大戦開始まもなく東条英機が陸軍大臣となるが、陸軍では政治的、軍事的な戦略構想においては武藤が主導していた。
昭和陸軍における「戦略家」として著名な存在といえば、総力戦の時代に対応した国家体制の整備と中国大陸への進出を主導した永田鉄山や、満州事変を仕掛け、『最終戦争論』などの著作でも知られる石原莞爾が挙げられる。彼らに次ぐ世代で、陸軍の戦略を担ったのが武藤であった。
さらに武藤の興味深いところは、日中戦争では戦局の拡大を強く主張し、日独伊三国同盟の成立、南北仏印進駐などの決定に深く関与する一方で、アメリカとの戦争には反対し続けたことだ。
一般的な理解では、日本は対中戦争の解決が困難になったために、南方に進出、対米戦争に向かった、とされてきた。それでは武藤の戦略や行動は、単に矛盾したもの、苦しまぎれの変節としか思えない。しかし、彼の軌跡を丹念に追っていくと、そこには一貫した論理が見えてくる。
武藤は、陸軍きっての戦略家であった永田鉄山の後継者として、世界大戦を予期し、それに備えるべく国防国家の実現を自らの使命とした。日中戦争への傾斜も、対米戦回避への努力も、武藤のなかでは矛盾したものではなかった。
日本を中国大陸での戦争に導きながら、アメリカとの戦争を避けるために尽力し、その努力も潰えて日米戦争が開始されると、陸軍中央から戦闘の最前線に送られる。そして最後には極東国際軍事裁判でA級戦犯となり、最年少で死刑判決を受けた──。本書は、昭和日本の抱えた困難を象徴する人物として、武藤の思考と行動をたどっていきたい。
一九三八年(昭和一三年)一月、陸軍のシンクタンク的存在だった民間団体「国策研究会」の常任理事、矢次一夫は、上海に滞在していた武藤を訪ねた。当時、武藤は中支那方面軍参謀副長(大佐)だった。
そこに、二枚の色紙があり、二人の似顔絵に、それぞれ添え書きがしてあった。矢次が武藤にその由来を聞くと、次のような次第だった。
〈[ある漫画家が]司令部を訪ねたとき、たまたま塚田[攻]参謀長と武藤とが同席していたという。そこで塚田と武藤と二人の似顔を書いたそうだが、書き終わるやいなや、武藤が……筆をとって、塚田の似顔の横に、「頑迷不霊」[頑迷で無知な意]と書いた。塚田がこれを見て烈火のごとく怒り、それじゃ貴様は何だ、と卓を叩くのに、武藤は少しも騒がず、やおら自分の似顔の上に「傲慢不遜」と書いたので、さすがの塚田も呆気にとられ唖然としたという〉(矢次一夫『昭和動乱私史』上巻。以下、[]内は引用者註)
矢次は、これを聞き、つい失笑して、「傲慢不遜」とは自らを知るものだなと、武藤に伝えたとのことである。当時、武藤は陸軍内でその態度が傲慢にすぎると噂されていたからである。矢次は「武藤壮年時の一面」としてこれを書き残している。
また、敗戦後フィリピンのカランバン捕虜収容所で、フィリピン第一四方面軍参謀長(中将)だった武藤に接した作家、山本七平は、その時の印象を次のように記している。
〈昼食の時間が来た。閣下たち[将官]は三々五々、歩いてきた。だがその日には、いつもと違った一人の新顔が見えた。その人は、米軍のジャングル戦用迷彩服を着ており、それが奇妙によく似合った。彼は、あたかも収容所も鉄柵も軽蔑するかの如く傲然と見下し、それらの一切を無視するかの如く、堂々と歩いてくる。その態度は、終戦前の帝国軍人のそれと、寸分違わなかった。
丸い眼鏡、丸刈りの頭、ぐっとひいた顎、ちょっと突き出た、つっかかるような口許、体中にみなぎる一種の緊張感──「彼だな」私はすぐに気づいた。それは第十四方面軍参謀長武藤章中将その人であった。そして彼の姿と同時に、反射的に四つの言葉がよみがえってきた。
「統帥権、臨時軍事費、軍の実力者、軍の名誉(日本の名誉ではない)」。軍部ファシズムをその実施面で支えたものは何かと問われれば、私はこの四つをあげる。そして私にとってこの四つを一身に具えた体現者は彼であった。〉(山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』)
山本は、武藤の第一印象をこう記し、さらに後年、かつて陸軍を取材していた老記者と語り合う。
〈すべてを剥奪されて、収容所に入れられても、他の将官とは全く違う、彼の持つ一種異様の威圧感。数年前、戦前長いあいだ陸軍省づめをしていた老記者に、この不思議な威圧感の話をしたところ、その人は深くうなずきながらさまざまな「武藤伝説」を語ってくれた。
一佐官だった彼に威圧されて将官があわてて敬礼してしまったこと。彼の上級者が、私を退役にするのはこの男だろうと言ったこと等々から、一にらみで雀が落ちたとか、彼が歩けば自然に人が道をあけたとかいった他愛のないものまで──そのすべては、彼が、そのとき私が受けた印象通りの人物であることを物語っていた。そして、本当に意志決定を行うのは常に、こういうタイプの人物だったのである。〉(同右)
山本は同書で武藤、および武藤の体現する日本陸軍を厳しく批判しているが、次のような考察も書き留めている。
〈「いったいなぜ彼[武藤]は[捕虜収容所内でも]このような支配力をもちうるのであろうか」。……彼のもっていた異常な実力[支配力]の背後にあるものは……「生きながら死者の特権をもつ」という……基本的な姿勢……をそのまま持ちつづけていたからであろう。……[A級戦犯としての]処刑……を覚悟し「死を生きている」のであろう。したがって一切を無視しうる。……これがどれだけの力をもちうるかは、少なくとも武器を手にした経験のある人間には、説明不要のはずである。〉(同右)
この時、武藤はA級戦犯指名を受け日本本土に送られていたが、一時、第一四方面軍司令官山下奉文の裁判の証人として、フィリピンに召喚されていた。
矢次と山本の描く武藤像、中国とフィリピン、この間の武藤に何があったのだろうか。そして太平洋戦争開戦に至る、武藤の戦略構想とその結末はどのようなものだったのだろうか。それを描いていきたい。
軍人志望から煩悶時代へ
さて、本文に入る前に、ここで武藤の略歴に簡単にふれておこう。
武藤は、一八九二年(明治二五年)一二月、熊本県上益城郡白水村(現菊陽郡菊陽町)に生まれた。父は武藤定治、母は加野、代々医師の家系で、藩医も務めていた。また武藤が生まれた頃は、中規模の農地を所有する地主でもあった。武藤自身は必ずしも軍人志望ではなく、文学書、思想書、哲学書、歴史書などを耽読していた。また剣道にも興味をもち、新陰流の「目録」をうけている。しかし、母親の強い希望で軍人を志望することとなった。
彼は、この頃の少年時代について、戦後に著した『比島から巣鴨へ』で「私の村は阿蘇火山から肥後平原に流れ出る白川の左岸で、熊本市から約二里半の田舎である。朝夕私は東方六里に白煙を上げる阿蘇山やこれに連なる嶽々を眺め、平和な野や川に喜戯しながら育った」と回想している。
その後、武藤は、熊本の済々黌中学校に入り、念願の熊本陸軍幼年学校に入学、陸軍士官学校へと進んだ。ただ、幼年学校入学時の姓は、武藤ではなく井上となっている。これは、軍人の子弟の方が入試に有利だとの母親の判断から、従兄の井上喜伝陸軍大尉と養子縁組をさせられたためである。この井上姓は陸軍士官学校まで続けているが、卒業とともに武藤姓に戻っている。のちに「傲慢」とされた武藤も、生涯、母親には極めて従順だったようである。ただ、幼年学校時代、陸軍士官学校時代は、授業の内容に満足できず、様々な本を読みふけった。
士官学校卒業後、部隊勤務をへて陸軍大学校に進み、優秀な成績で卒業したものに贈られる「恩賜の軍刀」を得た。
武藤は、前出の『比島から巣鴨へ』で、自らの陸軍大学時代を次のように記している。
〈当時の私を回顧すると全く煩悶懊悩時代であった。第一次世界戦争の中頃から世界をあげて軍国主義打破、平和主義の横行、デモクラシー謳歌の最も華やかな時代であって、……我々軍人の軍服姿にさえ嫌悪の眼をむけ、甚しきは露骨に電車や道路上で罵倒した。……物価は騰貴するも軍人の俸給は昔ながらであって、青年将校の東京生活はどん底であった。
書店の新刊書や新聞雑誌は、デモクラシー、平和主義、マルクス主義の横溢であった。鋭敏な神経をもつ青年将校で、煩悶せぬのはどうかしている。〉
そして、しばらくして、陸軍中央の教育総監部勤務となった。ちなみに当時の教育総監は、日露戦争を描いた司馬遼太郎『坂の上の雲』でも有名な秋山好古だった。
一方、私生活では、福岡出身の尾野実信(陸軍中将)の長女初子と結婚している。尾野は当時、陸軍次官であり、武藤本人が意識していたかどうかは分からないが、その後の武藤の経歴にとっては、かなり有利に働いたようである。ただ、武藤夫妻には子供がなく、のちに初子の姪を養女にしている。
統制派の一員として
一九二三年(大正一二年)、教育総監部にいた武藤は、軍隊教育の観点から第一次世界大戦の研究のため、ドイツに派遣される。期間は二年半であった。当初はベルリンに滞在したが、日本人が多く、日本語使用が多くなるのを避けて、主にドレスデンに滞在している。
なお、ベルリン滞在中、前年からドイツに駐在していた三歳上の石原莞爾との交流が生じ、彼から日蓮宗の一派「国柱会」への入会を強く勧められるが、これは断っている。後述するように、これ以後、武藤と石原との関係は、思わぬ展開を見せることになる。
一九二六年(大正一五年)、帰国の途につくが、途中、アメリカに二ヵ月滞在する。
〈欧州文化を見た眼で米大陸に渡ると、一見その差異に驚く。米国には何にも古いものはない。すべて新しい。大袈裟である。すべてが動いている。近代文明の具体化である。……私の米国視察の価値報告は上司を動かしたと見え、その後欧州に留学する将校は、米国を一応視察するように定められた。〉(武藤章『比島から巣鴨へ』)
帰国後、武藤は一時体調を崩すが、まもなく回復し、陸軍大学専攻学生となる。ここで一年間、高度な戦略戦術の教育を受け、また「クラウゼウィッツと孫子との比較研究」と題する論考を書き上げる。この論文は高い評価を受け、雑誌『偕行社記事』にも掲載された。
専攻学生の期間が終わり、武藤は内心、陸軍大学教官になることを希望していたが、それはかなわず、参謀本部勤務となった。以後の武藤の動きは次章以降で詳述するが、ここでは概略を示しておこう。参謀本部でのポストは当初、情報部(第二部)の欧米課でドイツ班員だった。ここで情報部長だった永田鉄山の部下となる。まもなく作戦部(第一部)作戦課に転じ兵站班長となる。そこで満州事変が起こる。一九三一年(昭和六年)九月のことである。このころ武藤は、関東軍の動きを支援する一夕会のメンバーとなっており、後述するように、満州での関東軍の動きをコントロールしようとしていた今村均作戦課長と対立する。
翌年、情報部にもどり、新設された総合班の責任者となる。総合班は欧米課など情報部各課が集めた情報を総合的に分析するための機関で、情報部長直属だった。
この総合班長の時に、武藤は、約三ヵ月をかけて、ソ連、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカに、現状視察のために派遣されている。国際連盟脱退の直後だった。そのころ一夕会は、皇道派と統制派に分裂しており、武藤は統制派の一員とみなされていた。
その後、部隊所属となるが、一九三五年(昭和一〇年)三月、陸軍省軍務局の軍事課員となる。この年の八月、陸軍省内で永田鉄山が刺殺される事件が起きる。武藤はその現場に駆け付け、息も絶え絶えの永田を抱き起し、慟哭したと伝えられる。翌一九三六年には二・二六事件が起こる。武藤は、決起将校から統制派の一人として狙われながら、軍事課高級課員(課長補佐相当)として、決起部隊の鎮圧にあたった。このときの武藤の働きを高く評価したのが石原莞爾だった。
事件後、武藤は、作戦課長の石原らと共に、寺内寿一陸軍大臣候補を通じて、広田弘毅内閣の組閣に介入し、陸軍にとって都合の良い内閣を作らせようとした。また石原らと、広田首相に圧力をかけ、陸海軍大臣の現役武官制を復活させることに成功する。本格的に陸軍の政治工作に関わるようになったのである。だが、こののち、武藤は、日中戦争をめぐって、石原と対立し、彼を陸軍中央から放逐する。
さらに、第二次世界大戦が欧州で始まるや、陸軍省軍務局長となり、陸軍を牽引する存在となる。東条陸相も、太平洋戦争開戦時まで、大きな戦略については、基本的に武藤の考えを尊重していた。だが、開戦直後、武藤と東条の意見が対立。武藤は近衛師団長として、スマトラに派遣される。これ以後、陸軍中央に復帰することはなく、フィリピン・ルソン島で終戦を迎える。そして、東京裁判で死刑判決を受け、一九四八年(昭和二三年)一二月二三日、刑死する。A級戦犯では最年少の五六歳だった。
このような経歴の中で、歴史的にみて、武藤が最も重要な役割を果たすのは、太平洋戦争開戦へと至る軍務局長時代であり、彼自身にとって最も充実した時期だったのではないかと思われる。したがって本書では、軍務局長時代の武藤に焦点をあて、その前後の時代にもふれながら、彼の思想と行動を明らかにしていこうと思う。
<はじめにより>