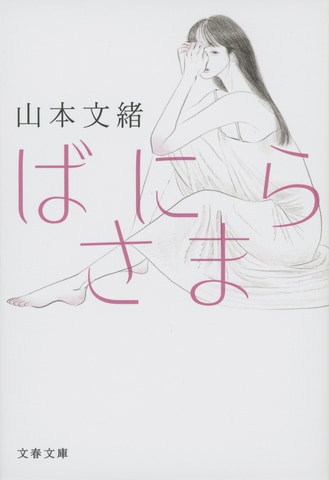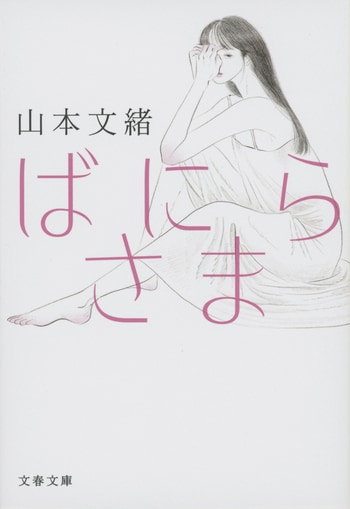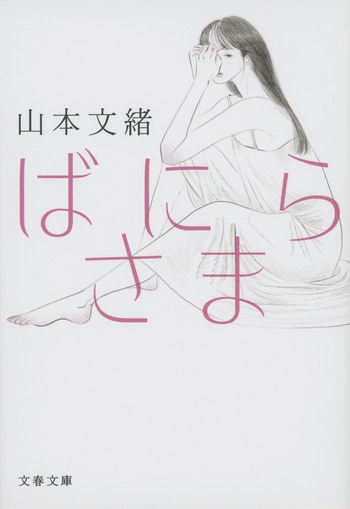基本的に物語というものは、生活を排除しがちである。ハリー・ポッターが洗濯する場面を読んだことがない。桃太郎がどんな服を着ていたのか、ほとんど知らない。恥の多い生涯を送って来ましたと言う主人公が、どんな布団でどんなパジャマでどれくらいの時間寝ているのか、よく分かっていない。しかしそんな情報が物語で語られることは少ない。なぜなら物語とは非日常を語るものだと、私たちは思い込んでいるからだ。
私たちは物語のなかで、巨大な敵を倒したり、呪われた運命に抵抗したり、生きる意味を問うたりする。その過程に高揚し、興奮し、そしてページをめくり終え、本をぱたんと閉じる。そして視線を本から上げたとき、私たちの目の前にひろがっているのは、ただただ、生活そのものなのだ。
生活は、重たくて粘っこくて、私たちの肩と背中にどっぷりと貼りつく。明日どんな服を着ていくのか、アイロンは必要なのか、税金の支払いをいつするのか、祖母にお中元のお礼の電話をいつするのか、マイナンバーカードのコピーを取引先にいつ送るのか、明日何時に家を出て今日はあと何分で寝なければいけないのか、ダイエットしたいけどお腹が空いたから何か食べたいさてどんなものなら食べてもいいのか。無数の生活が私たちの肩に乗っかっている。
しかしそんな重たい生活の痕は、ほとんどの場合、小説で綴られない。綴られたとしても、展開を邪魔しない場所に留め置かれる。なぜなら起伏のない生活を主題に綴ったところで、大抵の作家はその小説を面白くできないから。
しかし山本文緒さんは違う。生活にこそ人生のカタルシスがあることを誰より知っていた。そして誰より生活を面白く描くことができる作家だった。だから私は山本さんの生活描写がなにより好きなのである。
短い枚数で綴られる作品においても、その手腕は遺憾なく発揮される。たとえば表題作「ばにらさま」は、ある女性のブログを挿入しながら展開する。そこには彼女の視点から切り取った半径5メートル以内の生活が綴られる。たとえば外食に行ったらごはんの味だけではなくて酔っ払いの声が大きいかどうかが気になること。ずっとおろしたかったワンピースがあっても、派手だと思われるなら着られないこと。いつ髪を洗うのか、いつご飯パックを買うのか、寒くなってきたが冬の予定はどうするのか。ある日の日記は「毎日つまんないことで忙しくていやんなる」という言葉で締めくくられる。
たしかに人生は、つまんないことで忙しい。この実感に共感しない人がこの世にいるのだろうか。銀行口座の残金や、上司の嫌味、苦労の絶えない仕事。SNSに載せてみんなに見せられるようなキラキラした非日常なんて一瞬で通り過ぎ、あとは果てしなく重たい日常だけが人生には広がっている。誰だってそうだろう。
しかし山本さんの凄いところは、この「つまんないことで忙しい」彼女の日常を、作中で少しずつ私たちの日常からずらしていくところだ。読者を彼女にただ共感させるだけでは、終わらせない。そして彼女を現実から遠いフィクショナルな存在として描き出すことも、しない。
読者が彼女のことをどう思っているのか、山本さんは注意深くコントロールしつつ、最後には読者の欺瞞まで鮮やかに気づかせる。結末部分の読後感はさすがとしか言いようがない。まだ本作を読んでいない方がいたら、今すぐ読んでくれ、と私は肩を揺さぶるだろう。
誰かの日常の肯定。それを、ちゃんとカタルシスをもって、エンターテインメントとして高水準に読者を楽しませながらやってのけた作家を、私はほかに知らない。稀有な作家なのだ。本作を読みながら私はその事実を噛み締める。
1988年に少女小説家としてデビューした山本さんは、1992年に『パイナップルの彼方』で一般文芸作家に転向して以来、長編と短編、どちらも執筆する作家だった。島清恋愛文学賞・中央公論文芸賞を受賞した『自転しながら公転する』、ドラマ化した『恋愛中毒』『あなたには帰る家がある』といった長編小説も有名で、傑作が多い。しかし直木賞を受賞した『プラナリア』や本作を読めば分かるとおり、短編小説もまた、絶品なのである。
山本さんはうつ病治療のため執筆活動を休んだ時期があり、6年の歳月を挟み、復帰している(その様子はエッセイ『再婚生活─私のうつ闘病日記』で綴られている)。そのキャリアのなかで、とくに復帰後の短編・中編小説は、他に同じような小説を紹介してくれと訊ねられても困ってしまうような、山本さんにしか描けない手触りをもったものばかりなのだ。
たとえば『アカペラ』に収録された「ソリチュード」は山本さんの復帰後第1作である。風車の多い街を舞台にした中編小説だ。登場するのは、生活の重たさから逃げようとする男と、生活の重たさに覚悟を決めている女たち。そのような男女の対比が、お客さんに出す料理や、制服のスカート丈、変なトレーナー、そして財布から出したお金といった、生活の具体的な描写によって浮き彫りになる。
あるいは本作に収録された「子供おばさん」もまた、他に類を見ない小説だと言ってよいだろう。自分は子供おばさんだと自嘲する女性の物語。通夜の帰りに喪服のまま食べるパフェの味はどこかちぐはぐだった。香典返しの紙袋を、電車に置き忘れたい、と願う40代の女性もまた、どこかちぐはぐな気がしてしまう。亡くなった人が連れてきたある贈り物もまた、ちぐはぐなのだ。そんな生活に違和感を持ちながら生き続ける主人公の姿勢は、「子供おばさん」という言葉、そして社会の片隅で社会から飛び出さないようにちまちまと生きる私たちの生活を、肯定する。ちょっとくらい、社会でちぐはぐになっても、生き延びられるのだ、と読者へ静かに語りかける。
作家・山本文緒の短編小説を、もっと読みたかった。そう思うたび悲しさがこみ上げる。短い枚数のなかで、生活の重たさときらめきを、ぎゅっと濃縮する作品を書いてくれる作家なんて、もう他にいない。
だけど、それでいいのだろう。他の誰も、山本さんの代わりはいない。そしてそれは山本さんに限ったことではない。みんなそうなのだ。
社会で生きていると、みんな同じような日常、同じような生活を送っているように見える。自分の代わりはどこにでもいるように思える。だがその生活の様相は、たしかに少しずつ異なっている。誰ひとりとして、同じ生活を送っている人はいない。庶民的でせせこましい、「つまんないことで忙しい」日常を送っている私たちの、代わりは、誰ひとりとして存在しない。
山本さんの小説を読むたび、その事実にはっとする。
誰も代わりはいない。それは家族の有無や、仕事の達成や、容姿の在り方とはまったく関係ないところで、本当のことなのである。誰ひとり代替可能ではない。山本さんは小説のなかで、私たちに何度もそう語りかけているように思う。
別れに痛みが伴わないわけではない。現代の日本を舞台にしながら、これだけの作品を書ける作家が58歳の若さで突然亡くなってしまったのだ。『ばにらさま』が小説としては遺作となってしまったなんて、読者としていまだに悲しい。
しかしそれでも、山本さんの代わりは誰ひとりとして存在しない。そのことを誰よりも山本さん自身が小説のなかで繰り返し描いていたから、私たち読者は、その山本さんの不在を抱えながら生きていける。
「つまんないことで忙しい」日常にこそ、どうしようもない痛みも、生きていけると思える光も、どちらも存在する。重たい生活を肩に乗せながら、私たちはひとりひとりとして生きていくほかない。
山本文緒さんという作家は、生活の描写を、小説という芸術に昇華してくれる人だった。
私たちは山本文緒と出会うことで、生活にまばゆい光を見つけることができた。それは彼女の才能が贈ってくれた、ぬくもりと信頼、そのものだったのかもしれないのだ。