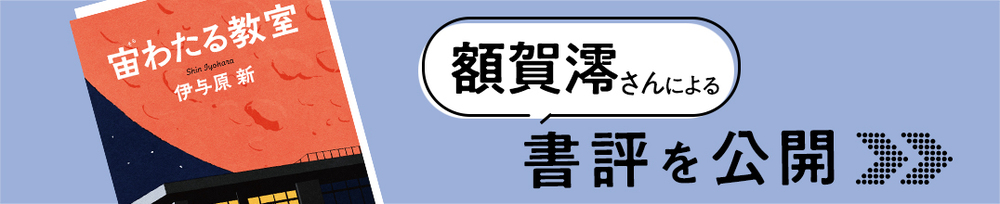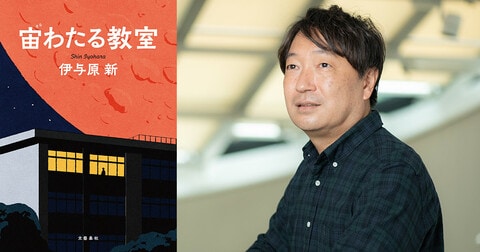第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書〈高校生の部〉に選出された、伊与原新さんの『宙わたる教室』。窪田正孝さん主演のNHK「ドラマ10」の原作にも決定しました!
本作の舞台は、東京・新宿にある定時制都立高校。そこには年代も、抱える事情もさまざまな生徒たちが通っています。負のスパイラルから抜け出せない21歳の岳人、日比ハーフで40代のアジェラ、起立性調節障害で不登校になった佳純、中学を出てすぐ東京で集団就職した70代の長嶺。彼らは理科教師の藤竹を顧問として科学部を結成し、「火星のクレーター」を再現する実験を始めるが――。
実際にあった「定時制高校科学部」の功績に着想を得た、胸熱の青春小説の魅力を皆さまに感じていただくべく、短編としても読み切れる本作第1章を、丸ごと特別無料公開します。どうぞお楽しみください。
第一章 夜八時の青空教室
牛丼屋を出ると、ホストクラブの宣伝トラックが目の前を通り過ぎた。耳障りな音楽を大音量で垂れ流しながら、新宿駅のほうへ走り去っていく。
柳田岳人は、唾と一緒に爪楊枝を吐き捨て、腕時計に目をやる。夜七時半。もう三限目が始まっているが、そんなことよりまず食後の一服だ。
すぐ隣のコンビニで、さっき切らしてしまったたばこを買った。店先で封を切り、ゆっくり二口ほど味わってから、大久保通りを歩き出す。すれ違うのは、ほとんどが自分と同世代の若者たちだ。これから新大久保のコリアンタウンへ遊びに行くのだろう。
岳人はくわえたばこのまま、あえて歩道の真ん中を進んだ。薄汚れた作業着にぼさぼさの金髪。左右の耳にはシルバーのピアスが合わせて十個光っている。無遠慮に煙を吐き出しても、咎めるような目を向けてくる者はいない。
地下鉄東新宿駅の入り口がある交差点を越えたあたりで、街の雰囲気が変わる。人通りはぐっと減り、飲食店に代わって目立ち始めるのは住宅やマンションだ。
ゆるやかな坂の途中にある校門のそばまで来ると、中から聞き覚えのあるけたたましいバイクの排気音が響いてきた。岳人は短く息をつき、都立東新宿高校の薄暗い構内へ入っていく。この時間、ブレザーの制服を着た全日制の生徒たちはもういない。
二本並んだ葉桜のわきを通り、渡り廊下の下をくぐってグラウンドへ出ると、思ったとおりだった。三浦が朴を後ろに乗せて、マフラーに穴の開いたオンボロの原付で走り回っている。もちろん二人ともノーヘルだ。
右手の校舎の三階から、誰かが「うっせえぞクソが!」と叫んだ。明かりがついているのはその階だけ。定時制が使っている四つの教室だ。
岳人が三浦たちのほうへ近づいていこうとしたとき、どこからともなく現れた人影が原付の前に立ちはだかった。どうにか届く外灯の光に、ジャケットに包まれた貧相な体が浮かび上がる。
腕組みをして首をわずかにかたむけたあの立ち姿は、担任の藤竹だ。なまっちろい顔もなで肩もいかにも頼りなげなのに、態度だけは妙にでかい。以前、クラスの誰かに訊かれて、歳は三十四だと言っていた。
バイクを停めた三浦に、藤竹が何か言っている。怒鳴るでもにらみつけるでもなく、いつものむかつくほど淡々とした様子でだ。藤竹の言葉は聞き取れなかったが、三浦の甲高い声は届いた。
「勉強の邪魔ってよ」三浦はへらへら笑いながら食ってかかる。「こんなとこに、まともに勉強してるやつなんているかよ」
「いますよ、もちろん」今度は藤竹が答えるのも聞こえた。
「どこにだよ」三浦が挑発するように校舎のほうへあごをしゃくる。
三階の四つの教室の窓から、大勢の生徒たちが顔を突き出してこっちを見ていた。「タイマンはれよ!」などとヤジを飛ばす男子もいる。
「ここにもいます」藤竹は眼鏡に手をやり、平然と言い放った。「私は勉強中でした」
「ああ? 何言ってんだお前」
三浦は細く剃った眉をひそめ、アクセルを吹かして藤竹のまわりをぐるぐる回り始める。それを見て岳人は、暗がりから「おい」と声をかけた。こちらの姿に気づいた三浦が、ブレーキを軋らせる。
「おっせえよ、ガッくん」三浦はおどけて言った。「遅刻ばっかしてると、退学だよ」
「仕事が長引いたんだって」半分は本当だが、半分は嘘だった。仕事帰りにゲームセンターに寄っていたのだ。二本目のたばこに火をつけながら、彼らのそばまで行く。
「なあガッくん、この人誰?」坊主頭を赤く染めた朴が、藤竹を指差して訊ねる。
「うちの担任」先月この掃き溜めに赴任してきた、運の悪い男だ。
「え、佐藤ちゃんは?」佐藤というのは、昨年度――岳人たちが一年生のときの担任だった。ここの定時制では原則、担任は四年間の持ち上がり制になっている。
「病気だってよ」噂では、メンタルの不調で休職したらしい。「お前らのせいだな」
「いやいや、そりゃないっしょ」三浦がにやける。「俺ら、おとなしくしてたっしょ」
二人とも確かに暴れたりはしていないが、まともに授業を受けていたわけでもない。仲間と連れ立って校舎をぶらついたり、中庭でほうきをバットに野球をしたりしていただけだ。
「君たちは、ここの生徒だったんですか」藤竹が三浦たちに言う。
「そ。だから部外者じゃねーの。OBだよ、OB」
「バーカ。OBってのは、ちゃんと卒業したやつのことをいうんだよ」岳人は鼻息を漏らし、二人の顔を交互に見る。「で、何? 俺に用なんだろ?」
「何、じゃねーって。こないだの話だよ」
「ああ――」もちろん最初からわかっていたが、曖昧に応じた。
三浦はポケットから小さく折り畳んだ紙切れを取り出し、岳人の手に握らせてくる。
「だいたいこんな感じになってっから。よろしく」
さすがに藤竹の前で開くわけにはいかないので、そのまま作業着の胸ポケットにねじ込む。それを承諾のしるしと受け取ったのか、三浦が親指を立てた。
ハンドルを握った三浦は、「また電話するわ」と言い残し、原付を発進させる。去り際に朴がこちらを振り返り、「アンニョン」と右手を上げた。
二人が校門のほうへ消えるのを見届けて、岳人も踵を返した。後ろから藤竹が「教室に行くんじゃないんですか」と言ってきたが、無視して中庭に向かう。四限目が始まるまで、そこで時間をつぶすつもりだった。
中庭の隅に一本だけ立っている外灯のまわりには、いつものように吸い殻が散乱していた。
構内は当然禁煙なので、岳人のように成人した生徒が喫煙するのも校則違反だ。しかし、たとえ未成年の生徒がたばこを吸っていても、教師たちはそこまで目くじらを立てない。現場を目撃すればさすがに注意はするが、停学などの処分は簡単には下されない。他に問題が多過ぎてそこまで手が回らないというのが、本当のところだろう。
定時制の生徒は年齢もタイプも様々だが、構内にいくつかある喫煙者たちのたまり場には似たような目つきの連中が集まってくる。三浦や朴ともこの中庭で親しくなった。だが、一服しながら悪さ自慢に興じていた同級生たちは、三浦たち同様、大半がすでに学校を去った。
東新宿高校定時制は一学年一クラスで、定員は三十人。とはいえ例年定員割れで、入ってきた一年生も二年生になるまでに六、七割、ひどい年には半分以下に減る。進級できないのではない。学校に馴染めなかったり、嫌気がさしたりして退学するのだ。
授業は週五日、五時四十五分に一限目が始まり、九時ちょうどに四限目が終わる。一日四限しかないので、卒業するのに四年かかる。
岳人は一年生の間、仕事の都合で遅刻することはあっても、学校を休んだことは一日もなかった。一年間何とか踏ん張れば、今度こそ投げ出さずにいれば、少しはよくなるのではないかと思っていた。だがそれはやはり甘かった。毎日きちんと授業を受け、教科書を開き続けてきたというのに、状況は何一つ変わらない。
二年生にはなったものの、もう糸は半分切れている。実際、五月に入ってから一限目の授業に出た日は数えるほどしかないし、登校しても気が乗らなければこうして中庭で過ごしている。
辞めどきか――。作業着の胸ポケットからたばことさっきの紙切れをつまみ出した。一本くわえて火をつけてから、紙切れを開く。下手くそな字だったが、片仮名と数字だけだったのでどうにか読み取れた。〈ヤサイ七五〇〇 リキッド一八〇〇〇〉。大麻の価格表だ。
三浦と朴は中退後、大麻の売人のようなことを始めている。客はネットで引っかけた常用者や、歌舞伎町にたむろしている若者たち。仕入れ先までは聞いていないが、やくざの息のかかった人間か、新大久保あたりの不良外国人だろう。
三浦に頼まれていたのは、この定時制の生徒やその周辺に販売ルートを作ってほしいということだった。新規の客がつかまれば、売り上げの何パーセントかをマージンとしてこちらに渡すという。
やばい話だともおいしい話だとも思わなかった。今さら真面目ぶるつもりはない。大麻なら岳人自身、十五、六のときに何度か試したことがある。体がふわふわするようなあの感覚が好きになれず、はまらなかっただけだ。たぶん、常にシラフでいたい質なのだろう。酒もほとんど飲まない。
三浦にはっきり返事をしていない理由は二つ。一つは単に、面倒だから。そしてもう一つは、また同じ轍を踏むのはうんざりだったからだ。売人の片棒をかつぐようになれば、そのうち仕事や学校に行くのもばからしくなるだろう。定時制に入ろうと一念発起したときの自分より、もっと落ちぶれることになる。
一段上がろうと挑戦して失敗し、逆に一段落ちる。岳人の二十一年の人生は、その繰り返しだった。このまま負のスパイラルから抜け出せないでいると、数年後には新宿の裏通りで野たれ死にだ。
だからといって、これ以上ここに通い続ける意味があるとも思えない。
学校なんてものに期待した自分がばかだったのか。それとも、不良品がいくらあがいたところで、無駄なのか――。
岳人は紙切れを四つに破り、たばこと一緒に地面に捨てた。
*
プリントの方程式をじっと見て、答えの数字だけを書き殴る。二問目の文章題は、ひと目見てあきらめた。シャーペンを置くと、つい右手が作業着の胸ポケットにいき、たばこを取り出してしまう。通学し始めて一年経つというのに、この癖がまだ抜けない。
教卓の藤竹とまた目が合った。腕組みをして、こちらをじっと見つめてくる。吸わねーよボケ。心の中で毒づきながら、小さく舌打ちをした。
今日は二限目に間に合うように登校した。この「数学Ⅰ」の授業があるからだ。教科の中で、学んでいるという感覚が多少なりとも得られるのは、数学だけだった。だがそれも、二年生になってからはすっかり調子が狂ってしまっている。
藤竹のせいだ。この新しい担任とはなぜか、やたらに目が合う。ふと気づけば、眼鏡越しに観察されている。気があるのでなければ、文句があるのだろう。いずれにせよ、何を考えているのかよくわからないあの眼差しを向けられると、背筋に悪寒が走るのだ。
藤竹の本業は、数学ではなく理科だ。この二年A組では「物理基礎」と「地学基礎」を受け持っている。数学を担当していたのは休職した前の担任、佐藤なのだが、補充の非常勤講師が決まるまでの間、藤竹が数学も教えることになった。少数の教員でやりくりしている定時制ではよくあることらしい。
頬づえをつき、たばこの箱を机で転がす。窓際の一番後ろに座っているので、教室中が見渡せる。クラスに在籍しているのは確か十八人だが、今日来ているのは十四、五人というところか。全員が出席していることはまずないので、まあ平常通りだ。プリントの問題に取り組んでいるやつもいれば、手もつけずにスマホをいじっているやつもいる。
最前列に陣取っているのは、三人の年配組。最年長は七十代くらいのやせこけた男――通称「長老」で、出来はともかく誰より勉強熱心だ。授業中、度々手を挙げて要領を得ない質問を繰り返す。こちらが珍しく集中して授業を聞いているときなどは、後ろから蹴りを入れたくなる。
あとの二人は四、五十代の女。一人はいつも黙々とノートを取っている。もう一人は小太りの東南アジア系で、とにかくよくしゃべる。誰かが「フィリピンパブのママとかじゃね?」と冗談で言い出して、「ママ」というあだ名がついた。
東新宿という場所柄もあってか、外国にルーツを持つ生徒は他にも数名いる。何人かは来日してまだ日が浅いようで、日本語が不自由だ。ママはそんな彼らを気遣い、頼まれもしないのによく世話を焼いている。
岳人と同じく最後列を指定席にしているのは、素行不良で全日制の高校をつまみ出された生徒たちだ。カラフルな髪色にごついアクセサリーなど、見た目は派手だが授業中は意外とおとなしい。漫画や動画を見ているか、そうでなければ机に突っ伏して眠っているからだ。立ち歩いて授業を妨害していた連中はだんだん学校に来なくなり、知らないうちに辞めていった。
数は決して少なくないのに、教室にいるのかいないのかわからないような生徒たちが、元不登校組。岳人などにはまず近づかず、服装も地味で、年齢より幼く見える。小中学校でいじめに遭ったり、集団生活に馴染めなかったりした者がほとんどらしい。オタクが多いのか、二、三人でかたまってアニメの話をよくしている。
そんな調子だから、クラスとしてのまとまりはまったくない。岳人を含めほとんどの生徒が、自分のことで精いっぱい、あるいは、自分と世界の違う者たちとは関わりたくないという空気を発している。
岳人の隣でスマホをにらみ、長いネイルの指を猛スピードで動かしていた麻衣が、突然それを耳に当てた。
「あ、マサオちゃん?」当たり前のように電話に出ると、甘えた声とヒールの音を響かせながら廊下に出ていく。「ライン見てくれた? うん、そう。そろそろ会いたいなーと思って」
麻衣は現役のキャバクラ嬢だ。この時間帯は、彼女が昼間に送った営業メッセージを見て、仕事終わりの客がよく電話をかけてくる。この様子だと、今夜も三限目以降はパスして歌舞伎町の店に出るつもりだろう。
藤竹は、何事もなかったかのように生徒たちを見回し、「そろそろいいですか」と言った。プリントを集め、その場で答案の出来をざっと確認してから、問題の解説を始める。それが藤竹の授業のやり方だった。
今日の内容は、連立方程式。本来は中学二年で習うことらしい。「数学Ⅰ」とは名ばかりで、実際はほとんどの時間が中学校の数学の復習に費やされる。それでも、分数や小数の計算さえ怪しい一部の生徒たちにとっては相当ハードルが高い。
「前回の問題とほとんど同じはずなんですが」藤竹がプリントの束を教卓に置く。「苦戦しているようですね」
「難しいヨ」ママが言った。「式一つでも大変なのに、二つもある。わからないヨ」
藤竹はママにうなずきかけ、正面に向き直る。
「自動的にはわからない」
「どういう意味?」ママが訊いた。
「授業をただ聞いていればわかるとか、教科書をただ読んでいればわかるとかいうものではないってことです。数学や物理はとくに」
「じゃあ、どうすりゃいいんです?」長老が不満げに言う。
「手を動かすんです。何度も何度も書く。やみくもにでも式をいじくり回す。いろんな図をしつこく描いてみる。そうしているうちに、わかった、という瞬間が来ます。必ず」
バカかこいつ。岳人は鼻で笑った。十五、六の頃なら、この席からたばこの箱を投げつけているところだ。そんなふうに勉強ができるくらいなら、定時制なんかにいやしない。
まわりを見ても、若い生徒たちは皆しらけた顔をしている。それを気にする様子もなく、藤竹は真顔で続けた。
「私は天才ではありません。たぶん、あなたたちも。だから結局、方法はそれしかないんです。もし本当にわかりたいのなら」
四限目が終わるのを待って職員室を訪ねたが、そこに担任の姿はなかった。国語の教師が「物理準備室だと思うよ」と言うので、そちらへ行ってみる。
二階から渡り廊下を通って隣の校舎に入り、L字になった建物の角を曲がった先だ。
部屋の扉は開いていて、中に藤竹がいるのが見えた。窓際の机に向かって何か読んでいる。
「ちょっといいすか」
廊下から声をかけると、藤竹は振り向かずに「どうぞ」と応じた。ビーカーなどが収められた棚と実験台の間をとおり、奥へと進む。足を踏み入れたのは初めてだ。
その机は藤竹専用なのか、私物らしき本や辞典が並んでいた。その横には、リアルな恐竜のフィギュアが二つと、木の板でできた骨格模型が一つ飾られている。
藤竹が机で開いていたのは、英語で書かれた分厚い本。グラフや図が見えるので、科学の教科書か何かだろう。ふと、昨夜藤竹が三浦に返した言葉がよぎる。
私は勉強中でした――。
「仕事、忙しいんですか」
「え?」虚をつかれた。
「最近、一限目の欠席が多いから」藤竹はこちらに椅子を回した。「勤め先は確か、リサイクル関係でしたよね」
「ただのごみ収集すよ、俺がやってんのは」
岳人が去年から働いているのは、ビン、空き缶、ペットボトルなどの廃棄物の回収と、リサイクルのための中間処理を行う会社だ。あてがわれている仕事は、事業系資源ごみの収集で、毎日朝早くから収集車に乗り込み、委託を受けた会社やビルのごみ庫を回っている。
「柳田君の一年のときの出席状況を確認したんですが、ほとんど毎日一限目から出てましたよね。仕事のシフトが変わったんですか。もしそうなら、一度職場と相談して――」
「いいんすよ」いらついてさえぎった。「たぶん、もう辞めるんで」
「辞めるって、学校を?」藤竹があごを上げ、眼鏡に手をやる。
「だから、やり方聞いとこうと思って。退学届とか」
藤竹はまたあの観察するような目で数秒こちらを凝視すると、腕時計をちらりと見た。
「少し、時間ありますか」
「あ? ああ――」
「ちょっと、歩きながら話しましょう」
今週は藤竹が「モク拾い」の当番だという。教師たちが毎晩放課後、ごみバサミを手に構内の吸い殻を掃除して回る業務のことだ。定時制高校ならどこでもおこなわれていることで、怠ると全日制の教員から苦情が出るらしい。
喫煙者のたまり場は外階段の踊り場や男子トイレなどいくつかあるが、藤竹はまず中庭に出た。
定時制の放課後は、わずかな人の気配と明かりも徐々に消え、校舎が暗闇に包まれるのを待つだけの時間だ。中庭にも人影はなく、遠くで救急車のサイレンの音だけが聞こえる。
外灯のまわりに固まって捨てられている吸い殻の半分は、三、四限目の間ここで時間をつぶしていた岳人のものだった。藤竹はそれを一つずつごみバサミでつまみ、ポリ袋に入れていく。それを突っ立って見ていた岳人は、校舎の壁際にコーヒーの空き缶が一つ転がっていることに気づいた。拾い上げて振ってみると、案の定かさかさと音がする。
「こういうのがマジ最低なんだよ」岳人は舌打ちをして言った。空き缶を藤竹のポリ袋の口へ持っていき、飲み口から中の吸い殻をふるい落とす。「集める側のことを、何も考えてねえ」
出された資源ごみの中に灰皿代わりに使われた空き缶が混ざっていると、リサイクルの前処理にひどく手間がかかるのだ。
「では、ここに吸い殻を捨てている君たちは、我々教師のことを考えているんですか」藤竹が淡々とした調子で言った。
もちろんぐうの音も出ない。唇を歪めたまま黙っていると、藤竹は急に話題を変えた。
「学校を辞めて、どうするんです?」
「どうもしねーよ。だいたい、そういうのは普通の高校に行ってるやつに言う台詞だろ」
「じゃあ、昼間は働いて、夜は大麻の売人ですか」
「え――」思わずうわずった声が漏れた。慌てて平静を装う。「何だよ、それ」
「昨日の夜、ここでメモを拾ったんです」
藤竹はごみバサミをかちゃかちゃと鳴らし、ポケットからそれを取り出した。四つに破ったはずの紙切れが、ご丁寧にテープで張り合わされている。
「君が、昨日のバイクの彼から受け取っていたものではないですか」
迂闊だったと思うと同時に、また背筋が寒くなった。大麻の件がばれたからではない。その異常なほどの几帳面さに、執念深さのようなものを感じたからだ。
「だったらどうだっつうんだよ」虚勢を張るしかなかった。
「どうもしません。〈ヤサイ〉というのが大麻の隠語だということは、ネットで調べてすぐわかりました。でも、君がその売買に関わろうとしているのではないかというのは、私の想像にすぎない。ところで――」
藤竹はメモの文字をちらりと見て、それを手の中に隠した。
「乾燥大麻を三グラム。大麻リキッドを四本ほしい。全部でいくらですか」
「何言ってんだ、あんた」
「いいから」藤竹は真顔だった。「合計いくらです? 単価を言いましょうか。乾燥大麻は一グラム七千五百円、リキッドは――」
「九万四千五百円だよ、全部で」もうどうでもよくなって、投げやりに答えた。
「ご名答」藤竹が初めて口もとをほころばせる。「やはり計算能力が高いですね。子どもの頃、そろばんでもやってましたか」
「やってるかよ、そんなもん」
藤竹はごみバサミを握ったまま、腕組みをした。
「柳田君は、とても興味深い生徒ですよ。数Ⅰの授業で毎回やってもらっているプリントの解答も、注目に値します」
「んなわけねーだろ。いつも半分は白紙だよ」
「連立方程式や二次方程式の解は、難なく求める。かなり複雑な平方根の計算問題なんかも、間違うことはまずない。しかも、途中の計算は一切書かずに、答えだけをぽんと書いている。全部頭の中で計算しているんですか」
「ごちゃごちゃ書くのが面倒なんだよ」
「もっと不思議なのは、問題がいわゆる文章題になると、まったく手をつけないということです。小学生でも解けるような問題にも、答えようとしない」
それは本当のことだったが、教師に指摘されたのは初めてだった。岳人は小さく息をつき、吐き出すように言った。
「文章を読むのが嫌いなんだよ、昔っから。真面目に教科書なんか読もうとした日にゃ、気が狂いそうになる。吐き気がしてくる。何も頭に入ってこねえ。不良品なんだよ」
「不良品?」
「バカなんだよ。頭がわりいの。おまけに辛抱も足りねえんだと」言っているうちに、感情がたかぶってくる。「でもどうしようもねーんだ。不良品に教科書なんて、豚に真珠なんだよ。中学の教科書なんか、もらったその日にごみ箱にぶち込んでやった」
「それで高校へは進学しなかったわけですか」
「中学にもろくに行ってねーよ」
「それでも二十歳になって、この高校へ来た。勉強するのが嫌というわけではないんじゃないですか」
「あんたさ」鼻で笑った。「やっぱ定時制の教師なんか向いてないんじゃね? こんなとこへ来るやつらは、お利口に勉強しに来てるんじゃねんだよ。高卒の学歴ぐらいなきゃやべえってことがわかって、仕方なく四年間椅子に座りに来てるだけなんだよ」
「君もそうなんですか」
「俺は――」なんでこいつに話す必要がある。つい藤竹のペースに乗せられていたことに気づき、いらだちが増した。「あんたには関係ねえ。それに、もう辞めるって言ってんだろ」
藤竹はまた観察するような目を向けてきた。やがて組んでいた腕をほどき、「わかりました」と淡白に告げる。「退学の手続きについては、明日にでも確認してみます」
*
仕事を終えて休憩室に戻り、奥に並んだロッカーに向かう。
続いて入ってきた三人の同僚は、疲れた疲れたと口々に言いながら、真ん中のテーブルを囲んでパイプ椅子に腰を下ろした。
会社があるのは北区の新河岸川べり。収集車の駐車場と廃棄物の保管庫、中間処理の工場などがあるので、立地はこういう場所になる。働き始めたばかりの頃は、敷地に漂う饐えた臭いに辟易したが、もうすっかり慣れて何も感じなくなった。
ここを五時に出て赤羽駅からJRに乗れば、五時四十五分から始まる一限目にぎりぎり間に合う。終業時刻は四時五十分なので、以前は荷物だけ引っつかんで飛び出ていた。
今はもう急ぐつもりもないが、同僚たちとここで無駄話をしていく気もなかった。こいつらはすぐに勘違いをする。どこの職場でもそうだった。たまたま同じところで働いているというだけなのに、気の合う仲間だと思い込むのだ。
そして、大して親しくもなっていないうちに、ずかずかと土足で踏み込んでくる。生まれはどこだ? 家族の構成は? 学校はどこを出た? こっちは友だちを作りに来てるんじゃない。金さえもらえりゃそれでいいんだ。
岳人は一人無言でロッカーからリュックを取り出し、荒っぽく扉を閉めた。作業着で通勤しているので、私服に着替えたりはしない。収集作業中にひどく汚れたときだけ、ここに置いてある替えの作業着を着て帰る。
「お先っす」と言い捨ててテーブルのわきを通り過ぎようとしたとき、椅子にふんぞり返っていた同僚に「おい」と呼び止められた。四月に工場から収集班に移ってきた角刈りの中年男だ。名前も聞いたはずだが、忘れてしまった。
「お前、名前何やったかいの」太い指にたばこをはさんだ角刈りが、関西弁で訊いてくる。人の名前を覚える気がないのは向こうも同じらしい。名字を告げると、「せやせや」とわざとらしくうなずいた。
「わしらこれから駅前で一杯やるんやけど、お前もどうや。OK横丁にええ店あんねん」
「いや、俺はちょっと」素っ気なく言った。
「柳田は、これから学校なんすよ」岳人とペアを組んでいるドライバーの武井が言った。
「学校? 何の学校や」
岳人は顔をしかめてみせたが、武井は気づかずのんきな声で答える。
「高校ですよ、定時制」
「定時制?」角刈りは口の端を歪めた。「それは感心と言いたいところやが、今の定時制はひどいらしいのう。健気な勤労学生が通うてたのは昔の話で、最近は高校を中退した悪ガキと、不登校やったような連中ばっかりやいうやんけ」
「あ?」定時制を悪く言われて、自分でも驚くほどの怒りがこみ上げてきた。大した仲間意識もないはずの、クラスメイトたちの顔が浮かぶ。
「お前も中退したクチか。ええ?」角刈りが、岳人のピアスを揶揄するように自分の耳たぶをちょんちょんと弾く。「そんなにグレとったんか」
「あんたには関係ねえだろ」
怒りが爆発する前に部屋を出て行こうとすると、「待てや」と角刈りに右腕をつかまれた。
「中卒は、口のきき方も知らんのか」
腕を強く振って角刈りの手をほどいた拍子に、右肩に引っ掛けていたリュックがすべり落ちた。ふたのバックルを留めていなかったので、中身が床に飛び出る。表紙の擦り切れた運転教本を慌ててつかみ上げ、隠すようにリュックに押し込んだ。ひざまずいて筆記具を拾い集めていると、頭の上で角刈りが「何のノートや」と言った。
「〈させつするとき〉」いつの間に拾ったのか、勝手に開いて読み上げる。「〈させつしようとするちてんの三〇メートルてまえであいずをだします〉。ミミズがのたくったような字やのう」
血が沸騰するような感覚とともに、全身の毛穴が開く。「おい!」と怒鳴りながら、飛びかかるようにしてノートを奪い取った。
「何してんだオラ!」角刈りの胸ぐらをつかみ、ねじり上げる。「殺すぞてめえ!」
「しかも、全部ひらがなやないか」角刈りは嘲るように言った。「定時制行く前に、小学校からやり直しちゃうか」
目の前が一瞬真っ白になった。無意識のうちに右腕がのび、拳が角刈りの顔面にめり込む感触だけが伝わってきた。
リュックを畳に放り投げ、明かりもつけずにパイプベッドに身を投げ出した。
アパートは百人町の路地の奥なので、コリアンタウンの喧騒は届かない。カーテン代わりに窓にはりつけた布の隙間から、黄色とピンクの点滅する光が漏れ入ってくる。斜め向かいにある汚いラブホテルの看板だ。
拳の痛み具合からして、二、三発は入れたのだろう。武井たちに二人がかりで引きはがされて、やっと我に返った。すぐに上司が飛んできて事情を訊かれたのだが、ただ悪態をつき続けていた覚えしかない。今日はとにかく帰れと言われて、会社を出たようだ。新大久保駅からアパートまで歩いている間に、やっと頭が冷えてきた。
これでまたクビか。いったい何度目だろう。
十五歳のときから転々としてきたアルバイトも、十八で初めて契約社員になった食品会社も、ほとんど同じ理由で辞めている。
読み書きに難があることは、どの職場でもふとしたきっかけで知られてしまった。露骨にばかにされたときはもちろん、冗談半分にからかわれただけで、今回のように手が出た。目の前で笑う者がいなくても、陰で何か言われているような気がして、些細なことで周囲に突っかかった。そんな人間が、職場に長く留まれるわけがない。
決して粗野な環境で育ったわけではない。父親は大手電機メーカーに勤める会社員で、母親は専業主婦。調布市のごく普通の家庭に一人息子として生まれた。「岳人」と名付けたのは、若い頃登山に熱中していた父親だと聞いている。人生という山を一歩一歩着実に登っていってほしい、ということだったらしい。
母親によれば、岳人はむしろおとなしい子どもだったそうだ。確かに幼稚園の頃は、公園にいるやんちゃな子どもたちと遊ぶのが嫌で、いつも家で一人図鑑や絵本を眺めていた記憶がある。写真や絵を見ているだけでも楽しいけれど、字が読めるようになればもっと楽しいはず。そう思って一年生になれるのを心待ちにしていた。
ところが、小学校に入学するといきなりつまずいた。ひらがなはどうにか覚えたものの、教科書の文章がうまく読めない。目で追っている文字が、消える、飛ぶ、重なる。どこを読んでいるのか、すぐにわからなくなるのだ。教師に指されて音読をさせられると、二つ目の単語でつまってしまい、いつも笑い者になった。
書くのも苦手で、文字がノートの罫線の間になかなかおさまらない。宿題のワークやドリルは何度もやり直しをさせられた。少し複雑な漢字を習うようになると、なぞって書くことさえできなかった。
だからその分、授業は一生懸命聞いて、教師の話をできるだけ記憶しようとした。数字と〈+〉や〈=〉の記号は比較的読みやすかったので、算数の授業はとくに頑張った。九九はもちろん、二桁の数同士のかけ算もかなり暗記した。だが、たとえ学んだ内容を理解していても、テストでは問題文がうまく読めないのだから、解答しようがない。テストの点数は毎回ひどいものだった。
父親はいつも多忙で、岳人の勉強を見るどころか、休日に一緒に遊んでくれることもほとんどなかった。そのくせ通知表を見るたびに、「お前が悪いんじゃないのか」と母親をなじった。岳人は教科書を読むのが辛いようだと母親が訴えても、「辛抱が足りないんだ。怠けたいだけの言い訳だよ」と面倒くさそうに繰り返すだけだった。
そこそこ名の知れた大学を卒業した父親と違って、母親はどうにか高校だけは出たという人だった。そこにどれほどの引け目があったのかは知らないが、ときに高圧的な態度に出る父親に、決して口答えをしなかった。息子が勉強ができないのも、育て方のせいではなく、自分の血を受け継いだからだと感じていたのかもしれない。
確か、三年生くらいの頃だったと思う。母親がディスカウントショップで買ってきたキッチンタイマーが、一度使っただけで動かなくなった。父親は、「わけのわからんメーカーのものを買ってくるお前が悪いんだ。不良品だよ」と言って、それをその場でごみ箱に捨ててしまった。その様子を見ていた岳人は、胸が締めつけられるような痛みを感じた。自分がそう言われたような気がした。
中学に上がる頃には、まともに授業に出ることはなくなっていた。努力などとっくにばからしくなっていたし、読み書きのことで晒し者にならずにいるためにはそうする他なかったというのもある。先輩の不良グループがたむろする公園に出入りして、パシリのような真似を始めた。岳人のことを「ガク」や「ガッくん」と呼び始めたのは、その先輩たちだ。岳人自身、むしろそっちが本当の名だと感じるようになった。
そこまで来ると、転落ははやい。たばこや深夜徘徊で度々補導され、鑑別所行きは免れたものの、万引きや無免許運転でも捕まった。こんな出来損ないが自分の息子であるはずがないという態度の父親と、ただおろおろするばかりの母親。自宅にはだんだん帰らなくなり、仲間の家を泊まり歩くうちに、当たり前のように新宿の夜の街に飲み込まれていった――。
枕もとのスマホの振動で目が覚めた。いつの間にか眠ってしまっていたらしい。ぼうっとしたまま電話に出ると、藤竹の声がした。
「何だ、寝てたんですか」
「ああ……今何時すか」
「八時五分です。いや、もう六分か」
相変わらずだな、こいつは。その無意味な几帳面さにも、なぜか今はいらつかない。暗い泥沼から、整頓された明るい部屋をのぞき見たような、不思議な安堵感――。
「四限目だけでも来ないかと思って。話したいことがあるんですよ」
「退学届のこと?」
「それも含めて、です」
まだ頭が回らず、「行けたら行くよ」とだけ答えて、通話を終えた。
体を起こし、たばこに火をつける。最後の一本だった。とりあえずこれだけは買いに行かなければならない。スマホと財布だけ持って、部屋を出た。
大久保通りのコンビニでたばこを仕入れたあと、アパートには戻らずにぶらぶらと駅のほうへ歩く。何も食べていないことに気づいたからだが、立ち並ぶチェーンの飲食店を見ても食欲は湧いてこない。
それよりも、藤竹が言った「話したいこと」の中身が気になり出していた。山手線の高架をくぐり、結局そのまま学校に向かった。
四限目が終わるのを中庭で待ち、物理準備室を訪ねる。途中、廊下の窓から、サッカー部の連中がナイター照明のついたグラウンドに出ていくのが見えた。定時制にも一応部活動があって、九時から十時までの一時間、活動が許されている。
部屋の前まで着くと、ちょうど授業を終えて戻ってきた藤竹に中へ招き入れられた。奥の机には、昨夜も見た分厚い洋書が開いてある。
それを片付けようと藤竹が手に取ったとき、表紙に地球や土星の写真が見えた。天体が並ぶその構図に、幼い頃の記憶が呼び起こされる。
「それ、何の本?」つい訊いてしまった。
「比較惑星学の教科書ですよ。どうしてですか」
「いや」つっけんどんに答える。「ちっちゃい頃、似た表紙の図鑑を持ってたなと思って。『地球と宇宙』とか、そういうの」
「そういう分野が好きだったんですか」
「覚えてねーよ、んなこと。ただ、空はなんで青いのかとか、雲はどうして白いのかとか、虹はなんで七色なのかとか、母親にしつこく訊いてた子どもでさ。うちの母親、そういうの全然答えらんねーから、その図鑑を買ってきたわけよ」
本当はよく覚えている。持っている中で一番好きな図鑑だった。説明書きは結局読めずじまいだったが、美しい写真やわくわくするようなイラストをいつまでも飽かずに眺めていた。
何か言いたげな藤竹を見て急に気恥ずかしくなり、またこちらから問う。
「その本、授業の資料か何かに使うの」
「いえ、これは純粋に私の勉強です。学生時代、地球惑星科学という学問を専攻してましてね」
「教師になったら教えるだけで、もう勉強なんかしないもんだと思ってたよ」
「勉強しない教師から勉強しろと言われるのは、嫌でしょう」
「んなこと、どっちでもいいよ。言ったろ。勉強しに来てたわけじゃねえんだって」
「でも、高卒の資格が欲しかっただけでもない。ですよね?」
藤竹が真っすぐ見つめてくる。眼鏡の奥でわずかに細めた目は、すでにこちらの胸の内を見透かしているようにも、真剣に答えを求めているようにも見えた。
面倒くさいやつには違いないが、こいつならどんな相手も嗤ったりはしない。そんな確信が、さっきの出来事の燃えかすを吐き出させようと背中を叩いてくる。
「俺はここに――修行しに来てたんだよ」
「修行?」
「目の前に教科書を開いて、毎日きっちり四時間授業を受ける。昔みたいに途中で投げ出さないで、我慢して続けてみる。そしたら俺にも忍耐力とか集中力がついて、少しはまともに文章が読めるようになるんじゃないかって」
「なるほど」藤竹は腕組みをして言った。「でも、それは勉強とは違うんですか」
「ちげーよ。俺が読めるようになりたいのは、教科書じゃなくて、運転教本。高卒の資格より、免許がほしいんだよ」
「仕事のためにですか」
岳人はうなずいた。普通免許があれば、仕事の選択肢がぐっと増える。物流業界で経験を積んで、いつか大型や牽引の免許にも挑戦してみたい。そう考えるようになったのは、今の会社で最初にペアを組んだドライバーが、以前トレーラーの運転手をしていたときの話をよく聞かせてくれたからだ。
巨大なトレーラーを駆り、街から街、港から港へと日本中を巡る。車だけを相棒に、高速道路の片隅で一人食べ、一人眠る。人の目を気にする必要はなく、誰かにばかにされることもない。生まれて初めて、やってみたいと思えた仕事だった。
問題は、学科試験だ。問題文が読めるかどうかはともかく、とりあえず運転教本を一字一句丸暗記してみようと考えた。印刷物よりは自分の字のほうがまだ読みやすいので、知り合いからもらった古い教本を一文字ずつひらがなで書き写す作業を始めていた。それが、あのノートだった。
「でも」岳人は自嘲するように口もとを引きつらせた。「やっぱ無駄だったね。一年間ここに通い続けてみたけど、なーんも変わんね。教科書の文章を追っかけようとしても、すぐぐちゃぐちゃになって、文字がつかまらねえ」
「文字がつかまらない」藤竹は小さく繰り返し、机の上のタブレットを手に取った。何か手早く操作して、こちらに手渡す。画面いっぱいに文章がぎっしり表示されている。
「電子書籍の地学の教科書なんですが、どうですか」
「どうもこうもねーって」さすがにいらだった。「無理だっつってんだろ」
小さな文字が無秩序に目に飛び込んでくるので、見ているだけで酔いそうになる。読み取れたのは、〈マグマ〉という単語だけだ。
タブレットを荒っぽく突き返すと、藤竹は画面を数回タップし、「今度はどうです?」ともう一度差し出してくる。
あまりの驚きに、声も出なかった。
何が起きているかよくわからず、タブレットを持つ手が小刻みに震える。
〈マグマが地表に噴出したものを溶岩、地下に貫入して冷え固まったものを貫入岩体という。貫入岩体にはいくつか種類があり――〉
読める。読めるのだ。もちろん、行は歪んで見えるし、文字も大きくなったり小さくなったりする。しかし、目を凝らしてさえいれば、文章がきちんと追えた。
「――何だよ、これ……」喉を絞るようにしてどうにか言った。
「読めるんですね?」
画面を見つめたまま、二度うなずいた。「でも、なんで……あんた、何やったんだよ」
「文字を少し大きくして、行間も広げましたが」藤竹は平然と答える。「一番のポイントは、フォントを変えたことです。さっきのは一般的な教科書体。今見てもらっているのは少しばかり特殊なフォントでしてね。はねやはらいも含めて線の太さが均一で、濁点なども大きめ。より手書きに近いので、文字の形をとらえやすい。ディスレクシアのために開発されたフォントです」
「ディスレクシア……」初めて聞く言葉だった。
「読み書きに困難がある学習障害です。音と文字を結びつけて脳で処理する力が弱かったり、文字の形をうまく認識できなかったりするせいで、文章をスムーズに読めない。当然、書くことも苦手になる」
「俺が、そうだってのかよ」
「おそらく。ディスレクシアの中には、そういう特別なフォントに変えるだけで、劇的に読めるようになる人がいるそうですから」
そんなことで。そんな簡単なことで――。
「この学習障害の存在は、最近まであまり広く認知されていませんでした。親や教師にも気づかれず、本人もそうだと知らないまま大人になるケースも多い。理由の一つは、ディスレクシアの多くは文字情報のデコーディングが不得手なだけで、情報の中身はちゃんと理解できるからです。つまり、知能には問題がない」
「――バカじゃねえってことか、俺も」
「バカどころか、聡明な人だと私は思いますよ。いくら練習しても歌が下手な人、球技がだめな人がいるように、単に君は読むことや書くことが――」
藤竹の言葉は、耳を素通りした。体の芯が痺れるような悔しさとやるせなさが、行き場を求めて暴れ出す。
「不良品じゃねえか!」結局それは、口から勢いよくあふれ出た。「あいつの言ったとおり、やっぱり不良品じゃねえかよ!」
藤竹が、「柳田君」と言った気がした。目の前がぼやけてきたのは、涙のせいか。小学三年生に戻ったのか、俺は。
「でも――」震える声が止まらない。「俺は、バカじゃねえ。怠けてたわけでもねえ。それなのにあいつら、笑いやがって。よってたかって、バカにしやがって。俺は――」
うなだれて両の拳を握りしめ、嗚咽した。
*
「ちょっとお兄ちゃん」
ベルトコンベアの下流側にいるパートの女から、とげのある声が飛んできた。
「またボーッとして。さっきから何回言わせんの? こっちが追っつかないじゃない」
「――ああ」
我に返り、次々流れてくるペットボトルの中から一つつかんでキャップを外す。キャップやラベルがついたままであれば取り除き、汚れのひどいものははじく。減容機で圧縮処理をする前の選別作業だ。
このライン作業を命じられて、早一週間。配置換えの理由はもちろん、角刈りとの一件だ。向こうにも非があったことが認められ、懲戒処分などは免れた。工場内にある休憩室も収集班とは別なので、角刈りと顔を合わせることもない。
あの夜、物理準備室で一方的にわめき散らしたあと、藤竹の顔も見ずに部屋を出てきた。以来、学校へは一度も行っていない。学校も仕事も免許も、もうどうでもよかった。
失ったのは、何年だろう。十年――いや、もっとか。
本当なら、失わなくてよかった年月だ。両親がもっと真剣に向き合ってくれていたら。誰か一人でも教師が気づいてくれていたら。まともな中学生活を送り、普通に高校を出て、今頃は大学にだって通っていたかもしれない。
無心に手を動かそうとしても、恨みが絶え間なく胸に湧き上がり、悔しさに叫び出しそうになる。
怒りの矛先は、藤竹にも向いていた。当せんした宝くじを知らずに捨ててしまった人間に、あれは実は大当たりだったのだとわざわざ告げる。あいつのやったことは、それと同じだ。
そんな真似をして、俺が喜ぶと思ったのか。前向きになれるとでも思ったのか。こんな苦しい思いをするぐらいなら、知らないままでよかった――。
昼休みに入り、食事もとらずに敷地の隅でたばこをくゆらせていると、作業着のポケットでスマホが震えた。また藤竹からの着信だ。
三日ほど前から、今の時間と夜八時に必ずかけてくるのだが、ずっと無視している。とはいえあの執念深い男のことだ。放っておけばこれからも毎日かけてくるだろう。
仕方なく〈応答〉をタップして、いきなり言った。
「しつけーよ」
「よかった。間に合いました」藤竹の声は妙に明るい。
「ああ?」
「今日の四限目、出ませんか。『地学基礎』です」
「出ねえ」即座に吐き捨てた。「退学の手続きにも行かねえ。授業料払わなかったら、勝手にクビになるんだろ。それでいいから、もう電話もかけてくんな。うぜえんだよ毎日」
「まあそう言わずに。今夜はちょっとした実験をやろうと思ってるんですよ。柳田君の長年の疑問に答える実験です」
「はあ? 何言ってんだ、お前」
「で、お願いがあるんです」藤竹は一方的に続けた。「教室に、たばこを持ってきてくれませんか。まあ、常に持っているとは思いますが。待ってますよ」
その夜、八時過ぎに校門をくぐった。
四限目の授業に出ようということではない。仕事を終えてスマホを見ると、タイミングよくというか悪くというか、留守番電話に三浦からメッセージが入っていたのだ。
この一週間、何度かかかっていた三浦からの電話にも応じなかったので、しびれを切らしたらしい。〈なんでシカトすんのよ。今日の夜、また学校に突撃すっから、よろしく〉とおどけた調子で吹き込んであった。
あのけたたましい排気音は聞こえてこないが、まずはグラウンドをのぞいてみる。すると、前回とまったく同じ場所で、原付のシートにまたがった三浦と朴が藤竹と向かい合っていた。暗闇の中を近づいていくと、「なんかさあ」と三浦が声を高くした。
「あんた、ムカつくわ。その顔と眼鏡がムカつく。勉強勉強うるせーっての。こんな、誰もやる気のねえ学校でよ」
「『誰も』の中には、私も入っているんですか」
「定時制の教師なんて、みんな腰掛けっしょ? 知ってるよそれぐらい。だいたい、お前ら教師が、俺たちに何してくれたっつーの。ああ?」
腕組みをした藤竹は、口角だけを上げて言った。
「待っているんですよ。我々定時制の教員は、高校生活を一度あきらめた人たちが、それを取り戻す場所を用意して待っている。あとは生徒たち次第です」
「取り戻せるかボケ」三浦が嘲笑を浮かべ、三階以外は明かりの消えた校舎に向けてあごをしゃくる。「こんな暗い学校でよ。ジジイとヒッキーとヤンキーしかいねえ高校でよ」
「取り戻せますよ」藤竹はきっぱりと言った。「この学校には、何だってある。教室があり、教師がいて、クラスメイトがいる。ここは、取り戻せると思っている人たちが、来るところです」
その言葉に、岳人は足を止めた。取り戻せるのか、本当に――。
岳人の姿に気づいた藤竹が、わずかに目を細める。
「来ましたね。待ってましたよ」
岳人は何も答えずそばまで行き、原付の二人に顔を向けた。
「悪いけど、今日は帰ってくれ。俺たちこれから、実験やんだよ」
「あ?」さすがに三浦の目つきも険しくなる。「何なのガッくんまで」
すると後ろの朴が、「いいよ、もう行こう」と言った。三浦は舌打ちして藤竹をひとにらみし、勢いよく原付を発進させる。
去り際にまた朴が振り返り、真顔で「ヒムネ、ガッくん」と言った。その後ろ姿を見送りながら、藤竹が訊く。
「『ヒムネ』というのは、どういう意味ですか」
「『頑張れ』だよ、確か」
三浦たちのせいで、四限目の「地学基礎」は十分遅れて始まった。
教室に入ったのは一週間ぶりだったが、岳人の指定席、窓際の最後列はちゃんと空いていた。ただ一人、隣の麻衣だけが、「あ、生きてたんだ」と声をかけてきた。
藤竹は、高さが七、八十センチほどある縦長の段ボール箱を抱えてやってきて、黒板の前に置いた。実験に使う器具だろうか。
教卓についた藤竹は、「さて」と眼鏡を持ち上げて教科書を開く。
「今日から第三章『大気と海洋』に入っていきます。百四十ページですね」
最前列の長老が、人差し指を何度も舐めながら教科書をめくる。シャーペン一本持っていない岳人は、ただ机に頬づえをついていた。
「大気の話をする前に、一つ訊いてみましょう。小さな子どもがよくする質問ですよ」藤竹は天井を指差した。「空はなぜ青いのか? 正しく答えられる人はいますか」
岳人は驚いて体を起こし、藤竹に目を向けた。長年の疑問がどうのと言っていたのは、このことか。向こうは素知らぬ顔で、教室を見回している。
答える者は当然いない。せめて何か発言したいと思ったらしく、ママが口を開く。
「青とは限らないヨ。夕焼けは赤い」
「そうですね。実は、空が青いのも、夕焼けが赤いのも、雲が白いのも、すべて同じ原理で説明できるんです。ただしそれを理解するには、高校程度の物理の知識が必要です。ですから、子どもに訊かれて正しく答えられる大人は意外と少ない。
今日は、簡単な実験をしながらそれを説明してみましょう。今からこの教室に、ささやかな“青空”を作ります」
ママが声を立てて笑う。「できたらすごいネ、そんなこと」
藤竹は、黒板の前に立てた縦長の段ボール箱の頭を開き、上から中に腕を突っ込んだ。何かスイッチを入れたらしく、白い光が開いた口から上方に放たれる。
「箱に入っているのは、強力なスポットライトです。部屋を暗くしたいので、スマホを見るのはしばらく我慢してください」
藤竹はそう言って教室の照明をすべて落とした。スポットライトの白い光だけが、黒板の際をとおって天井を照らす。
「このライトを太陽だと思ってください。太陽の光は白色光ですが、プリズムなどを通すと、赤、橙、黄、緑、青というふうに連続的に色に分かれて見えることは知っていますか」
「虹の七色でしょう?」長老がさも常識とばかりに言った。
「そうです。太陽光には様々な波長の光が含まれていて、波長によって色が違う。波長が短いのが青色で、長いのが赤。すべて混ざっていると白い光になる。とりあえずそれだけ覚えておいてください。では――」
藤竹は首をのばし、後ろの席を見回した。
「誰か、たばこを吸う人――ああ、柳田君、たばこ持ってますよね? ちょっと前へ来て、手伝ってください」
なんだこいつ、わざとらしい。ため息をついて席を立ち、渋々教壇まで行った。無言でたばこを箱ごと渡すと、ライターも貸せと言う。
教室中が訝しげに見守る中、藤竹は平然とたばこを三本抜き取り、まとめて火をつける。
「おい、いいのかよ」さすがに驚いて口にした。
「大丈夫です。火災報知器には覆いをしておきましたから」
そういう問題じゃねえと言おうとしたが、藤竹はすたすたとスポットライトに近づき、その直上にたばこの束を掲げた。光の帯の中に、煙が立ちのぼる。
「どうです? 煙が青く見えませんか?」
「ほんとだ。結構青いネ」ママが感心して声を上げた。言われてみれば、光の当たった部分が青みがかって見える。煙の薄いところは、とくにそうだ。
「太陽光が大気中で、空気の分子などの微粒子にぶつかると、四方八方に散乱を起こします。レイリー散乱という現象です。その際、波長の短い光は空気分子にぶつかりやすく、波長の長い光は通り抜けやすい。つまり、太陽光のうち波長の短い青い光がもっとも強く散乱されて空全体に広がり、たとえ太陽に背を向けていても、我々の目に飛び込んでくる。それが、空が青い理由です。
たばこの煙の粒子も、レイリー散乱を引き起こすほど小さい。だから白い光を当てると、青色がより強く散乱されて見えるわけです」
藤竹は次に、火をつけたたばこの束から一本取り、口にくわえた。煙を深く吸い込んだかと思うと、すぐに激しくむせる。
「いかんよ、慣れんことしちゃあ」長老がたしなめるように言った。
「やっぱり無理ですね。柳田君」咳込みながら、藤竹は別の一本をこちらに差し出す。「すみませんが、煙をしばらく肺に溜めてもらえませんか。できれば一分間」
「一分?」岳人は眉根を寄せて受け取った。何がしたいのかまるでわからない。口にくわえていつものように吸い、途中で息をとめる。
一分待つのは思ったより辛かった。苦しいと目で訴えるが、藤竹は腕時計を見つめたままだ。しばらく耐えていると、ようやく顔を上げた。
「はい、光の当たっているところに吐き出して。ゆっくり、そっとですよ」
岳人は口をすぼめ、静かに煙を吐く。
「今度は煙が真っ白でしょう。雲のように」
藤竹がそれを示して言った。確かに、さっきの煙とは明らかに違う。何年もたばこを吸っているのに、気づいていなかった。
「煙の粒が、柳田君の肺の中で水蒸気を含んで、ふくらんだんです。粒子がある程度大きくなると、すべての波長の光を同程度に散乱させます。だから、出てくる光は白くなる。ミー散乱という現象です。雲を構成する水滴や氷の結晶は粒が大きいので、ミー散乱が起きます。それが、雲が白く見える理由」
四限目が終わるとすぐ、中庭へたばこを吸いに出た。
先客の四年生が一本吸って去っていき、岳人一人になる。壁にもたれてしゃがみ込み、校舎の間にのぞく夜空を見上げた。星が二つだけ輝いている。
普通の高校に、行きたかった。本物の青空がある高校に。
ひと口吸った煙を、ため息にして吐き出す。それはやはり、雲のように白かった。
闇の中から、音もなく藤竹が現れた。隣へ来て言う。
「たばこ、今度買って返しますから」
「いいよ、別に」
「全日制の高校では、なかなかやりにくい実験でした」
「だろうね」灰を地面に落とし、口の端を歪める。「でもさ、あれのどこが“青空”なんだよ。ショボすぎる」
「空が青い理由、少しはわかりましたか」
「あんまり」
「まあ、自動的にはわかりませんよ」
藤竹はこちらに顔を向けずに、「柳田君」と続けた。
「君は、学校を辞めてはいけない。スタートですよ。ここからが」
何も答えずにもうひと口吸ってから、言った。
「あんた、さっき三浦に、『この学校には、何だってある』って言ったよな」
「言いました。教室、図書室、体育館。使える設備は全日制と同じです。文化祭も体育祭も、部活だってある」
「でもさ――」
青空は、ねえよ。
そう口にする代わりに、視線を上にやった。たばこの先から立ちのぼる煙が、そばに立っている外灯の光に透けて、うっすら青く見えた。
「俺がやりたい部活がねーよ」
「私もなんです」藤竹が真顔で言う。「だから、作ろうと思って。科学部」
「科学部?」露骨に顔をしかめてみせる。「うわ、だりい部活」
「一緒にやりませんか」
「冗談」鼻で笑った。
「知ってますか」藤竹が眼鏡の奥の目を光らせる。「火星の夕焼けは、青いんですよ」
「え、マジ?」思わず反応してしまった。
藤竹が滔々と理由を語り出す。半分もわからないその説明を聞いているうちに、たばこはフィルターのところまで燃え尽きていた。
額賀澪さんによる書評が公開中です。下記バナーよりご覧ください!