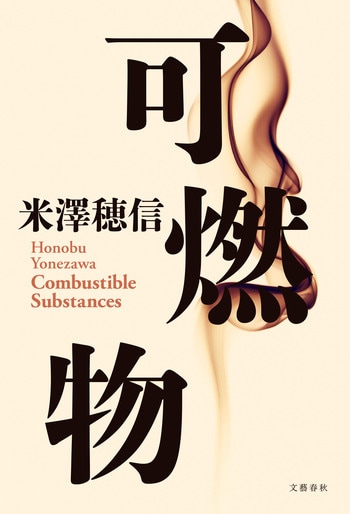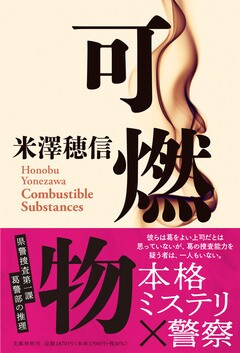『可燃物』が『このミス』「ミステリが読みたい!」「週刊文春ミステリーベスト10」の各ランキングで1位を獲得。3冠を記念して、刊行記念ネタバレOKイベントから、ネタバレ部分をカットして特別公開。米澤さんを長年担当し、ミステリ大好きなオール讀物編集長が、刑事が名探偵役になることで生まれる謎解きの新たな魅力と作品の源流について伺いました。

◆◆◆
――本書には「オール讀物」掲載の、葛(かつら)警部が捜査する短編5作が収録されています。それぞれ早い段階で謎が提示され、読者も推理できる趣向になっていますが……。
米澤 お集まりの方に最初にお伺いしたいのですが、5作の中で「1作は正解した」という方は挙手をお願いします。おお、結構手が挙がりましたね。2作では? なるほど。……3作以上的中は私の心が削れるので、聞かないでおきます(笑)。ミステリは、読者が解こうと思って隅々まで追えば真相に至れるのが“良問”だと考えて書いているので、いま挙手して下さったくらいの正解率なら、フェアネスが守れていたかと安心しました。
――帯に〈本格ミステリ×警察〉とありますが、実は米澤さん、刑事が探偵役をつとめるシリーズは初ですよね。この葛警部の造型を考えるとき、エッセイ・書評集『米澤屋書店』(文藝春秋)がヒントになるのでは、と感じています。例えば同書のp278~279、ロス・マクドナルド『さむけ』を紹介する一文に、〈本作において、主人公自身はほぼまったく語られません。自宅すら出てこないんじゃなかったでしたっけ。ですが、アーチャーを無個性な、つまらない人物だと思う読者は皆無でしょう。魅力的なキャラクターとはなにか、と考え込んでしまいます。〉とありますが、これ、そのまま葛警部に当てはまるのではありませんか? 他にも『米澤屋書店』では警察ミステリの名作に言及されています。『可燃物』執筆にあたってヒントにされた古典などはあるのでしょうか。
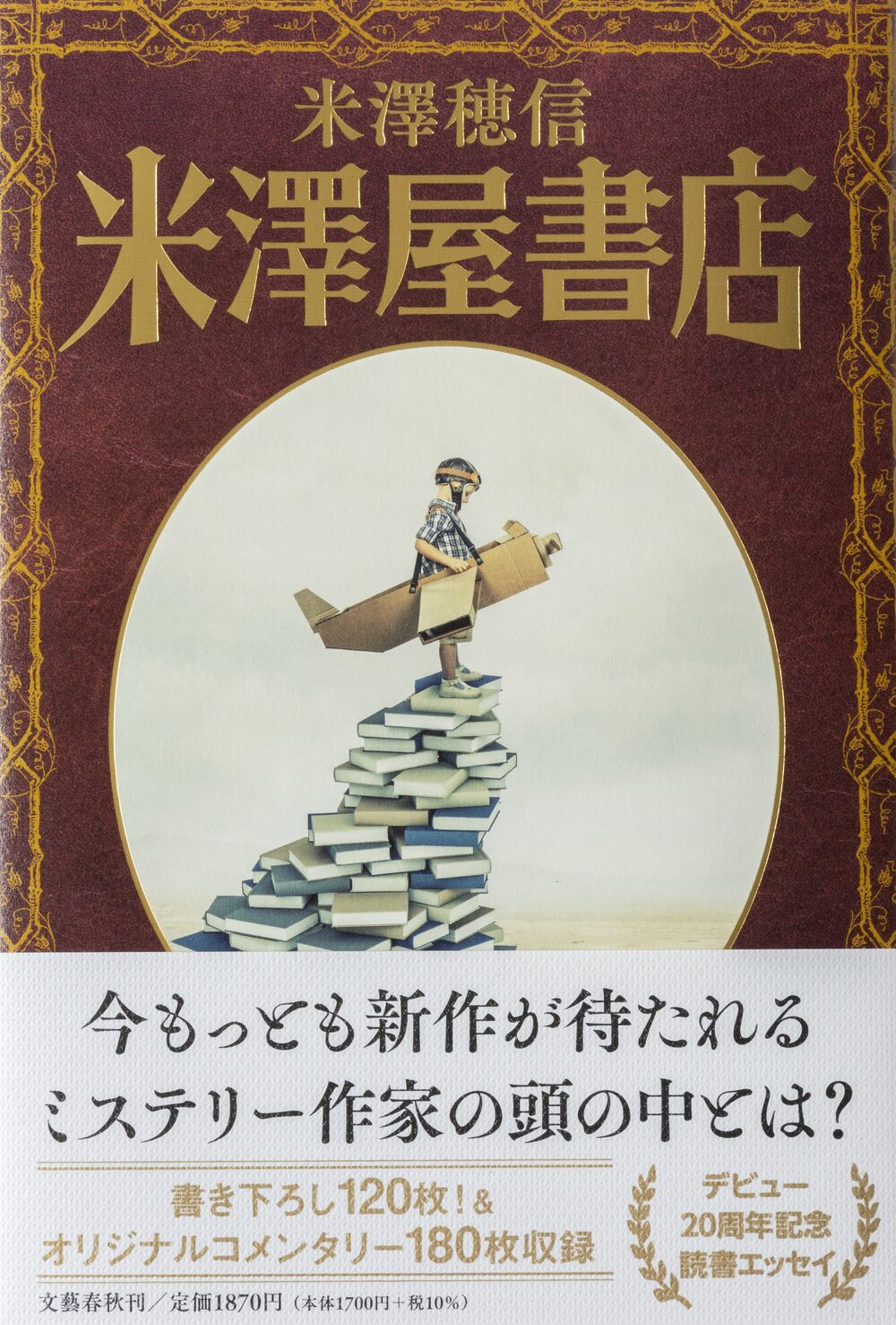
米澤 ヒラリー・ウォーの『失踪当時の服装は』や『事件当夜は雨』で描かれる警察署長しかり、コリン・デクスターのモース警部しかり、警察ミステリには黙々と職務に邁進する刑事というキャラクターの系譜があると思うんです。私の中の源流はF・W・クロフツの、たとえば『樽』だと思うのですが。この、“名探偵としての警察官”の系譜に属するものであれば、私も書けると考えたのが葛警部です。
彼の外見や心理描写は極力抑え、仕事だから謎を解くというシンプルな作りにしています。しかし、ある程度の大人であれば、仕事の進め方に人格が表れるものです。例えば、被疑者から情報を引き出すためなら強い言葉も使うけれど、逮捕された父親を心配して訪ねてきた娘には労をいとわず対応する。事情聴取のやり方ひとつとっても、どういう人間であるかが分かる。葛警部のキャラクターは、すべて仕事を通じて伝わるように意図しています。
――唯一、生活感ある描写といえば、捜査本部に詰めている葛が菓子パンとカフェオレを摂取するシーンですが。
米澤 これは、ホームズを意識していますね。満腹は頭の回転を妨げるという思考機械的な生活態度ゆえですが、とはいえ脳の活動にはブドウ糖が必要ですから糖分摂取のために菓子パンを食べる。じゃあなんでコーヒーではなくカフェオレかというと、ブラックでは胃に悪いからせめて牛乳入りを選んでいる(笑)。
――こういうキャラ立ての方法もあるんだなと思いました。
米澤 輪郭を描かない、朦朧体のような手法は意識していたかもしれません。
凶器当てと偽の手掛かり
――そんな葛警部の初登場作は巻頭の「崖の下」。遭難したスノボ仲間2人のうち1人が刺殺体で発見され、犯人は一緒に救助されたもう1人としか考えられないのに、雪山の孤立した現場で凶器となるものが見つからず……という“凶器当て”の1編です。
原稿を途中まで拝見して、雪山、崖ときた時に、まさかとは思うけどアレが凶器だったら米澤さんに一言申さねば、と(笑)、ドキドキ読み進めたのを覚えています。
米澤 いわゆる“御相談”というやつですね(笑)。その反応はしてやったりで、「アレを使ったのでは?」と思わせるのは典型的なレッドへリングです。
――本格ミステリ用語ですね。
米澤 レッドへリングとは燻製ニシンのことで、強烈な臭いで猟犬の鼻をも惑わしてしまう。転じて、推理を誤った方向に誘導する偽の手掛かりを指します。もちろん、偽の手掛かりを出しっぱなしではいけないわけで、「崖の下」でも作中で提示した情報を引き合わせるとアレの可能性は排除できるように書いています。
――他にも、真相が解ってから再読すると「あっ!」と声の出る一文があります。
米澤 ミステリ的な遊びということで……。ふざけるわけでなく、ユーモアを直接的なユーモアシーン以外の形で潜ませるのは好きです。
凶器が焦点になるのは、どうやって犯行がなされたかを問う、つまりハウダニットの趣向です。凶器当てとして古典的な作品に松本清張の、タイトルもずばり「凶器」(『黒い画集』所収)があります。この中では監察医による鑑定書の内容が詳述されているんです。凶器特定の手掛かりが読者に明示され、ゆえに真相にも説得力がある。「崖の下」で監察医が所見を克明に伝える場面は、清張が源流にあったかもしれません。
人間の観察力は当てにならない
――続いて「ねむけ」。先ほど申し上げたロス・マクの『さむけ』のパロディかと思ったら全然違って、読後にはこれしかないと思えるタイトルです。
深夜の交通事故でどちらの信号が赤だったのかを、葛が目撃証言を集めて検証する。合致する証言が多数出て、簡単に解決できてラッキー……と物語が進むのかと思いきや、葛はそういう判断をしませんね。
米澤 葛が上司の新戸部(にとべ)から、逮捕に踏み切らない理由を訊かれ、深夜3時に4人も目撃者がいて、しかもその内容が全員一致したからだと答えた瞬間、新戸部も「そうか」と納得するシーンは、自分でも気に入っています。警察官なら直感的に怪しいと思う事態だと描いているわけです。
証言者が多数いるからこそ疑うべき、というロジックの源流は、ジョン・ディクスン・カー『緑のカプセルの謎』だと思っています。犯罪研究家が“人間の観察力がいかに当てにならないか”を証明するために寸劇を行うのですが、3人の人物に劇中で見たものの詳細を問うと全員が食い違う。これがとても印象的でした。ここから一歩進んで、合致には何らかの作為があると疑う葛の思考に繋がっています。
――新戸部捜査第一課長、さほど出番が多くはないけれど、存在感のあるキャラですね。
米澤 部下にお追従してほしいのに、誰も応えてくれない。なぜなら新戸部本人がご機嫌取りより捜査能力重視で部下を選んでいるから、という自己矛盾の人です(笑)。
犯人逮捕の後が本番!
――収録作中でも屈指の複雑な構造を持つのが「命の恩」です。
米澤 中盤で犯人が逮捕されますが、実はそこからが本番ですね。
――人目につく場所に捨てられたバラバラ死体。犯人は隠し易くするために死体を小さく切断したはずなのに、すぐ発見されるような捨て方をしたのはなぜか、というホワイダニットで物語は始まります。
米澤 一見無駄に思える行動の理由を問う出発点ですが、その謎、ホワイは最終的にはもっとミクロな謎に移行していく。物語の進行につれて謎の焦点が変わるように作ったつもりです。
――ある時点で第1ホワイダニットが転調し、第2ホワイダニットへとさらなる謎が発生する贅沢なミステリです。
米澤 なぜ、を問うミステリは大きく2つに分類できると思います。犯行の動機を問う、いわば王道を大ホワイダニットとするなら(次に収録した「可燃物」がこのタイプ)、動機そのものではないけれど犯人の非合理な行為の理由を追求することが解決につながる、小ホワイダニットとでも呼ぶべきものもある。例えば「犯人はなぜ現場でピザを食べたのか?」(津原泰水「冷えたピザはいかが」『ルピナス探偵団の当惑』所収)とか、そういう種類の謎です。
本格ミステリ的な「なぜ?」の極めつけは、何と言っても、綾辻行人『迷路館の殺人』、第五章の題にもなっている「首切りの論理」でしょう。なぜ、首を切ったのか。この小ホワイダニットを解くことで、一気に全体の構造が見えてくる。「命の恩」はこうした二段構えの作品を目指しました。
――重層構造の謎解きも素晴らしいですが、人物描写も読みどころです。
葛自身は無口ですが、読者が知る登場人物の言動というのは実は葛の目を通して結像したものです。おのずと、その描写にも葛が思ったこと、内面が投影されているのですよね。だからつい、人間関係を深読みしてしまう。
米澤 詳しくは言えませんが、それもレッドへリングなんです。ある人物が言っていることは、あくまでも当人の認知で事実とは限らない。そのズレを利用して……。
――まんまと引っかかりました。
ホワイダニットの面白さと難しさ
米澤 前述の通り、「可燃物」は真正面から犯行の「なぜ」を問うホワイダニットです。逆説のミステリでもありますね。逆説といえばブラウン神父のG・K・チェスタトンが有名ですが、私は泡坂妻夫こそ逆説の大家だと思っていて、自分はそちらに学んだつもりでいます。
――放火が相次ぎますが、葛たちが見張りを始めた途端にぴたりと止む。放火犯はなぜ火をつけ、なぜ火をつけるのを止めたのか? ホワイダニットは人気の趣向ですし作例も大変に多い。しかし、あらゆる謎の中でも書くのが一番難しいものではないかとも思うのですが、いかがでしょう。
米澤 大きなくくりで言うならばフーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット、ミステリの謎はこの3つが代表例です。フーダニットは必ず登場人物の中に犯人がいなくてはいけないし、ハウダニットは犯行周辺に存在した物や事象を全部書かなければいけない。前二者の制約の多さに比して、ホワイダニットならば、作者も読者も人間の心を想像することはできる、つまり可能性は無限なわけです。だから、奇妙な動機やいわゆる“奇妙な味”とも相性がいい。「まさかそんな犯人がいたなんて」「まさかそんな凶器があったなんて」はアンフェアな感を与えがちですが、「まさかそんなことを考えていたなんて」は、書き方次第でとても面白いミステリになる。それだけに“何でもあり”にならないよう、フェアネスの担保に苦心するんです。
――人の心を問うものですからね。真相に至った時に誰もが腑に落ちるように作るのはやはり相当ハードルが高い。
米澤 あまりに異様な動機に呆然として、「なんだか凄いものを読んだな」という気持ちだけが残ることはあります。そういう小説も大好きですし、傑作もいくつも思いつきます。ただ、本格ミステリという、読者と作者の間のある種の決まり事の上に成り立つ勝負としてフェアであるか否かというと、また別の話になるのでしょう。
そのギリギリのラインを攻めている傑作が、連城三紀彦『戻り川心中』ではないかと思います。作中に描かれる心理は異常なものが多いけど、同じ人間として「ああ、たしかに人間には、そう考えかねない一面がある」と思わされる納得感がある。そこが、素晴らしいです。
――動機については「可燃物」に〈葛は動機を重視しない〉とありますね。動機とは突き詰めれば欲望だが、説明のつかない欲望というものも存在し、それは人智を尽くしても予測できない。〈予測できないものを頼りに捜査をすれば迷路に迷い込む〉、だから葛は動機を重んじない、というこれまた明快な論理です。
米澤 これについては、平石貴樹『だれもがポオを愛していた』の影響もありそうですね。探偵役の更科ニッキが堂々と動機無視を謳い、謎の本質は動機ではないということが物語でもすごくフィーチャーされていて、とても面白く思ったのを覚えています。あと、これは今気づいたのですが、〈迷路に迷い込む〉という一節はJ・L・ボルヘス「死とコンパス」(『伝奇集』所収)にある、「おまえの迷路には三本、余計な線がある」というフレーズのイメージから来たのかもしれません。一本の直線でできているギリシアの迷路の中でも多くの哲学者が道に迷った。推理に余計な線があっては刑事が迷うのは当然だ、というくだりですね。
“日常の謎”からの流れ
――「本物か」は、ラストを飾るにふさわしいサプライズ度の高い1編だと思います。
米澤 一番トリッキーな作りのミステリですね。ここまでの4編は変形を含みつつも何が謎であるか、何を追求すべきかという、いわゆる設問を明確にしていました。「本物か」に限っては設問が伏せられ、読者が補助線を引かないと真相に辿り着けない構造になっています。
――読者が“何を考えなくてはいけないか”が最初のうちは提示されないということですか。
米澤 そうです。目の前で次々と出来事が起きるが、一見して読者への問題、謎の提示と思えるものはない。では、葛は何を問題にしているのか……をトレースして補助線を引くと真相が見えてきます。
設問を伏せるのはアンフェアではないかという迷いもありましたが、5編目であるからこそ許される作り方だと考えて自分の中でこのプロットを通しました。
――凶器当て、ミッシングリンク、大小のホワイダニット、と謎の所在や問いを明確にした4編を経て、最後は自分で問いを立てる、そういうスタイルになっているということですね。
米澤 葛はこれまで何をゴールに捜査をしてきたか、がヒントかもしれません。
――ファミリーレストランで立てこもり事件が発生し、犯人の手に拳銃のような物が見えたことで現場に緊張が走る。臨場した葛は逃げて来た客や店員の証言を集めていきます。
米澤 葛が真相に近づいていく手段そのものは、“日常の謎”的なんですよね。厨房スタッフたちから聞き取ったパスタの茹で時間から推論を立てたり。
日常の謎といえばの北村薫先生に「六月の花嫁」(『夜の蝉』所収)という短編があります。大学生たちが遊びに行った別荘でいくつかの他愛ない物がなくなっていく。消えた物に法則はあるのか、次になくなる物は何かという会話をしながら、最後の最後で、別荘で起きていたことは何だったのかという問いがいきなり投げかけられる。今日のイベントのために自分の本棚を見ていてふと、「問いがスイングされる小説を確かに自分は読んできたのだな」と思い、「六月の花嫁」の鮮やかさにも改めて気付きました。
――「本物か」の源流に「六月の花嫁」があるというのは意外ですが、伺うと納得ですね。そして5編目は、読後感の点でも他と少し違うように思います。
米澤 警察が出てきているということは事件が起きていて、ということは被害が発生している。解決したからといって被害は取り返しがつかない。後味としてはどうしたって苦い物が残るし、それは警察という仕事の宿命だと思っています。その上で、1冊の小説を読んできて、最後の話くらいは何か1つくらい、少しは「まあ、これについては良かったね」と読者が思えるところがあればいいなと。
名探偵警察小説という系譜
――各編について伺うほど、やはり米澤さんは“ミステリである”ということを強く意識して葛警部シリーズを書いておられるのが分かります。
米澤 もともと、特別な理由がなくても事件解決に携われる探偵役とは何かと考え、あ、警察なら「仕事ですから」で済む! という発想ですので、やはり謎解きのスタイルとフェアネスは重んじていますね。
――元来、警察小説というと概ね3つのタイプがあると思うんです。横山秀夫さんがお書きになるような、警察組織そのものに焦点を当て、そこから生まれる謎を描くもの。大沢在昌さんの「新宿鮫」のような、組織のはぐれ者が己の才覚だけで強敵と渡り合う一匹狼型ハードボイルド。そして、翻訳小説に多いのが「87分署」シリーズをはじめとする群像劇スタイル。色んな刑事が出てきて、彼らが別々の事件を追っていると思ったら終盤で1つの大事件に集約していくという。
米澤 たまに「結局これは関係なかった」みたいな線が出てくるのも面白いんですよね。
――葛警部は3つのどれにも分類されませんね。
米澤 先に、葛はヒラリー・ウォーの警察署長的なキャラクターとして考えたとお話ししましたが、1950年代アメリカの警察より、現代日本の警察はもっと組織化されているので、葛も組織から完全には逃れられない。結果として、組織に焦点を当ててはいないが、ウォーのコピーでもない、オリジナルなものになった気がしています。名探偵警察小説の系譜として葛には活躍してほしいですね。
(2023年8月19日 文藝春秋にて)
米澤穂信(よねざわ・ほのぶ)
1978年岐阜県生まれ。2011年『折れた竜骨』で日本推理作家協会賞、14年『満願』で山本周五郎賞、21年『黒牢城』で山田風太郎賞、翌年同作で直木賞、本格ミステリ大賞を受賞。近著に『栞と嘘の季節』など。