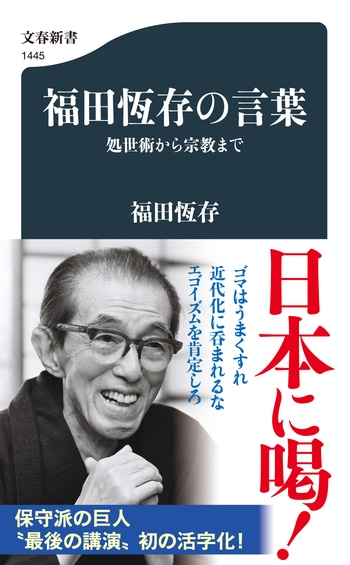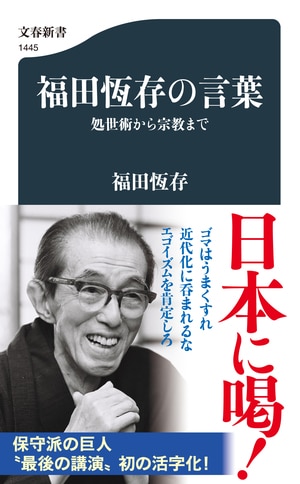
本書に収められた福田恆存の講演は、昭和五十一年(一九七六年)の三月から、翌昭和五十二年(一九七七年)の三月までの一年のあいだになされたものである。年齢で言うと、六十三歳から六十四歳の福田恆存による講演ということになるが、脳梗塞で福田が倒れるのが、その四年後の昭和五十六年(一九八一年)であることを踏まえると、記録として残されたものとしては、これが“福田恆存、最後の講演録”だと考えてよさそうである。
講演がなされたいきさつについては、福田逸氏の「あとがき」を読んでいただくとして、さすがに一年間にわたってなされた講演なだけあって、話題の幅が広く、福田恆存を知らない読者にとっては、大筋が掴みにくい話になっている可能性がある──当日の観客の顔を見て、話を即興で繰り広げるところに講演の醍醐味はあるのだが──。そこで、「まえがき」に求められるのは、予め講演の大筋を整理し、それを話の迷子にならぬための地図として読者に提示しておくことだろう。少しでも、講演の見晴らしがよくなることを願って、以下、話の要点を記しておく。
まず、福田は、「処世術はいいものである、処世術がうまくなくちゃいけない」と、社会のなかでうまくやっていくことを素直に肯定する。それどころか、エゴイズムを否定するような道徳(キレイゴト)を全て排して、ゴマは上手にするべきだと言うのである。もしそれが鼻につくようなら、それはゴマをする技術が拙いだけで、処世術自体が悪いわけではない。福田は、生き方の問題を、まず精神論から切り離し、それを“自分の欲望”に沿った技術の問題に還元するのだ。
しかし、そこから翻って福田は、近代化と共に、次第に自分のエゴを素直に認められなくなってしまった日本人、あるいは、処世術を見失ってしまった日本人の現実に話題を移していく。というのも、近代日本人は、近代(西洋化)に適応すれば日本の現実に適応できず、日本の現実に適応すれば近代(西洋化)に適応できないといった分裂的現実を生きねばならなかったからである。かくして、適応異常の症状を呈することになった日本人は、その不安から逃れるために、文学なら文学、演劇なら演劇、政治なら政治と、本来なら繋がり合っていたはずの文化を切り分け、その区切られた枠組み(制度)の中に閉じこもろうとする傾向を見せはじめる。が、そうなると日本人は、ますますハエ取り紙に捕まったハエよろしく、処世の柔軟性を見失い、不自由になってしまうことになるだろう。
そこで福田は、改めて「個人の確立」や「精神の近代化」を言うのだが、ここで言われる「近代化」の意味合いは、いかにも福田恆存的である。それは“近代化に吞まれない”ことも含めて、全ての水平的な価値(場)を相対化できる自己の強さを意味しているのだ。
そして最後に、だからこそ、弱いはずの「個人」を強く支える日本人の「宗教」が語られなければならなかったのである。が、それは、もちろん処世から切り離された宗教ではない。処世の果てに見出されるべき宗教である。
最後に、この処世と宗教との関係を一言で纏めた福田の言葉を引いておきたい。
福田は言う、「人はパンのみにて生きるものではないと悟ればよいのである。さうしないと、パンさへ手に入らなくなる」と。そして、宗教を喪った戦後日本人に対して、さらに、こう警告を発するのだ、「別に脅迫する気ではないが、自由、平等、民主主義、平和といふ徳目が戦後の日本人にやうやく根づいたなどと夢を見てゐると、とんでもないことになる」(「消費ブームを論ず」、『保守とは何か』文春学藝ライブラリー所収)と。
昨今のコロナ騒動を見れば分かる通り、すでに「とんでもないこと」は起こりはじめているかに思えるが、実際、日本人の処世下手と、宗教音痴と、軽薄な徳目好き(偽善への鈍感)は相変わらずである。福田恆存の言葉が古くならないわけである。
「はじめに 古びない警句」より