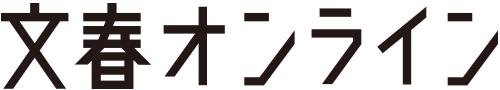〈試合中トスが上がってくると、自分が消える〉〈身体が反射だけで自動的に動いていくこの感覚は、いつだって気持ちよかった〉
春高バレー予選。明鹿高校バレーボール部の宮下景(けい)は躍動していた。そのスパイクに相手選手は追いつけない。エースの尾久遊晴(ゆうせい)らチームメイトの意気込みもさかん、明鹿は勝ち進む。いまなら全国も夢じゃない――。だが、準々決勝の数日前、景は下校中、学校のフェンスを乗り越えようとする女子生徒、真島綾に驚き、自転車ごと転倒。右足を痛め、翌日の練習試合で、足首の靱帯を断裂してしまう……。
坪田侑也さんの小説『八秒で跳べ』は、そんな主人公の“挫折”から、幕を開ける。
「王道のスポーツ小説のように試合の白熱の攻防を描くのも魅力ですが、動きに切れ目のないバレーではちょっと難しい。漫画『ハイキュー!!』のような偉大な作品もありますので、僕は違ったアプローチで、部活としてバレーに打ち込む高校生たちの姿を描きました」
スタメンを外れた景。かといって悔しがるでも、泣くわけでもない。自分と交替した北村がコートにいることには違和感を抱きつつ、どこか冷めている。引退せずにバレーを続ける先輩の〈バレーに高校生活捧げすぎだろ〉との自嘲に共感するほど。坪田さん自身、中高と大学生となった現在まで、7年間バレーボールに打ち込んできた経験を踏まえて、景の感情の機微が描き出される。
「たとえば、バレーは好きだけど、練習はだるい。高2になれば進学も考えねばならず、部活にばかり集中していられない。高3の夏には引退というタイムリミットがあって、それまでどれだけ頑張れるか。様々な感情が曖昧に揺れ動くものではないかと思います」
自分にとってバレーボールとは何か。自問し悩む景に、思いもよらぬ気づきを与えたのは、真島だった。バレーボールは〈変というか、異質な感じ〉だ、と。
「誰かのミスがチーム全体の失点に直結する。バレー特有の論理で、外から見れば歪なものかもしれない。僕も不思議でした。さらに部活という特殊な環境も含め自覚的に描こうと思いました。そのためにも、部員たちを単にポジションを埋めるだけの“記号”にしたくなかった。『自分に責任があるんじゃないか』と景に熱く詰め寄る部員はもちろん、強豪校へ進学しなかったエース、バレーをやめるきっかけを探していた部員……。そうした1人1人のバレーへの思いや背景を深めると部活がより立体的になり、景との繋がりも深く見えてきました」

他校に出張った合宿。先輩たちのユニフォームを洗いに行ったコインランドリー。顧問の先生の言葉。何気ない日常。自ら記憶を呼び起こすうちに、リアルな青春小説が紡がれていった。
前作『探偵はぼっちじゃない』でデビューしたのが高校一年のとき。進学を挟んで、いま医学部3年生。5年ぶりの新作となった。「本にできるとお話をいただいたときは、嬉しいだけじゃなく、本当に安心した」と振り返る。
「新人賞をいただいたあと、書きたい題材はあるのに、自分の小説のスタイルがわからず、何が書けるんだろうと苦悩するばかりで。そんな自分の姿は、漫画家を目指す真島にも投影されています。彼女が言う『深海にいる気分になる』とは、本人は没頭して心地良いことでも、傍から見れば自分を見失っているようで不安な様子。何かに打ち込む楽しさと呪い。その間の揺らぎを楽しんでいただければ」
つぼたゆうや/2002年東京都生まれ。18年、15歳の時に書いた『探偵はぼっちじゃない』で、第21回ボイルドエッグズ新人賞を当時史上最年少で受賞(翌年、KADOKAWAより出版)。中学、高校時代はバレー部に所属。現在は慶應義塾大学医学部在学中。