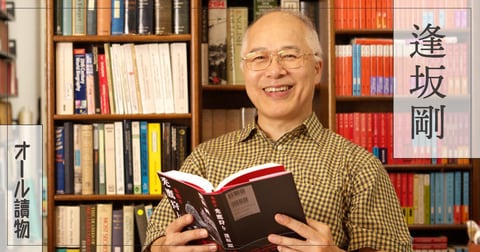本書の解説を書くことになり、あらためて逢坂剛が「火付盗賊改方・長谷川平蔵」シリーズを執筆するまでの道程を考えてみた。すると太い創作の流れが浮かび上がってきた。もちろん現時点から振り返ったからこそ、そう感じるのかもしれない。だが道程を検証することで、作品の理解が深まることだろう。そこでまず、作者の経歴から始めたい。
逢坂剛は、一九四三年、東京に生まれる。中央大学法学部卒。博報堂に入社して働きながら、一九八〇年、スペインを舞台にした「屠殺者よグラナダに死ね」で第十九回オール讀物推理小説新人賞を受賞(後に「暗殺者グラナダに死す」と改題)。十代の頃から独学でクラシック・ギターを弾いていたが、フラメンコ・ギターのレコードを聞き、衝撃を受ける。そこからスペインに興味を持つようになった。一九八七年に第九十六回直木賞及び第四十回日本推理作家協会賞を受賞した『カディスの赤い星』を筆頭に、さまざまな形でスペインと、その近代の歴史を扱った作品を発表する。
ただし作者は非常に多趣味で、他にも西部劇・古書・将棋など、愛好しているものがたくさんある。小説も同様であり、多彩なジャンルを手掛けているのだ。その中に時代小説もある。スペインの近代史や、アメリカの時代劇ともいうべき西部劇を熱愛するところに、作者の歴史指向が早い段階からあったと思えなくもない。なお後に作者は、西部を舞台にした小説を幾つか執筆している。
そんな作者の初めての時代小説が、「週刊新潮」一九九四年五月二十六日号に掲載された短篇「いその浪まくら」である。相撲を題材にした好篇だ。その後、やはり「週刊新潮」に、「相撲稲荷」「五輪くだき」を発表。すべて戦前から挿絵家として活躍していた父親の中一弥がイラストを担当した。極めて珍しい父子のコラボレーション作品となっているのだ。
さて、中一弥の名前が出たことで、作者と池波正太郎の『鬼平犯科帳』との繋がりが見えてくる。というのも「オール讀物」に掲載された『鬼平犯科帳』のイラストを担当していたのが中一弥だったのだ。本シリーズ第二弾『平蔵狩り』の文庫の巻末に掲載されている、作者と諸田玲子の対談の中で、家に「オール讀物」が届くたびに『鬼平犯科帳』を読んでいたが、
「そのときは作家になろうなんておもってもいなかったから、何気なく読んで、スラスラ読めるけど、後には何も残らないなあ、なんて思ってましたよ。重くないからスラスラ読める。無邪気な読者でしたね」
といい、池波の文体に関心を持つようになったのは、作家になってからだと語っている。では作者は、いつ頃から時代小説の執筆を考えるようになったのか。書店チェーンの有隣堂が発行している「有隣」四七〇号に掲載された座談会を読むと、五十歳前後であるようだ。また古本屋で、蝦夷地の探検で知られる近藤重蔵のことを立ち読みし、深い関心を抱くようになる。その結果、二〇〇一年の『重蔵始末』から始まる、シリーズが生れたのである。連作スタイルで重蔵の生涯を描き切った「重蔵始末」シリーズは、時代小説でありながら、歴史小説の部分も持ち合わせている。このハイブリッド感が、大きな特徴だろう。
さらに第三巻まで、重蔵が火付盗賊改方だった時代を扱っていることを、注目ポイントとして挙げておきたい。いうまでもなく重蔵が火付盗賊改方の一員だったことは事実だが、『重蔵始末』を最初に読んだとき、これは逢坂版『鬼平犯科帳』だと思ったものである。
そんな作者が「火付盗賊改方・長谷川平蔵」シリーズを開始したのは、必然というべきか。二〇一二年三月刊行の『平蔵の首』を皮切りに、『平蔵狩り』『闇の平蔵』、そして本書『平蔵の母』と、現在までに四冊が刊行されている。二〇一五年に『平蔵狩り』で第四十九回吉川英治文学賞を受賞していることからも分かるように、作品の評価は高い。だが作者には、並々ならぬ苦労があったことだろう。
そもそも本シリーズを手にする多くの読者は、大なり小なり、池波の『鬼平犯科帳』を意識しているはずだ。「人間は、よいことをしながら悪いことをし、悪いことをしながらよいことをしている」という人間観に貫かれた、ハードでありながら潤いのある物語世界。それを壊すようなまねはしてほしくないと思ったのではなかろうか。
一方、逢坂剛のファンは、作者ならではの“鬼平”の世界を期待している。つまり、二つの要素を両立させなければならないのだ。それを作者はやってのけた。この観点から本シリーズを眺めると、いろいろなことが見えてくる。たとえば、平蔵――配下の与力・同心――手先(密偵)という図式は、『鬼平犯科帳』と一緒だ。また、盗賊たちのいかにも“らしい”異名や、配下の者たちや手先と集まる店があるのも、池波作品を踏襲している。
しかし一方で、池波作品の特色である盗人世界独自の用語などは使用されていない。さらに、平蔵が悪党たちに滅多に顔を見せず、筆頭与力の柳井誠一郎をときには影武者として使うという、独自の設定が盛り込まれている。『鬼平犯科帳』テイストを感じさせながら、自分なりの世界を創り上げているのである。
その中で、もっとも逢坂剛らしさを感じさせるのが、ミステリーの要素だ。当然ながら『鬼平犯科帳』にも、ミステリーの要素はある。ただ、どちらかといえばサスペンス主体だろう。それに対して本シリーズは、ミステリーのサプライズを入れていることが多いのだ。このことに留意しながら、収録作に触れていきたい。
冒頭の「平蔵の母」は、手先の美於が柳井誠一郎のもとに、とんでもない情報をもたらす。料理屋の〈元喜世〉に客として訪れた、織物問屋〈岩崎屋〉の主の母親・きえが倒れ、店で看病することになる。だが、〈岩崎屋〉などという店は存在していない。さらにきえの言葉から、彼女が平蔵の母親である可能性が浮上するのだ。この騒動を通じて、長谷川家の過去に関する説明を入れながら、意外な真相へとストーリーを運ぶ、作者の手練が素晴らしい。
続く「せせりの辨介」は手先の小平治が、かつての盗賊仲間・ばってらの徳三を見かけたことから、平蔵たちが動き出す。今は神楽坂にある古物商〈壺天楽〉の主をしている徳三。平蔵や同心の俵井小源太、手先のりんたちが見張っていると、三十前後の女が店に、薬師如来の立像を持ち込む。ここから物語が予想外の方向に転がっていき、平蔵たちは徳三を仲間に引き入れようとする盗賊・せせりの辨介一味を追うことになる。邪魔な相手をあっさりと殺す凶悪なせせりの辨介一味と、平蔵たちの水面下での読み合いが見どころと思っていたら、ラストで特大のサプライズが待ち構えていた。これは凄い。また、ある浪人者の扱いから、平蔵の情けが伝わってきた。ここも本作の魅力であろう。
なお本作が「オール讀物」に掲載されたときのタイトルは「簪」であり、二〇一七年十月に刊行された『鬼平犯科帳』トリビュート・アンソロジー『池波正太郎と七人の作家 蘇える鬼平犯科帳』に収録された際に、現在のタイトルに改題されたことを付け加えておく。
以下の話は簡潔に記すことにしよう。「旧恩」は、若手同心の今永仁兵衛が、幼い頃の自分の命を救ってくれた、うめのという女と再会。そこから盗賊の捕物へと繋がっていく。発句に託した暗号もあるが、注目すべきは、うめのの心の変化。本書の中で、『鬼平犯科帳』テイストが、もっともよく出た作品になっている。
「陰徳」も、ある人物の描き方が、『鬼平犯科帳』テイスト。そこにミステリーの要素を色濃く入れて、興趣に富んだ物語にしている。
「深川油堀」は、手先の銀松が、かつて縁のあった掏摸・梵天の善三を見かけ、後を追う。ところが浅草の〈矢場一〉という楊弓場に入った善三が連れ出してきたのは、店の看板娘で、仁兵衛の手先の可久であった。ここから可久の過去と、善三の罪が露わになっていく。シリーズ物の面白さのひとつは、脇役陣にスポットを当てること。それにより物語世界に厚みが生れるのである。後半の緊迫した展開も、大いに堪能した。
そしてラストの「かわほりお仙」は、押し込み強盗の引き込み役を務めていた仙と、手先の歌吉が再会し、新たな事件が起こる。歌吉にスポットを当てながら、揺れ動く女心の恐ろしさと悲しさを巧みに表現したところが、読みどころとなっている。
火付盗賊改方と盗賊の闘いを描いているのだから、本シリーズの内容は基本的にハードである。しかし濃淡こそあるものの、どこかに人の情が盛り込まれている。これも『鬼平犯科帳』を意識してのことだろうが、作者本来の資質もあるのではないか。というのも作者は、警察小説の優れた書き手であると同時に、警察小説の大ファンである。エッセイと対談を収録した『わたしのミステリー』でも、何度も警察小説に触れているが、その中でウィリアム・P・マッギヴァーンの『最悪のとき』について、
「わたしにとって警察小説の原点ともいえるのが、マッギヴァーン。ハードボイルドでありながら、ほどよいセンチメンタリズムを失わない彼の作品を読むなら、まずはコレから」
と述べているのだ。拡大解釈になるが、本シリーズは「江戸の警察小説」といえるのではないか。だから“ハードボイルドでありながら、ほどよいセンチメンタリズムを失わない”作品になった。長き読者人生と、作家人生の積み重ねを糧にしているからこそ、本シリーズは逢坂版『鬼平犯科帳』として、独自の光彩を放っているのである。