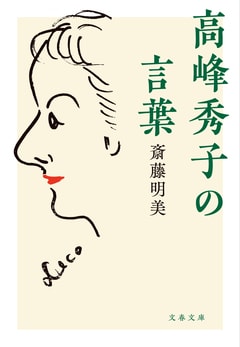生きていたら、高峰は百歳になる。
それが今年、二〇二四年である。
各方面にご協力をお願いしながら、片手にも足りない数のメンバーで会議をし、手紙を書き、メールを送り、挨拶に回り、打合せし、ポスターやチラシを作り……様々な記念事業を計画準備して、今年を迎えた。
だが、しかしである。
高峰は喜んでいない。それどころか、怒っていると思う。
天上から下界を見下ろして、松山とこんな会話をしているのが私の耳元で聞こえる。
「善三さん、あの子はもともとそう出来がいい子ではなかったけど、やっぱりバカですね、こんなことをして」
「違うよ、秀さん。あの子はバカじゃないよ。ただ、秀さんのことが好きで好きでしょうがないんだよ」
「相変わらず甘ったれです、明美は」
「いいじゃないか、ああして一所懸命やってるんだから、やらせておやりよ」
「明美には他に一所懸命やらなきゃいけないことがあるはずです。ホントにしょうのない子……」
そして高峰は深くため息をつく。
恐ろしいことに、この仮想会話は99%当たっている。
高峰が死んでも、私にはこういう時、彼女がどう言うか、こんな場面でどんな言葉を発するか、わかる。
「斎藤明美という人は私を理解してくれた」
高峰が最後に書いてくれた拙著のあとがきにこの一文がある。私の勲章である。
それほど理解しているはずなのに、高峰が良しとしないことを全力でやっている。
なぜ高峰が怒っているのか、理由もよくわかっている。人様に迷惑をかけること、自分のために他人様の手を煩わせることを、高峰は何より嫌ったからだ。事実、そんなことを一度もしてこなかった人だ。
私は松山家の番犬として、松山の言うことには逆らったことはあっても、鎖の端を握っている女主人にだけは絶対忠実だった。「お座り!」と言われれば嬉々として座り、「伏せ!」と言われれば喜んで伏せた。それが私の幸せだった。
逆らったことは二度だけだ。一度目は高峰が私に折れてくれた。だが二度目の今回ばかりは無理だと思う。
松山が私に言ったことがある、
「愛情というのは、相手が望むようにしてあげることだよ」
その言葉にも逆らっている。
だが私は、高峰秀子という一人の人間には、生誕一〇〇年を記念するだけの値打ちがあると信じている。逆らう理由はそれだけである。
いつか自分が死ぬ間際に、そっと「高峰秀子」という引き出しを開けると、紙片が一枚入っているだろう。
「私の名も存在も、すべて無くなることを望んでいます。ただ煙のようになって消えていきたい」
高峰が言うように、「しょうのない」ヤツだ、私は。
令和六年二月 斎藤明美