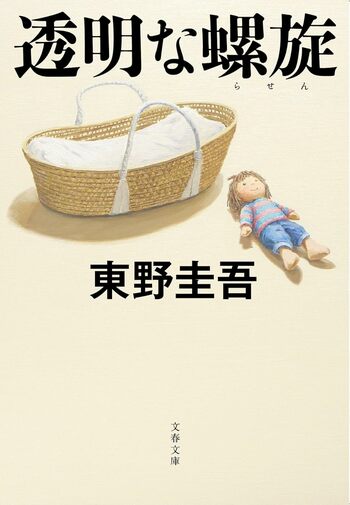【東野圭吾『透明な螺旋』文庫化記念】「ガリレオ」の魅力がすべて詰まった名篇! 「落下る(おちる)」を期間限定で公開!
ジャンル : #エンタメ・ミステリ
「実験する価値はあるでしょうか」
「価値のない実験なんかはない」
東野圭吾さんの大人気作で、天才物理学者・湯川学が科学知識を駆使して謎を解く「ガリレオ」シリーズ。その最新作『透明な螺旋』が、9月4日に文春文庫より発売されます。
冒頭のやりとりは『ガリレオの苦悩』収録「落下る」からの引用。「ガリレオ」こと湯川と、女性刑事・内海薫が初めて会った時にかわされた名会話です。
独り暮らしの女性が、マンションから落下して死亡する事件が発生。内海は女性ならではの視点でさまざまな推理を働かせますが決め手がなく、先輩刑事・草薙の紹介で湯川の研究室を訪ねます。
捜査への協力を拒む湯川は内海を追い返そうとしますが、彼女は食い下がり、殺害方法として一つの仮説を提示。湯川は初めて興味を示し「アイデアがあるなら試せばいい」と促すのですが…。
内海薫の初登場回で、湯川、内海、草薙の主要三人が揃い踏み、「ガリレオ」シリーズの魅力がすべて詰まったこの名篇を、『透明な螺旋』発売を記念して期間限定で公開します。
第一章 落下る
1
つい先程までぱらついていた雨はやんだようだ。今日はついている――ワゴンタイプのスクーターから降りながら、三井礼治はほんの少し儲けたような気分になっていた。雨が本降りの最中にも配達はしたが、いずれも駐車場が地下にあるマンションで、全く濡れずに部屋までピザを送り届けられたのだ。
ケースに入れているとはいえ、宅配物を、しかも食べ物を持って雨の中を行き来するのは気持ちのいいものではない。身体が濡れるのも不快だ。
スクーターに鍵をかけ、ピザを抱えて歩きだそうとした時、三井の顔の前に大きな傘がぶつかってきた。彼はあやうくピザを落とすところだった。
あっと声を出したが、傘をさした男は何もいわずに歩き去ろうとしている。濃い色のスーツを着た男だった。サラリーマンのようだ。雨がやんでいることに気づかず、傘をさしたまま歩いていたらしい。しかも、その傘のせいで前が見えなかったのだろう。
「ちょっと待てよ、あんた」
三井は声をかけながら駆け寄り、
男が振り向いた。迷惑そうに眉をひそめている。
「ぶつかっといて、シカトかよ。こっちは商品を落とすところだったんだぜ」
「あ……すまん」男はそういって顔をそむけると、また歩きだそうとする。
「すまんって、それだけかよ」
三井が舌打ちをした時だった。彼の目の端に、奇妙なものが入った。黒い影のようなものがすごい勢いで縦に走ったのだ。
その直後、ずしんと腹に響くような音がした。そちらに目を向けると、マンションの横の道路上に、黒い塊が横たわっていた。たまたまそばを通りかかっていた女性が、悲鳴をあげて後ずさりした。
「うわっ、うわっ、うわわ」
三井はおそるおそる近寄っていった。悲鳴をあげた女性は、そばの電柱の陰に隠れるように立っている。
黒い塊と思われたものは明らかに人の形をしていた。しかし手足の向きは、ありえない方向に曲がっていた。長い髪が広がっていて顔は見えない。見えなくて幸いだったかもしれない。頭部と思われる部分から、ゆっくりと液体が流れ出てきた。
どよめきがあちらこちらから聞こえた。気づくと三井の周囲に人が集まってきた。
飛び降りか、と誰かがいった。それでようやく三井は事態を理解した。
すげえ、すげえ、すげえ、マジかよ、すっげえもん見ちゃったよ――たちまち興奮した。このことを仲間たちに話したら、どれほどうけるだろうとわくわくした。
しかし彼はそれ以上、死体に近づけなかった。もっと近くで見たいと思いつつ、やはり
救急車を呼べとか、警察に通報といった言葉が耳に入ってきた。周りの人々は落ちる瞬間を見ていないからか、幾分冷静のようだった。
三井も少しずつ落ち着きを取り戻してきた。それと同時に自分が大事に抱えているもののことも思い出した。
いけねえ、まずは配達だ――彼はピザを手に駆けだした。
2
現場はマンションの一室だった。間取りは2LDK。しかもリビングルームはどう見ても十四畳以上ある。ほかの洋室もゆったりとしている。女の独り暮らしといってもいろいろとあるものだ、と
この部屋は整理が行き届いていた。高級そうなソファには、丸いクッションがふたつ載っているだけだし、テレビの周りや本棚の中もすっきりとしている。特にダイニングテーブルの上に何も載っていないというのは、薫にとっては考えられないことだった。
当然、床の上も奇麗だ。ベランダに出るガラス戸のそばに掃除機が置かれているが、それを使って毎日のように掃除をしているのだろう。ひとつだけ違和感があるとすれば、その掃除機の脇に鍋が落ちていることだ。外れた蓋はテレビのそばまで転がっていた。
料理を始めるところだったのだろうかと思い、薫はキッチンを覗いた。流し台の横にオリーブオイルの瓶が載っていた。水切りの中にはアルミボウル、包丁、小皿といったものが入っている。流し台の三角コーナーには、トマトの皮が捨てられていた。
冷蔵庫の扉を開けてみた。最初に目についたのは、大皿に盛られたトマトとチーズだった。白ワインが一本、その隣に横たわっている。
誰かとワインで乾杯でもするつもりだったのかな、と薫は思った。
部屋の住人の名前は江島
リビングルームに戻った。何人かの刑事たちがベランダを頻繁に出入りしていた。薫は彼等の動きが一段落するまで待っていることにした。早く見たところで何か得するわけではないと割り切っている。我先にと焦るところが男の子供っぽいところだとも思う。
薫は壁際に置かれたリビングボードに近づいた。横にマガジンラックが置いてあり、雑誌が入っている。それを
写真のファイルを戻して引き出しを閉めた時、薫の先輩である
「どうですか」彼女は訊いた。
「何ともいえないな」草薙は下唇を突き出した。「ただの飛び降りじゃないかと思うんだけどな。争った形跡もないし」
「でも、玄関の鍵はあいてたんですよ」
「それは知ってる」
「部屋に一人でいたのなら、鍵はかけてると思うんですけど」
「自殺をするような精神状態だったら、ふつうとは違うことだってするだろ」
薫は先輩刑事を見つめ、かぶりを振った。
「どんな精神状態でも、習慣的になっていることは変わらないと思うんです。ドアを開けて中に入り、ドアを閉めたら鍵をかける――それって癖になってるはずです」
「誰でもそうだとはかぎらないだろ」
「独り暮らしをしている女性で、それが習慣になってない人はいないと思います」
やや強い口調で薫がいうと、草薙は不愉快そうに口をつぐんだ。それから気を取り直すように鼻の横を搔いた。
「じゃあ、おまえの考えを聞こうか。どうして鍵はかかってなかったんだ?」
「簡単なことです。誰かが鍵をかけずに出ていったからです。つまり、この部屋にはもう一人いたことになります。おそらく亡くなった女性の恋人です」
草薙は片方の眉をぴくりと動かした。
「大胆な推理だな」
「そうでしょうか。冷蔵庫の中を御覧になられましたか」
「冷蔵庫? いや」
薫はキッチンに行くと冷蔵庫のドアを開け、大皿とワインの瓶とを取り出した。それを草薙の前まで持っていった。
「独り暮らしの女が自宅でワインを飲まないとはいいません。でも自分のためだけに、オードブルをこんなに奇麗に盛りつけたりはしません」
草薙は鼻の上に皺を寄せ、頭を搔いた。
「所轄さんたちが明日の朝から会議をするらしいから、とりあえずそこに顔を出そう。その頃には解剖の結果も出てるだろうしさ。議論するのはその後だ」そういって彼は顔の前の蠅を追い払うようなしぐさをした。
先輩刑事の後に続いて部屋を出ようとした時だった。玄関の靴箱の上に段ボール箱が載っているのを見て、薫は靴を履くのを中断した。
「どうした?」草薙が訊いてくる。
「これ、何でしょう?」
「宅配便みたいだな」
「開けてもいいですか」
段ボール箱はまだガムテープで閉じられたままだった。
「勝手に触るな。どうせ所轄さんが中身を確かめるだろう」
「今すぐ見たいんですけど。所轄さんに断ればいいですか」
「内海」草薙が眉をひそめた。「目立つようなことはするな。ただでさえおまえは浮いてんだから」
「私、浮いてますか」
「いや、そうじゃなくて……みんなが注目してるってことだよ。だから、ちょっとは遠慮しておけ」
何だそれ、と思いながら薫は頷いた。不可解なことを無理矢理受け入れなければならないのは、昨日今日のことではない。
翌朝、薫が所轄である深川警察署に行くと、草薙が不機嫌そうな顔で待っていた。上司の間宮も一緒だった。
薫の顔を見て、ごくろうさん、と間宮はいかつい顔でいった。
「係長……どうしてここに?」
「呼ばれたからだ。うちが担当することになった」
「担当って……」
「他殺の疑いが出てきたんだ。被害者の頭を殴ったと思われる凶器が、部屋から見つかった。ここに合同捜査本部を置くことになりそうだ」
「凶器? 何だったんですか」
「鍋だよ。長い
「ああ」薫は床に転がっていた鍋を思い出した。「あれがそうだったんだ……」
「鍋の底に、微量だが被害者の血痕がついていた。殴り殺すか、昏倒させるかした後、ベランダから落としたんだろう。ひどいことをする奴もいたもんだ」
話を聞きながら、薫は草薙のほうを盗み見した。彼は彼女の視線から逃れるように横を向き、大きな空咳をひとつした。
「犯人は男でしょうか」薫は間宮に訊いた。
「まず間違いない。女にできる芸当じゃない」
「見つかったのは凶器だけですか」
「指紋を消した跡がある。凶器の把手の部分、テーブル、それからドアノブだ」
「指紋を消したということは、強盗とかではないんでしょうね」
強盗ならば手袋を使うはずだからだ。
「顔見知りの犯行と考えていいだろう。凶器も、そこにあったものを使っているしな。財布やカード類も手つかずだし、唯一なくなっているのは携帯電話だ」
「ケータイが……。履歴を調べられたらまずいと思ったんでしょうね」
「だとしたら間抜けな話だな」草薙がいった。「通話記録なんてものは、電話会社に当たればすぐにわかるものなのに。顔見知りってことを、わざわざ白状しているようなものだ」
「気が動転していたんだろう。どう見ても計画性のある犯行じゃないからな。電話会社から通話記録を取り寄せて、男性関係を中心に片っ端から当たってみよう」間宮が締めくくるようにいった。
この後、すぐに捜査会議が開かれた。その場では、主に目撃情報についての報告がなされた。
「転落した直後、マンションの周辺にはすぐに人が集まってきたようですが、不審な人物は目撃されていません。江島千夏の部屋は七階ですが、六階の住人が物音を聞いて窓の下を見た後、すぐに部屋を出てエレベータに乗っています。で、乗る前にエレベータは七階に止まっていて、その住人が乗る時には無人だったそうです。もし何者かが江島千夏を突き落とした直後に逃走したのだとしたら、そのタイミングでエレベータが七階に止まったままだったということはないのではないか、と思われます。尚、エレベータは一基しかありません」初動捜査に当たった五十歳ぐらいの捜査員が落ち着いた口調でいった。
犯人が非常階段を使用した可能性についても検討された。しかし階段は転落現場と同じ側にあり、おまけに外階段なので、もし犯人が下りていったなら、集まっていた野次馬から丸見えになるはずだという意見が深川署の捜査員から出された。
犯人は被害者を落とした後、どこに消えたのか――それが現時点での最大の謎だった。
「ひとつ考えられることがありますね」間宮が意見を述べた。「犯人が同じマンションの住人ならどうですか。犯行後、自分の部屋に戻れば、誰にも目撃されずに済みます」
警視庁捜査一課の係長の意見に、誰もが大きく頷いた。
3
岡崎光也という男が深川署に名乗り出てきたのは、その夜のことだった。ちょうど薫と草薙が聞き込みから戻ってきたところだったので、二人で会うことになった。
岡崎は三十代半ばの痩せた男だった。短い髪を奇麗に分けている。セールスマン、というイメージを薫は抱いたのだが、職業を尋ねてみると、本当にそうだった。大型店舗で有名な家具店で営業をしているらしい。
岡崎によれば、昨日の夜、江島千夏の部屋を訪れたという。
「彼女は大学のテニス同好会の後輩なんです。学年は五つも離れてるんですけど、僕は卒業後もよく遊びに行ってたものですから、彼女とも顔見知りになりました。ずいぶん長い間会ってなかったんですが、半年ほど前に街でばったり会いましてね、それ以来、メールのやりとりなんかをするようになりました」
「メールだけですか。デートとかは?」薫は訊いてみた。
岡崎は慌てた様子で手を横に振った。
「そういう関係じゃありません。昨日、彼女の部屋に行ったのは、一昨日の昼間に電話をもらったからです。ベッドを買い換えたいからカタログを持ってきてほしい、と」
「後輩が先輩を部屋に呼びつけた、というわけですか」草薙が語尾に疑問符を付けた。
「私どもの場合、部屋に伺うのが一番いいんです。どういう部屋なのかがわからないと、いい品をお勧めすることができません」
たとえ相手が後輩であっても通常と同様の対応をする、ということらしい。
「そういうことはこれまでにも何度かあったんですか。つまり、江島さん相手に商売をされたことはありますか」草薙が訊く。
「ありました。ソファとかテーブルを買ってもらいました」
「なるほど。で、昨日は何時頃に江島さんの部屋に行かれたんですか」
「八時という約束をしていました。さほど遅れなかったはずです」
「その時、江島さんに何か変わった様子は?」
「特に気になったことはありません。カタログを見せて、いろいろなベッドがあることを説明しました。江島さんは頷きながら聞いてました。結局、その場では決められなかったんですけどね。ベッドの場合、やはり実物を触ってから決めたほうがいいとアドバイスしました」
「どこで話をされたんですか」
「部屋の中で、です。リビングルームのソファに座って……」
「何時頃までいらっしゃったんですか」
「そうですね。たしか八時四十分頃には部屋を出たと思います。後から来客があるようなことをいってましたし」
「客が? 何時頃に来ると?」
「さあ、そこまでは……」岡崎は首を捻った。
「あのう」薫はいった。「玄関に靴箱がありましたよね」
「はっ?」
「靴箱です。江島さんの部屋の玄関に」
「ああ……そうですね、ありましたね。いや、でもあれはあの部屋に備え付けのもので、当店の品物では……」
「そうじゃなくて、靴箱の上に段ボール箱が載っていたと思うんですけど、覚えておられますか」
「段ボール箱……」岡崎は戸惑ったように視線を動かした後、小さく首を傾げた。「どうでしょう。あったような気もしますが、よく覚えてません。申し訳ないんですが」
「そうですか。それならいいです」
「ええと、その段ボール箱がどうかしたんでしょうか」
「いえ、何でもありません」薫は手を振ってから、草薙のほうを見て、小さく頷いた。質問を割り込ませたことを詫びたつもりだった。
「事件のことはいつお知りになったんですか」草薙が訊いた。
「ニュースを見たのは今日になってからです。ただ、事件そのものは、もっと前から知っていたといいますか、起きた時から知っていたといいますか……」岡崎の歯切れが突然悪くなった。話の意味もよくわからない。
「どういうことですか」
「じつは私、見ているんです。あの、落ちた瞬間をです」
えっ、と薫は草薙と共に声をあげた。
「江島さんの部屋を出た後、しばらくあの近所にいたんです。たしか別のお得意様が近くにいらっしゃったはずだと思い出しまして、挨拶だけでもしておこうと思って歩き回っていたわけです。でも結局そのお宅を見つけられなくて、またあのマンションのそばまで戻ってきた時、あの転落事件が起きたんです。それだけでもびっくりしましたが、今日のニュースで江島さんだったと知り、びっくりを通り越して怖くなってしまいました。だって、自分が会ってきた人が、その直後に殺されたんですからね。それで何かお役に立てるかもしれないと思って、こうして名乗り出たというわけです」
「それはどうもありがとうございます。貴重な情報です」草薙は頭を下げた。「落ちた時、そばにいたとおっしゃいましたが、当然お一人だったわけですよね」
「もちろんそうです」
「そうですか」
「それが何か?」
「いやあ、せっかく貴重な情報を提供してくださった方にこういう言い方をするのはまことに心苦しいのですが、我々の仕事というのは何事につけ裏づけを取らないことには始まらないんです。ですから今のままですと、岡崎さんが江島さんの部屋に行ったということだけが捜査記録に残るわけでして……」
「ははあ」岡崎は意外そうな顔で草薙と薫とを見比べた。「私に疑いがかかると?」
「いえ、そういうわけではないんですが」
「江島さんが落ちた時、たしかに私は一人でしたが、そばに人がいないわけではありませんでしたよ。むしろ、話しかけられているところでした」
「誰にですか」
「ピザ屋の店員さんです。たしか、『ドレミピザ』だったと思うんですけどね」
岡崎によれば、宅配中の店員から呼び止められ、何か文句をいわれたということだった。江島千夏が転落したのは、その直後だという。
「あの店員さんの名前、聞いておけばよかったなあ」岡崎は悔しそうに唇を嚙んだ。
「いえ、こちらで確認できると思いますから、大丈夫です」
草薙の言葉に、「それならいいんですけど」と岡崎は安堵の笑みを浮かべた。
「顔写真の付いた身分証か何かをお持ちではないですか。できればコピーさせていただきたいのですが。もちろん、確認が終われば破棄します」
「そういうことなら構いません」岡崎は社員証を出してきた。そこに貼られた写真には、正面を向き、口元にうっすらと笑みを浮かべた彼が写っていた。
4
岡崎を帰した後、二人で間宮のところへ報告にいった。
「つまり被害者は、家具屋を帰した後、誰かと会う約束をしていたというわけか」間宮は腕組みをした。
「これで大皿のオードブルの謎も解けたな」草薙が薫に
「状況から被害者と深い仲にある男と考えて、まず間違いない」間宮が立てた人差し指を振った。「で、その男が、事件から丸一日経った今も名乗り出てこないのはおかしい。何らかの形で事件に関わっているとみていいだろう」
「ひとつ気になることがあります。被害者は、次の来客とは何時に会う約束をしていたんでしょうか」薫は上司と先輩刑事を交互に見た。
「家具屋が帰ったのが八時四十分頃ってことだったから、九時頃に客が来ることになっていたんじゃないか」
そう答えた草薙の顔を薫は見返した。
「だとすると、犯人が部屋に入ってから事件が起きるまで、十分程度しかありませんよね」
「十分あれば犯行は可能だろ」
「それはそうですけど、凶器は鍋ですよ」
「それがどうした」
「犯行は計画的なものではない、という話でしたよね」
おっ、と声を漏らしたのは間宮だ。「なるほどな。そういうことか」
「何ですか、係長まで」
「まあとにかく、内海の話を聞いてみよう。――続けてくれ」
「犯行が計画的なものじゃなくて衝動的なものなのだとしたら、そうなってしまった理由があるはずです。訪問からたった十分の間に、衝動的に殺すような何かが起きたということでしょうか」
間宮はにやにやして草薙を見上げた。
「どうする、草薙刑事。若手女性刑事の指摘はなかなか鋭いぞ」
「じゃあ、犯人が部屋を訪れたのは、九時よりもう少し前だったのかもしれない。八時四十五分とか」
「訪問の約束をするには、やけに中途半端な時間ですね」
「そんなのは人の好きずきだろ」
「それはそうですけど」
「内海」間宮がじろりと睨んできた。「おまえ、何かいいたいことがあるのか」
薫は俯き、唇を結んだ。いいたいことはあった。しかし自分の感覚が果たして彼等に理解してもらえるかどうか自信がなかった。
「何でもいいからいってみろ。黙ってたんじゃわからん」
間宮にいわれ、薫は顔を上げた。ふっと息を吐いた。
「宅配便の荷物です」
「宅配便?」
「江島千夏は宅配便を受け取っています。玄関の靴箱の上に置いてありました。受け取ったのは昨日の夕方のようです」
「おまえ、ずっとあの箱にこだわってるよなあ」草薙がいった。「家具屋にも訊いてたじゃないか。何がそんなに気になるんだ」
「その宅配便のことは何も聞いてないなあ。どういうものなんだ」間宮が草薙に訊いた。
「通信販売で本人が注文した品物らしいです」
「中身は?」
「そこまでは確認してませんが……」
「下着です」
薫の言葉に二人の男は、えっと声をあげた。
「おまえ、勝手に見たのか」草薙が訊いてきた。
「いいえ。でもわかるんです。中身はたぶん下着だと思います。あるいはそれに類するものです」
「何でわかるんだ」間宮が質問してきた。
薫は一瞬
「箱に会社名が印刷してありました。その会社は有名な下着メーカーです。最近、通販で業績を伸ばしています」さらに、少し迷ったが付け足した。「女性なら、大抵知っていると思います」
先輩刑事や上司の顔に戸惑いの色が浮かんだ。特に草薙は、下品な冗談のひとつでもいいたいが、薫の前なので我慢しているといった表情だ。
「そう……か。下着か」間宮はコメントを探しているようだった。「で、何が問題なんだ」
「状況から推測しますと、被害者は宅配便で受け取った後、あの段ボール箱をずっと靴箱の上に置いていたと考えられます」
「それで?」
「来客の予定があれば、そういうことはしないと思います」
「どうして?」
「どうしてって……」薫は思わず眉根を寄せていた。「何度もいうようですが、下着だからです。他人に見せたくはありません」
「そうはいっても、新品だろ。それに箱に入ってるわけだし。大して気にすることでもないだろう。――なあ」間宮は草薙に同意を求めた。
「そう思います。それにおまえだから中身がわかったわけで、ふつうならわからないよ。ましてや男にはさあ」
薫はいらいらしたが、辛抱強く説明を続けることにした。
「男でもわかるかもしれない、そう考えるのがふつうです。たとえ新品であろうと箱に入っていようと、自分の下着に関する情報なんかは遮断したいんです。来客の予定があれば、絶対に隠します。仮にその時には忘れていたのだとしても、玄関でドアを開ける前に気づくはずです」
草薙と間宮は困ったように顔を見合わせた。女性心理に関することだけに、強く反論する自信もないのだろう。
「だけどさ、そうはいっても、実際に段ボール箱はあそこに置いてあったんだ。それとも何か、犯人が置いたっていうのか」草薙がいった。
「そんなことをいいたいんじゃありません」
「じゃあ、何だよ」
「隠す必要がなかったんじゃないかと思うんです」
「どういう意味だ?」間宮が訊いた。
「今もいいましたように、ふつうなら客が来る前に箱を隠します。相手が男性なら尚のことです。それをしなかったのは、必要がなかったからじゃないかと思うんです」
「どうして必要ないんだ。客は来たわけだろ? 家具屋が」
「ええ」
「それなら必要あるんじゃないのか」
「ふつうなら。でもひとつだけ、来客があっても下着を隠さなくていいケースがあります」
「どういうケースだ」
「その来客が恋人の場合です」薫は続けた。「岡崎光也が江島千夏の恋人なら、わざわざ段ボール箱を隠さないと思います」
『ドレミピザ木場店』は、深川署からは歩いて行ける距離にあった。
問題の時間にピザを配達した人物を特定することは難しいことではなかった。三井礼治という青年だった。
「ええ、たしかにこの人だったと思います。俺がピザをスクーターから降ろしている時、ぶつかってきたんです。で、そのまま謝りもせずに行き過ぎようとするものだから、呼び止めて文句をいったんです。飛び降りがあったのはそのすぐ後です」三井は岡崎の顔写真を見ながら、はっきりとした口調でいった。
「間違いないですね」草薙が念を押す。
「間違いないです。あんなことがあったから、結構印象に残ってるんです」
「どうもありがとうございます。助かりました」草薙は写真を胸ポケットにしまい、同時に薫を睨みつけてきた。これで気が済んだか、とでもいいたそうだ。
「この人の様子、どうでした?」薫は三井に訊いた。
「どうって?」
「何か変わった点はありませんでしたか」
「えー、覚えてねえなあ」三井はしかめっ面で首を傾げた後、ふっと何かを思い出した顔になった。「そういえば、傘をさしてたな」
「傘?」
「あの時はもう雨はやんでたんです。それなのに傘なんかさしてるから、前が見えなくて人にぶつかったりするんですよ」三井は唇を尖らせていった。
5
「そういう話を江島さんとしたことは殆どないんです。ほかの刑事さんからも訊かれたんですけど、そうお答えするしかなくて」前田典子は申し訳なさそうに俯いた。白いブラウスの上からブルーのベストを羽織っている。この銀行の制服らしい。
薫は江島千夏の職場に来ていた。日本橋の小伝馬町にある支店だ。二階にある接客室の一つを使わせてもらい、江島千夏と一番親しかったという前田典子から話を聞いている。
彼女が「そういう話」といったのは、江島千夏の男性関係についてだった。前田典子によれば、江島千夏は結婚に否定的な意見を持っていたという。一生独身でも構わない、と話していたこともあるらしい。
「では、最近の様子に特に変わったところはなかったということですか」
「そうですね。少なくとも、あたしは気づきませんでした」
「では、この男性に見覚えはないですか」薫は一枚の写真を見せた。
しかし前田典子の反応は芳しくなかった。「知らない人です」
薫は小さく吐息をついた。
「わかりました。お忙しいところを申し訳ありませんでした。最後に、江島さんの机を見せていただけませんか」
「机……ですか」
「ええ。どういうところで働いておられたのかを見ておきたくて」
前田典子は、やや戸惑い気味に頷いた。「では上司に訊いてきます」
数分して、前田典子が戻ってきた。許可が下りたということだった。
江島千夏の席は、二階の融資相談窓口の近くにあった。机の上は奇麗に片づけられている。薫は椅子に腰を下ろし、引き出しを開けた。筆記具や大小様々な書類、判子などが整然と収められている。あの部屋と同じだなと薫は思った。ただしあの部屋と違い、この中には恋人の存在を
小柄な中年男が近づいてきた。
「この机、いつまで置いておかなきゃいけませんか」
「あ……それは」薫は口籠もった。
「前に来た刑事さんに、しばらくこのままにしておいてくれといわれたんですけど、うちとしても、別の人間を連れてこなきゃいけないし、そろそろ片づけたいんですけどねえ」
「わかりました。上司に確認しておきます」
よろしくお願いします、といって男性は去っていった。
薫は諦めて、引き出しを閉じようとした。その時、一枚の書類が目に留まった。
「これは何ですか」前田典子に尋ねた。
「暗証番号の変更届ですね」書類を見て、彼女は答えた。
「お客さんのものですか」
「いえ、彼女が自分のキャッシュカードの暗証番号を変えようとしていたみたいです。彼女の名前が書いてあります」
「どうして変えようとされてたんでしょうか」
「さあ、それは……」前田典子は首を傾げた。「何か問題が生じたのかもしれませんね」
薫の脳裏に、何かが引っかかった。
「すみません。もう一つお願いがあるんですが、よろしいでしょうか」思わず大きな声が出た。薫の剣幕に、周囲の人間までもが注目した。
その夜、薫は深川署の小会議室に籠もっていた。彼女の前にある段ボール箱には、江島千夏の部屋から見つかった書簡類が収められている。それら一つ一つを丹念に調べているが、期待しているものは見つかっていない。
薫がため息をついた時、ドアの開く音が聞こえた。
部屋に入ってきたのは草薙だった。彼は薫を見て、苦笑を浮かべた。
「何か面白いものでも見つかったか」
「そう簡単に見つかるとは思ってません」
「一体、何を探してるんだ。スタンドプレーをするには百年早いぜ」
「スタンドプレーだとは思いません。江島千夏の人間関係を探れという指示に従って、彼女の恋人を探しているだけです」
「係長からは、マンションの住民の中に江島千夏と深い関係にあった人間がいないかどうかをまず調べろ、といわれたはずだ」
薫は深呼吸してから首を振った。
「マンション内に江島千夏の交際相手はいません」
「どうして断言できる?」
「まず、彼女の携帯電話の通話記録に、同じマンション内に住む人物の番号はありませんでした。メールアドレスも同様です」
「同じマンション内だからこそ、電話やメールを交わす必要がなかったのかもしれない」
薫は首を振った。「ありえません」
「どうして?」
「そばにいるからこそ、余計に電話をかけたくなるものです。女とはそういうものです」
草薙は気を悪くしたように黙り込んだ。女とはそういうものだ、といわれれば返す言葉がないのだろう。
「それともう一つ、私が調べたところ、このマンションにいる男性は全員が妻帯者です。そうでなければ十八歳未満です」
「それがどうかしたのか」
「被害者の結婚の対象にはなりません」
草薙は肩をすくめた。
「男女の関係に、必ずしも結婚が絡んでくるとはかぎらないぜ」
「それはわかっています。でも江島千夏さんの場合は違います。彼女は結婚を前提に交際していました」
「どうしていいきれる?」
「リビングボードの横にマガジンラックがあったのを覚えておられますか。あの中に結婚情報誌が入っていました。しかも先月発行されたばかりのものです」
薫の言葉に草薙は一旦口をつぐんだが、唇を舐めていった。
「単に結婚に憧れてただけじゃないのか。江島千夏は三十歳だったな。焦ってたって不思議じゃない」
「憧れだけで結婚情報誌を買う女なんていません」
「そうかなあ。車を買う予定はないけど、カー雑誌を買う男はいっぱいいるぜ」
「結婚と車を一緒にしないでください。私は、江島千夏には具体的に結婚を考えて付き合っている相手がいたと思います」
「もしそうなら、それこそ通話記録に残っていそうなものじゃないか。ところが今のところ、それらしき人物は見つからない。それはどういうことだ」
「見つかってるんです。見つかってるのに、見逃しているんだと思います」
草薙は腰に両手を当て、薫を見下ろしてきた。
「岡崎光也だといいたいわけだな」
薫が答えないでいると、彼は苛立ったように頭を搔きむしった。
「おまえ、被害者の職場に行ったそうだな。いろいろと聞き込みをしたそうじゃないか。それはまずいぞ。職場の聞き込みを担当してる連中から嫌味をいわれたぜ」
「すみません」
「まあ連中も、おまえだから大目に見てくれてるけどな。でも女だからって特別扱いされるのは、おまえが一番嫌なことじゃないのか」
「後で謝っておきます」
「いいよ、俺が謝っといたから。それよりおまえ、被害者の知り合いに岡崎の写真を見せて回ってるそうだな。この男を知らないかって」
薫は再び口を閉ざす。いずればれるだろうと覚悟はしていた。
「まだ岡崎を疑ってるのか」
「私の中では一番の容疑者です」
「その奇抜なアイデアについては結論が出てるはずだぜ。それにあいつが犯人なら、自分から名乗り出てきたりしないんじゃないか」
「そうでしょうか。私は岡崎が名乗り出てきたのは、携帯電話の通話記録を調べられたら、どうせ自分も調べられるだろうと思い、先手を打ってきたんだと思います」
「だったら、携帯電話を持ち去る理由がないじゃないか」
「時間稼ぎです。名乗り出るまでの間、岡崎は供述内容を必死で考えたのだと思います」
「岡崎は江島千夏が落ちるところを見ているんだ。証人だっている。それともピザ屋の店員もグルだっていうのか」
「そうはいいません」
「じゃあ、どうやったら下にいる人間が、七階にいる人間を殺せるっていうんだ」
「もちろん殺す時には岡崎は部屋にいたと思います。その後、何らかの仕掛けを使って、自分がマンションを出た後で死体が落ちるように細工したとは考えられませんか」
「離れたところにいて、遠隔操作で落とすっていうのか」
「あるいはタイマーみたいな仕掛けを使って……」
草薙は会議室の天井を見上げ、お手上げのポーズを作った。
「事件直後、江島千夏の部屋には警官が入ってるんだ。そんな仕掛けがしてあったなら、当然発見されたはずだ」
「見つからないような仕掛けだとしたら?」
「どんな?」
「それは……私にはわかりません。でもおかしいと思うんです。ピザ屋の話では、岡崎は雨がやんだのに傘をさしていたということでした。それまで岡崎は、近くを歩きまわっていたといってるんです。それなら雨がやんだことにも気づいたはずです」
草薙はゆっくりと首を振った。
「考えすぎだ。いろいろと納得できないことはあるだろうけれど、ほかに答えがないって時には、それを受け入れるべきなんだよ。岡崎はシロだ」そういって草薙は薫に背中を向けた。
「草薙さん」薫は先輩刑事の前に回り込んだ。「お願いがあります」
「なんだ」
「あの方を紹介していただけないでしょうか」
「あの方?」草薙は
「帝都大の湯川学准教授です」
草薙は顔の前で手を振った。「やめておけ」
「どうしてですか。草薙さんはこれまでに何度か、湯川准教授のアドバイスによって事件を解決したと聞きました。だったら、私が協力をお願いしてもいいのではないでしょうか」
「あいつはもう警察には協力しないよ」
「どうしてですか」
「それは……いろいろと事情があるんだ。それに奴の本業は学者であって、探偵じゃない」
「事件を解決してもらおうというんじゃありません。離れた場所にいて、死体を七階のベランダから落とすことが可能かどうか、それを検証してもらいたいだけなんです」
「あいつはきっとこういうよ。科学は魔法じゃないってね。あきらめろ」草薙は薫の身体をおしのけ、廊下に出ようとした。
「待ってください。これを見てください」薫はバッグから一枚の書類を取り出した。
草薙がげんなりした顔で振り返った。「なんだ、それ」
「江島千夏の職場の机に入っていたものです。キャッシュカードの暗証番号の変更届です。まだ提出されていませんが、彼女は暗証番号を変更しようとしていたんです」
「それがどうかしたのか」
「なぜ変更しようとしたと思いますか」
「番号を誰かに知られちゃったんじゃないのか」
「いえ、たぶんそうではないと思います」
「どうしてわかる」
「彼女のカードの暗証番号は0829でした。でも彼女は、この番号のままではまずいと思ったんです」
「どうして?」
薫は大きく息を吸い、ゆっくりと吐き出してからいった。
「岡崎光也の誕生日が八月二十九日だからです」
「えっ……」
「もちろん偶然です。江島千夏がカードを作ったのは、岡崎と付き合うよりもはるか前のはずですから。でもその偶然の一致を、江島千夏は危険だと考えたんです。仮に岡崎と結婚すれば、カードの暗証番号が夫の誕生日と同一ということになります。銀行に勤めている彼女は、真っ先にそういうことを心配したんです」
話を聞いている草薙の顔つきが変わってきた。見開いた目に、真剣な光が宿っていた。
お願いします、と薫は頭を下げた。「湯川先生を紹介してください」
草薙が太い息を吐く音が聞こえた。
「紹介状は書いてやるよ。だけどたぶん無駄だと思うぜ」
6
封筒から取り出した便箋の中身をさらりと読み流し、湯川は再びそれを封筒に戻した。顔つきは端正だが、表情には何の色もなかった。金縁眼鏡の向こうに見える目も冷めている。
彼は封筒を机の上に置き、薫を見上げた。「草薙は元気かい?」
「お元気です」
「そうか。それならよかった」
「あのう、じつは今日お伺いしたのは――」
薫が用件をきりだそうとすると、湯川はそれを制するように右手を広げた。
「この紹介状に、こう書いてある。気が進まないだろうが、何とか相談に乗ってやってほしい、とね。彼のいう通りなんだよ。つまり僕は気が進まない」
まわりくどい言い方をする男だな、と薫は思った。学者というのは、こういう人種が多いのだろうか。
「でも以前はよく協力してくださったそうじゃないですか」
「以前はね。だけど今は違う」
「なぜですか」
「個人的な理由からだ。君には関係がない」
「話だけでも聞いていただけませんか」
「その必要はない。協力する気はないからね。それに、大体のことはこの紹介状に書いてある。手を触れず、離れた場所にいて、人をベランダから落とす方法を知りたいようだね」
「ただの人ではなく、たぶん死体です」
「どっちでもいい。とにかく、そんなことを考えるほど僕は暇じゃない。悪いけど、帰ってくれるかな」湯川は封筒を薫のほうに押した。
薫は封筒には手を伸ばさず、物理学者の眼鏡の奥を見つめた。
「やはり不可能だと?」
「そんなことは知らない。僕には関係のないことだといってるんだ。警察の捜査に関わるのは、もうやめたんだよ」湯川の口調には、ややむきになっているような響きがあった。
「警察の捜査とは考えず、単なる物理に関する相談だと受け取っていただけませんか。理科の苦手な人間が、わからないことがあるので質問しに来た、そう考えてください」
「だったら、僕以外にも教えられる人間はたくさんいる。ほかを当たってくれ」
「先生は人に教えるのが仕事のはずです。わからないことを質問しに来た学生を門前払いにするんですか」
「君は僕の教え子じゃない。君だって僕の講義を受けたことなんてないだろ? 警察の権威を使って、他人を便利屋のように利用しようとしているだけだ」
「そんなことはありませんっ」
「大きな声を出さないでくれ。じゃあ訊くが、君は今までにどれだけ科学について勉強した? 理科が苦手だといったが、それを克服する努力をしたことがあるのか? 早々に投げ出して、科学から目をそむけてきたくちじゃないのか。それならそれでいい。一生、科学とは関わらないことだ。困った時だけ警察手帳を
「私は命令なんて……」
「とにかく君の期待には応えられない。申し訳ないが、教える側の人間にだって、相手を選ぶ権利はある」
薫は俯き、唇を嚙んだ。
「女だからですか」
「何だって?」
「私が女だから、理系の難しいことなんかはどうせわからないだろう、そう思っておられるんじゃないですか」薫は物理学者を睨んだ。
湯川はふっと唇を緩ませた。
「そんなことをいうと、世界中の女性科学者から石を投げられるぞ」
「でも」
「それにだ」彼は鋭い目になって薫のほうを指差してきた。「相手の対応が期待通りにならないたびに、女だからなのかとぼやくようなら、今の仕事はさっさとやめたほうがいい」
薫は奥歯をかみしめた。悔しいが、物理学者のいうとおりだった。あらゆるハンディは覚悟の上で、この仕事を選んだはずなのだ。
警察の権威を使って科学者に謎を解かせようとした、という指摘も的外れではなかった。湯川学の噂を聞き、相談すれば何とかしてくれるのではないかと安易に考えていたのは事実だ。
「すみません。どうしてもお力を借りたくて……」
「君が女だからとか、そういうことは関係ない。僕は警察捜査には関わらないと決めたんだよ」湯川の口調は穏やかなものに戻っていた。
「わかりました。お忙しいところ、申し訳ありませんでした」
「こちらこそ、力になれなくてすまない」
薫は会釈し、湯川に背中を向けた。だがドアに向かう前にいってみた。
「ローソクを使ったんじゃないかと思うんです」
「ローソク?」
「死体に紐を繋いで、ベランダから吊すんです。その紐のもう一方をどこかに固定します。で、そのそばに火のついたローソクをセットします。ローソクが短くなると引火して紐が切れる――そういう仕掛けは考えられないでしょうか」
湯川の返事がないので、薫は後ろを振り向いた。湯川はマグカップでコーヒーを飲みながら窓の外を眺めている。
「あのう……」
「やってみたらいいじゃないか」彼はいった。「アイデアがあるなら試せばいい。実験で結果を得るほうが、僕なんかのアドバイスを聞くより、よっぽど有意義だ」
「実験する価値はあるでしょうか」
「価値のない実験なんかはない」湯川は即答した。
「ありがとうございます。お邪魔しました」薫は湯川の背中に向かって頭を下げた。
帝都大学を出ると、コンビニに寄った。そこでローソクとそれを立てるための台、さらにビニール紐を買い、江島千夏の部屋に向かった。部屋の鍵は警察署を出る時に預かってきた。もし湯川が捜査に協力してくれる場合には、彼に部屋を見せる必要があると思ったからだ。
部屋に入ると早速実験を始めることにした。本当は死体の代わりになるものをベランダから吊したいところだが、実際に七階から何かを落とすわけにはいかない。仕方なく、ビニール紐の一端をベランダの手すりに結びつけた。
問題は、紐のもう一端をどこに結びつけるかだった。死体の重さに耐えねばならないのだから、相当しっかりとしたものでないといけない。ところが室内を見回しても、そういう都合のいいものは見当たらなかった。
結局、紐をキッチンまで延ばし、蛇口に結びつけることにした。そのそばにローソクを立て、火をつけた。炎の位置は、ぴんと張られた紐の五ミリほど上にある。
時計を見ながら待った。ローソクがゆっくりと短くなっていく。
ついに炎と紐が重なりかけた時、ジジジという音を立てて紐が燃えた。ベランダからキッチンまで張られていた紐は、音もなく床に落ちた。
その瞬間、誰かが拍手をする音が聞こえた。薫は驚いてキッチンを出た。黒いジャケット姿の湯川が、リビングの入り口に立っていた。
「お見事。実験は成功のようだな」
「先生……どうしてここに?」
「捜査には関心がないが、実験には興味があったんでね。しかも素人学者がどんなことをするのか見てみたかった。この場所は草薙から教えてもらった」
「冷やかしですか」
「まあ、そう思ってもらって差し支えない」
薫はむっとしてキッチンに戻った。まだ燃え続けているローソクを見つめた。
「何をしてるんだ?」後ろから湯川が訊いてきた。
「ローソクを見ています」
「何のために?」
「燃え尽きたらどうなるかをたしかめるためです」
「なるほど。現場にはローソクの痕跡がなかったわけだから、完全に燃え尽きたと考えなければいけないわけだ。しかしそれにしても、そんなに長いローソクで実験しなくてもいいんじゃないか。それが燃え尽きるには、相当時間がかかりそうだがね」
湯川にいわれ、たしかにそうだと薫は気づいた。しゃくだったが、無言でローソクの火を吹き消すと、一センチほどの長さに折り、もう一度火をつけた。
「じっと見張ってる必要もないだろ。ローソクの火は勝手に消えるさ」そういうと湯川はキッチンを出て、ソファに腰を下ろした。
薫はハサミを手にし、ベランダに出た。手すりに結びつけた紐を切り、部屋に戻った。
「念のために訊くんだけど、死体にそういうビニール紐が結びつけてあったという事実はあるのかい?」湯川が訊いてきた。
「ありません」
「すると、ローソクによって切断された後、紐はどこへ消えたんだろう?」
「それは……まだ課題です。でももしかしたら紐は死体に巻き付けてあった程度で、落ちる時に外れて、どこかへ飛んでいってしまったのかも」
「犯人はそういう都合のいいことを期待し、結果、そのとおりになったというわけだ」
「だから、まだ課題だといってるじゃないですか」
薫はキッチンのローソクを見に行った。火は消えていた。しかしローソクの痕跡は残っていた。半ば予想したことではあったが、がっかりした。
「仮に燃え尽きた時に痕跡が全く残らないとしても、犯人はローソクを使わなかったと思う」湯川が薫の後ろに立った。
「どうしてですか」
「事件の後、いつ人がここに駆けつけてくるか、犯人には予想できないからだ。思ったよりも早く人が来た場合には、まだ燃えているローソクが発見されることになる」
薫は前髪をかき上げ、ついでに頭を両手でかきむしった。
「先生って陰険ですね」
「そうかな」
「そこまでわかってるなら、なぜ先にいってくれなかったんですか。そんな実験はやっても意味がないって」
「意味がない? 僕は問題点を指摘しただけで、意味がないとはいってない。価値のない実験なんかないといっただろ」湯川は再びソファに腰を下ろし、足を組んだ。「まずはやってみる――その姿勢が大事なんだ。理系の学生でも、頭の中で理屈をこね回すばかりで行動の伴わない連中が多い。そんな奴らはまず大成しない。どんなにわかりきったことでも、まずやってみる。実際の現象からしか新発見は生まれない。僕は草薙から場所を訊いてここへやってきたけど、もし君が実験をしていなければ、そのまま帰っていただろう。そうして、おそらく二度と協力する気にはなれなかっただろうね」
「それ、褒めてくださってるんですか」
「もちろんそうだ」
「……ありがとうございます」自分でも無愛想だと思うほど低い声で、ぼそりといった。
「草薙の紹介状によれば、君一人がある人物を疑っているということだね。その根拠というのを聞かせてもらえないかな」
「いくつかあるんです」
「じゃあ、全部聞かせてくれ。なるべく手短に」
「わかりました」
薫は玄関に置かれた下着入りの段ボール箱のこと、被害者が変更しようとしていた暗証番号が岡崎の誕生日と合致していたことなどを説明した。
湯川は頷き、指先で眼鏡を押し上げた。
「なるほど。君の話を聞いていると、たしかにその人物が怪しいように思われるね。ところが彼には完璧なアリバイがあるわけか。転落を下で見ていたというのでは、文句のつけようがないね」
「でも私は、そもそも転落ということ自体に引っかかってるんです」
「どういうことだ」
「犯人は被害者の頭を殴っています。それで被害者が死に至ったのか、昏倒した程度だったのかは、まだわかっていません。でもいずれにせよ、ベランダから落とす必要はなかったと思うんです。死んだのなら、そのままにしておけばいいし、気絶しただけなら、首を絞めるなりして殺せばいいだけのことです。体重が軽いとはいえ、一人の女性をベランダに運ぶのは大変ですし、誰かに目撃されるおそれもあります。どう考えてもメリットがありません」
「自殺に見せかけようとした、とは考えられないか」
「草薙さんや係長は、そういう意見です。でもそれなら、凶器を始末していくはずです。気が動転していたんだろうと草薙さんたちはいいますけど、指紋を消す冷静さはあったんです」
「だけど、被害者が落とされたのは事実なんだろ」
「そうです。だから犯人には、自殺に見せかけられるということとは別の、もっと大きなメリットがあったんじゃないかと思うんです」
「それがアリバイ工作というわけか」
「そうです。突飛でしょうか」
湯川は黙ったままソファから立ち上がり、リビングを歩き回り始めた。
「離れた場所にいながら、死体をいかにしてベランダから落とすか。この問題自体は、さほど難しくない。最大の課題は、さっきから何度もいっているように、痕跡をどうするかだ。何かを使ったのなら、その痕跡が必ず残る」
「でも、何もありません」
「そう見えているだけだ。痕跡だと気づかず、見過ごしているんだ。この部屋に存在するすべてのものに目を向け、トリックを成立させる要素を見抜かねばならない」
「そういわれても……」
薫は室内を改めて見回した。彼女の目には、遠隔操作を行うための機械も、タイマーらしきものも見当たらなかった。
「君のアイデアは基本的には悪くない。死体を吊すには紐が必要だ。死体が落ちた後で姿を消す紐があれば問題は解決する」
「姿を消す紐?」
「その紐を切断するにはどうすればいいか。痕跡が残らないようにするには何を使えばいいか」湯川は足を止め、腰に手を当てた。「この部屋は本当に事件が起きた時のままなのかい?」
「そのはずです」
湯川は眉間に皺を寄せ、顎を撫で始めた。
「それにしてもよく片づいている部屋だな。床に殆ど何も置かれていない」
「それは私も感心したことです。凶器が落ちていただけでしたから」
「凶器?」湯川は足元を見回した。「落ちてないじゃないか」
「そりゃあそうです。鑑識が持っていきましたから」
「ふうん。で、凶器は何だったんだ」
「ステンレス製の鍋です」
「鍋?」
「長い柄のついた鍋です。かなり重くて頑丈なものでしたから、あれで殴られたら、仮に死ななくても気絶ぐらいはすると思います」
「鍋ねえ。どこに落ちてたんだ?」
「そのあたりだったと思います」薫はガラス戸のそばを指差した。「で、蓋がこのへんに転がっていました」壁際を指した。
えっ、と湯川がいった。「蓋もあったのか」
「ありましたけど」
「そうか。鍋と蓋がねえ……」
湯川はベランダのほうを向くと、直立不動の姿勢になった。そのまましばらく動かなかった。やがて彼の目は、そばに置かれた掃除機に向けられた。
不意に彼は含み笑いを始めた。笑いながら、何度も首を縦に振った。
「あのう、先生」
「君に頼みたいことがあるんだがね」湯川はいった。「買い物をしてきてほしい」
「何を買ってくるんですか」
「そんなのは決まってるだろ」湯川はにやりと笑った。「鍋だよ。犯行に使われたのと同じものを買ってきてくれ」
7
「……まずこの鍋に少量の水を入れ、火にかけます」
ビデオモニターには湯川の姿が映っていた。場所はマンションのキッチンだ。江島千夏の部屋と同じ間取りだが、内装はまるで違っている。二階の部屋を使わせてもらったのだ。
「沸騰してきました。このように水蒸気がたっぷり上がるようになれば蓋をします。さらにそのまま、一気に冷やします」
湯川は鍋を流し台に用意してあった、大きな鍋に突っ込んだ。そこには水が張ってある。さらに彼は二センチ角ほどの氷を手にした。
「この氷で蓋の蒸気穴を塞ぎます。氷は少し溶ければ、蒸気穴の形に馴染むので、ずれることはありません。ここまでくると、このように蓋はぴったりと閉じ、鍋から離れなくなります」
湯川は蓋を持ち上げた。彼のいうとおり、蓋は鍋から離れない。
「これは鍋を冷やすことで中の水蒸気が水に戻ったからです。内部の圧力が低いため、大気圧で押されて離れなくなってしまったのです。お吸い物の蓋がお椀にくっついて取れなくなることがよくありますが、あれと同じです」
湯川はリビングに移動した。鍋を床に置く。そばには細長い砂袋と掃除機が用意されている。
「この砂袋は約四十キロあります。江島千夏さんとほぼ同じ重さです。江島さんは死亡時、トレーナーを着ていましたので、砂袋にも同じ生地のカバーをかぶせてあります。トレーナーには首、胴体、腕を通す部分がありますから、このカバーにも二カ所穴を開けておきました。この穴に掃除機のコードを通します。まずコードをいっぱいまで引き出します」
彼は掃除機のコードを最後まで引っ張り出した。その後、それを砂袋のカバーに通していった。
「次はちょっと大変なんですが、がんばってやってみましょう。この砂袋をベランダまで移動させます。――よいしょ」
ベランダまで砂袋を運ぶと、湯川は掃除機をガラス戸のすぐ手前まで移動させた。さらに、ガラス戸を五センチほどの隙間を残して閉じた。
「こうすれば、コードを引っ張っても掃除機がガラス戸につかえてしまいます。これでコードの一端は固定できました。ではもう一端をどうするかですが、その前に死体を吊してしまいましょう」
湯川は反対側のガラス戸を開け、再びベランダに出た。砂袋を持ち上げると、布団を干すように手すりに載せた。さらにコードのプラグ側を持ち、ゆっくりと砂袋を外側に押した。砂袋は外側に滑り落ちそうになるが、湯川がコードをしっかりと持っているので、辛うじて止まっている。
カメラが掃除機を映した。コードが引っ張られ、掃除機はガラス戸に押しつけられている。
湯川がコードを握りしめたまま部屋に入ってきた。
「ここでさっきの鍋の登場です」彼は片手で鍋を引き寄せた。蓋のツマミにコードを巻き付け、プラグをコードの下に挟み込んだ。その上でガラス戸を、もう一方と同じように数センチを残して閉じた。コードを巻き付けられた鍋は、掃除機と同様、ガラス戸に押しつけられる格好になった。それを確認してから湯川はゆっくりと手を離した。
「これで仕掛けは完了です。どうなるのか見てみましょう。まず最初の変化は、鍋の蓋の蒸気穴にくっつけられた氷です。当然溶けていきます。溶ければ中に空気が入ります。空気が入れば大気圧に押さえつけられることもなくなり、蓋が外れます。ここでは氷が早く溶けるよう、通常よりもエアコンの設定温度を高くしてあります」
カメラは仕掛け全体を撮影している。すでに湯川の姿はフレームから外れている。
がん、という音がして鍋の蓋が外れた。同時に巻き付けてあったコードが蛇のように跳ね上がった。次の瞬間には砂袋はベランダの手すりから消えていた。
再び湯川が現れた。彼はベランダに出ると、下を覗き込んだ。
「大丈夫ですか。ああ、よかった。それはそのままにしておいてください。後で片づけにいきます。どうもありがとうございました」彼はこちらを向き、掃除機を調べた。「見事にコードも収まっています。そして鍋も転がっています。実験完了でした」
湯川が頭を下げたところで、薫はビデオデッキとモニターのスイッチを切った。それからおそるおそる上司たちの様子を窺った。
間宮は仏頂面で椅子にもたれかかっている。草薙は腕組みをして天井を睨んでいた。ほかの先輩刑事たちの殆どは呆然としていた。
「と、いうわけなんですけど」薫はいってみた。
「草薙」間宮が口を開いた。「おまえがガリレオ先生に頼んだのか」
「俺は紹介状を書いただけです」
「ふうん」間宮は頬杖をついた。「だけどさあ、岡崎がそういうふうにやったという証拠はないんだろ」
「ありません。でも、こういう方法が存在する以上、岡崎をシロだと断定する理由もなくなったわけです」薫はいった。
「そんなことはいわれなくてもわかってるんだよ」間宮は吐き捨てた後、部下たちを見回した。「このまま打ち合わせに入る。捜査の軌道修正だ」
草薙が薫を見て、小さく親指を立てた。
8
ドアを開けると白衣姿の背中が見えた。試験管に入れた透明の液体を、下からアルコールランプで加熱し、その模様をビデオカメラで撮影している。
「危ないから、それ以上は近づくな」湯川が向こうをむいたままでいった。
「何をやってるんだ」草薙は訊いた。
「ちょっとした爆発実験だ」
「爆発?」
湯川が試験管から離れ、そばのモニターを指差した。
「そこに数字が出ているだろ。試験管内の液体の温度を示したものだ」
「九十五、となってるな。おっ、九十六に上がった」
数字はさらに上がっていく。ついには百を超え、百五に達した時、試験管から突然液体が噴き出した。その
「百五度か。大体予想通りだな」湯川は試験管に近づき、アルコールランプの火を消した。それからようやく草薙のほうを向いた。「試験管の中の液体は何だと思う?」
「俺にわかるわけがないだろ」
「見たままをいえばいい」
「見たままって、俺にはふつうの水にしか見えないけど」
「そのとおり、ふつうの水だ」湯川は雑巾で濡れた机の上を拭き始めた。「ただし、イオン交換で作った超純水だけどな。通常、水は百度で沸騰する。だけど突然起きるのではなく、まず小さな気泡が発生し、続いて大きな気泡が現れるという段階を踏む。ところが条件を整えてやると、そうした段階を踏まずに沸騰が起きることがある。その場合、沸点であるはずの百度ではなく、それ以上の温度になって突然爆発する。
草薙は苦笑し、部屋を見回した。
「おまえのそういう講釈を聞くのも久しぶりだな。この研究室も何だか懐かしい」
「君がここで何か研究したかな」
「実験なら何度も見せてもらったぜ」そういって草薙は提げていた紙袋から細長い箱を取り出し、そばの机に置いた。
「なんだい、それは」
「赤ワインだ。詳しいことはわからんが、店員に勧められた」
「君が土産を持ってくるとは珍しいな」
「礼だよ。うちの後輩が世話になった」
「別に大したことはしていない。簡単な物理実験をしただけだ」
「そのおかげで事件が解決したんだから、やっぱり礼をいっておきたいと思ってさ。ただし、ひとつだけ残念な知らせがある」
「当ててみようか」湯川は白衣を脱ぎ、椅子の背もたれにかけた。「あの謎解きは違ってたんだろ」
草薙は友人の顔を見返した。「知ってるのか」
「いや、僕自身、あれが真相だとは最初から思っていない。僕はただ、あの部屋にあるものだけを使って死体を落とす時限装置が作れるかどうか、という問題に挑んだだけだ。君は今、残念な知らせだといったが、僕にとっては残念でも何でもない。どうでもいいことだ。あの女性刑事がどう思ったかは知らないがね」
「あいつは、少し残念そうだったかな」
「で、真相は?」
「自殺だった」
「やっぱりね。それしかないと思った」湯川は頷く。
「どういうことだ」
「まあ、インスタントコーヒーでも飲みながら話そう」
湯川が出してきたのは、相変わらずあまり奇麗とはいえないマグカップだった。草薙は苦笑しながらコーヒーを啜った。
「岡崎が江島千夏の恋人だったという証拠を揃えるのは、かなり大変だった。決め手になったのは、江島千夏が持っていた一枚のカードだ。調べたところ、千葉にあるラブホテルのカードだった。それに岡崎の指紋がついていた。岡崎によれば、ホテルのゴミ箱に捨てたつもりだったらしいが、江島千夏がこっそりと回収していたようだ」
「どうしてそんなことを?」湯川が不思議そうに訊く。
「わかりきったことだ。そのカードがあれば、次にそのホテルを使う時、割引がきくんだ」
「なるほど。それで、岡崎君は観念したわけか」
「いや、付き合っていたことは認めたが、事件への関与は否定した。被害者が転落するところを目撃したんだから、自分には犯行は不可能だ――それを主張した」
「それで君たちは?」
「反則だと思ったけど、例のビデオを見せた。おまえが熱演している、あの実験ビデオだ」
「岡崎君、びっくりしてただろ」
「目を丸くしてたよ」その時の岡崎光也の顔を思い出すと、草薙は今でも噴き出しそうになる。「こんな方法があるなんて知らなかった、自分はこんなことしてないって、かなり焦ってた。それで白状したわけだ。殴ったことは認めるってな」
「あのステンレス鍋でか」
草薙は頷いた。
「岡崎には女房も子供もいる。江島千夏とは遊びのつもりで付き合っていたが、彼女のほうが本気になってしまったようだ。岡崎によれば、そんな約束をしたつもりはないんだが、いつの間にか江島千夏は、岡崎は離婚して自分と結婚してくれると思い込んでいたというんだな。まあ、死人に口なし、本当のところはわからん。とにかくあの夜、岡崎は別れ話をしに行った。ところがそれを聞いて江島千夏は逆上した。これから岡崎の家に電話をかけるといいだした」
「それで今度は岡崎のほうが逆上したというわけか」
「本人によれば、無我夢中で詳しいことは覚えていないそうだ。倒れた彼女を見て、死んだと思い込み、逃げ出すことしか考えられなかったらしい。マンションを出て、あの転落事件に出くわしたわけだが、落ちたのがまさか江島千夏だとは夢にも思わなかったそうだ。ところが翌日のニュースでそれを知り、奴は事情を理解した。彼女は殴られた時点では死んでいなくて、その後、自分で飛び降りたんだとね」
「たまたまピザ屋にからまれてたことから、自分には鉄壁のアリバイがあると思い直し、わざわざ警察に名乗り出たというわけか」
「ま、そういうことだ」
「なるほどねえ」湯川はにやにやしながらコーヒーを飲んでいる。
「傷害で起訴することになりそうだ。殺人では無理だ。あのトリックを使ったという証拠はないしな」
「あのトリックは」湯川はコーヒーを飲み干し、マグカップをふらふらと振った。「あれは無理だ。実行不可能だ」
草薙は少しのけぞり、友人の顔を見返した。
「そうなのか。だけど、ビデオじゃ……」
「たしかにあのビデオでは成功している。でも、あれを撮影するのに、どれぐらい苦労したと思う? 十回以上は失敗したんじゃなかったかな」湯川はくすくす笑い始めた。「掃除機のコードがうまく戻らなかったり、鍋の蓋が簡単に外れたり、とにかく失敗の連続だった。内海君だったかな。彼女、よく辛抱強く付き合ってくれたよ」
「あいつ、そんなこと一言もいわなかったぞ」
「そりゃあそうだ。いう必要がない。うまくいったケースだけを誇張して発表する。科学者の世界では、それは常識なんだ」
「あいつめ……」
「いいじゃないか。おかげで事件が解決したんだ。彼女はいい刑事になるよ。僕も久しぶりに面白い経験をした」
「面白い? じゃあ、これからも……」
草薙がいいかけると、それ以上はしゃべるな、とでもいうように湯川は立てた人差し指を自分の唇に触れさせた。そしてにっこり笑い、その指を左右に振った。
-
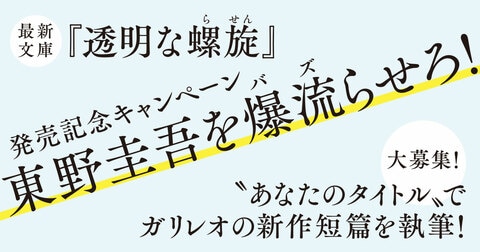
あなたの“タイトル”で東野圭吾がガリレオの短篇を執筆!「東野圭吾を爆流(バズ)らせろ!」キャンペーン開催。
2024.08.07ニュース -

東野圭吾さん『透明な螺旋(らせん)』がついに文庫に! 世界で愛され続けるガリレオシリーズ
-

国内1億部突破の東野圭吾さんを支える先輩作家の言葉。そして福山雅治さんが考える、東野作品が「読者に愛される」理由とは?
-

【結果発表!】ガリレオシリーズ『透明な螺旋』&最新文庫『沈黙のパレード』発売記念キャンペーン、「二次創作」の最優秀作品を東野圭吾さんが決定!
-

なぜ湯川はインスタントコーヒーを偏愛するのか? ガリレオシリーズとインスタントコーヒーの特別な関係
-
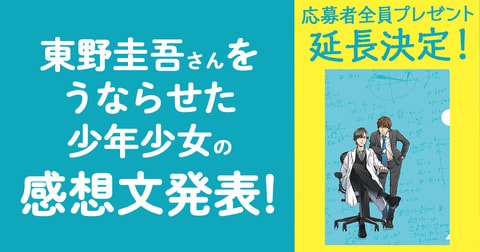
ガリレオ・ジュニア版『ガリレオの事件簿』に寄せられた感想文を発表! ベストセラー作家・東野圭吾の心を動かした、少年少女の言葉とは!
-
『赤毛のアン論』松本侑子・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2024/11/20~2024/11/28 賞品 『赤毛のアン論』松本侑子・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。