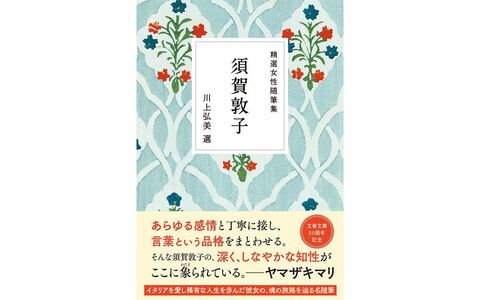ずっしりと持ち重りする、苦みも甘みも凝縮された石井好子(一九二二―二〇一〇)の文章が本書には編まれている。その新鮮な驚きは、たとえば舞台に立つすがたに別の角度から、または異なる色合いのスポットライトが当たったとき、思いもかけず現れた佇まいにこころを摑まれたときの高鳴りにも似ている。
石井好子の文章を広く世に知らしめたのは、一九六三年に暮しの手帖社から刊行された『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』である。花森安治のすすめに応えて「暮しの手帖」に二年間執筆したエッセイをまとめた一冊で、舶来の料理の味わいや香りを自由闊達に描きだす筆致はたちまち読者を魅了、はるか彼方の日本の空の下まで香ばしいオムレツのにおいが伝わってくるかのようだった。遠い外国の食卓が、それこそ隣の家のドアを開けるとすぐそこに。そんな日常的な親近感を抱かせたのである。素朴な発見や感動を書きながらも、けれん味がなく、自慢や自己顕示とも無縁の文章を読むとき、わたしたちは食卓で、台所で、むじゃきな笑顔を向けられたうれしさを受け取る。ただし、思わずつばを飲みこむバターたっぷりのオムレツ、ニース風サラダ、ポトフ、グラティネ、ヴィシソワーズ……かずかずの描写の背景には、独自の観察眼や分析がたっぷりと注ぎこまれている。そのおおもとは石井好子が自分自身に水をやり、みずから育ててきた意志、精神力。
『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』以前、はじめての著作は五五年、パリの下町暮らしの裏側を書いた『女ひとりの巴里ぐらし』である。その袖文を書いた三島由紀夫はこう表している。
好子さんは自分のことを書くと、心のやさしい普通のお嬢さんにすぎないが、人のことを書くと、自分でも「意地悪」と言ってるやうに、すばらしい描写の才を発揮する。
本書のなかにも三島由紀夫との交流について触れたくだり(「懐しき人びと」)があるが、三島由紀夫をして「すばらしい描写の才」といわしめた石井好子の随筆は、読めば読むほど人生を生き抜く強靭な意志と精神によって培われたものだという感が強くなる。なにしろ、日本がまだ貧しく、海外旅行など夢のまた夢の時代にたったひとりでアメリカに渡って留学に出たのだから。父の石井光次郎は大臣や衆議院議長を歴任した政治家で、恵まれた家庭に育ったが、自分の環境に甘えるということがまるでなかった。それどころか、険しいほうへ、険しいほうへ、娘が選ぶ道はつねに自分を追いこむものだった。
「第一部 アメリカでの私」に書き記された十代から二十代までの軌跡には、きびしさを自分に課して人生のコマを進めてゆく様子がはっきりと見てとれる。歌を歌うのがすきなこどもだったから、志望した東京音楽学校(現・東京藝術大学)に入学してドイツ歌曲を専門にした。しかしほどなくドイツ歌曲の奥深さに打ちのめされ、戦局の悪化や、二十一歳のとき結婚した夫がポピュラー音楽に関わっていたことなどにも影響され、一転ポピュラー音楽歌手、しかもジャズ歌手へ。しかし、結婚にもジャズ歌手にも破綻が生じた。文中で「自分は何になりたいのかもよくわからなかった」と吐露しているが、そのタイミングで「外国へ行きたかった」という願いをなにがなんでも実現させるところに意気地の強さ、大胆さがあらわれている。終戦のわずか五年後、単身渡米。二年におよぶ留学生活は、学校へ通いながらバレエやミュージカル、オペラの舞台を鑑賞し、ダンスや発声法のレッスンを受け、食べるものを倹約してでも夢に向かって邁進する日々だった。ところが、それでも自分に満足がいかなかった。日本へ帰れば「アメリカ帰り」というだけで箔がつくことは容易に想像できたし、別れた夫と近い場所にいれば、またぞろお互い傷つく。こうして本場でシャンソンを聴くという理由を見つけ、石井好子は自分で自分の手を引いて運命の土地へ導かれてゆく。
「第二部 パリでの私」に収録された四編の情感の豊かさはどうだろう。「舞台裏の女たち」では、一年間の契約をむすんで主役をつとめた「ナチュリスト」での人間模様が活写され、読みながら喧しい楽屋裏に紛れこんだような軽い興奮さえ味わう。モンマルトルの盛り場、ピガール広場一番地。あたりはキャバレー、カフェ、ホテルがひしめき合う不夜城だったという。そのまっただなかで日本人の若い歌手がロングランの主役を張るのだから、並大抵の努力では務まらなかっただろう。なのに、「舞台裏の女たち」をはじめ当時を綴った文章は自分の苦労話などあっさりとしたもの、もっぱら周囲のひとびとの描写に費やされる。「パリで一番のお尻」など、パリの風俗を浮き彫りにしながら女の人生の悲哀を描いて一級の随筆だ。「お金のために、いやな男にしばられてんの」とこぼす女給のイルダにせがまれて歌うシャンソン「泣くなネリー」。こうして生身のどん底の暮らしにじかに触れることで、石井好子のシャンソンに磨きがかかっていったのは言うまでもない。「懐しき人びと」に登場するのは、三百六十五日休みなくつづくレビューの日々のなか、出会ったひとびとのこと。過酷な夜の二回公演を支えたのは、アパルトマンで同居生活を送った朝吹登水子。多才な俳優マルセル・ムルージとの想い出。パリを訪れた三島由紀夫、今日出海、小林秀雄、毎日新聞支局長板倉進、そしておたがいに励まし合った歌手仲間の越路吹雪。ひとりひとりについてはみじかい文章なのに、人生の一瞬の交差が驚くほどの陰影をともなって心にふかく刻まれる。
パリ時代を語る極めつきともいうべき一編は、「千年生きることができなかったアルベルト・ジャコメッティ」だろう。わたしは、何度読み直しても温もりとともにあてどない寂しさを味わう。すさまじいほど仕事に没頭していたジャコメッティは、こんなふうに描写されている。
「私は何となく彼の気魄に押され始めていた。仕事のことしか頭にない。仕事の中でしか生きられない苦痛にみちた彫りの深い顔が美しく見え出していた」
年若い妻アネット、モデルを務めていた矢内原伊作、その三人の横にいつも自分がいたと述懐しながら描く、交錯した感情。そして、ジャコメッティから身をもって教わった純粋な芸術性は、その無類の生きかたとともに、歌手人生を全うするうえで生涯の指針となった。
「第三部 母たちのこと」には、日本での心象が綴られる。パリから帰国したのは五八年、三十六歳のときだった。その四年後、相手の離婚が成立するのを待ちつづけて新聞記者・土居通夫と再婚。シャンソン歌手のかたわら、みずからの事務所を設立、後進の育成や外国からのアーティストの招聘、レストラン「メゾン・ド・フランス」経営、日本シャンソン協会の設立、チャリティ活動、やっぱり自分で自分の道を切り拓かずにはいられない女性だった。そして八〇年、五十八歳のとき夫が急死――。「我が家の土鍋」は、夫を亡くしたあとしまいこんでいた土鍋にまつわる記憶がほろ苦い。歌手ジョセフィン・ベーカーとエリザベス・サンダース・ホーム園長、沢田美喜との交友にまつわる「母たることは」には、なにかにつけて面倒見のよかった石井好子の母性が行間から滲んでおり、料理やパリを語るときの筆致とは異なる痛切が伝わってきて胸を衝かれる。
こうして石井好子が辿ってきた道をあらためて振り返って気づくのは、「ボンジュール」「こんにちは」とおなじ数だけ「オルヴォワール」「さよなら」があったということ。悲哀にたっぷりと身を浸したひとだから、そのぶん勇気をふるって人生を謳歌した。だからこそ、おしまいの一編「グッドラック」、かすれた声で発せられた母の最後の言葉が重いものとして輝く。石井好子はずっと、グッドラックの言葉に守られて生きたのだ。