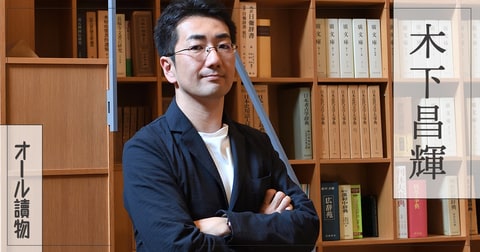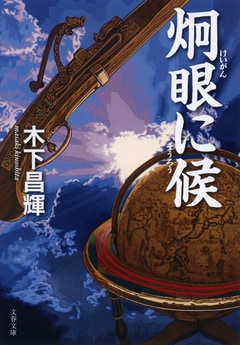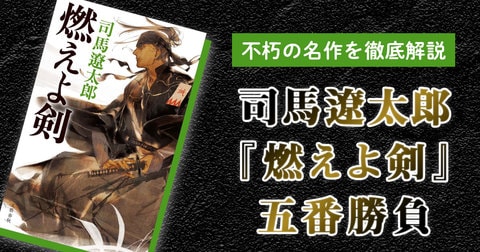時は大坂の陣の前夜。大御所・徳川家康を呪詛した“呪い首”が街道で発見される。生首を一級用意し、骸からくり抜いた目に諱を刻み、左右の眼球を入れ替えてはめ込むことで、彼岸と此岸のあわいにある呪い首となる――それが「五霊鬼の呪い」。諱を刻まれた者は二年の内に呪い殺されるという。
一方、かつて無敵を誇った宮本武蔵は、戦国の気風が急速に失われ、太平の世が近づく中、その峻厳すぎる剣はもはや時代遅れだと感じていた。呪詛者の探索の依頼を固辞した武蔵だったが、唯一人、自分の剣を慕い続け、「円明流を託してほしい」と願い出た弟子が殺される。その事件が「五霊鬼の呪い」とつながった時、武蔵は正体不明の呪詛者を追うことを決意する。徳川家康を呪ったのは、いったい誰なのか――?
歴史小説の第一線を走り続け、常に新しい挑戦を続ける著者が放つ本作は、ミステリーとしても第一級。物語の推進力になる「謎」が、二転三転どころか七転八転、どんでん返しの連続……! 「ページを捲る手が止まらない」とはこういうことか、と思いました。
色彩、匂い、決闘の息づかいから土埃までが圧倒的なスケールで迫ってきて、『魔界転生』の雰囲気で深作欣二に撮ってもらったらカッコいいな、いや、『キル・ビル』の乾いた雰囲気でタランティーノもいいかな……と妄想が止まりませんでした。自分も選考委員の一人として参加した第12回「本屋が選ぶ時代小説大賞」で『孤剣の涯て』が大賞を受賞したのはご存じの通りです。
木下さんのデビュー作『宇喜多の捨て嫁』を読んだ時、すごい人が出てきた、と舌を巻きました。戦国の梟雄・宇喜多直家の英雄譚ですが、残酷なのに美しく、格調高い。いきなり直木賞にノミネートされたことでも話題になりましたが、木下さんにしか書けない作品の虜になり、自分の勤務する書店一店舗だけで約1300冊を売り上げました。そこから木下作品を追い続けています。
木下さんは、作品ごとにコンセプトや作風をガラリと変える作家でもあります。本作はエンターテインメント色の強い作品でありながら、玄人筋を唸らせる仕掛けが随所に散りばめられています。生涯、妻帯しなかった武蔵が「三木之助」という名の少年を養子に取っていることもそうですが、僕が注目したのは、本作の悪役、坂崎直盛が失態を犯した部下に紙の陣羽織を着せるシーンです。その紙羽織には異様な文言が墨書されています。「この人身さぐりの上手、家中にはいやな人」、つまり「逃げることばかり上手く、不要の人」と蔑んでいるのです。このような逸話はこれまで聞いたことがありませんでしたし、探してみてもそうした記述は見つかりませんでした。
しかし、実は、江戸時代、山鹿素行によって書かれた歴史書『武家事紀』に、まさにこうした記述があったというのです! 木下昌輝、恐るべし……奇想天外なストーリーの裏には、緻密に原典にあたる気の遠くなるような作業があり、それが物語に厚みやリアリティを与えているのです。このエピソード一つとっても、おそらく、小説では本邦初公開ではないでしょうか。
さらに、このシーンがひどくエロティックに僕には思えたのです。もしかしたら、この時、直盛はサディスティックな性的興奮を覚えていたのではないか? 直盛は悲惨な生い立ちで、愛する従姉を守れなかったという深い心の傷を抱えています。そこから、性的な倒錯を抱えてしまったのではないか、という思いに囚われました。直盛が奇声を上げながら剣を振るうシーンを「赤子を失った母の絶叫を思わせる」と書くセンスも抜群に良くて、感動してしまいます。
木下作品の悪役は、悪いやつほど魅力的なんです。『宇喜多の捨て嫁』の「ぐひんの鼻」も名作中の名作ですが、浦上宗景にも同じような歪みや、その底にある哀しみを感じました。嗜虐心にとり憑かれながら、どこか滑稽で、思わず情が湧いてしまうような悪役を描けるのは、木下さんにしかない類稀なる才能だと思っています。
木下作品には山田風太郎のような伝奇小説的な空気感と、昔の日活映画のような濃厚なエロティシズムが漂い、陰惨な場面も容赦なく描写されます。それと同時に、独特の「乾いた味わい」も存在する。これは、メタ視点で歴史を俯瞰しているからでもあり、木下さんの気質でもあると思いますね。
そもそも、本作は「呪い」がテーマでありながら、当の武蔵は呪いなど信じていないのです。本当に恐いものは、別のところにある。木下さんは、インタビューで、本作を執筆するきっかけについてこう語っています。皆、巌流島での武蔵は知っているけれど、そのあとの武蔵を知らない。実は、60回以上の決闘にすべて勝利した武蔵は、非常に現代的な、当時の風潮に抗うような考えを持つようになったというのです。当時は殉死の風潮があったのですが、武蔵は「死を肯定するのは間違っている」というようなことを言っていた。60回も決闘した武蔵が、なぜこんな現代的な人間に変わったのだろうか。そこに何かがあるように感じたことが、『孤剣の涯て』執筆の出発点だった、と。
呪いの謎を解く、血沸き肉躍る活劇で読者を魅了しつつ、「滅ぶことが決まっているのに、人は何かを生み出さずにはいられない」という人間の性や、無常の定めに抗おうとする者たちの姿を、木下さんは静かに見つめ続けています。
読んでいて、思わず背筋がゾクッとしたのが、合戦の最中の「味方崩れ」の場面です。前線で戦い、狂乱の様相で撤退してくる味方を、弓矢で射殺する非情な行為が繰り広げられますが、こうした戦場のリアリズム――史実を丹念に調べ上げる骨太さと、伝奇小説的なファンタジーの色彩が両立している、これこそが木下作品の真骨頂だと思いました。
本作のテーマにも、現代に通ずるリアリズムが込められています。戦国武将が華々しく活躍する時代が終わり、剣よりも鉄砲が力を持ち、徳川を頂点とする武家支配の構図が確立された。その流れについていけない武蔵の葛藤や、禁じられた女傾奇の無念は、現代を生きる私たちにも常に突きつけられるものではないでしょうか。
今、織田信長や坂本龍馬は、昔ほど人気が無いように感じています。楽天的に未来を信じられず、サクセスストーリーに読者が鼻白んでしまう時代には、木下さんの描く、線香花火のような、脆弱な存在だけれども、刹那の鮮烈な閃光を放って消えてゆくような登場人物たちこそ、共感を呼ぶのではないかと思っています。