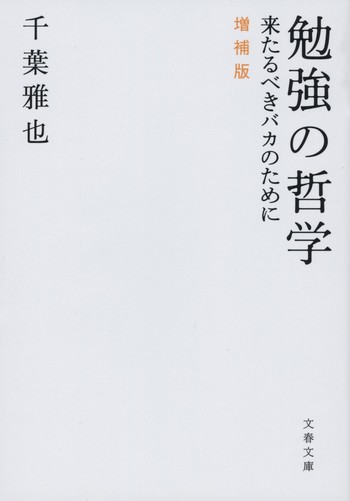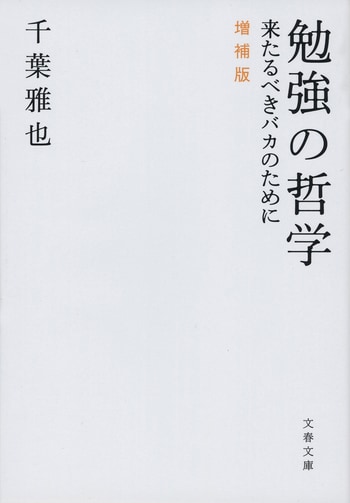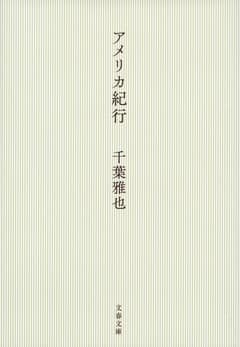〈「見上げるように見ていた千葉くん」(濱口竜介)、「濱口監督も宇高文化圏の一部」(千葉雅也) 旧知の二人が「見ること」「作ること」を語り合う〉から続く
音楽、絵画、小説、映画など芸術的諸ジャンルを横断して「センスとは何か」を考える、哲学者の千葉雅也さんによる『センスの哲学』。「見ること」「作ること」を分析した芸術入門の一冊でもあり、『勉強の哲学』『現代思想入門』に続く哲学三部作を締めくくる本書は、2024年4月の発売以来、累計55000部のベストセラーに。
『寝ても覚めても』『ドライブ・マイ・カー』などの監督作で知られ、話題の最新作『悪は存在しない』に続き、映画論『他なる映画と』全2冊を出版した濱口竜介監督との対談が実現。大学時代からの旧知の仲でもあるというふたりの待望の初対談は、「鑑賞と制作」(見ることと作ること)の深みへと展開した。「文學界」(2024年9月号)より一部抜粋してお届けします。(最初から読む)
“実用的な哲学”というスタイルができるまで
濱口 気が付けば25年以上、四半世紀以上知っている千葉雅也さんが、『勉強の哲学』以降、ある種の展開を遂げるわけじゃないですか。いま振り返ると、どういうことなんでしょう? 小説も書き始めて哲学者と同じかそれ以上に、創作者になる道が開けてきたタイミングでもあると思うんですけど、それは書いたものに影響してるんですか。
千葉 『センスの哲学』に関して言うと、芸術について書くには随分時間がかかりました。こういう本は、20代で書くのは無理だった。もっと細かく書こうとしちゃったと思うんです。だからざっくり、しかも実用的に書く覚悟、あるいは『現代思想入門』では一種の「諦め」だと書いてますけど、自分が分かっている範囲はこれぐらいだということ。それを伝えられるように伝えよう、と。もちろん自分も研究者として新しいことを考えているので、そういう学問的な部分も盛り込む。例えば、今回は精神分析と神経科学を接続することを、さりげなくやっている。そういうことも含めて、実用的に伝えるというのが、自分のスタイルになってきました。


1978年生まれ。東京大学教養学部卒業。パリ第10大学および高等師範学校を経て、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(第4回紀伊國屋じんぶん大賞、第5回表象文化論学会賞)、『勉強の哲学――来たるべきバカのために』、『アメリカ紀行』、『デッドライン』(第41回野間文芸新人賞)、「マジックミラー」(第45回川端康成文学賞、『オーバーヒート』所収)、『現代思想入門』(新書大賞2023)など著書多数。
濱口 哲学者である自分が、実用的なことを考えるというのは、どうなんですか。
千葉 哲学は、いろいろあっていいと思うんです。議論を効率良く展開するというのは近代的なモデルですが、歴史を見ると、いろんなやり方がある。ソクラテスは人に働き掛けて喋ってるし、ルソーやドゥニ・ディドロはいろんなジャンルのものを書いている。哲学的な思考には、共通して抽象性があるわけですが、それでもってどういうふうにコミュニケーションを取るかは、もっと各自にいろんなやり方が考えられるんじゃないのかなと思っています。
「何かエフェクトを起こすことに関心がある」
濱口 勝手な僕の想像ですけど、哲学がどこか社会から切り離されてしまっているという、ある種の危機感はあるのかなと思いました。これだけ分かりやすく、かみ砕いてくれるというのは、千葉くんがどこかそういうものを請け負ったというか、自分が切れかかってる線を繋ぐんだと思ってやっているような気がして、それがすごく感動的です。

千葉 そうね、昔みたいに小難しそうな書き方はしなくなりました。またやるかもしれないけど。いまは実用というか、もっと面白い生活の捉え方があるとか、何かエフェクトを起こすことに関心があるんです。
濱口 この文章自体が実用的というか、要するに直接的に読んだ人に働き掛け、人を変えていくところがあると思います。さっき、これを読んでいるときはちょっと頭が良くなっているような気がする、ということを言いましたけど、一回読み通して、でもメモを取らなかったので、頭が良くなったような気がしたけど、実は全然そうではない。覚えてないから、もう一回ちゃんと読む。でも、そうやって変わっていくんですよね。何かが分かりかけたような感覚があって、その分かりかけた感覚を確かなものにしたくて何度も読む。確かにこの文章を読むと、ある種の変化が生じるっていう、そういう文章になっている気がします。
「芸術映画」と俗な趣味との奇妙な混合
千葉 ハマの場合は自分の映画を見た体験を通して、どういうことが起きてほしいとか、何か期待してることがありますか。
濱口 自分は大学に入って知的環境が変化したことに、十分付いていけなかった。田舎じゃないけど千葉県の高校にいて、それまでは受験勉強みたいなことをずっとやってるわけですよね。教養はほぼないっていう中で、当時周囲にいた人たちは千葉君だけじゃなくて、大学の先生とか文筆家になったりする人たち。そういう環境の中に急に入ったので、自分は全然何も知らないんだなっていうのがスタートだった。映画もちょこちょこ見てるつもりだったけど、全然見てないと気づく。そういう自分が、だんだん変わっていく。実際、映画を見て、よく分からないけどいいじゃないかっていうことがたくさんあって。
千葉 かつては反応できなかったものに。
濱口 徐々に反応できるようになっていった。でも、基本的には自分の10代は、トレンディードラマを見たり、テレビゲームをやったり、マンガを読んだり、そんなところからできているわけです。急にはできなかったけれども、そういうものとだんだんと接続できるようになってきている。シネフィルたちが好むような芸術映画じゃないけど、でも、これぞ映画であるっていうものと、自分が俗な趣味として持っていたものというものが、奇妙な混合を果たすようになっていく。
千葉 なるほど、混合しているんですね。
濱口 完全に切り替えることはできないから、だんだん混合していく。でも、そこにはある種、諦めがあるんです。自分にはこういうものしか撮れない。映画は本質的に視覚芸術で、視覚から発想するのが望ましいとは思っても、セリフを書くことのほうが得意だった。得意だったというか、そういうふうにしか発想が出てこなかった。だから、どんどんそっちに逃げちゃう。逃げちゃうというか、そっちに力が逃げていく。
濱口流映画制作――対話から生まれる
千葉 ここで、作り方の話を聞いてみたいと思います。映画は脚本、プロットがあると考えると、それは散文じゃないですか。だけど、どういう画が欲しいとかはあるでしょう。あと、音がある。なので、どうやって作っていくのかなと思うんです。僕が小説を書くときは、言葉なわけです。最初はメモ。僕はアウトライン・プロセッサを使うことも多くて、写真資料とかはそんなに使わない。だけど、今、セリフを書くのが得意って言ったじゃないですか。だとしたら基本は文章、しかもセリフからなんですか?
濱口 そうだと思います。誰かと誰かが話している情景は、思いつくことができる。
千葉 会話なの?
濱口 そう。誰か一人が滔々と喋るというよりも、誰かと誰かが喋っていて、話すにつれて何かが発展していくというのは、書けた。視覚的には全く面白くない可能性があるけれども、ただ、そこには話す人が確かにいる。実生活でも単純にそこに人がいて何かをしていて、それをカメラで撮っていれば、映画には一応なるわけですよね。大学時代に友人たちと出会って、言葉の力を知るわけです。
そういう友人たちと話しているときに、今ここにカメラがあってくれたら、特にスペクタクルのないファミレスの深夜だけど、きっと強度のある映画になるに違いない、という気持ちになる体験をたくさんした。それでもう自分はこれしかできないんだから、これでやっていこうと。
今にして思えば会話を書いているのは、結局のところ、話者の身体を想像しているということで、まったく視覚的ではない、というわけではなかったとも思う。そうして話者の「身体」を撮るのにシフトをしていく。そういうふうにだんだんと変わりながら映画を作っていった自分がいるので、これぞ映画であるような映画と、そうでないものの架け橋になったらいいなとは思っているかな。と言ったけど、別に狙ってそうできるものでもなくて、『勉強の哲学』には「身体がついやってしまう」享楽について書かれていますけど、自分はそういうふうにしかつくれないのだから、それを楽しんでくれる人がいたらラッキーと思ってやっている感じです。