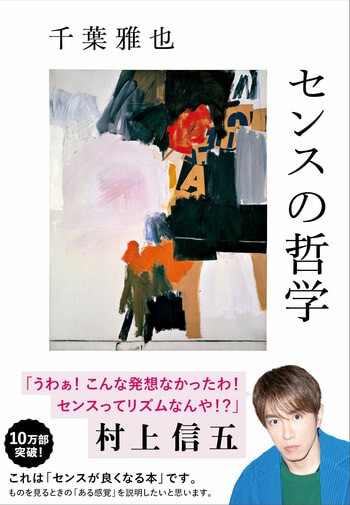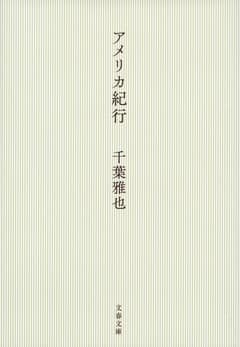『勉強の哲学』、『現代思想入門』から続く哲学三部作を締めくくる、千葉雅也氏の新著『センスの哲学』が話題になっています。センスを良くするにはどうすればいいのか? そもそもセンスとは? 『センスの哲学』から「はじめに」をお届けします。
◆◆◆
はじめに 「センス」という言葉
「センスがいい」というのは、ちょっとドキッとする言い方だと思うんです。なにか自分の体質を言われてるみたいな、努力ではどうにもできないという感じがしないでしょうか。
でも、世間では、けっこう気軽にセンスという言葉が使われているようです。
センスがいい悪いというのは、いろんなことについて言われます。服のセンスとか、ご飯を食べに行くときのお店のセンスのような、日常生活での「選ぶセンス」もある。絵がわかるとか音楽がわかるといった「芸術のセンス」もあります。「会話のセンスがいい」とか、仕事をしていて、「あの人は考え方のセンスがいい」といった使い方もある。
センスというのは、いろんな対象やジャンルについて言われるわけです。だから、「センスがいい」、「センスが悪い」と言われると、ひとつのことだけでなく、自分が丸ごと評価されているみたいで、ドキッとするんだと思います。
さて、実は、この本は「センスが良くなる本」です。
と言うと、そんなバカな、「お前にセンスがわかるのか」と非難が飛んでくるんじゃないかと思うんですが……ひとまず、そう言ってみましょう。
「センスが良くなる」というのは、まあ、ハッタリだと思ってください。この本によって、皆さんが期待されている意味で「センスが良くなる」かどうかは、わかりません。ただ、ものを見るときの「ある感覚」が伝わってほしいと希望しています。
自己紹介をすると、僕は、哲学が専門なのですが、芸術・文化と結びつけながら哲学を研究してきました。文系の研究者ですが、芸術作品を作ってきた経験もあります。
もともと中学時代には美大に進もうと思っていて、絵を描いたり、立体の作品を作ったり、ピアノも弾いていましたが、高校のときに文章を書くことに興味が移っていき、現在の専門に至っています。二〇一九年からは小説も書き始めました。肩書きとしては、「哲学者・作家」です。最近では、十代の頃に戻るようにして、美術制作も再開しています。
そういう経緯で、一応、物作りのノウハウをある程度持っているつもりで、それと哲学を組み合わせたらどうなるか、ということで本を書きたいと思っていました。
この本は、一種の「芸術論」だと言えます。ただ、狭い意味での芸術(美術、音楽、文学など)だけではありません。芸術を、生活とつなげて説明します。
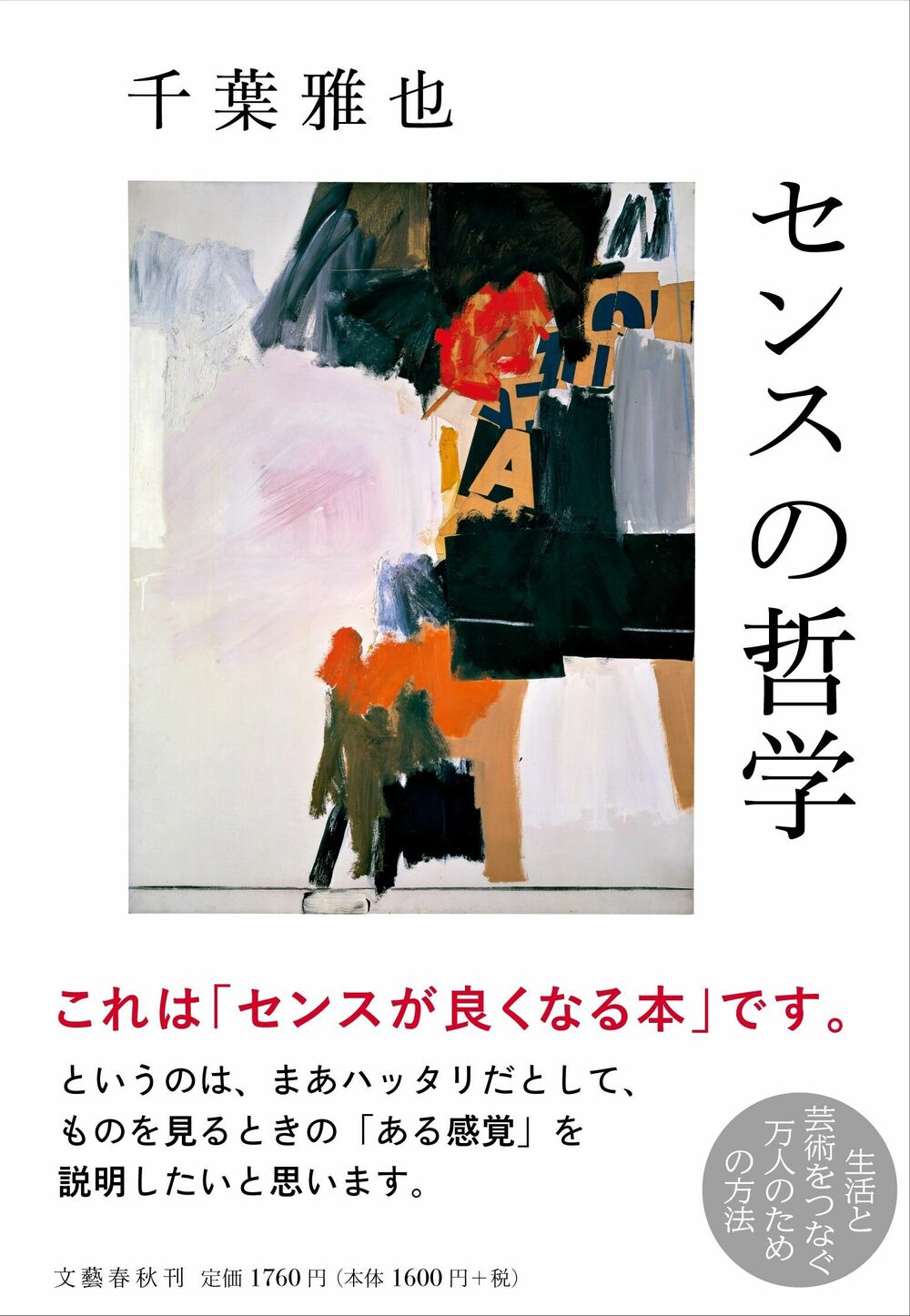
本書の狙いは、芸術と生活をつなげる感覚を伝えることです。
いわば、広い意味での「芸術感覚」がテーマで、それをどう呼ぶかと考えたとき、まず浮かんだのが「センス」でした。センスというのは、冒頭で言ったように、どこかトゲのある言葉だと思いますが、それも含めて考察してみたいわけです。
芸術といっても異なるジャンルがあり、普通は別々に語られることが多いでしょう。それでも、美術や音楽、文学などを行き来してきた経験から、「こういう共通の話ができるな」という実感を僕は持っています。それは経験的な勘ですが、それを哲学や芸術論などと照らし合わせて、ある説明の仕方ができてきました。
この本は、自分の経験から出てきた理論ですが、専門的な議論もふまえています。しかし、専門的に細かいことには、踏み込みすぎないようにしたいと思います。なにより、読みやすく、役に立つ本であってほしいからです(エビデンスというとちょっと強いですが、何を根拠に言っているのかというのは、途中で示していきます。参考文献も挙げたいと思います)。
この本では、いったんセンスが良くなる方向を目指します。
しかし、センスとは何なのか?
センスとは何か、センスの良し悪しとはどういうことかを、いろんな角度から考えて定義していきます。一気に定義するのではなく、段階的に行います。それはあくまでも、「この本では」という仮の定義であり、ひとつの参考になれば、というものだと思ってください。
そして、先取りして言うと、最終的には、センスの良し悪しの「向こう側」にまで向かっていくことになります。ある意味、センスなどもはやどうでもよくなるところまで、です。最終的にそれを「アンチセンス」と呼ぶことになります。本書が進むにつれて、アンチセンスをどう考えるかという問題が、だんだん浮上してくるでしょう。
僕の『勉強の哲学』(二〇一七年)と『現代思想入門』(二〇二二年)の言い方を使うなら、センスとは何かを「仮固定」した上で、その「脱構築」へ向かうことになります。
この本は、センスという言葉の、よくある使い方から出発します。
実は、センスというのは、芸術論や美学の用語と言えるかは微妙なところです。専門的に言うと、「センスについて研究する」というのは……うーん、ちょっと怪しい話に見えるかもしれません。大学で研究するなら、「センスとはこうである」と、真正面から定義することは難しいでしょう。でも、次のように問題を立てるのなら可能だと思います。
「センスという曖昧な言葉で言われているのは、どういうことなのか」
これは、「言葉の使われ方の分析」です。センスとは何か、と真正面から答えを求めているのではない。センスという言葉の「用例」を分析するわけです。
この本でも、「センスってこんなふうに使われますよね」という用例から始めたわけです。
そして、手堅い研究としては、「人々はこういう意味でセンスという言い方をしているようです」という、社会観察のような結論にとどめるのではないか。
センスとはこうだ、というストレートな定義は控えるわけです。
しかし、この本では、その禁を破るというか、蛮勇として、センスとはこうだというひとつの見方を提案することになります。
まあ、いま「禁を破る」なんて言いましたが、それも弱腰すぎる言い方で、概念って、やはり誰かが勇気を出して定義するしかないじゃないですか、とも言える。難しいですね。
理論を新たに立ち上げようとするなら、自分なりに片寄った話をせざるをえません。ゆえに、責任が生じます。哲学でも、芸術論でも社会学でも、誰かが勇気を出して何かを定義したことが発端となって、その後の議論が続いているわけです。
というわけで、センスという曖昧な言葉を、僕なりに、概念として作り直すような試みをしてみたいんですね。それには勇気が必要です。

すいません、ややこしい話になりましたが、「センスの哲学」などと言うと、専門的に見て、いかがなものかと疑問が出てくるかもしれないので、一応の説明をしました。
話を戻しましょう。
センスという言葉には、トゲがあると思います。
つまり、どこか排他的に聞こえるところがある。「あの人、がんばってるけど、センス悪いんだよね」——というような。つまりそれは、努力ではどうしようもない部分を指していて、努力していてもそれを否定するようなニュアンスがあったりするわけです。
良くない言葉ですが、いわゆる「」に似ているところがあると思います。地頭とは、もとからの変えられないものとして言われる。僕はこういう言葉に警戒しています。なぜなら、努力による変化を認めず、多様性を尊重せず、人を振り分けようとする発想があるからです。
ですが、この本では、センスはどうにもならないものだとは考えません。
ひとまず、センスがいいと言われる「好ましい状態」があると仮定します。そして、センスなるものに、人を解放してくれるような意味を与えるように考察を進めていきたい。
人をより自由にしてくれるようなセンスを、楽しみながら育てることが可能である。というのが本書の立場です。
直観的にわかる
さて、センスというカタカナ語は、どういう言葉なのでしょうか。
和製英語みたいにも見えますが、そうではありません。もとの英語、senseという単語を辞書で引くと、カタカナでセンスと言うときの意味が載っています。「ユーモアのセンス sense of humor」とか、「服のセンス dress sense」といった例がそれに当たるでしょう。
こうした意味でのセンスとは、ある事柄について、「なんとなく、深く考えなくてもわかっている、わかってしまう」というような意味だと思います。
英語でのsenseについて、詳しくは、第一章で調べることにしましょう。ここでは、まず、次のように定義しておきます。
・最初の定義:センスとは、「直観的にわかる」ことである。
ここでの「直観的に」とは、「なんとなく、深く考えなくても」というのを言い換えたものです。キーワードは「直観」です。英語ではintuition(イントゥイション)と言いますが、これは、古くから問題にされてきた哲学の概念です。哲学の専門用語としては、直「観」と書きます。「直感」との違いは、まあ今回は気にしないでおきましょう。
辞書でsenseを引くと、基本的な語義として、「意味」、「感覚」、「判断力」などが並んでいます。それらに加えて、というか、それらを合成したような語義として、カタカナで「センス」と書いてある辞書もあります(この原稿はMacで書いていますが、Macの辞書アプリに入っている『ウィズダム英和辞典』には書いてあります)。
この話の続きは、第一章に送ることにします。
さて、センスとは「直観的にわかる」ことである、とします。
直観的に——というのは、いろんな含みがあります。ラフに言えば、ごちゃごちゃ考えないでわかる、ということです。もっと説明するなら、「順を追って推論していった結果わかるのではない」とか、「ディベート的に、ああでもないこうでもないと悩んで結論するのではない」などと言えそうです。
すなわち、「一挙に」、「全体的に」、「総合的に」わかることです。
スピード感も伴っています。「パッとわかる」わけです。なんとかわかろうと努めてわかるのではなく、「もうわかっている」というニュアンスもあります。などと言うと、そんなことできるか! とイライラの声が聞こえてきそうですが、でも、広い意味で「直観的」判断というのは普段からやっていることです。

家から一番近い駅に行く。十分慣れていれば、直観的に歩きます。どう行くかをごちゃごちゃ考えたりしません。カツカレーを食べる。食べ方を「順を追って推論」したりしません。
「りんご」と聞けば、どういう果物かわかります。頭の中で辞書を引いたりしません。人の話も、複雑になればいろいろ考えるわけですが、言われたことの基本的な意味はパッとわかっている。買い物をするときの簡単な足し算も、どういうわけか人間にはそれがパッとできる計算能力がある。
ここで、注意深い方は、「おや、違う話をまぜこぜにしてないか?」と思うかもしれません。
駅に迷わず行けるのは「慣れ」でしょう。「習慣」ですね。では、言葉の意味がわかるのもそうなのか。「りんご→この果物」という結びつけの習慣化なのか。その面は確実にあると思いますが、言語能力はもっと複雑なものだという学説もあります。数学の能力はどうでしょう。基本的な計算や図形の把握は、先天的にできるように思われます。
先ほどの例では、あとからの学習=習慣と、先天的なものが混ざっています。
じゃあ、ダメな説明じゃないかと思うかもしれませんが、僕が思うに、むしろそれがポイントなんです。直観という概念は古くから使われてきましたが、その意味には振れ幅があります。現在でも、直観をどう定義するかで、学問において最終的な一致はないと見受けられます。
その背後にどんなプロセスがあるかは脇に置いて、「深く考えずにわかること」を広く意味するもの、として直観を捉えることにします。
生活は、自然な動きの連続です。深く考えずともそれなりにやれている。誰だってそうです。さまざまな障害を持っている場合もありますが、それもなんとかカバーして生活している。
芸術や、難しい仕事に「パッとわかる」ことを求められると、そんなことできるか! という声が上がると思うのですが、日常の大まかな流れとしては、誰もが直観的に動いている。これを再確認した上で、そこから芸術などの話につなげていきたいのです。
「わかる」というのを、「判断、判断力」と言うことにしましょう。センスとは、「直観的な判断力」です。あるいは「理解」でもいいでしょうし、「分別」や「識別」とも言えますが、判断力という言い方を代表者にします(これは、カントの『判断力批判』という著作を念頭に置いています)。
ところで、服のセンスが良くても音楽選びのセンスはいまいちだ、などと言われることがあります。これまた、センスのトゲの話ですね。「あの人、服はカッコいいのに音楽のセンスはなあ」とか。「あるものについてセンスが良ければ、他のことでもセンスが良くていいはずなのに……」という期待があるのかもしれません。なにか「すべてに共通するような判断力」を持っている人、というふうに、総合的に褒めるときにセンスがいいと言われることがあります。すなわち、センス:直観的で総合的な判断力、というわけです。
この本は「センスが良くなる本」だと言ったわけですが、それはまさに、総合的にセンスを広げていくことを目標にしています。音楽、ファッション、インテリア、美術、文学……などなどにまたがって、「直観的にわかる」を広げていきたいと思うわけです。それが生活や仕事にもつながってくる。
センスと文化資本
センスの良し悪しは、しばしば、小さいときからの積み重ね、「文化資本」に左右されると思われています。それは育ちの良さに結びつけられ、身も蓋もなく言えば、もともとお金持ちで、いろんなものを鑑賞できる環境にあったとか、経済的格差の話にもなります。
しかし、文化資本はあとから育成することが可能だと僕は思います。この本では、文化資本を人生の途中から形成することを目標とする、と言い換えてもいいかもしれません。いや、それはちょっと不正確なので、もう少し説明します。
文化資本があるとは、たくさんのものに触れ、いろいろなものを食べ、つまり量をこなしているということ。ビッグデータを蓄積しているわけです。量をこなしているから、自然と判断力が身についている。さらに言えばそれは、AIのプログラムに、ネット上のものすごい量の文章や画像を「食わせる」ことで、それをもとにして「生成」ができるというのに似ています。
量をベースにして判断力が出てくるわけですが、僕の考えでは、ある程度、判断力の原理を先に考えてしまうこともできると思います。
昔から量を積み重ねている人に対して、途中から物量作戦で勝とうとしても無理です。ですが、量を積み重ねるなかで得られる判断力のポイントを学び、そこから再出発して、量を積み重ねていくことはできる。民主的な教育というのはそういうことではないでしょうか。
多くの人は、生まれ育つ過程で、何か特定の、少ないものに固着して視野が狭くなる——と言うと言葉が悪いですが、あまり他のものに興味を広げないで、ある範囲のなかで満足するようになります。それに対して、もっと興味を広げてみましょう、とよく言われる。この本にしてもその一種です。
ですが、あまり興味を広げたくないという気持ちにも、正当な理由があると思います。
人間とは「余っている」動物である
人間は、他の動物種よりも自由の余地が大きく、いろいろなものに関心を向け、欲望を流動的に変化させることができる存在です。
自由の余地が大きいために、人間は、(1) 関心の範囲を「ある狭さ」に限定しないと、不安定になってしまう。過剰に多くのことが気になってしまうからです。(2) その一方で、未知のものに触れてみたいという気持ちは誰にでもある。それもまた、人間の自由ゆえです。
いわば、人間とは「認知が余っている」動物で、余っているからいろいろ見てみたくなるけれど、自分を制限しないと落ち着かない、というジレンマを生きている。僕はそんなふうに人間を捉えています(なお、この説明は、フロイト以来の「精神分析」という理論にもとづくもので、それに含まれる生物学的な部分を強調しています)。
だから、新しい分野にチャレンジする気持ちがなかなか湧かないとしても自然だし、新しいことが急にやりたくなったとしても、それまた自然。そういう二重性がある。
文化資本を積み重ねてきた場合では、いろんなことに興味を持つことによる不安定に慣れて、平気になっている、という面もあるのでしょう。
あとから文化資本を形成するのは、そうすればビジネスで勝てる、みたいなことではありません。次のように考えてみたいのです。
・文化資本の形成とは、多様なものに触れるときの不安を緩和し、不安を面白さに変換する回路を作ることである。
そこで、柔軟体操を行って、精神を動かせる範囲を広げてみようというわけです。
あるジャンルの面白さは、別のジャンルの面白さにつながります。たとえば、ファッションの判断は、美術や文学の判断ともリンクする。ファッションが文学に、料理に、仕事の仕方につながるといった拡張を信じられない方も多いと思います。だんだんと体を柔らかくして、「ものごとを広く見る」モードに入ることが、センスを育成していくことです。
ここでも留保ですが、ひとつの専門分野に自分を限定し、その論理や倫理観に従って生きることが、真面目さであり、プロフェッショナルであり、という基準もあります。その基準からすれば、この本でお勧めするような「センスの拡張」は、そんな余計なことはしなくていい、と却下されるかもしれません。そうしたご意見も、尊重すべきだと僕は思います。頑固一徹にひとつの領域を守ることも人間のすばらしい力です。
センスの良し悪しから、その彼方へ
本書は最終的に、センスの良し悪しの向こう側、センスの彼方について考察します。
センスがいいも悪いもない、というのは、人それぞれの感性の面白さを肯定することです。それだけだと、「みんな違ってみんないい」という話になりそうですが、もうちょっと複雑な話をすることになります。「みんな違ってみんないい」というのは、ウソっぽい明るさがあると僕は感じますが、もっとりのある話をします。むしろ、人間の「どうしようもなさ」をどう考えるかという話になります。どうしようもなさ、そこには、なにか否定的なものが含まれます。人が持っている陰影です。そのことと、先ほど述べた、ひとつのことに自分を限定する、あるいは「せざるをえない」ということが関係してきます。
そこに至るまでの過程で、いったん、ある意味でのセンスの良さを考えるわけです。逆に、「センスが悪い」ことを定義することにもなります。それをふまえた上で、センスとアンチセンスの複合体として人間の陰影を考えることになる。
イントロはこのくらいにしましょう。センスとは何か、センスの良し悪しとはどういうことか。それは、歴史を通して、美術や文学などにおいて何が評価されてきたのかということと、ある程度関係しています。その経緯にも触れることになります。
センスの良し悪しから、その彼方へ——。
まずは、センスというカタカナ語の扱い方をあらためて検討しましょう。