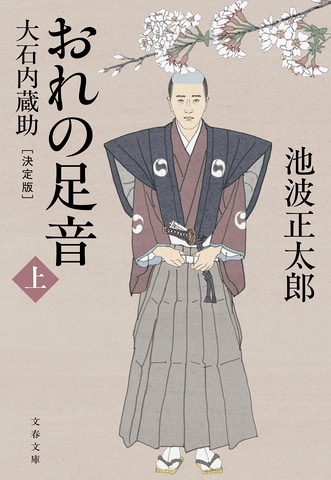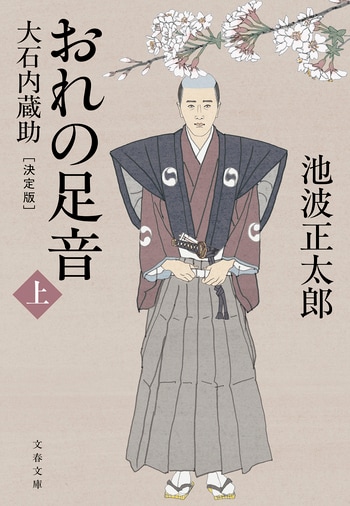池波正太郎は大正十二年(一九二三)に生まれ、平成二年(一九九〇)に没している。大正と平成のあいだにある「昭和」という時代(六十二年と十四日)をまるまる生きた人だ。
昭和をふりかえってみれば、さまざまな「正義」が席捲した時代であった。好戦主義、唯心論、国粋思想、その反動としての非戦主義、唯物論、左翼思想などが声高に叫ばれた。そのつど政治は正道の大義をふりかざし、思想は正論という鎧をまとった。
正義はいつも「歴史主義」と手をたずさえている。歴史主義とは、歴史から照射を受け、その延長線上にある使命への参加を呼びかける運動である。煽動者たちは「あらたな歴史をつくるのだ」と声をからしてアジり、みずからの信奉する正義の旗を勇ましく振るのだった。小説の世界においても、正義は蔓延した。書き手はみずからの信じる主義(イズム)を主人公に託し、苦悩を大仰に吐露させ、拠って立つイデオロギーの無謬性を訴えた。
しかし彼らは、熱病から醒めるやいなや、他人を焚きつけたことなど忘れ、そしらぬ顔で職場や大学や文壇に戻り、こんどは組織内での権力を手に入れようとして立ちまわるのだった。
正太郎は、こうした時代思潮や人生態度をにんがりとした表情で眺めていた。
もとより正太郎は「大げさ」がきらいだった。教条的な原理をなんの疑いもなく叫ぶ連中がきらい。観念的な理想を賢しらぶってわめく輩がきらい。それを煽って参加を呼びかけるジャーナリズムはもっときらい。それは「終戦のときの、一夜にして白が黒となり、黒が白となった衝撃が尾を引いているから」だ。信用するのは、自分の眼でとらえた「一個人が表現しているもの」だけである。
正太郎の関心は「個人」と、その人間がいつくしんでいる「暮らしの些事」に向けられた。先入観を排して史料を読み、共感や反感を抑えて歴史の実相に迫る。身分をとっぱらい、装飾をはがし、裸にひんむいて、虚心に人間を読み解く。裸眼の思索者が書く小説は、おのずと細部を描いて人間の正味を浮かびあがらせる手法へと向かうのだった。
池波小説の登場人物で不幸になるのは、きまって「我欲」の強い人たちだ。物欲、金銭欲、名誉欲で身の内を充満させた我利我利亡者。他人にたいする思いやりの心がなく、自分さえよければそれでいいという利己的人間。正太郎は彼らの、危機に際しては臆病、利にのぞんでは貪欲な態度にげんなりして、容赦ない筆致で不幸な行く末を用意した。
逆に、好意を寄せたのは「寡欲」の人だ。それは自恃と中庸、礼節と定法をみずからに課すことのできる人間である。武士でいえば、名利に無頓着で、惻隠の情を忘れない者が好みだった。なかでもいちばん好きだったのは、本書の主人公である大石内蔵助である。
多くの赤穂事件(「忠臣蔵」というのは浄瑠璃や歌舞伎の外題)の物語は、事件の経緯、顚末の微細、数々の謎の究明に関心が向けられている。そこに描かれている内蔵助は「主君のために敵を討った忠節の士」であり、なにより「歴史に名をとどめる武士」だ。仇討ちという正義、名利という歴史主義に依拠して語られたものがほとんどだ。むろんのことに、舞台や映画では、客を喜ばすために脚色と華美がぞんぶんにほどこされた。内蔵助もまた、くりかえし語られることで偶像化、神格化の度合いを深めていった。
正太郎はこうしたありように違和感をおぼえる。「武士の鑑」たる内蔵助について書き始めるまえに、次のような一節を記している。
《あの事件が起こってから討ち入りまでの短い年月において、この男は、それまでの四十数年の〈おだやかな沈黙〉をかなぐり捨てて、すばらしい炎の色をふきあげる。
ぼくは内蔵助の四十年の沈黙を描きたいと思いはじめている》
(〔安兵衛の旅〕『わたくしの旅』)
作者の関心は、事績の詳細ではなく、裸の大石内蔵助にある。
そこで、本書を開いてみると――子どもの時分から居眠り癖があり、国家老(主君参勤の留守をあずかる家老)という要職についてからも「昼行燈」というあだ名をもらっていた男がいる。好物の柚子味噌をなめながら晩酌をし、妻女や子どもたちと仲よく暮らしている。身分の上下がやかましかった時代にあって、立場の弱い者に気やすく声をかけ、相手の気持ちをおもんぱかる。世情につうじ、心きいたやさしい気持ちを忘れない。残された時日をまえにしても、「おだやかな沈黙」につつまれたままだ。脱盟者がでても、不忠不義の臣だと咎めることをしない。首府に赴いてからも、町の片隅で女郎と同衾し、討ち入り当日は、降りつもった雪の中を「冷えるのう……寒い寒い」とつぶやきながら、吉良邸に向かって歩をすすめる。人心収攬には長けているが、気負ったところがまるでない。これらを記述する正太郎のペンは心なしか愉しそうだ。
吉良邸に討ち入って、いよいよというとき、内蔵助の脳裡に浮かぶのは、これで歴史に我が名をとどめられるという名声欲ではない。本懐を遂げようとする初一念だけが頭を領している。と、そこへ、内蔵助の頭をよぎるものがある。おのれの生を充実させてくれた妻りくの豊満であたたかい肌身だ。
これが物語の最後である。未完のまま途絶してしまったのか。吉良の首級を掲げて浅野家の菩提寺である芝高輪の泉岳寺まで行進する勇姿がない。悲壮な切腹の場面がない。偉業を讃える美辞麗句も見あたらない。内蔵助は物語世界からすっと姿を消してしまった。
主君による「松の廊下」での刃傷沙汰がなければ、内蔵助は名を知られることもなく、色好みの平凡な国家老として生涯を終えたであろう男であった。だが、その日、肚のすわった熟慮断行の武士へと変貌を遂げる。侍は侍らしく生き、本懐を遂げて、侍らしく死なねばならぬ。その一心だけがあった。
本書の題を『おれの足跡』とはせず、『おれの足音』としたところにも著者の趣意が込められている。運命を従容として我が身に引き受けて歴史の舞台から静かに立ち去っていった内蔵助。歴史に名を刻もうともくろんだ足跡はどこにも見あたらない。行間から聞こえてくるのは、やむにやまれず、歩むべくして歩んだ武士の、静かな足音だけだ。
歴史の真実というものは、客観的なかたちでは存在せず、たえまない見直しのなかで再発見される過程のなかにのみ存在する。正太郎は、ひとりの武士の日々の暮らしぶりに透徹の視線を投げかけることにより、“定説”の背後にひそむ灰汁をすくいとり、歴史小説の可能性と、現在にもつうじる人間の普遍性を読者に知らしめた。こうして、昭和という歴史主義の時代に書かれた本作品は、池波文学の芯棒である「反歴史主義」を標榜する記念碑的小説となったのだった。