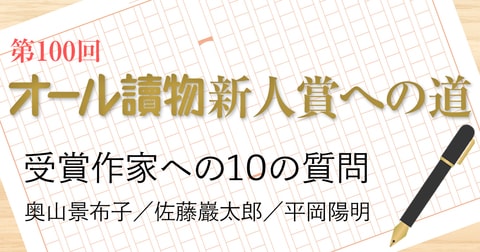平岡陽明さんが、亡くなったお父様をモデルに紡いだ最新長篇『マイ・グレート・ファーザー』が2月21日(金)に刊行になります。
妻を失い、息子は引き籠り、自身の仕事にも未来はない。そんな人生のどん詰まりで、30年前の世界へとタイムスリップしてしまう男の数奇な3日間を描いた本作。
刊行に先立ち、本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、冒頭40ページ分を先行無料公開します。
もしも、生前の家族に再び会えるとしたら、あなたはどんな言葉を交わしたいでしょうか。
亡き父へ
1
約束の日、時岡直志は十四時過ぎに横浜の自宅マンションを出た。途端に熱波が顔のまわりを包み込んだ。歩いて五分もする頃には、顔じゅうから汗を噴いていた。ポロシャツも体にべとべとと纏わりついて気持ち悪い。このところの日本の夏の酷暑は常軌を逸している。
日陰を辿り辿りしつつ、横浜駅まで出て、電車に乗った。カメラマンとしての師にあたる、大山一郎の自宅を訪れるためである。こんなふうに大山の家へ足を運ぶのはいつ以来のことだろうか。あれは大山が還暦を迎えたとき、一門の弟子たちで集まったのが最後になるから、十数年ぶりのことになるはずだった。
あの時の大山は赤い贈り物に囲まれて嬉しそうにしていた。末弟子の直志は当日かぎりの専属カメラマンとして、部屋のあちこちから、またあらゆる角度から、師と兄弟子たちを写真におさめた。今となっては、カメラを置いてしまった兄弟子のほうが多かった。
弟子たちは独立するとき、大山にこう言われるのを常とした。
「年賀状もお中元も要らない。その代わり、カメラマン廃業を考えたときは一度だけ俺のところに相談に来い」
その言いつけを守らねば、と思いつつも、正式に廃業しようか思い悩んでいるうちに、二年の月日が経ってしまっていた。今日、訪問するつもりになったのは、これ以上、決断を引き延ばすことの方が心理的に辛くなってきたからだった。一週間前に、相談したいことがあるので自宅を訪ねていいかと尋ねた。大山は「電車で来なさい」とだけ言って電話を切った。
手土産を持って、歩いて大山の自宅へ向かった。東京の郊外にある閑静な住宅街の一軒家だった。この土地に駅から徒歩圏のマイホームを構えていることは、大山のカメラマン人生が成功であったことを物語っていた。
門扉の前を二度ばかり行き来したあと、自分の二の腕あたりをくんくんと嗅いだ。人と会うとき匂いを確かめるようになったのは、カメラで食えなくなり、生ゴミ収集のバイトを始めてから身についた習慣だった。体に染みついた現場の匂いは、洗っても洗っても抜け切らないことがあった。とくに夏場の生ゴミから立ちのぼる臭気はひどい。自分はその臭いにとっくに慣れてしまったが、それ故にバイト仲間以外と会うときは、努めて体臭に気を使うようにしていた。
匂いに支障がないことを確認してからインタフォンを押した。白髪の目立つようになった大山の妻が出てきて、応接間へ案内してくれた。テーブルの上には、すでに水割りのセットが用意されていた。このために電車で来いと言われたのだ。ウィスキーの瓶はまだ封を切られておらず、今日のために夫妻が購めてくれたものかもしれなかった。
目にも涼しげな水玉模様の浴衣を着て、大山が現れた。
「よっ、辞めんのか?」
微笑に毒を含ませながら尋ねてきた。直志は苦笑を以ってこれに応えた。
「僕ももう、四十六ですから。これでも保った方じゃないですかね」
大山がいきなり訪問の核心をついてくれたことは有り難かった。十数年ぶりの来訪が廃業の報せであることに、多少の居心地のわるさを覚えていたからだ。
「まあ、飲めや」
大山は袂を上手に捌きながら水割りをつくってくれた。現役時代から洒落者の師匠だった。引退してからは和服で過ごすことが多いと聞いていた。素人目にもなかなか粋な着こなしに見える。それに比べて、と直志は己の不格好さを恥じざるを得なかった。ファストファッションで上下を固めている。カメラマンは身なりも商品価値の一つであることは百も承知だった。だが貧すれば鈍するで、ここ数年、生活が苦しくなってからは、ほとんど構わなくなってしまった。むかし凝っていた値の張るヴィンテージのデニムも、すっかり古着屋に売り払ってしまった。
「大方そんなことだろうと思って、これを引っ張り出しておいたんだよ」
大山が何枚か綴じられたコピー用紙をテーブルの上に広げた。
「ここには二百の雑誌社の連絡先が書いてある。まだやりたい気持ちがあるなら、片っ端から電話をかけてみたらどうだ。少し古い資料になるが、アポを入れて、作品集を持って足を運んで、仕事を下さいってお願いしてみるんだ」
直志は資料を手に取り、ぱらぱらと捲った。そんなことならとっくの昔にやりました、とは言いづらかった。この二年ほど、直志は旧知の編集者に、それこそ片っ端から連絡を取ったのだ。
――たまには仕事を下さいよ。
冗談めかしながらも、じつは切実なお願いを口にした。しかし芳しい応答は一度もなかった。一度も、だ。
「もう一つはこれだ」
大山が一枚の紙をテーブルの上に置いた。中華料理店のホームページか何かのプリントアウトらしかった。
「久世さんの店だけど、覚えてる?」
直志は頷いた。久世は大山の古くからの知り合いで、一門の集まりがあるときは彼の中華料理店をよく使った。弟子たちも何かの集まりがあるときは積極的に利用した。久世の店を使うと大山が喜ぶからだ。
「久世さんに事情を話したら、いつでも歓迎するって言ってくれたよ。週休二日で、手取りは二十七万。正社員扱いで、社会保険完備。もちろん交通費も支給する。ただし初めは皿洗いからやってもらうから、そこだけは覚悟しておいてくれって」
大山はプリントアウトの端に記してあったメモを一息に読み上げた。それからソファの背もたれに身をあずけ、俺にできるのはこれくらいだよ、とつぶやくように言った。
久世さんの店に世話になれるなら、悪くないのかもしれなかった。社員にして貰えたら、少しずつでも借金を返していける。
借金で首が回らなくなりつつあること。それが直志に廃業を決意させた最大の理由だった。すべては住宅ローンの返済のために借りたものである。
久世の店に興味がありそうな素ぶりを見せると、大山は「いまから聞いてみようか」と立ち上がった。まだ決めた訳では……と遠慮がちに制止したが、大山は「いいんだよ。聞いてみるだけだから」と部屋を出て行った。せっかちなところは昔と変わらない。
ひとりで部屋に残された。壁には古い広告ポスター群が並んでいた。昭和を代表する女優が、日本を代表する化粧品会社の商品を持ち、笑顔をつくっている写真。世界中の女性が憧れるジュエリーブランドのダイヤの指輪。誰もが聞いたことのある高級ブランドの腕時計。
いずれも大山が八〇年代に撮った広告写真だった。どの写真も背景が暈しに暈してあるのは、当時一世を風靡した手法だった。大山はその流行のど真ん中にいた。直志はそんな大山に憧れて弟子入りしたのだった。
大山が古めかしいガラパゴス携帯を持って戻ってきた。それは大山が時代に取り残された象徴と見ることができたし、悠々自適の隠居生活を送っている証と見ることもできた。大山はそれを使って久世に電話をかけた。
「あ、久世さん? このまえ話した弟子の時岡ね。いま目の前にいるんだけど、もしお世話になりたいって言ったら、いちど連れて行ってもいい? うん。そうそう。ありがとう」
ものの一分の電話で、なんとなく話がまとまってしまった。大山は師匠としての務めを果たして一安心したらしく、ソファに深く座りなおし、グラスを傾けた。そして兄弟子たちの近況について語り始めた。
直志はその話に耳を傾けながらも、心の一隅が雲におおわれているのを感じた。師に伝えるべきことは伝え、来訪の目的は果たした。だが、このまま流されるようにカメラを置いてしまっていいものだろうか。今更ながら、そんな思いがじくじくと心を衝いてきた。情けなかった。思い悩んだこの二年は、なんのためにあったのか。
雑談が尽きると小一時間が過ぎていた。近いうちに久世の店を一緒に訪れる約束をして大山邸を出た。
表はすでに日が傾き始めていた。夕暮れどきの街を駅へ向けて歩き出すと、額にうっすら汗が滲んだ。冷房で適度に冷やされた体にはむしろ心地いい汗だった。酷暑がやむ気配のない夏も、この時刻になるといくぶん凌ぎやすくなる。
一つ目の角を曲がるまでは、大山邸に大きな忘れ物をしてきてしまったような感覚に囚われていた。まだカメラを置きたくない、と駄々をこねる赤子が胸中にいた。二つ目の角に差し掛かる頃には、もう一人の分別ある大人の直志が、その赤子を諄々と諭していた。カメラで食えなくなったから、カメラを置く。至極、当然なことではないか、と。
なんのことはない。この二年ほど悶々とくりかえしてきた問答を、二つの角を曲がるあいだに再演していたに過ぎなかった。師の手を煩わせたのだから、きっぱり諦めろ。そう己を𠮟りつけた時だった。不意に空から声が降ってきた。
「戻れ」
直志は立ち止まり、上空を見上げた。当然だが、茜色に染まった雲の他には何者の姿も認められなかった。水色とオレンジが捩れ合う夕暮れのグラデーションが、どこまでも続いているだけだ。空耳だろうか。
そしてなぜかふと、この空を作品としてカメラに収めたいと思った。こんなふうに心を動かされたのは実に久しぶりのことだった。生活に追われ出してからは作品の撮影どころではなかったからだ。作品撮り用の愛機であるライカのM6は道具箱の奥にずっと蔵われている。
夕空にじっと見入った。重たそうな買い物袋を提げた女性が、「何事か」と、同じように空を見上げながら通り過ぎていった。やがて直志は地面に伸びた己の長い影に目を落とした。それはゆらゆらと揺蕩い、今にも消え入ってしまいそうだった。
「戻れ」
謎の声を反芻した。空耳や幻聴でなければ裡なる声の具現化であろうと解釈した。
直志は踵を返し、いま来た道を歩き始めた。久世の店を訪れる約束をいったん白紙に戻してもらおう。そうすることで、もう一度だけ自分の白紙の気持ちと向き合うのだ。ふたたびチャイムを鳴らしたら大山は驚くだろう。だがいま戻らなければ、きっと後悔する。その一事が、羞恥やためらいを振り払った。直志は十六歳で父を亡くしていたから、自然と大山を第二の父と仰ぐことが多いことは自覚していた。だからこそ甘えたくなかった。だがこれは甘えだろう。そう思うと頬が熱くなった。
最後の角を曲がった。驚いたことに、大山が玄関先で逆光に目を細めながら悠然と煙草を吸っていた。大山の口から吐き出された煙は、つかのま入道雲のような形をとり、やがて夕暮れに搔き消えていった。直志が目の前まで行くと、大山はにやりと笑った。
「二本喫うあいだに、お前が戻ってくるような気がしてたんだ。なんとなく片づかない顔をしてたから」
家の中へ促されたが、直志はここで結構ですと丁重に断った。そして戻った理由を告げようとしたら、
「迷ってるんだろ?」
大山に機先を制された。直志は微かに頷いた。
「わかるよ」
大山は再び煙草に口をつけて、訥々と語り出した。
自分の退き際くらい、自分で決めればいいさ。俺も末弟子がカメラマンを辞めちまうのかと思うと、寂しかったんだ。久世さんには俺からうまく言っておくから心配しなくていいよ。また一週間後の同じ時間に、答えを持って来な。ただし、と大山はそこで語気を強めた。
「ひとつだけ宿題を出しておく。これまでの自分にいちばん足りなかったものは何か、考えてくるんだ。それについて考えるのは、カメラマンを続けるにせよ、辞めるにせよ、今後の人生に絶対に役に立つから」
それはカメラマンとしての自分に足りなかったものですか、と直志は尋ねた。むろんそうだと師は答えた。
直志は大山に辞意を告げて、ふたたび駅へ向けて歩き出した。みっともない姿を晒してしまったという気持ちと、それを温かな心づかいで包んでもらえたという気持ちが、こもごも湧いてきていた。
自分のカメラマン人生にもっとも足りなかったもの……。それは何だろう。才能やセンス、腕や営業力に先見性。そうしたものが少しずつ足りなかった気がする。大いに足りなかったものもあるだろう。だがここで問われているのは、もっと別なもののような気もした。果たして一週間でその答えが見つかるだろうか。
どこからともなく、夕餉の香りが漂ってきた。侘しくもあれば、懐かしくもある匂いだった。それに心惹かれていると、ポケットに入れたスマホが震えた。息子の玲司からのメッセージだった。
〈チャーハン切れた。買ってきて〉
2
スーパーで冷凍チャーハンを六パック買い、保冷剤を詰めこんで帰宅した。シンクには食器類が乱雑に投げ込まれていた。玲司が最後の冷凍チャーハンを食い散らかした残骸だ。
洗い物を始めると、背後で玲司の部屋のドアが開く音がした。すぐに閉まる音が続く。トイレへ行きたいという合図だ。直志は手早く洗い物を済ませ、玲司の部屋のドアをノックした。
「十秒後」
そう告げて、急いで衝立の陰へ身を隠した。きっかり十秒後、玲司が控えめな足音を立ててトイレへ向かった。直志は息を潜めて息子が用を足すのを待った。そして玲司が部屋へ戻ると、いつのまにか浅くなっていた呼吸を取り戻すために、ふう、と深く息をついた。
――もう、高校へは行かない。
玲司がそう宣言したのは二ヶ月前のことだ。まだ高一の一学期も終わっていない時期だった。理由を尋ねるとたった一言、「疲れた」という答えが返ってきた。感情を押し殺したような口ぶりだった。
それから玲司は一度も家を出なかった。それどころか直志が家にいる時は、リビングにすら姿を見せたがらなかった。1LDKの一部屋は玲司に与え、直志はリビングの隅に衝立を立ててそこで寝起きした。だから玲司がトイレに行きたがる度に、こうして衝立の陰に身を隠さねばならない。
どう接すればいいか分からなかった。どんな言葉を掛ければいいのかも分からなかった。直志はちょうど今の玲司の年齢で父親を亡くしていた。だから範とすべき父親像を持ち合わせていなかった。模範になるような父親でもなかったのだが。
この年頃の子が陽に当たらないのはさすがにまずいだろうと、何度も外へ誘った。食事、散歩、買い物。玲司は頑として応じなかった。それでもめげずに誘った。自分でもしつこいと思うくらいに。すると玲司は会話を遮断した。意思の疎通はすべてメッセージアプリを通じてのものになった。
直志はアプリを通じて、なおも外出をうながした。焦りのあまり、脅すような語調になってしまったこともある。もともと通信簿に「気持ちが優しすぎる」と書かれるような子だった。そんな子を脅してしまったのかと思うと気が滅入った。だが外には連れ出したい。八方塞がりだった。玲司がどう接して欲しいと思っているのか想像がつかなかった。それを相談できる相手もいなかった。カメラマン失格に加えて、父親としても失格なのではないか……。そう思うと、自分の精神がまだ正気を保っていることの方が不思議だった。やがて外出をうながすメッセージには返信すらなくなった。そんな気塞ぎな生活が、もう二ヶ月も続いている。
シャワーを浴びたあと、発泡酒をあけて、溜まっていた郵便物をテーブルに広げた。消費者金融からの今月の返済額を報せる緑色の封筒が目についた。もう見慣れてしまったので動揺はなかった。だが、動揺しなくなった自分には少しだけ動揺した。
直志は父親の久春が借金で身を滅ぼす様を見ていた。だから借金だけはすまいと心に誓っていた。けれども住宅ローンの返済が滞れば、すぐにでもこの部屋を差し押さえられてしまうという状況には抗う術がなかった。毎月、数万ずつ摘んできたに過ぎない。だが塵も積もれば、それは動かしがたい山となって、眼前に聳えていた。
国民年金の督促状もあった。期日までに支払わなければ強制徴収もあり得ると書かれている。預金残高などほとんどないぞ、やれるものならやってみろ、と胸中で毒づくのが精いっぱいの反抗だった。ここ数年は、財布の中も貧乏学生のように心細い額しか持ち歩けていない。
差し迫った出費はこれだけではなかった。つい先日、車を車検に出したら「ラジエーターを交換したほうがいい」と言われたし、玲司の塾代の振り込みも近づいていた。高校に行かなくなった玲司に「オンラインでいいから、せめてこれだけは出てくれ」と懇願して受講を承知させたものだ。
直志の目が、サイドテーブルに飾られた妻の姿を求めた。もし妻と共働きだったら、こんな困窮は避けられただろうか? もし妻が生きていたら、玲司は引きこもりにならなかっただろうか?
彼女は写真立ての中で優しい笑みを浮かべるだけだった。彼女はもう歳を取らない。もう悲しまない。もう泣かない。その代わり触れることもできなければ、言葉を交わすこともできない。妻が亡くなったのは八年前。急性白血病だった。
「きちんと玲司を育てるって約束したでしょ。頑張ってよ」
そんな声がサイドテーブルの写真立てから聴こえてくるようだった。
いったい自分は、どこで間違ってしまったのだろう。自分のカメラマン人生に最も足りなかったものとは何か。大山から与えられた宿題について考えようとしたら、テーブルに置いたスマホが光った。玲司からのメッセージだ。
〈こんどオンラインゲームの大会に出たいんだけど、このゲーミングマウス買ってくれない? 俺のマウスの性能が悪いと、チームのみんなに迷惑が掛かる〉
添えられた画像を見た。使途不明のボタンがたくさん付いた、装甲車のように背の高いマウスだ。価格を見ると五万円近くするので驚いた。どうしてもこれでなくてはいけないのか。もっと安いものでこれと似た性能のものがあるのではないか。そう思って玲司の部屋のドアをノックした。
「メッセージ、見たよ。申し訳ないけど今は買ってやれないな」
すぐに玲司からメッセージが届いた。
〈でもチームの足手まといになりたくない〉
玲司の気持ちは痛いほどよくわかった。玲司は引きこもりになってから、プロゲーマーになりたいと言い出した。どこかのオンライン・チームに所属していることも知っていた。プロゲーマーなど夢の世界の話だろう。だがこの広い世界で玲司の居場所が今はそのオンラインにしかないのなら、無下に扱うことは絶対にできないと感じてもいた。
けれども現状の経済事情に照らすなら、五万のマウスをぽんと買ってやる訳にもいかなかった。もしこれが「一人旅に出たい」などという申し出だったら、どんなことをしてでも工面してやっただろう。玲司の外出は、直志にとって今や悲願と言えるものになっていたからだ。
直志はドア越しに一つのプランを提示した。
「だったら俺と一緒に、ゴミ収集のバイトに来ないか。バイトは十六歳からオーケーだし、俺と同じ現場に回して貰えるように所長に頼んでみるから」
思いつきにしてはいい案だと思った。バイト代プラス日光浴。一石二鳥だ。だが、しばらく待っても返事はなかった。
「おい、聞いてるか」
催促するとメッセージが届いた。
〈もういい〉
最近の玲司の決まり文句だった。直志はこの四文字を浴びせられるたびに、胸を抉られる思いがした。あなたは何もわかってない。故にあなたには何も期待していない、と言われているような気がしたからだ。
とにかく、外に出てほしい。
明日から一泊で久しぶりの撮影仕事が入っていた。尻切れトンボのまま家を空けねばならぬことが心苦しかった。
3
車に機材を詰め込んで家を発った。行き先は伊東のゴルフコースである。フロントガラスの向こうには晩夏とは思えぬほどくっきりした青空が広がっていた。今日も暑くなりそうな予感がする。
目覚めた時から、なぜか頭に靄が掛かっている感じがして、体も重かった。それを振り払うためにボリュームを控えめにラジオを入れて、久しぶりの遠出を少しでも楽しもうとした。
ところが信号に捕まると、すぐに玲司の顔が浮かんだ。本当なら今日の撮影に連れて行きたいくらいだった。玲司に伊東の自然の空気を胸一杯に吸わせて、澱んだ細胞と総取り替えできたら、どんなに清々するだろう。
きのう見せられたゲーミングマウスの画像も浮かんだ。なぜゲームをするのに五万もするマウスが必要なのか、納得しづらかった。けれどもあれくらいぽんと買ってやれる父親でありたかった。
しばらく運転しても、頭に掛かった靄は取れなかった。バックミラーで自分の顔を見た。目の下にはわずかながら隈ができていた。もう何年も、ひょっとしたら十年以上のあいだ、風邪ひとつ引いたことがないのが密かな自慢の一つだった。なぜ、よりによってこんな日に……。そう思わざるを得なかった。なにかしら胸がざわめく。
ふと、この体調不良はメンタルから来たものかもしれないと思った。この二年、カメラマンを正式に廃業することばかり考えてきた。そのあいだにじわじわと心が削られてきた可能性は高い。それが昨日、大山邸を訪れてケジメをつけたことで顕在化したとは言えないだろうか。
やがて横浜横須賀道路方面の標識が見えてきた。この有料道路を使えば近道だが直志は黙殺して一般道を走り続けた。伊東へ行くときはいつもこうだ。“横横”を回避するのは父・久春の事故死現場を見たくないからだった。父は三十年前にゴルフ場へ向かう途中で、横横のカーブの側壁に衝突して亡くなった。今の直志と同じ四十六歳だった。
「本当に、あなたの両親っていう人たちは……」
父の葬儀のあと、母方の叔母に言われた。どうやら保険金詐欺疑惑を仄めかしているように直志には聞こえた。たしかに不動産業を営んでいた父はバブルが弾けて借金まみれだった。叩けばホコリどころか、私文書偽造という前科まで出てくるキナ臭い人物でもあったのだ。
ゴルフコースに着いたのは昼過ぎだった。あいかわらず頭に掛かった靄は取れていなかった。こんなコンディションで満足のいく写真が撮れるだろうかと心配になった。しかし、レストランの片隅で新メニューの「紅鮭の香草焼き」と「特製ビーフカレー」を撮り終えると、信じられない成果が待ち構えていた。これまでのカメラマン人生で最高の料理写真が撮れていたのだ。
体調不良のせいで自分の目が曇っているのではないか。そう疑って全カットを見返してみた。やはりどの写真にも大山が撮ったような香気が漂っているように感じられた。紅鮭には、えも言われぬ照りがあった。カレーのルーも滑らかさが際立っており、写真からコクや甘みまで伝わってきそうだ。
どうして今更こんな写真が撮れてしまったのだろう? 思い当たる節があるとするなら、これが商業カメラマンとして最後の料理撮影になるかもしれない、という想いでシャッターを切ったからだ。
そのとき余計な思念は一切なかった。自分というものはなく、いい写真を撮ってやろうという気持ちすらなかった。それが結果として、生涯最高の料理写真につながったのかもしれない。直志は静まりかえったレストランの片隅で、慎ましい悟りの一端をつかまえた気がした。ひょっとしたら自分に最も足りなかったものとは、これだったのだろうか……。
支配人と料理長が挨拶に来た。仕上がりを見せると、二人は一緒になって出来栄えを喜んでくれた。大山の教えの一つに、「プロよりもアマを満足させるほうが難しい」というものがある。直志は満更でもない気持ちになった。明日の早朝、朝焼けのコース写真を撮る約束を確認して、伊東駅の近くにあるビジネスホテルへ向けて出発した。
ゴルフ場を出ると、すぐに急峻な下り坂に入った。濃い緑におおわれた山道を運転しながら、自分にもあれくらいの料理写真が撮れるのかという余韻に浸った。すると突如、天から声が降ってきた。
「来い」
驚きにハンドルを取られ、車体がよろめいた。後続車から怒りに満ちたクラクションが鳴らされる。次の信号で停車したときも、心臓はまだ音を立てて鳴っていた。謎の声が聞こえたのは二日連続だった。昨日、大山邸からの帰り道に聞こえたのと同じ男の声だ。中年か、それよりすこし上くらいの声に感じられた。聞き覚えのない声であることは確かだった。やはり空耳か、そうでなければ幻聴だろう。メンタルのせいで自律神経をやられたのかもしれないという疑いは、ますます強まった。父が側壁に衝突したのは――もしあれが保険金詐欺でなかったとするならば――案外こんなことが原因だったのではないか。頭に掛かった靄、人生最高の料理写真、天から降ってきた声。何かチグハグな一日のような気がする。
ホテルに到着し、フロントで宿泊費の七千円を前払いして鍵を受け取った。伊東へ来たときの定宿で、この築五十年のホテルには何度も泊まったことがある。これで財布の中の残りは三千円と小銭が少しとなった。一泊出張に持ってくる現金は一万円と決めてある。節約のためだ。
部屋に入りスマホを充電しようとしたら、充電ケーブルを家に忘れてきたことに気がついた。使い古したスマホだからバッテリーの減りは速かったが、いますぐ充電が必要な訳ではない。あとでフロントで借りればいいだろうと、ベッドへ倒れるように横になった。久しぶりの遠出で疲れていたらしい。すぐにウトウトしてしまった。
短い夢を見た。父と二人で車で出掛ける夢だ。はっと目覚めると十五分が経っていた。
伊東へ来ると自然と父へ考えが引き寄せられるのはよくあることだった。父は亡くなる一週間ほど前にここへ逃避行を敢行したからだ。バブルが弾けて父の会社は倒産の危機にあった。自宅も競売に掛けられる寸前まできていた。それらすべてに嫌気が差したのだろう。そう心配する母と直志をよそに、父は失踪から四日後に帰ってきて、ケロッとした顔で告げたのだった。
「伊東競輪に行ってきた。旅先で仲間もできて、いやー、楽しかったよ」
二人は呆れてものも言えなかった。
このとき父はライカのM6を土産に買ってきてくれた。当時十六歳でカメラをいじり始めていた直志は小躍りするほどに喜んだ。名機の誉れ高いカメラだった。なぜこんな高価な物を買ってくれたのか聞こうと思っていた矢先、父は二日後に亡くなってしまったのだった。
直志はベッドから起き上がった。体は重いままだったが、せっかくの遠征先である。どこかを散歩して夕食までの時間を潰そうと思った。自然の中で空気を吸えば自律神経にもいい効果があるかもしれない。
ふと、道具箱の奥に眠るライカのM6を久しぶりに持ち出そうかと思ったが、やめた。ここ数年がそうであったように、ライカで自分の作品を撮るような気分には、やはりなれそうになかった。商業カメラマンとして需要のない自分が、芸術にこだわるなんて――。そんなある種の精神的な潔癖さが、ライカを取り出す手に待ったをかけるのだ。
ロビーで伊東の観光地図を手に取りホテルを出た。途端に全身から汗が噴き出す。八月も後半に入るというのに酷暑は一向に収まる気配がなかった。頭の天辺からアイスキャンディのように溶けてしまいそうだ。明後日からまたゴミ収集の現場に戻るのかと思うと気が重かった。
汗をぬぐいつつ、緩やかな坂道を登りきった。駅前に垂れ幕が掛かっていた。
〈伊東競輪開催中〉
父が逃避行中に通い詰めたという競輪場だ。地図で確かめると伊東競輪場は少し離れた山あいの杜の中にあった。そのことが直志の気を惹いた。森林浴をしながら往復して汗をかけば、体調も戻るかもしれない。そういえば幼いころ、父によく川崎競輪場へ連れて行かれたな……と思い出していたら、またしてもあの声が空から降ってきたのだった。
「来い」
もはや空耳とは思えなかった。直志は堪え切れなくなって、「誰だ」と空に向かって尋ねた。誰が、なんの目的で、どこへ招ぼうとしているのか。直志は伊東の空を睨みつけながら答えを待った。だが、それが降ってくることはなかった。
諦めて、競輪場を目指して歩き始めた。市街地を抜けて川沿いの道に出ると、竹灯籠が置かれた遊歩道になっていた。川には大きな鯉が泳ぎ、その川向こうには由緒ありげな旅館が見えてくる。
伊東は山と海が近い街だから、空気に自然の匂いが濃い。本来なら玲司にこそ、この空気を吸わせてやりたかった。玲司の生っ白いうなじが目に浮かんだ。とにかく、外に出て欲しい。新鮮な外の空気を吸って欲しい。旅先でもふとした拍子にそのことが頭を占領する。
歩いていると額から汗が滴り落ちてきた。都心よりはいくぶん涼しく感じられるが、今年の酷暑はどこも同じことである。休憩を取りたいと思っていたら、ちょうど前方に濃い緑におおわれた神社が現れた。直志は一服の涼を乞うつもりで境内に足を踏み入れた。
そこは昼なお暗く、土も湿っぽかった。参道の脇に巨樹があった。直志はそれをひとしきり見上げ、大山ならどんな構図で撮るだろうと考えた。やはりライカのM6を持ってくれば良かったかもしれないとわずかに悔いた。シャッターは押さなくてもいい。ライカのレンズを通して被写体を覗くだけで、世界は一瞬だけ自分のものになる。そしてその間だけは、現実世界の嫌なことを忘れることができる。そのことが尊いのだ。
そんなふうに思ったのは、きのう大山邸のある街で、夕陽に心を動かされたことが大きいのかもしれなかった。移ろう美しい景色を、自分の目と指で切り取りたい。そんな衝動が自分の中にまだ生きていたのは嬉しかった。同時に、それがもう世に求められておらず、行き場を失っていることに向き合うのは寂しかった。
じめじめした石段をのぼり、本殿にお参りした。形ばかりの二礼・二拍手・一礼を済ませ、石段を降りかけたとき、ぐらっと揺れがきた。
初動の大きい地震だった。
靴底が滑り、足が石段をつかみ損ねる。しまった、と思ったときには、仰向けのまま転んでいた。石段に頭をぶつける音をスローモーションのように聞いた。目の前が昏くなった。
どれくらい倒れていただろう。「早く起き上がらなくては」という自分の意識の声だけを、暗闇の中で聞いた。次に聞こえたのは、けたたましいカラスたちの鳴き声だった。異変を察知して飛び立ったのだろう。
直志は恐る恐る起き上がった。後頭部に手を当てると痺れがあった。だが、外傷や瘤ができた訳ではなさそうだった。若いつもりでいるが反射神経は鈍っているのかもしれないと情けなく感じた。
石段の下にあるベンチで休んでから神社を出た。川沿いの道は先ほどまでの暑さが嘘のように涼しかった。今しがたの後頭部への一撃で調温機能に異常をきたしてしまったのだろうか。それとも夕立でもくるのか。直志はスマホを取り出して雨雲レーダーで確かめようとした。圏外だった。首をかしげた。
やがてある異変に気がついた。朝から掛かり続けていた頭の靄がすっきり取れ、体も若い頃のように軽くなっているのだ。いったい何が起きたのだろう?
その時だった。風に乗って、競輪場の打鐘の音が聴こえてきた。残り一周半、レースが勝負所に差し掛かった所であるらしい。鐘の音は徐々に高まり、音と音の間隔も次第に短くなってゆく。直志は得体の知れない胸騒ぎを感じた。
〈ようこそ伊東競輪場へ〉
そう書かれたアーチの前に立った。
ぞくりとしたものが、なぜか背中に走った。
4
懐かしい光景だった。
酒焼けした不健康そうな男たちが、場内のそこかしこにいた。ある者は地べたに尻をつき、ある者はベンチで立膝をしながら予想紙に目を光らせている。つっかけやサンダルを引っ掛けている者が多かった。
彼らは気怠さと射倖心を綯い交ぜにしたような独特の雰囲気を放ちながら、そこらじゅうに唾を吐き、紙屑を撒き散らしていた。むかし父によく連れられて行った川崎競輪場も、成らず者や敗残者たちの吹き溜まりに見えたものだった。とくに血眼で地面を探索している者たちの存在が、幼い直志には不思議で仕方なかった。
「なんであのおじさんたちは、いつも下を向いて歩いてるの?」
「あれは吸殻狙いの浮浪者か、間違って捨てられた当たり車券を探す拾い屋だ。害はないけど近寄るな」
彼らの中にはレースが終わるたびに、金網越しに選手たちへ罵声を浴びせる者がいた。あいつら車券も買ってねぇくせに、と父は吐き捨てるように言ったものだ。幼い直志にも、彼らが、ままならぬ境涯の鬱憤を選手たちにぶつけていることはなんとなく感得できた。どこを見回しても灰色で、人も地面もうす汚れている。それが直志にとって競輪場の原風景だった。
その頃とあまり変わらない光景が眼前に広がっていた。場内の雑踏ばかり目にしていると胸焼けしてしまいそうだったので、直志は広い空を見上げて一服の清涼を求めた。夏の陽はまだ大きな光を放っていたが、神社を出たときから感じている涼しさは続いていた。なぜ突然、こんなにも過ごしやすい気候に様変わりしたのだろう。だしぬけに秋が訪れたのか。しかしそれも今年の酷暑を思えば的外れな気がする。ともかくも頭に掛かっていた靄が取れ、体がすっきり軽くなったことは嬉しかった。
競輪場を訪れるのは三十数年ぶりのことだった。時おりスポーツ新聞を覗く限りでは、どこも閑古鳥が鳴いているらしかった。とくに地方競輪場はそうだ。一日の総入場者数が数百人などということはザラだった。
ところが今ざっと見渡した限りでも、その数ではとても収まりそうにない男たちが蜷局を巻いていた。まっすぐ歩くのが困難なほどだ。場内には三日間の平開催の初日であると掲げてあった。つまりスター選手たちが走る特別競輪といったグレードレースとは、比べものにならないほど地味な開催であるということだ。それにしては人が多すぎる気がする。伊東の街には娯楽が少ないのだろうか。そんなはずはあるまい。仮にそうだったところで、競輪などという古めかしいギャンブルに人々が雪崩を打って押しかけることもなさそうなものだ。
訝しみながらバンクの方へ向かうと、ちょうど次のレースが始まるところだった。客が選手たちへ檄を飛ばしていた。
「こらァ池崎! この前みたいなレースしたら母ちゃんに浮気されっぞ!」
「山本ォ、今日逃げなかったら、伊東から生かして帰さねぇからな!」
あまりに時代錯誤な野次に、苦笑いが漏れる。
レースが始まり、やがて打鐘が鳴った。後方から捲ってきた選手を止めようと、前方の選手が頭突きをかましてスピードを殺しにかかる。まるで格闘技のようだ。
幼い頃は、いい大人たちが自転車を漕いで生活している姿にどことなく滑稽味を感じていたものだった。自転車は子供の乗り物である、という思い込みがあったせいだろう。だが今はアスリート同士の体を張った踏み合いに魅入られた。時速六十キロとも言われる走行を写真に収めるなら、デジカメではなく、あえてライカで撮ってみるのも面白いかもしれないと思った。どんな露出とシャッタースピードで撮るのがふさわしいか頭の中で計算していた。
レースが終わり、直志はふたたび場内を歩き始めた。少し行くといい匂いが漂ってきた。食堂の店先に〈煮込み丼三百五十円〉と貼り紙が出ている。安い。ここで夕食を済ませば出張費を浮かせられるが、残念ながらまだ腹は減っていなかった。
次に公衆電話から電話を掛けている人を見かけた。それだけでも珍しいのに、後ろに順番待ちらしき人まで並んでいる。直志は不思議に思いながらスマホを取り出してみた。まだ圏外のままだ。なぜかと首をひねっていたら、
「おい、邪魔だよ」
と声を掛けられた。見れば老人が直志を忌々しげに睨みつけていた。直志が立っていたのは換金所の列の並びだったらしい。知らぬうちに、通せんぼをする格好になってしまっていたのだ。
直志は詫びを入れて立ち退いた。老人から、つぅんと饐えた臭いが漂ってきた。生ゴミの収集現場でかぐ臭いに似ていた。発生源は老人の赤茶けたよれよれのポロシャツだろうか。それとも不器用な鳥が巣づくりに失敗したみたいに爆発している頭髪か。どちらも最後に洗ったのはいつのことだか想像もつかない。
老人が換金所で払い戻しを受けた。千円札が一枚と、小銭が少しだ。直志の目はその手元に釘づけとなり、咄嗟に老人に声を掛けた。
「あの、その千円札をちょっと見せて貰えませんか」
「はあ? なんだって?」
老人が右耳を突き出してきた。よく見ると補聴器をつけていた。直志は大きな声で繰りかえした。
「その、千円札を、見せてください」
今度は聴こえたらしかった。老人はすぐには答えず、カー、ペッと痰を吐いた。歯はほとんど欠けており、残った数本も脂で黄ばんでいた。その歯と同じように黄ばんだ粘液が地面にへばりつく。老人は丸めた塵紙を取り出して口元をぬぐった。そしていかにも耳の悪い人らしく、ゆっくりと大きな声で答えた。
「なんで、お前に、見せなきゃいけねぇんだよ」
もっともだった。直志は辞を低くして、自分が持っている千円札と違う気がするからだと説明して、野口英世の千円札を広げて見せた。老人はまじまじと見つめ、「それ、おもちゃか?」と言った。直志は首を横に振った。すると老人は渋々ながらも自分の千円札を見せてくれた。やはり思ったとおり、一世代前の夏目漱石のものだった。野口英世よりも髭が濃い。
「おい、もういいか」
「大丈夫です。でもその千円札、いまどき珍しいですよね」
「おめぇ、外国人か? ずっとこれだろうが」
直志は呆然と老人を見つめた。いまは二〇二三年である。来年には新紙幣への刷新が告知されている。つまり来年になれば漱石の千円札は二世代前のものになるのだ。それを「ずっとこれ」と主張するとは……。老人の脳内で起きていることに朧げながら察しがついてきた。おそらく認知症が始まっているのだろう。直志の母も晩年はその気が出ていたので、症状の出始めた老人が真顔で恍けたことを言う様子には免疫があった。
母に付き添って初めて認知症外来を訪れたとき、医師は症状の進行具合を確かめるために三つの質問をした。「今日は何曜日ですか」「いまは西暦何年ですか」「いまの総理は」の三つだ。まるで年端もいかぬ子供に尋ねるような優しい口調だった。直志はそのときの口調を思い出しながら老人に尋ねた。
「今日は何曜でしたっけ」
「土曜だろ」
違う。金曜だ。
「いまは西暦何年でしたっけ」
「九三年に決まってんだろ」
あまりに想定外な回答に面食らった。だが、どうにか気を取り直し「総理は?」と三つ目の質問を口にした。
「おめぇは新聞もテレビも見ねぇのか? ついこのあいだ細川内閣ができたばっかりじゃねぇか。自民党は調子に乗り過ぎたんだよ。ざまぁみろだ」
間違いない。この老人は精神が錯乱している。三十年前で時間が止まってしまっているのだ。けれども老人は漱石の千円札を換金所で受け取っていた。そのことにどう説明をつけたらいいのだろう。そう考えていたら、老人が手にしたスポーツ新聞に目が止まった。一面に〈長嶋監督〉〈中畑コーチ〉という大見出しの文字が見える。なぜいまさら長嶋と中畑? 疑問に思い、それを見せてくれと老人に頼んだ。
「おめぇ、さっきから、あれ見せろ、これ見せろってうるせぇんだよ」
「これで最後にします」
「煙草、持ってねぇか?」
「はい?」
「一服つけてぇんだ。持ってねぇか」
「すみません。ずっと前に禁煙に成功したんです」
老人はむっと口を結び、どこまでも使えない奴だという目で直志を睨みつけてきた。その後も何度か「見せてくれ」「やだ」と子供のおもちゃの奪い合いのような問答が続いた。埒が明かないので、珈琲でも奢ったら見せてくれるかと尋ねた。
「あ、それならいいよ」
老人は途端に猫撫で声になった。現金なものだ。なけなしの出張費をこんなことで使ってしまうのは惜しかった。だが直志のほうでも、この老人からスポーツ新聞をせしめてやりたいという、多少、子供っぽい意地を張り出していた。
「ホットとアイス、どちらにします?」
「ホットがいいな」
直志は売店まで行き、百五十円の珈琲を買った。千円札を差し出すと、エプロンをつけた老女が「お客さん、なにこれ?」と眉を曇らせた。
「えっ、なにって……。これ、ほんとに使えないの?」
老女は答えず、直志の風体を上から下までじろじろ見つめてきた。あわてて小銭入れを覗いたが、十円玉しか見当たらなかった。
「あの、やっぱり買うのやめていいですか」
「そういうことされると困るんだけどね。どうすんの、この珈琲」
「ごめんなさい」
直志は逃げるように店先を去った。老人のもとへ戻り、自分の千円札が本当に使えなかったと告げた。すると老人は奇人でも見るような目で直志を見つめてきた。そして触らぬ神にはとばかりに、直志にスポーツ新聞を押しつけて立ち去った。
認知症気味の老人にそんな扱いを受けたことには少しモヤモヤしたが、直志はベンチに腰をおろして新聞を広げた。一面にはやはり「長嶋監督が中畑コーチを𠮟った」という大見出しが踊っていた。新聞の日付は〈1993年 8月21日〉。曜日も老人が言ったように〈土曜日〉となっている。
これはたちの悪いドッキリか何かだろうか。直志はあたりをきょろきょろ見回した。しかし隠しカメラは見つかりそうになかった。そもそも一般人の自分にドッキリを仕掛けたところで何にもなるまい。
スマホを取り出すとやはり圏外のままだった。玲司に電話を掛けてみたが繫がらない。直志は首をかしげながら、近くの車券売場まで行き、売り子の中年女性に尋ねた。
「ここらでスマホの電波が繫がりやすい場所ってありますかね」
「なんですかそれ」
「つまり、インターネットの電波のことです」
「さあ、聞いたことありませんねぇ」と女性は不可解な面持ちで答えた。
近くのゴミ箱にスポーツ新聞を捨てた客がいた。それを手に取って確かめると、そこにも〈1993年 8月21日〉と記されている。直志は周囲の人々の格好を注視した。サンダル。ズボン。シャツ。髪型。すべてに、そこはかとない古めかしさを感じた。だが競輪場の客なんて昔から冴えない格好をした中高年男性ばかりと相場が決まっている。これだけではなんとも言えない。しかし、何かがおかしい気がする。
ベンチに座り、老人から貰ったスポーツ新聞をぱらぱらと捲った。どのページも「1993年 8月20日」の出来事で埋まっていた。つまりこの新聞の日付の前日の出来事だ。これがドッキリの小道具だとするなら、手が込みすぎている。
ふと、セリーグの打撃三十傑に目が留まった。
1位 オマリー(神).352
2位 ブラックス(横).345
3位 ローズ(横).325
4位 ハドラー(ヤ).323
5位 ブラウン(広).315
6位 前田智(広).314
7位 江藤(広).311
…………
懐かしい名前が並んでいた。この年の上位はこんなにも外国人選手が占めていたのかと思った。本当かどうか調べてやろうとスマホを取り出したが、電波が繫がらないことを思い出してポケットに戻した。
さらにページを捲ると、ゴルフ欄では〈夢の組が実現!〉という見出しが踊っていた。伊藤園レディスの初日で岡本綾子、服部道子、福島晃子が同組で回ったというのだ。この三人ならむかしゴルフ雑誌の取材で撮影したことがあった。今やレジェンドの岡本が現役でトップ争いをしていることが新鮮だった。
新聞を折りたたんで膝に置いた。漱石の千円札。細川内閣。繫がらない電波。懐かしいスポーツ選手たちの名前。一九九三年という日付。
いま何が起きているのか、頭では最適な仮説が浮かびつつあった。だがそれを認めてしまうと、自分が真人間ではいられなくなってしまうような気がした。そもそもこれは現実なのだろうか。自分はまだ駅近くのビジネスホテルのベッドの上で夢の続きを見ているのではあるまいか。そう思いたかった。だが、そうでないことは自分がいちばんよく分かっていた。四十六年のあいだ頼りにしてきた自分の肌感覚が、これは現実だと告げてくる。
もし仮説どおりのことが起きているなら、いちばんの気掛かりは玲司のことだった。このまま連絡が取れず、帰ることもできなかったら、玲司は飢え死にしてしまうかもしれない。借金の返済だって滞る。ある日突然、差し押さえ要員がのりこんできて身一つで放り出されたら、玲司は途方に暮れてしまうだろう。
わが身のことも心配だった。金はあと三千円しかない。野口英世が使用できないなら、実質ゼロだ。充電ケーブルさえないこの世界で、どうやって生きて行けばいいのか。もとより電波は繫がらないのだから、充電の心配はしなくていいのかもしれないが。
というよりも、戻るとか戻れないとか考えている時点で、自分の頭はおかしくなってしまったのではないか。そういえば今日は朝から体調が悪かったのだ。幻聴だけでなく幻視まで加わってしまったとするなら、自分の自律神経は思っていたよりも深刻な病状なのかもしれない。
「おい」
だしぬけに耳元で声がした。振り向くと先ほどの老人が立っていた。
「さっきの千円札、もういっぺん見せてくれねぇか」
直志は野口英世を広げて見せてやった。貸してくれよ、と老人が手を差し出してくる。一抹の不安を感じたが、まさか持ち逃げしたりはしないだろうと渡してやった。老人は札を光にかざしたり、裏返したりしながら、「おもちゃにしちゃ良くできてるな」と感心したように言った。するとその時、すこし離れたところから怒鳴り合う声が聴こえてきた。
「おっ、喧嘩だ!」
老人は補聴器をつけているとは思えないほどの速さで反応し、声のする方角へひょこひょこと駆けて行った。
「あ、お札――」
直志は老人のあとを追った。なけなしの金を取られる訳にはいかない。
5
「だからさっきのレースは、穴予想だって言っただろ!」
予想屋が台上から客を怒鳴りつけた。歳の頃は直志と同じくらいだろうか。サーファーくずれを思わせる日焼けした茶髪だが、髪の根本から黒い毛が生えてプリンのようになっている。
「予想が外れたことを責めてるんじゃねぇ!」
負けじと客も声を張り上げる。直志からは後ろ姿しか見えないが、白いポロシャツを着た、小柄な男だ。
「穴予想ならもっと点数を広げて買わせろ、ってアドバイスしてやったんじゃねぇか。現に抜け目を喰ってるんだし。俺は朝からお前に乗っかって、もう十万やられてるんだよ!」
「そんなこと知るか」
「知るかとはなんだ。だいたいお前は、ちゃらちゃらし過ぎなんだよ。茶髪なんかにしやがって。そんな暇があったらもっと競輪の勉強しろ!」
予想屋はうんざりした様子で「いい加減にしろよ。警察呼ぶぞ」と言った。客は「呼ぶなら呼べ。ついでに顧問弁護士と用心棒にも声を掛けたらどうだ」と訳のわからない開き直り方をした。先ほどの老人が隣で「いいぞいいぞ、もっとやれぃ!」と囃し立てる。
予想屋は競輪場の許可を得た公職で、たしか一レースにつき百円で予想を売っているはずだった。そんな予想屋に嚙みつく客なんて滅多にいないのだろう。人だかりができていた。やり取りを聞く限りでは、負けて熱くなった客が八つ当たりしているようにしか思えなかった。直志はこの仕様もない客の顔を拝んでやろうと正面に回った。
瞬間、息が止まった。深海魚のように眼球が飛び出てもおかしくないほどの驚きだった。
禿げかけた頭頂を横髪で隠した、いわゆるバーコード風の髪型。往年のジャンボ尾崎に影響されたゴルフルック。唾を飛ばさんばかりに権高な話しぶり。なにより、その顔だち。
親父……か?
声にならぬ音が直志の喉奥から漏れた。男は見れば見るほど父に似ていた。胸に広がりかけた奇妙な懐かしさを、畏れに似た感情のベールが包み込んだ。見てはいけないもの。遇ってはいけないもの。そんなものに遭遇してしまったという禁忌の念が直志を捕えた。
同時に驚くほど生々しい感情が甦った。それは思春期の男子が父親に抱く、ごくありふれた反撥心や嫌悪感だった。そうした感情は大人になるにつれ、昇華されていくものだろう。だが直志の場合、思春期の頃に父と死別したので、その手の感情が手つかずのまま、どこかに冷凍保存されていたらしかった。
いけない、いけない、と頭を振った。この男が父であるはずがないのだ。この世には自分と全く同じ見た目の人間が三人はいるというではないか。その類いだろう。自分にそう言い聞かせる。
やがて父にそっくりな男は、悪態をついて気が済んだとでも言うように、車券売場へ向かった。直志は男のあとを尾けた。頭で考えるよりも体が先に動いていた。
男は車券を買うとゴール前の金網付近まで行き、二人の男と親しげに会話を始めた。あの二人は誰だろう。現地で親しくなった地元の常連客か何かだろうか。そういえば父には、初対面の人とでもすぐに打ち解けられる特技があった。なにせ配偶者に「とにかく調子のいい山師だった」と言われ続けた男だから、それくらい朝飯前なのだ。
と、そこまで考えたところで、またしても頭を振った。あれが父であるはずがないのだ。そんな風に思い込みたがるなんて、自分の頭は本当にどうかしてしまったのだろうか……。
男は先ほどの喧嘩で、場内のちょっとした“有名人”になったらしかった。ちらほら新規の人たちに声を掛けられ、そのたびに「やあ、やあ」と愛想よく応じている。その応接ぶりにも父の片鱗があった。立ち姿やちょっとした仕草にも、父を彷彿とさせるものがある。人は見た目が似ていると、仕草まで似てくるものなのだろうか。
そのうち九名の選手たちが敢闘門から出てきて発走台についた。太腿や頰をぱんぱんと叩き気合いを入れる。男は選手たちに何か檄を飛ばしていた。先ほどの口喧嘩を聞く限りでは、聞いていてあまり気持ちいい種類の言葉ではなさそうだ。
号砲が鳴った。選手たちは牽制しあったのち、先頭誘導員のあとを追って初手の位置取りを定め、静かな周回に入った。九つの逞しい脚がからくり時計の歯車が並んだように一律にペダルを回す。
三周回目に入ったときだった。直志はある事実に思い当たり、愕然とした。
スポーツ新聞の日付にあった一九九三年という年が、父の亡くなった年だったことに思い当たったのだ。父が伊東へ出奔したのも、そこから帰ってきて二日後に亡くなったのも、すべては九三年の夏の出来事だった。つまりあそこにいるのが三十年前に伊東へ逃げてきた父であるとすれば、すべての説明がつく。そんな仮定はお伽話に過ぎないだろうが、もしそうなら、あの男は“いま”から四日後に亡くなる運命にある……。
打鐘が鳴った。しかし直志の脳内に響いていたのは、三十年前の叔母の言葉だった。
「本当に、あなたの両親っていう人たちは……」
叔母が疑ったであろう保険金目当ての自殺について、生前の母に一度だけ真相を尋ねたことがある。母は首を横に振るばかりだった。だが直志の中で疑念は燻り続け、八年前に妻が亡くなった時に再燃した。妻の保険金はささやかな額ではあったが、あまりにスムーズに下りたので、直志は担当者に尋ねた。
「父が亡くなった時はもっと時間が掛かりました。この二十年ほどで審査がスムーズになったのでしょうか」
担当者は直志から事情を聞くと、「失礼ですが、お父様のケースは自殺の可能性を調査していたと思われます」と言った。彼によれば、保険金詐欺が疑われる事案は、世間の人が思っている以上に多いらしい。そのため保険会社には専門の調査部署まであるそうだ。
レースは残り半周のバック線を過ぎた。先行していた選手のスピードに翳りが見える。そこへ脚を溜めていた後方の選手が一気に捲りあげた。わっと歓声が沸くなかで、ひとり直志だけが静まり返った心境で往時に思いを馳せていた。
三十年前に訪れた父とのふいの別れ。もしあれが計画的なものだったとするなら、自分は実の親に謀られたことになる。事故の真相を知りたいと心のどこかでずっと願ってきた。玲司が生まれ、自分も人の親となってからは尚更だ。どんな理由があれ、成人前の子供を残して自死するなんて親失格だ。俺の親父はそこまでクズだったのか、という思いをずっと抱いてきた。
車券が紙吹雪のように舞った。それでいつの間にかレースが終わっていたことに気づいた。男も車券を破き、宙へ放り投げた。どうやら朝からの連敗記録を更新したらしい。
場内アナウンスが第十レースの投票開始を告げた。本日の最終レースである。
直志は男に接触を図り、名前を聞き出してみてはどうかと考えた。もし男が「時岡」と名乗ったら、ここが一九九三年であるという設定をいったん受け入れて――やはりそれは信じ難いことではあったが――あの事故の真相を聞き出すのだ。
話し掛けるなら、男が予想屋との喧嘩でちょっとした有名人になっている今はチャンスといえた。信じられない光景が目の前で展開されている以上、話し掛けずに後悔するよりも、話し掛けて後悔したほうがいい。そんな方向へ気持ちは傾いていった。むろんこちらの正体は明かさないほうがいいだろう。「自分は未来から来たあなたの息子です」などと名乗ったら、さすがに男の脳内に警戒警報が鳴り響くだろうから。
直志が父と死に別れたのは十六歳のときだった。つまり四十六歳の父にとって、四十六歳の直志は未知の人物である。だから仮にあの人物が父だったとしても、こちらの正体を看破される可能性は少ないはずだ。
時刻は午後四時前。
夏の陽はようやく傾きはじめ、客席の庇が無人のバンクに影を落としていた。直志は男に向かって一歩を踏み出した。
【著者プロフィール】

平岡陽明
1977年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。出版社勤務を経て、2013年「松田さんの181日」でオール讀物新人賞を受賞し、デビュー。19年刊行の『ロス男』で吉川英治文学新人賞の候補に。他の著書に『ライオンズ、1958。』『イシマル書房編集部』『道をたずねる』『素数とバレーボール』『ぼくもだよ。神楽坂の奇跡の木曜日』など。